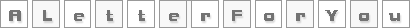
| |
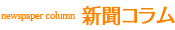
|
 |
Vol. 7 「日常からの非日常」 (2004/09/25) |
 |
「夏休みはどうするの?」
8月から9月にかけては、番組のスタッフどうしでこのような会話が交わされる。
順番に、夏休みを取ることになっているのだ。
この問いの意味するところは「どこに行くの?」。
年に一度の特別な休日は、無意識のうちに行楽地や避暑地で過ごすことと定義される。
どこにも行かないで、日常から脱出すことなど出来るのだろうか。
普段暮らす毎日を、透明な幽霊のように外から眺めてみたら…。
そんなわけで、今年は何も決めない夏休みを過ごした。
テレビをつけなくても、何時に起きても、お腹は減るし、決まった曜日にはゴミ出しもする。
例えば、平日の正午。
普段は会社にいる時間帯だ。
丸の内のオフィス街は、社員証を首から下げたスーツ姿の人たちでにわかに溢れかえる。
駐車場の入り口では、守衛さんがあくびをしている。
日が暮れてから思い立って出かけた初めての競馬場は、平日でも親子連れが多かった。
今の自分は、どこに行っても、何をしてもいい。
旅先では旅行者と位置付けられるが、街中でぼうっと佇む私は何者でもない。
気持ちの赴くままに過ごすのは、自由なのか、無計画なのか。
携帯電話に送信されてくるニュース速報のメールが、唯一の日常との接点だ。
ふと、急に不安になって、世の中がかえって遠くに見える。
例えば、ある日の朝。
心地良く目覚めたので、どこかに出かけようと思いつく。
道中小休止しながら、見知らぬ土地でポケット地図を広げて、指先で目的地をさまよう。
だんだんと変わりゆく街並。
コンテナが多くなっていく。
海が近い。
気が付けば、横浜に来ていた。
港の見える丘に上って街全体を見下ろした時、初めて自分が完全なよそ者になった気がした。
夕闇が空を押し下げていく中で、ベイブリッジが点灯し、
尾灯の帯がちかちか光り、身体で巨大な街を認識する。
瞼の内側には、遠くに暮らす父と母や、過ぎし日々の残像が映る。
高みからの視覚を通して、自身を複眼的に眺めているのだろうか。
住んでいる場所はどこだろう。
知っている建物はどれだろう。
今、どこにいるのだろう。
人はいつだって、自分の位置を確認したがる。
そうやって当たり前に一週間は過ぎていき、夏休みはひっそりと終わった。
日常に身を置いたままの非日常も、悪くない。
リゾートは案外、近所にも存在する。
(「日刊ゲンダイ」9月25日発刊) |
|
|
|
| |
|