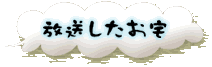
 |
2010年9月24日(金)放送 東京都世田谷区・高柳邸 - 古材が生きる家 - |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 山下保博 | ||||||||||
|
1960年生まれ。奄美大島出身。芝浦工業大学大学院修士課程修了。 |
||||||||||
| 一級建築士事務所 株式会社 アトリエ・天工人(テクト) | ||||||||||
|
||||||||||
| 高柳邸は、アトリエ・天工人が推進する「古民家プロジェクト-100+100 Aging-」の一環として、設計しました。 使われなくなった古民家を時代のニーズや構造基準に見合った新たなかたちに編集しなおし、古民家とともに育まれてきた伝統を、次の100年につなげるためのプロジェクトです。 本物件のコンセプトは「時間の継承」です。島根県で使われなくなった古民家の部材を、新しい空間に組み込んで、編集しなおすことによって、一棟丸ごとのリサイクルを実現しました。木材だけでなく、玄関のタイルには、同様に使われなくなった中国の古い煉瓦を使用するなど、ものと一緒に受け継がれる時間が醸し出す空間を感じていただければと思います。日本には、現在100万棟の古民家があるといわれていますが、人口の高齢化・減少によって空き家になったり、時代に見合わないという理由から不要となる古民家は多く、年間数万棟が解体・焼却処分されています。 私は古民家とともに受け継がれてきた時間が、現代社会のこのような理由で失われていく状況をなんとかしたいと思い、「古民家プロジェクト-100+100 Aging-」を立ち上げました。 また、古材の再活用は、実質的な環境保全にもつながります。実際に、日本の古民家を解体し、廃材として焼却時に排出するCO2よりも、移築のため輸送時に排出されるCO2の方が少ないという利点もあります。 私たちは、「古民家プロジェクト-100+100 Aging-」を通じて、日本の伝統を次の世代へ継承していきたいと考えています。 |
||||||||||
| 建物の大きさは数字では表せません。高柳さんのお宅も狭小住宅のジャンルに入ると思いますが、とても広く、大きく、豊かに感じます。それは、家のあちらこちらに使われた古材が、時間の重みを感じさせてくれるからでしょうか?そして、漆喰、鉄製品、古道具など、古材と一緒にあっても負けない存在感を持つ物が吟味されています。そういった物たちに癒されて、落ち着いて生活ができる建物です。 | ||||||||||























