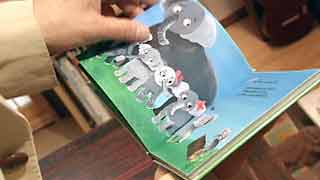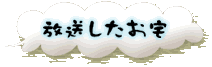

|
2007年9月16日(日)放送 茨城県龍ヶ崎市・坂本邸 - 田園を眺めて暮らす 築120年の古民家再生住宅 − |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 今井 俊介(いまい しゅんすけ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 株式会社 アカデメイア | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 「古民家再生」は、大きく3つに分類されます。もっとも簡単なのは、古民家の解体材を活かすもので、「古材活用」といわれます。 「現地再生」は、その言葉どおり、現地で半ば骨組みだけにし、水平垂直を立て直し、新しいプランのもと仕上げ工事を行うもの。「現地再生」の多くは、その持ち主が、さらに今後の100年の家の歴史を刻むためのものなので、再生に際しては、これまでの歴史をも引き継ぎます。最後の「移築再生」は、解体し、別の土地で新しいプランに基づき再建再生されるものです。「移築再生」の多くは、古民家の住人が変わります。従って、それまで延々と育まれてきたその家の歴史は、引き継がれることはありません。新しい持ち主にとっては、「古民家」での「新築」ということになりますが、しかし建築の文化を引き継ぐことになります。 「龍ヶ崎の家」は、長野県中条村から、茨城県竜ヶ崎市への「移築再生」でした。ここでは前の持ち主の方も、竣工後に龍ヶ崎に来られ、建築の文化だけでなく、その家に対する想いのようなものの受け継ぎもなされた感じがしました。従来、日本の建築は、使い捨てではありませんでした。従って、大工さんは、新材と古材を特に差別することなく、その構造材、仕上げ材としての評価で、同じように扱っていました。随分古い古民家の解体に立ち会うと、さらに古い年代の材が、「古材」として再使用されているのをよく見かけます。木の寿命は数百年から千年です。「住まう」という文化の担い手として木材ほど暖かく優れているものはありません。「古民家」は「解体」を経て、「再生」され、そのプロセスの中で、私たちにとって大切なものを再生し、継承する、住まいとの関わり方はそうありたいものです。 |
|||||||||||||||||||||
田園と里山を眺める、心落ち着く高台の敷地。そこに古民家を再生しました。日本の気候風土と共に永年歩んで来た建物ですから、居心地が良くないはずがありません。癒されます。現代的な生活をスポイルせずに、この雰囲気が味わえるということは大変贅沢なことだと思います。さらに嬉しいのは、近隣との協力により古民家で街並みが形成されていることです。 |
|||||||||||||||||||||