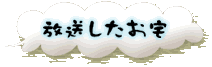
 |
2005年3月5日(土)放送 神奈川県横浜市・山本邸 -気分は白樺高原 横浜でロッジ生活- |
|
| 2003年12月完成 敷地面積 351平米(106坪) 建築面積 73平米(22坪) 延床面積 119平米(36坪) 木造2階建て 建築費:3045万円 坪単価:85万円 |
| 長谷川 順持(はせがわ じゅんじ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長谷川順持建築デザインオフィス株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-0033 東京都中央区新川2-19-8-7F
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長谷川順持 この住まいは正に「産みの苦しみ」をクライアントとともに楽しんだ住まいです。(今となってはこう言えるのですが、、)軟弱地盤の傾斜面が故に、斜面を杭で地盤補強、最小限の切り土を施しそこへ建築をふわりとなじませ載せていく。綴ってしまえば簡単なのですが、工事は難を極めました。なかなか進まない工事計画を辛抱強く見守り、私達を信じてくれたクライアントに、本当に感謝しています。さて、平らな場所がまったくない30度の傾斜とそこから展開する北側の景色はたいへん魅力的であり、この「土地」にこだわったクライアントの「熱」をいかに建築に写し取っていくかがテーマでした。北側風景を各所から望める「断面構成」。斜面になじむように上り下がりするスキップフロアー、そうした構成を柔らかくささえる自然素材。複雑な空間構成も、結果としては穏やかに風景と呼応する「優しい空気感覚」に結実させたかったのですが、その理由はこの家族の纏う雰囲気、世界が、そうした空気感に似合うと感じたからです。クライアントに似合った住まいとなっているのかどうか、答えは遠くにあるのかもしれませんね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本さんのお宅はとても心落ち着く建物です。この居心地の良い空間に身を置いていると、自分たちはオートメーションのベルトコンベアのような効率を優先の社会に生きているという事を考えさせらます。山本さんも研究者として技術の最先端のお仕事をされ、技術は日夜進歩しています。山本さん田舎暮らしをしたいと土地探しから苦労されたそうです。仕事と距離を置いた落ち着く場所で過ごしたいと思われたのではないでしょうか。何事も便利で効率良くということが良い訳ではありません。山本さんは音楽を聴くにしてもターンテーブルにレコードをかけています。アナログ的なものを大切にされています。交通などが都心より不便なのを承知で、自然豊かな土地を求められました。そして、できあがった建物は程よく機能的でどこかロッジを思わせます。基本は懐かしさ。そんな感じが致しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























