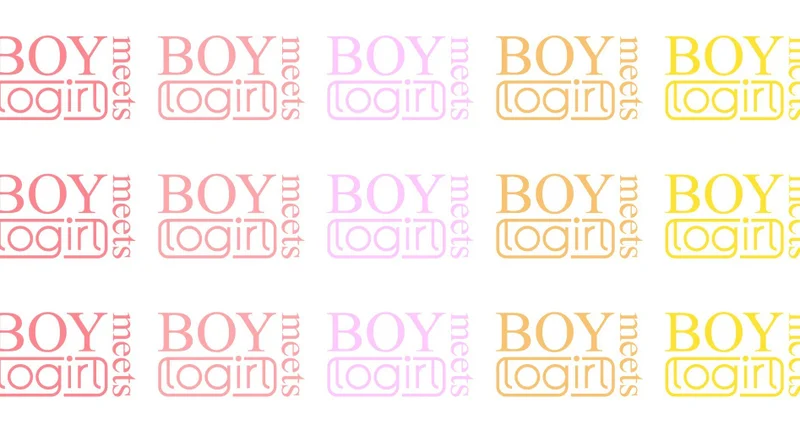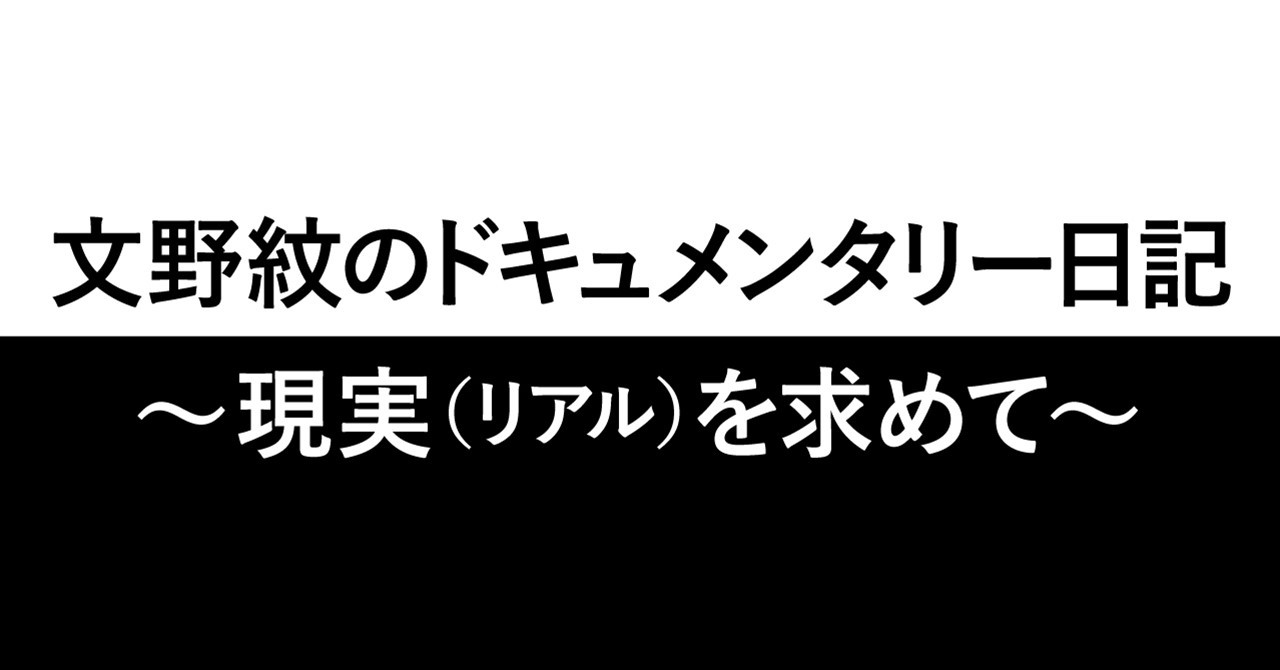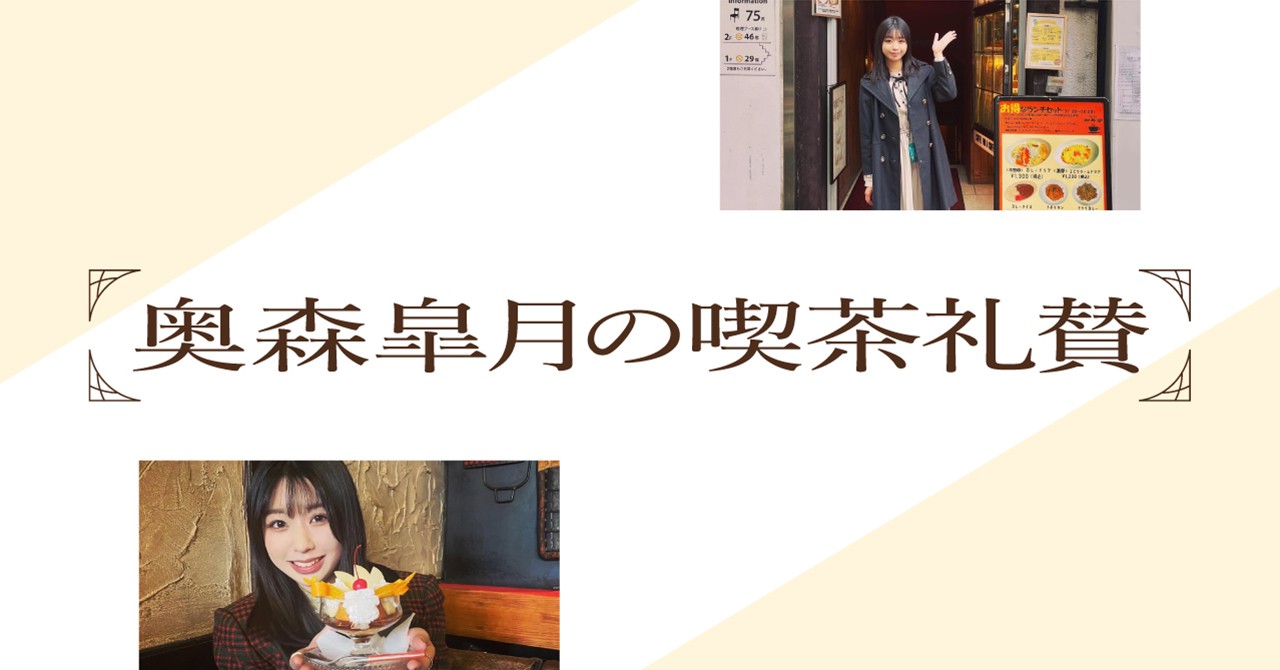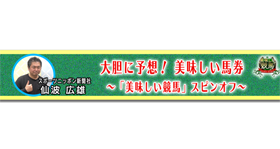サボリスト〜あの人のサボり方〜
-

「楽しむ気持ちがあるから、将棋にも研究にも夢中になれる」谷合廣紀のサボり方
クリエイターの活動とともに「サボり」にも焦点を当て、あの人はサボっているのか/いないのか、サボりは息抜きか/逃避か、などと掘り下げていくインタビュー連載「サボリスト~あの人のサボり方~」。 棋士でありながら、東大出身の情報工学者という顔も持つ谷合廣紀さん。将棋の対局だけでなく将棋AIの開発に勤しみ、さらには『M-1グランプリ』にも挑戦するなど、好奇心と行動力がずば抜けている谷合さんに、その原動力やサボり方を聞いた。 谷合廣紀 たにあい・ひろき 1994年、東京都生まれ。2006年に新進棋士奨励会に6級で入会し、2020年に四段昇段・棋士となる。第47期(2021年度)の棋王戦予選・決勝では、本戦トーナメント進出。また、東京大学に進学し電子情報学を専攻、自動車の自動運転技術や将棋の棋譜の自動記録プログラムなどの開発に携わる。現在は情報工学者として将棋AIの開発に力を入れており、2022年の第32回世界コンピュータ将棋選手権では独創賞を受賞した。 AIが将棋で人に勝つ時代がやってきて、自分の生き方を模索 ──まずは棋士としての活動について伺いますが、やはり奨励会(棋士志望者の育成機関)に入会したことで自然と棋士の道を意識されたのでしょうか。 谷合 そうですね。将棋道場といわれる場所に通うようになり、切磋琢磨していた同年代の人たちが奨励会に入って棋士を目指していくのを見て、私も同じ道を選んだので、けっこうまわりに流されやすいところがあるのかもしれません。高校生くらいまでは純粋に将棋が楽しくて続けていたので、将棋の本質や将来について考えたりするようなことも少なかったと思います。 ──意識が変わったきっかけなどはあるんですか? 谷合 ひとつには、高校生くらいでコンピューターが将棋で人間に勝ち始めていたタイミングだったことがあります。当時はまだ人間とAIが拮抗していましたが、いずれは成長したコンピューターに負かされていくわけで、将棋界や棋士という職業に不安を感じるようになったんです。そこで将棋や将来についてまじめに考えるようになり、将棋を続けつつちゃんと大学にも行っておこうと東大を目指すことにしました。 ──東大生と棋士の卵って、両立できるものなのでしょうか。 谷合 大学に入学したころには、棋士のひとつ手前である奨励会三段まで昇段していたので、辞めるのはもったいないと思っていましたし、両立もできると思っていました。とはいえ、そこから8年くらい三段に留まっていたので、将棋だけに打ち込まなかった弊害はあったのかもしれませんね。 ただ、棋士になれたのは年齢制限ギリギリの26歳でしたが、将棋一本でやっていると、最後の期に追い込まれて将棋のクオリティが下がってしまったりすることもあるんです。私の場合はリスクを分散したことで気持ちに多少の余裕があったので、最後の期でもちゃんと自分の将棋が指せたんじゃないかと思います。 ──棋士になったことで、見えてくる景色もまた変わってきますよね。 谷合 そうですね。棋士になれるかどうかのギリギリで追い詰められていたころに比べると、伸び伸びと自分のやりたい将棋が指せるようになったのは大きい気がします。棋士はもちろん勝つことも大事ですけど、いかに自分らしい将棋を指して将棋ファンの方々を魅せていくか、という意識も加わるので、将棋の内容も変わってくるんです。 将棋を軸に、自分にしかできないことを追求したい ──棋士としての谷合さんが思う「自分の将棋」とはどんなものなのでしょうか。 谷合 戦法の話になりますが、私はよく「四間飛車」という戦法で指していて、棋士はあまり指さないものの、アマチュアの方々には人気の戦法なんです。なので、アマチュアの方の見本になるような、教科書的な将棋を指すことを心がけています。あと、四間飛車は「振り飛車」という戦法に分類されるのですが、近年のAIではあまり評価されない終わった戦法だといわれることもあるんです。でも、そんなことはないと思っていて、棋士でも振り飛車で戦える可能性を見せたいという思いもあります。 ──逆にほかの棋士の将棋を見ていて、「強いな」と感じるのはどんなときですか? 谷合 いろんな要素があるのでひと口にはいえませんが、知識や戦略性が問われる序盤、読みの深さや早さが求められる中盤、詰むか詰まないかの判断力に左右される終盤とある中で、強い人には終盤力があると思いますね。「詰む/詰まない」の判断が正確で、優勢のときはそのまま勝ちきり、劣勢でも逆転に持っていく勝負力がある。まあ、藤井聡太さんみたいな方はそのすべてにおいて卓越していますが。 ──なるほど。では、ご自身の対局の中で印象深いものがあれば教えてください。 谷合 一度棋王戦というタイトル戦でベスト8まで勝ち上がったことがあるんですけど、そのベスト16のときに広瀬章人九段に勝てたことは印象に残っていますね。大きな舞台で、しかも広瀬九段という強い相手に自分らしい将棋で勝てたので。 ──谷合さんとしては、今後伸ばしていきたい点や棋士としての理想像はありますか? 谷合 あまり理想像みたいなものはないんです。ただ、普及活動にも力を入れたいとか、将棋AIを使った勉強ツールを作って実力向上に活かしたいとか、強い将棋AIを作りたいとか、将棋についてやりたいことは多角的にあります。将棋を軸に、自分にしかできないことをやりたい、伸ばしていきたいですね。 ──文化人として吉本興業に所属し、将棋好きな芸人さんたちのYouTubeチャンネルに登場されたりしているのも、そういった普及の一環なんですね。 谷合 そうですね。お笑い好きな方たちやAIに携わる情報系の方たちなど、将棋界の外にも声を届けたいと思っています。 ──『M-1』に挑戦(※)されたのは、芸人さんたちに触発されてのことなのでしょうか。 谷合 お笑い芸人さんと仕事をしていると、当然そのすごさを感じるわけですけど、やってみないとわからない部分もあるなと思ったんです。そんなときに、山本さんが『M-1』に出てみたいと言うので「じゃあやってみよう!」と。エントリー費を払えば誰でも参加できますし、アマチュアの参加も珍しくないので、一度は経験してみようという感じでしたね。 (※)2024年、山本博志五段と「銀沙飛燕(ぎんさひえん)」を結成して『M-1グランプリ』に挑戦。結果は1回戦敗退に終わった。 ──舞台に立ってみて、どうでしたか? 谷合 やっぱり緊張はしましたね。それに、人におもしろいと思ってもらえるネタを考えるのは難しいなと実感しました。一応将棋普及の目的もあるので将棋のネタにしたのですが、思った以上に伝わらなくてしっかりスベったというか……(笑)。初めて会ったお客さんも笑わせられる芸人さんはすごいなと、改めて感じました。 強いだけでなく学べる将棋AIの可能性を模索中 ──東大で情報工学を学ぶ道を選ばれたのは、やはり将棋があってのことなのでしょうか。 谷合 そうですね。ちょうど将棋AIが人間に勝とうとしていた時期だったとお話ししましたが、それでAIに興味を持って。勉強するなら、自分の将棋のスキルにつながるものがいいなと思ったんです。 ──実際に勉強してみて、どんなところに価値や魅力を感じましたか? 谷合 AIというよりプログラム全般の話になりますが、自分でプログラムを書けると、エクセルの作業といったタスクが自動化できるわけですよ。最近ではChatGPTみたいな大規模言語モデルが普及して、よりAIに任せられることも増えているので、どんどん便利になってきた気がします。それに、自分が書いたプログラムがかたちになり、アプリケーションとして世に出て使ってもらえる可能性があるところも、魅力のひとつですね。 ──まさにChatGPTによって日本でもAIの活用が一般化しつつありますが、ここまで普及すると思っていましたか? 谷合 日本語で指示できるAIがここまで早く浸透するとは思っていませんでしたね。とはいえ、今はまだその可能性を探っている状態なので、どういうふうに活用されるのか注視しているところです。私が研究している将棋AIの分野では、局面を入れたら最善手を示すことはできますが、なぜその結果になったのか、初心者にわかるように説明することはできませんでした。でも、ChatGPTのようなツールをつなげれば、日本語で解説するといったこともできるかもしれない。 ──膨大な計算を経て結果を導いているのだと思いますが、たしかにその過程がわかったほうが勉強になりますね。 谷合 今の将棋AIって、1秒間に数千万局面を計算できてしまうのですが、その過程はブラックボックスなんですよね。そこをわかりやすく解説するようなプログラムを実装していくか、そのあたりが研究の課題になっています。 ──そんなAIができれば、棋士としての谷合さんにもフィードバックがありそうな気がします。 谷合 そうですね。もちろん自分の将棋の勉強にも活かせると思いますが、勉強用ツールは別のかたちでも充実させたいと思っているんです。たとえば、将棋の定跡(決まった指し方、戦略)って膨大にあるので、一度暗記したものでもしばらくすると忘れてしまったりするんですよ。だから、自分が問題として取り組んでいた局面、定跡を、忘れたころに再び問題として出してくれるようなツールがあるといいなと思っています。 ──おもしろい。広く学習用のツールに活かせそうなアイデアだと思います。研究者としての展望も、AIを通じて将棋を豊かにしていく方向に広がっているんですね。 谷合 はい。自動車の自動運転技術に携わっていたこともあるのですが、自分が将棋を軸に置いている以上、研究も将棋に関するものに絞っていこうと思うようになりましたね。 趣味は将棋観戦。毎日観ていたい ──二足の草鞋を履いているような状態で非常にお忙しいと思いますが、谷合さんはサボることってありますか? 谷合 ずっとひとつのことに集中していても煮詰まったり、疲れたりしてしまいますから、何かを継続して長く続けるなら、サボりの時間も必要だと思いますね。私自身、やる気がないときは何をしてもダメな気がするので、「やる気がないときはやらない」というスタンスなんです。 ──そういうときは何をされているんですか? 谷合 基本、パソコンで作業しているのですが、やる気がないときはYouTubeを観ながら作業してみたり。それも集中の度合いによって違っていて、まだ集中力が残っているときは目で見なくてもいい音楽系、やる気がないときは芸人さんの動画、もっとひどいときはNetflixで映画を観てしまうときもあります。 ──Netflixは完全に息抜きモードですね(笑)。 谷合 そうですね。お皿洗いとか、家事をしているときもずっとNetflixを観ています。 ──お皿洗いとNetflixって両立できますか? 谷合 できませんか?(笑) ひとつのお皿を洗うのに1分以上かかったりと、効率的ではないと思いますが、Netflixを観ながらでもできているとは思います。 ──ほかに谷合さんにとっての息抜きって、どんなことがあるのでしょうか。 谷合 スマホのアプリで将棋の中継を観ているときはリラックスできるんですよ。逆に観ないと落ち着かないというか、土日は対局がないので、けっこうストレスに感じてしまいますね。 ──それは将棋ファンとして観ているということですか? お仕事でもあるので、いろいろ思うところがあったり、シンプルに観られないような気もします。 谷合 自分が対局するときはストレスというか緊張感がありますが、人の対局はあまり変な感情を抱かずに、エンタメとして楽しんで観ることができるんです。やっぱり将棋が好きなんですよね。クオリティの高い将棋を見せられると、「すごいな、自分もこれくらい指せなきゃな」って思いますし。 ──谷合さんにはプロ棋士の顔と研究者の顔があるということでお話を伺ってきましたが、なによりひとりの将棋ファンでもあるということなんですね。 谷合 そうですね。たしかに根底に将棋を楽しむ気持ちがないと、どれもできない気がするので、そこは本当に大切にしなきゃいけないなと思いますね。 撮影=石垣星児 編集・文=後藤亮平
-

「息苦しい世の中になっても、人をゆるさに引きずり込む仕事がしたい」スズキナオのサボり方
クリエイターの活動とともに「サボり」にも焦点を当て、あの人はサボっているのか/いないのか、サボりは息抜きか/逃避か、などと掘り下げていくインタビュー連載「サボリスト~あの人のサボり方~」。 フリーライターのスズキナオさんの著作には、あてもなくふらりと旅に出てみたり、家から5分の旅館に宿泊してみたりと、日常を軽やかに楽しむ術が詰まっている。当然、サボりの心得もあるに違いないと、その極意について聞いてみた。 スズキナオ 1979年、東京都生まれ、大阪在住のフリーライター。WEBサイト『デイリーポータルZ』などを中心に執筆中。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』、『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』、『家から5分の旅館に泊まる』(以上スタンド・ブックス)、『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』(新潮社)、『大阪環状線 降りて歩いて飲んでみる』(LLCインセクツ)などがある。 ライターになる前から、のんびりと街を散策していた ──今ではライターとして多数の著書を出されていますが、もともとは会社員をされていたんですね。 スズキ 30代半ばまで東京で会社員をしていました。でも、10年くらい会社員を続けてきたところで、それこそサボってきたツケが回ってきたというか、行き詰まりを感じるようになって。できればずっとダメな平社員でいたかったのに、部下ができたりして立場が変わってきちゃったんですよね。 ──いわゆる管理職を任されるようになると、ダメ社員ではいられない。 スズキ そうなんです。それで将来について考えていた矢先に、奥さんが大阪の実家の家業を継ぐという話が持ち上がったんです。だったら一家で大阪に移住して、自分のやりたいことをやってみるのもいいんじゃないかと、大阪でフリーライターとして活動するようになりました。それが2014年ですね。 ──それこそゼロからのスタートですよね。 スズキ はい。最初は会社員のときから記事を書かせてもらっていたWEBサイトの仕事くらいしかありませんでした。ネットで書いていた記事がだんだん人の目に触れるようになり、じわじわと「うちでも書いてみませんか?」みたいに声をかけてもらえるようになった感じです。 ──そのころから街歩きのような記事を書いていたんですか? スズキ ダラダラと街を散歩しながら、おもしろいものを見つけたらそのことについて書いて、取材ができたら取材もするような感じだったので、今とあまり変わらないですね。それ以外に書きたいこともなかったので、無理しなかったというか、できなかったと思います。 会社員時代からウロウロとお酒を飲み歩いたり、はしご酒したりするのが好きだったんですけど、おいしいお酒や料理を求めているわけではなくて、街や路地のたたずまいや、お店の雰囲気なんかを味わうのが好きでした。そこも今と変わらない。 ──たしかに、スズキさんの記事はグルメというよりは体験に軸があるイメージです。 スズキ そうなんですよ。だから、ライターとしての研鑽みたいなものが積まれていかないというか……(笑)。酒場の記事をよく書くのにお酒の銘柄にも詳しくないので、「え、これも知らないんですか?」ってよく驚かれます。 ──では、書くもの自体は変わらないなかで、状況が変わってきたのはどんなタイミングだったのでしょうか。 スズキ スタンド・ブックスから最初の本『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』を出してもらったことですね。ウェブのあちこちで書いてきたものをまとめて本にするお話をいただいて、最初はいったん無料で公開された記事を本にする意味がよくわからなかったんですけど、この本が名刺代わりとなって、自分のスタイルやキャラクターを知ってもらえるようになって。何度か増刷されるような反響もあって、おかげで自分にとってやりやすい仕事がいただけるようになりました。 ──今ではすごいペースで著書が刊行されてますよね。 スズキ 僕をスタンド・ブックスに紹介してくれた、酒場ライターのパリッコさんと一緒に記事や本を書くことも多いので、それで数が増えていったんじゃないかと思います。本を出せるなんて思っていなかった時期も長かったので、こうして振り返ってみるとありがたく感じますね。 ──パリッコさんとのユニット「酒の穴」といえば、「チェアリング」(※)が大きな話題になりました。 スズキ あれはもう我々の手を離れて、ひとつのアクティビティになった感がありますね。我が物顔で「あれは俺たちが考えたものだ」みたいなことは言わないようにしようと、パリッコさんとも話しています。コロナ禍によってお店で飲めない時期だったこともあって時代にフィットしたのかもしれませんが、我々は「チェアリング」と名づけただけで、やっている人は前からいたと思いますし。 (※)持ち運びできるアウトドア用のチェアを屋外の好きな場所で広げ、ぼーっとしたりお酒を飲んだりすること。スズキナオとパリッコによる飲酒ユニット「酒の穴」が「チェアリング」と名づけて提唱したところ、テレビなどのメディアに取り上げられるほどの反響を呼んだ。 名所を見終わったあとの旅も楽しい ──記事を書くために旅に出てみたものの、これといった出会いもなく「このままだとただ遠くに来ただけで終わってしまいそうだ」みたいなこともあるのでしょうか。 スズキ あります、あります。期待したようなことが起きなくても締め切りはあるので、ダラダラとその土地まで行く過程を書くとか、別のところでおもしろ味を作っていくしかなくて。でも、その感じも好きなんです。お店も何もない住宅街を歩いていても、コンビニで買ったお酒が飲めるちょっとした川べりにたどり着ければ、それはそれで気分がよかったりする。街歩きって、そもそもそういうものかもしれないですね。 ──たしかに、散歩ってそういうものですよね。でも、一応現地でもがいてみたりはするんですか? スズキ 本にもなった大阪の環状線の駅周辺をひと駅ずつ即興で旅するような連載では(『大阪環状線 降りて歩いて飲んでみる』)、ただの住宅街を2時間ぐらい歩いて「さすがに何も書けないかも……」と焦ったことはありました。でも、なんとかクリンチしていたら、住人の方にお話を聞くことができて。そうするとただの住宅街に見えた街でも、「自転車であの繁華街まですぐ行けるし、意外と便がいいんだな」とか、いろいろ見えてくる。そういう出会いでなんとかなってきた気がします。 ──住宅街にぽつんとある居酒屋とか、地元の人すらスルーしてしまうような場所を掘り下げるスズキさんのスタイルは、そういった粘りから生まれたところもあるんですね。 スズキ 何かしらお店があればしめたものですね。そういうところのほうが、かえって密な話が聞けたりするので。名店を調べて行くのも好きですなんですけど、それでは絶対に行けない場所もあるんですよ。 家から5分の旅館に泊まったのも、旅行をテーマにした連載の締め切りが迫ってきて、行ける場所が近所しかなかったという状況がきっかけでした。けっこう行き当たりばったりというか、せっぱ詰まって動き出すことが多いんです。でも、動いてみたら状況が好転するだろうと信じてやっている。 ──街歩きの際にチェックするポイントなどはあるのでしょうか。 スズキ 大衆酒場や銭湯が好きなので、そういった地元の方々が集まっていそうな場所を探します。そこでズケズケと話を聞くでもなく、なんとなく聞こえてくるその土地の情報をヒントにして歩いていく。ゲームしている感覚に近いかもしれないですね。 僕もミーハーなんで、大阪に旅行に行ったのなら、まず大阪城やグリコの看板は見たいんですよ。ただ、全部行き終わった4日目以降の旅もけっこうよくて。ヒマだしちょっと疲れてもいるからホテルの近くをウロウロしていたら、食べログでは評価されてないようなちょっといい店が見つかるとか、飽きてからの旅っておもしろい気がするんです。 ──3日目のカレーみたいな旅ですね。 スズキ まさにそうですね。3日目のカレーに初日からかぶりついてしまうこともよくあります(笑)。子供のころ、両親の故郷の山形に帰省するのがすごく好きだったんです。東京で新しいゲームソフトを買って遊ぶような楽しさとは違う、じわじわくるよさがあって。たまに行く田舎だったからかもしれませんが、優しい親戚に囲まれて、何もすることなくぼーっと過ごしているのが、幸せな退屈として記憶に残っています。それが原体験としてあるから、サボりグセがついたというか、ぼんやりした時間が好きなのかもしれないです。 ──それが仕事になっているからおもしろいですよね。「締め切りが近いから行かなきゃ!」って追われるように家を出て、お酒を飲んだりぼーっと街を歩いたりしているわけで。 スズキ そうなんですよ、その状況が発生しないと書きたくない。「これでいいのか?」という不安とも戦ってはいますが、ぼーっとできる仕事は気楽で楽しいですね。 ──記事を作るにあたって、ほかに大事にしていることはありますか? スズキ できれば自然に縁ができた土地を取材したくて。よそ者が「エキゾチックだ!」なんて外からのぞいている感じになるのがイヤなので、できるだけ自然な流れで入っていきたいんですよね。そうじゃないと自分らしい書き方にはならないような気がします。 最近では、日本の離島のイベントに行って琵琶湖にある「沖島」という有人島をおすすめされたという記事を書いたときに、沖島に縁のある方から「今度行きませんか?」って誘ってもらえたんです。1日巡っただけですが、自然な縁で行けたのがうれしかったし、島自体もおもしろかったですね。 ──そういった中で印象的な出会いを挙げるとしたら、どんなものがあるのでしょうか。 スズキ 『デイリーポータルZ』で記事を書いた、大阪市此花区にある千鳥温泉っていう銭湯ですね。洗い場の鏡にくっついている「鏡広告」の広告主を募集していたんですよ。銭湯の方がアイデアマンで、新たに街のカフェやレストランから広告を募ったら、意外と広告主になってくれる人がいるんじゃないかと思ったそうで、その広告ができるまでの過程を追いました。 ──実際に『デイリーポータルZ』の広告を作ったんですよね。 スズキ そうです。もう亡くなられてしまったんですけど、当時90歳になる松井さんという字書き職人さんがいて、手書きで文字を入れてくれました。独学による手書きとパソコンを組み合わせたレタリングの手法や戦争体験とか、松井さんにいろいろお話を聞くことができて。作業の工程なども見せていただき、すごく貴重な体験でしたね。 サボりの灯を絶やしてはいけない ──幼少期にサボりグセが刷り込まれたとおっしゃっていましたが、やはりそのクセは抜けていないのでしょうか。 スズキ はい、僕はもう本当にサボり人間です。締め切り当日になってもなかなか向き合わず、自分でもイヤになるくらいサボってしまいます。なんでだろう(笑)、追い込まれれば追い込まれるほどサボりが楽しくなっちゃって。一応やる気になる瞬間を待っている状態ではあって、うっすら記事の構成を考えたりしてるんです。それが固まるまで机に座って向き合っているよりは、散歩してるほうがいいような気がするんですよね。 ──いわゆる“寝かせる”タイプで、頭の中で記事の内容をなんとなくイメージしているから、書き出せさえすれば書ける、みたいな。 スズキ その時間も大事な気がして。「こういう話から始めようかな」と出発点を頭の中で何回も試して、どれがいいか考えながらサボってるつもりではあります。先ほどお話ししたように、僕は「なんでそこに行くことになったのか」から書きたいほうなので、きっかけとなった出会いから出発に至るまでのルートをたどっていくんですね。読む人にしてみたら、「なかなか行かねーな」って感じかもしれませんが(笑)。 ──罪悪感を抱くようなサボりではなく、積極的に息抜きをするためのサボりはありますか? スズキ ありますね。原稿を書き上げたあと、一回サボりを入れてから推敲したほうがいいと思うんですよ。書ききれなかった部分や配慮の足りなかった部分などが見えてくるなど、別の視点が生まれるので。だから視野が狭くならないように、一回飲みに行ったり公園を散歩したりしています。外の空気を吸って、全然自分と関係ない世界を見ておくことが大事なんでしょうね。 ──ちなみに平社員を満喫していた会社員時代は、どんな感じだったんですか? スズキ 僕と同じくらいやる気がない同僚と、いつも仕事帰りに飲みに行っていました。会社があった渋谷の街を歩きながら、缶チューハイを飲むスタイルで。そのせいか、会社ではいつも軽い二日酔いか寝不足の状態で、「こういうときは寝たほうが効率がいいんだよ」って自分に言い聞かせては、トイレや外のベンチなんかで寝てましたね。 その後、田町にオフィスがある会社に出向したんですけど、そっちは渋谷のときのようなゆるさがなくて。節電のために定時でオフィスの電気が消されるのに、それでも仕事してる人がいるような感じでした。でも、僕は夕日がきれいだったら、仕事の手を止めてみんなで窓の外を見たりしたほうがいいと思うんです。 ──なんだか『釣りバカ日誌』みたいな話ですね(笑)。 スズキ 本当にそういうつもりでしたね。みんなの息抜きキャラとしてサボり方を教えたい、「このくらいサボっていいんだ」とみんなに知らせる存在として自分はここにいるんだ、みたいな。でも、気がついたら怒りの対象になっていて……。 もっと科学的にサボりの大切さが研究されないとダメなのかな。海外の権威に言ってほしいですね、「ストレスは作業効率を低下させるから、会社には仮眠スペースを設けなさい。夕日がきれいだったらみんなで眺めなさい」って。 ──みんながスズキさんの本を読めば、少しは風向きも変わるような気がします。 スズキ そうなったらうれしいですね。大げさに言えば、世の中がせわしなく息苦しくなっていくなかで、逆サイドのゆるみ側に人を引きずるような仕事をしている気持ちもなくはないんです。本当に微力ではありますが、パリッコさんみたいな仲間と一緒にせめてもの抵抗をしている気がします。 ──「酒の穴」は政治団体だったのかもしれない(笑)。 スズキ タバコもそうですけど、お酒だっていつ自由に飲めなくなるかわかりませんからね。サボりだって禁止になるかもしれない。 ──本当に、今後もサボりを啓蒙していただきたいです。微力ながらこの連載でもお手伝いしていきますので。 スズキ そうですね。サボりの価値を訴えながら、上手にサボる。そういう洗練されたサボり方も提案してきたいと思います。 撮影=石垣星児 編集・文=後藤亮平
-

「仕事も趣味も“収集”をモチベーションにする」宇垣美里のサボり方
クリエイターの活動とともに「サボり」にも焦点を当て、あの人はサボっているのか/いないのか、サボりは息抜きか/逃避か、などと掘り下げていくインタビュー連載「サボリスト~あの人のサボり方~」。 今回お話を伺ったのは、フリーアナウンサー・俳優の宇垣美里さん。ドラマ出演やラジオパーソナリティ、コラムの連載など、さまざまな顔を持つ宇垣さんに、そのスタンスや切り替え方を聞いた。 宇垣美里 うがき・みさと 1991年、兵庫県生まれ。TBSアナウンサーとして数々の番組に出演し、2019年に退社。現在はドラマやラジオ、雑誌、舞台出演のほか、執筆活動も行うなど活躍の幅を広げている。『週刊文春』(文藝春秋)、『女子SPA!』(扶桑社)などでマンガや映画のコラムを連載中。著書に『今日もマンガを読んでいる』(文藝春秋)、フォトエッセイ『風をたべる』(集英社)など。 ラジオは自分の思いを話すことができる場所 ──現在はさまざまな分野で活躍されていますが、やはりTBSでアナウンサーをされていた経験が、活動の土台になっているところはあるのでしょうか。 宇垣 そうですね。中でもTBSにはラジオがあったので、ラジオで自分の思っていることや人におすすめしたいことなどをしゃべってきた経験は大きいです。こうしたインタビューでもなんでも、振られた質問やテーマに対してすぐに返すという反射神経は、TBS時代に鍛えられました。 また、何か心に残るものがあったら、それについてどうしゃべろうか考えたり、なぜそれがよかったのか、どこが響いたのか、言語化したりする習慣がついたのも、あのころの経験によるものだと思います。 ──TBSラジオというラジオ局もあることで、アナウンサーのみなさんがテレビとラジオ、両方出演されているのはTBSならではですよね。 宇垣 アナウンサーが自分の思ったことを話す機会は、なかなかないんです。番組にもよりますが、ラジオでは「あなたはどう思ったの?」と聞かれることが多いので、とても幸運だったと思っています。私は比較的早いうちからラジオの仕事につくことができて、すごくありがたかったです。 それに、スタッフさんから「あなたは何か書いてあることを話すよりは、それに対してどう思ったのか話すことのほうが好きなんだね」と言われたこともあり、ラジオは自分に向いているメディアなんだと思うようになりました。アナウンサーとしては、いいことなのかどうかわかりませんが。 ──ラジオでの経験というと、フリーになった現在も曜日パートナーを務められている『アフター6ジャンクション』(※)の存在は大きいのではないでしょうか。 宇垣 本が好きです、映画が好きです、舞台が好きです、マンガが好きですと言っていたら、アトロクというカルチャー・キュレーション番組を担当させていただけたので、好きなことを言い続けるのって、大事だなと思いました。 今ではもう実家みたいな存在です。番組もパーソナリティの宇多丸さんも、私たち曜日パートナーのことをひとりのパーソナリティとして大事にしてくださっていて、「この人が輝くもの、おもしろいと感じるものはなんだろう」と考えてくれるんです。だから、曜日によってカラーが全然違うんですよね。一番自分らしくいられて安心できる、とても大切な番組です。 (※)RHYMESTERの宇多丸がパーソナリティを務めるTBSラジオの生ワイド番組。通称『アトロク』。現在は『アフター6ジャンクション2』として放送中。 ──リスナーも、この番組を通じてパートナーの方々の個性を見出し、親しみを覚えているように感じます。 宇垣 そうですね。ある意味では甘やかされているとも思います。でも、たとえばお酒好きの日比麻音子アナウンサーに『おんな酒場放浪記』(BS-TBS)のお仕事が来るようなことって、なかなかないじゃないですか。知られざるパートナーの一面に光を当ててもらえている。私も番組で発信していたから映画のコメントや本のお仕事をいただけるようになったので、すごくありがたい場所だと思っています。 ──宇多丸さんから影響を受ける部分もありますか。 宇垣 それはもう、こんな大人になりたいと常々思っていて。私より忙しいのに、あまりにもたくさんの映画や本、ゲーム、ライブなどに触れていて、意味がわからないです(笑)。あと、インプットを続けているからこそ、自分の考え方が古びていないか常に懐疑的で、だから「おじさんみたいなことを言う!」と感じることが全然ない。それって奇跡みたいなことだなと思っています。私ですら若い世代の人たちに寄り添えているのか、ずっと自信がないのに。 文章の自分が、一番ウソがない ──最近はコラムやエッセイを書く仕事も多いですよね。書くことには立ち止まったり迷ったりしてしまう場面もあるかと思います。文章を書くことについて、どう思われていますか。 宇垣 もともと記者を志望していたくらい、書くことは好きだったんです。それが巡り巡ってお仕事になり、人に読んでもらって褒めていただけて、本当に運がいいなと思います。話す言葉ってパッションが伝わるぶん、思ってもない言葉が出てきたり、強すぎてしまったりすることもあるじゃないですか。でも、書くことは考えたり見返したりして推敲するし、編集者さんの意見や校閲も入るので、伝えたいことについて「これで勘違いされるなら、もうしょうがないよね」と思えるところまで研ぎ澄ますことができる。だからこそ、一番ウソがない、私自身だなと思います。 ──ご自身の濃度が高い文章を世に出して、人に読まれることについてはどう感じられていますか? 宇垣 エッセイはまた違ってきますが、映画評やマンガ評、書評などでは基本的に作品について書くので、あまり気にしていないかもしれません。ただ、私は作品について学術的に書くことはできないので、なぜ心に刺さったのか、自分を介して書くしかない。そういう意味では自分のことを書いているんですけど、書評なら「頼むからこの本を読んでくれ!」という思いがまずあって、そこから読んでくれた人に刺さったらうれしいという気持ちが大きいですね。 ──「自分」の出し方以外にも、ジャンルによって意識の違いはありますか? 宇垣 メディアによって読み心地は変わるべきだと思っています。たとえば『週刊プレイボーイ』(集英社)で連載しているエッセイなら、読んでいて楽しいリズムや読みやすさにこだわるなど。文章がリズミカルであることを大事にしていて、読み心地のために多少創作することもあります。 人の本を読むときも、文体がすごく気になるんですよ。同じことを書いているのにその人らしい文章になるのは、文体にその人が宿っているからだと思うので、自分の文章でも人の文章でも、そこはすごく意識していますね。 ──文体以外にも、エッセイだと「何に引っかかるか」といった着眼点にも個性が出ると思います。宇垣さんはどんなことが心に残りやすいと思いますか。 宇垣 プレイボーイは毎週締め切りがあるので、ネタになると思ったものはすぐに書いちゃうんですよね。ただ、心惹かれたエンタメについては、観ている人と観ていない人がいるので、よっぽど好きでない限りはあまり扱わないです。なので、人が「あるある」と思ってくれるような日常の些細な出来事や、「私だけじゃなかったんだ」と思ってもらえるような自分のダメな瞬間などを書くようにしています。 ──なんだか毎週エピソードトークを用意しているラジオパーソナリティみたいですね。やっぱり締め切りの数日前からソワソワしたりするものなのでしょうか。 宇垣 いや、だいたい締め切りの日になって「書くことなーい!」と絶望することがほとんどです。だから、前回の原稿を書くまでに時間がかかりすぎたときは、その翌週に先週いかにダラダラしていたか書いたりすることもあります。あとは、自分のめんどくさい部分について、心に引っかかったことだけメモしておいて書くこともありますね。たとえば初めて会った人に「どういう性格なんですか?」と聞かれて、どういう性格かひと言で答える人ってちょっとヤバくないか、と思ってしまったこととか。 けっこうメモ魔で、3年日記っていう、1ページが3年分に分かれている日記もずっと続けています。1年前、2年前に書いたことと見比べられるので、「うわ、1年前と同じこと言ってる」みたいな発見でエッセイが1本書けるんですよ。 自分の中の引き出しを埋めていきたい ──宇垣さんはラジオや執筆活動以外にも幅広く活躍されていますが、仕事ごとに求められる役割について、どのように向き合っているのでしょうか。 宇垣 特にテレビのバラエティなどはある種のキャラクターを求められることもありますが、それはお仕事としてできるだけ応えるようにしています。ただ、自分の中から出てこないもの、自分の倫理や思想に反するものはできないので、そこは厳しくジャッジしていますね。5センチぐらい思っていることを30センチにすることはできますが、0から5センチにしてしまったらウソになるので自分が悲しくなるし、責任も取れないです。 ──たしかに、宇垣さんは自分なりの倫理観を大事にされている印象があります。では、そういった求められることと資質がマッチしていると感じる仕事や、自分からやってみたいと思う仕事はありますか。 宇垣 私は表現することがすごく好きなので、書くことでも、しゃべることでも、番組に出ることでも、演じることでも、その媒体に合わせて自分が出したいものを表現するのが向いているなと思っています。 あとは、自分の中の空いている引き出しを埋めるのが好きで、やったことのないことをクリアしていくと、すごく豊かな気持ちになります。ちょっと収集癖に近くて、やったことのないことはなんでもチャレンジしてみたいし、食べたことのないものも食べたいし、行ったことのないところに行きたい。それが自分の原動力になっていますね。 ──珍しい引き出しを埋めた経験としては、どんなものがありますか? 宇垣 演技のお仕事も、最初は空いていた引き出しのひとつで。バラエティ番組のようなある瞬間に集合してパッと解散するような現場と違って、ドラマや舞台は長いスパンをかけてみんなで作り上げていく。チームとしてひとつの作品を作り上げていくという経験は新鮮でしたし、自分はそういうことが好きなんだという発見がありました。 ──では、今後埋めてみたい引き出しは? 宇垣 作る側ですね。映画やドラマの監督、小説家といった0から1を生み出す仕事にすごくリスペクトがあるからこそ、そんなに簡単にできるものではないだろう、と自分の中でハードルが上がってしまうのですが。 ──勝手ながら、小説はすごくイメージできる気がします。 宇垣 短編を書いたことはありますが、自分の中に蓄積がありすぎて、何をやってもダメだと思ってしまいそうなんですよ。自分の中にいろんな方の影響を感じてしまったり、すでに書かれているなと思ったり、そこをどうやって乗り越えていくかですね。あとは、虚実を織り交ぜるエッセイから、小説というウソへの一歩が踏み出せるかどうか。そのあたりはまだわかりませんね。 仕事としても、サボりとしても、本を読む ──原稿の締め切り前についダラけてしまうとおっしゃっていましたが、サボりグセはあると思いますか? 宇垣 ありますね。お仕事する時間はできるだけ短く巻いていくのが好きなんですけど、書くことだけはやる気スイッチ頼みすぎるっていう。結局、締め切りの日にため息をつきながら構成用のノートを広げることが多いです。 そこからまずノートに書きたいことを並べて、書く順番をつけていくんですけど、それができたところで一回「終わった〜」と思ってしまうんですね。それでダラダラしたり、本やマンガを読んだりして、日付が変わってから「うわーっ!!」と慌ててパソコンを開くこともよくあります。それもまた終わりが見えてくるとできた気になって、紅茶を淹れようとしたまま紅茶の並びを入れ替え始めたり……。 ──テスト前の学生みたいですね(笑)。よくわかります。本を読むような腰を据えたサボり方はなかなかできませんが。 宇垣 映画は受動的に観るので、家だとどうしても気が散ってしまう。でも、本は自分で目を動かしながら能動的に読むので、その労力によってムダな力がそがれるというか、無心になって作品に集中できるんですよ。違う世界にダイブしているような感覚ですね。 ただ、ちゃんとお仕事に関係のある本を読んではいるんですよ。エッセイの参考に人の作品を読んでみるとか、書評を書こうとして著者の昔の作品も読んでみるとか、帯コメントを依頼されている作品を読み返すとか、今読む必要があるかどうかは別として、読む理由はあるんです。 ──読書が仕事であり趣味でもあるから、読み分けることがリフレッシュにもなるんですね。 宇垣 そうですね。単に集中力がないだけかもしれませんが、ずっとパソコンの画面をにらみつけているくらいなら、気持ちを切り替えてほかのことをやっちゃったほうがいいような気もして。それに、「いつか絶対に原稿はできる」という自分に対する謎の自信と信頼があるんです(笑)。それが「今日中にやる」から「寝るまでにやる」、「編集者さんが起きるまでにやる」に変わっていったとしても。 ──では、読書以外で、もっとシンプルに息抜きや楽しみになっているものはありますか? 宇垣 1日休みがあれば日帰りで広島に行ったりするくらい旅行も好きなんですけど、最近ハマっているのは、シルバニアファミリーを集めることです。コンビニで売っているのを見て「かわいいな」と買ってしまったのが沼の入口で、ポップアップストアや専門店にまで行くようになりました。 シマエナガの服を着ているアザラシの赤ちゃんとかがいるんですよ。そんなかわいくて平和な世界を眺めてニコニコしています。あとは、ダム。ダムを見に行って、ダムカードを集めるのが好きです。 ──ダムカード? 宇垣 ダムに行くと、そのダムの写真や歴史、情報が載ったカードがもらえるんですよ。大きな人工建造物がすごく好きな上に、収集癖も満たされるところがいいですね。ダムを見ているうちにだんだん解像度が上がってきて、形状や仕組みの違いが見分けられるようになってきました。この前、ついにダムのお仕事もいただいて、またひとつ好きと言っていたものが仕事につながり、ダムカードまでもらえてうれしかったです。 撮影=石垣星児 編集・文=後藤亮平
-

「その時々の感じで生きているのが失敗につながって、その失敗がまた気持ちの揺れ、ひいては言葉や文になる」小原晩のサボり方
クリエイターの活動とともに「サボり」にも焦点を当て、あの人はサボっているのか/いないのか、サボりは息抜きか/逃避か、などと掘り下げていくインタビュー連載「サボリスト~あの人のサボり方~」。 エッセイ集『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』を自費出版するや、各方面から反響を呼び、注目の作家となった小原晩さん。そんな小原さんが語る、執筆のきっかけや心が動く瞬間、豪快なサボり方。 小原 晩 おばら・ばん 1996年、東京都生まれ。作家。2022年、デビュー作となるエッセイ集『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』を自費出版する。2023年、商業出版として『これが生活なのかしらん』(大和書房)を発売。2024年には、『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』が実業之日本社より商業出版される。現在は、多数の媒体でエッセイや小説を連載中。 何もわからず作った本が、1万部のヒットに ──そもそもは、なぜエッセイを書いてみようと思ったんですか? 小原 エッセイをよく読んでいたから、自然とそうなりました。ただ、もともと文学少女みたいな感じだったわけではないんです。18歳で就職して、すごく忙しくしている間に、中学生のころから好きだったピースの又吉直樹さんが芥川賞作家になっていたんです。19歳くらいのころ、仕事を辞めてフラフラしていたときに、下北沢のヴィレッジヴァンガードで又吉さんの作品や好きな本が特集されている「又吉直樹の本棚」を見つけて、『東京百景』(KADOKAWA)というエッセイ集を手に取ったんです。それがもうすごくおもしろくて、又吉さんのほかの作品や、又吉さんが好きだと言っている本などを読むようになり、読書が好きになっていきました。 ──とはいえ、文章を書き始めるのも、書き切るのも簡単ではないと思うのですが。 小原 自分で書いてみて、書くことの難しさを感じたし、改めて今まで読んできた作家さんのことを尊敬しました。でも同時に、自分で書いたり、人の作品を読み返したりすることで、「こういう構成になってたんだ」とか、「こういう仕組みがおもしろさにつながるんだ」とか、いろいろ気づくようになったんです。そうすると、書くことも、読むことも、どんどんおもしろくなって。 ──そこからいきなりデビュー作の『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』を自費出版で作ろうと思ったのは、なぜでしょうか。 小原 それも仕事をせずに貯金を切り崩しながらフラフラしていたころなんですけど、あと1〜2カ月で貯金もなくなるとなったときに、「最後にやり残したことをやろう」という気持ちになって。自費出版が「リトルプレス」と呼ばれていて、自分で本が作れることは知っていたので調べてみたら、200部の本を5万円で作れることがわかったんです。それで、本を作ることにしました。 ──そうなると、書くこと以外も自分でやらなきゃいけないわけですよね。 小原 そうですね。デザイナーの友達なんていなかったので、表紙の絵だけ絵描きの方にお願いして、あとは自分でわけもわからないまま作っていました。結局、本文の字がすごく小さかったり、失敗もたくさんありました。 ──そこからは、自費出版本を扱ってくれる書店などに売り込んでいったと。 小原 はい。できる限りお客さんとして足を運んで、「自分の本が合うかな?」とか、「置かれるならここかな?」とか考えながら見て回りました。それから、置いていただきたい本屋さんに見本をお送りしていいかメールしていきました。 ──反響を実感するようになったのは、どんなタイミングだったのでしょうか。 小原 独立系書店を中心に、本が売り切れて再入荷するようなことが何回かあったんです。たぶん、独立系書店と呼ばれる本屋さんには、店主の目利きを信用しているお客さんたちがいるので、そういう方々が買ってくれたりするようになったんだと思っています。最初は200部だったのが、たしか1年で5000部ぐらいまでいって、たまたま本を買ってくださったダウ90000の蓮見翔さんに、テレビプロデューサーの佐久間宣行さんのYouTubeで紹介していただいたことで、1万部くらいになりました。 最悪な思い出も、一歩引いたら喜劇になる ──1万部も売り上げたことで、『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』の商業出版のお話が持ち上がったのでしょうか。 小原 いえ、発売して半年くらいでお話はいただいていたんですけど、別の作品を出版する話が進んでいたので、一度待ってもらっていました。でも、そうしている間に1万部に達して、全部自分でサインして発送していたので、もう無理だとなってしまって。 ──全部にサインしていたんですか!? 小原 9000部くらいまではサインしていました。だから本当に大変で……。お仕事の話もたくさんいただくようになったのに、書く時間が取れなくなったのもあって、急いで商業出版のお話を進めていただきました。 ──状況が一気に変わって、とにかく大変だったと思いますが、たくさんの方に読んでもらったことで、うれしい反応や意外な発見などはありましたか? 小原 編集者の方に言っていただいたことなんですが、「人生は寄りで見ると悲劇だが、引きで見れば喜劇である」という言葉があるじゃないですか。でも、「小原さんの場合は、寄りで見ても喜劇だ」と言ってくださって、なるほど、うれしいな、と思いました。 ──たしかに、深刻になってもおかしくない場面でも、そう感じさせないところがある気がします。ご自身でも意識されていた部分はあるのでしょうか。 小原 特にエッセイに関してはそうですね。エッセイは基本的に自分語りではあるんですけど、だからこそ自分の人生や生活をどう表現するのかを大切にしています。つらかった過去をつらい気持ちのまま書いても、自分の文章ではあまり魅力的にならなかったので、もう少しトーンを意識してみよう、という感じというか。 ──結果としてそれが作風につながっているわけですね。自分の人生を表現するという点では、美容師時代や家族、恋愛について書かれていますが、そこに抵抗などはなかったのでしょうか。 小原 書くこと自体への抵抗はあまりなかったです。『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』を書いたときは、それこそ又吉さんの『東京百景』が頭にあって、「東京の生活」をテーマにしていました。ただ、同じようにある場所に付随する思い出を書くのはどうかと思いましたし、又吉さんのように書けるわけでもないので、自分が一番おもしろくなるように書いていこうと考えた結果、自分なりの「東京」をふくらませた感じですね。 ──では、書きながら過去と向き合うなかで、感じたことなどはありますか? 小原 書き始めはものすごくつらいんですよ。「自分の過去って最悪だ」「なんて自分は浅はかな人間なんだ」「どうして人を傷つけるようなことをしたんだろう」「なんだその謎の自信は!」「自分にはおもしろいところはひとつもない」とか考えて、最悪な気持ちになります。そこからあきらめがついて、「自分はつまらない人間だ」と開き直るゾーンに入ってやっと書き始めるんです。 ──一つひとつは苦い思い出として存在しているんですね。 小原 よく明るい人間だと思われて、「こんなふうに生きられたらいいな」と言ってもらえることもあるんですけど、それは、書くことで、過去を捉え直しているからかもしれません。ズタズタになった思い出でも、人には笑いながら話せたりするじゃないですか。悩みを話し始めたはずなのに、なんか話してたら笑ってもらえて、そしたら自分も笑えてくる。そういう感覚に近い気がします。 純粋さがエッセイの素材を引き寄せる? ──エッセイの中には、日常におけるちょっとした出来事を描いた作品などもありますが、気になったことはずっと心に残って記憶されていたりするのでしょうか。 小原 最近はメモを取ったりするようにもなりましたが、最初の作品を書いたときは、思い出のある場所に実際に行ったり、聴いていた音楽を聴き直したりして、当時の出来事を思い出していきました。基本的には、日常のディテールに興味があって、そういうことばかり覚えています。逆に、友達とディズニーランドに行ったことはすっかり忘れていたりするので、非日常にはあんまり興味がないのかもしれないです。 ──ディズニーランドの思い出を忘れちゃうんですか? 小原 写真を見せられても、何も思い出せないくらい。でもやっぱり、どうでもいいことは覚えてるんです。この前、ひとりでお蕎麦屋さんに行ったときに、そこにいたおばあちゃんが「八海山ひとつください」ってお酒を注文したら、一緒にいたおじいちゃんが「“八海さん”じゃなくて、“八海山”ね」って言ったんです。「そんなの知ってるわよ」ってみんなで笑ってるんですけど、何がおもしろいのかさっぱりわからない。でも、なんか「それでいいんだよな」っていう気持ちになって。そういうことのほうが心に残って覚えてるんですよね。 ──それはまさにエッセイ的なアンテナが日常的に張られているのかもしれないですね。同時に、小原さんはちょっと変な人に遭遇したり、おかしなことに巻き込まれたりする頻度も高いように感じるのですが、そういうものを引き寄せてしまうところはあると思いますか? 小原 自分ではあまり思わないですね。自分の人生で起こることは、自分にとっては普通のことなので。ただ、(歌人/エッセイストの)穂村弘さんとトークイベントでご一緒したときに、「純粋な人間ほど、イヤな目に遭ったり、変わった人を惹きつけたりするんだ」みたいなことを言ってくださって、「純粋だったのかな」って思うようになりました(笑)。 ──純粋な人だからこそ、ちょっと無防備だったり、人との距離感が独特だったりするのかなと思うと、納得できる気がします。 小原 純粋なんて、そんないいものだったらいいんですけどね。自分では最悪な人間だと思っているので……。 眠くなったら寝る。何時でも、何時間でも ──失礼なのですが、小原さんにはサボりのネタもあるような気がしています。性格的にサボりがちだなと思うようなところはありますか? 小原 基本はサボってますね。今はサボっている時間も創作の時間といえるので、「ぼーっとすることも大事だから」と自分に言い訳することもありますし。でも、生活と創作が密接なところにあると、線引きが難しくなってきますよね。 ──そんななかでもダメなサボりだと思うのは、どんなことでしょうか。 小原 一番イヤなのは、短い動画ばっかり観てしまうとき。YouTubeでもInstagramでもXでも、短い動画がずっと出てくるシステムになってるじゃないですか。興味もないのにずっと観ちゃったりするので、あのサボりだけは自分の中で悪ですね。世の中からなくなればいいなと思ってます。 ──では、よしとするのはどんなサボりですか? 小原 飲みに行って本を読んだり、散歩に出たり、スーパー銭湯に行ったり、買い物に出かけたりすることですかね。出先で作業しようという気持ちもあるので、一応パソコンも持っていきます。結局開くことなく、焦りだけを残して帰ってくるんですけど(笑)。 ──あるあるですよね、わかります。より後悔のない積極的なサボりとして、リフレッシュに近い気持ちでやることはありますか? 小原 昼寝です。眠くなったら寝る。何時でも、何時間でも、3度でも4度でも寝る。夜眠れなくなっても構わない。 ──カッコいい。バッチリ5時間ぐらい寝ちゃうこともあるんですか。 小原 全然あります。起きたら外が真っ暗で、「ふふふ、こんなことになっちゃった」と思います。 ──睡眠のサイクルがぐちゃぐちゃになりそうですが……そういった世のことわりも気にしない。 小原 そうですね。特に夏の昼間は、たまったもんじゃないぐらい暑いじゃないですか。だから、昼間に起きていても仕方がないっていう気持ちがあって。基本的に夕日が落ちるころに起きて、また朝日が出たときに眠る生活になります。昼間に連絡がつかなくなるのは申し訳ないと思うんですけど。 ──自分では怖くてできそうにありませんが、ちょっと理にかなっているような気もします。なにより自由な感じがしますね。 小原 でも、ルーティンには憧れてるんですよ。モーニングルーティンなんて、めちゃくちゃ憧れてますから。やっぱり「何時に起きて何時に寝る」って徹底したほうがいいんでしょうけど、ただ、その時々の感じで生きているのが失敗につながって、その失敗がまた気持ちの揺れ、ひいては言葉や文になるとも思ってるんですよね。 撮影=石垣星児 編集・文=後藤亮平
-

「人生における“サボりの期間”が、その後の糧になる」下田昌克のサボり方
クリエイターの活動とともに「サボり」にも焦点を当て、あの人はサボっているのか/いないのか、サボりは息抜きか/逃避か、などと掘り下げていくインタビュー連載「サボリスト~あの人のサボり方~」。 色鉛筆による生き生きとしたポートレートなどで知られる画家/イラストレーターの下田昌克さんは、近年のライフワークとして、キャンバス地で恐竜の被り物を制作している。恐竜の化石が放つ本質的なカッコよさをポップに落とし込んだ被り物を「衝動的に作り始めた」という下田さんに、その創作の経緯などについて聞いてみた。 下田昌克 しもだ・まさかつ 1967年、兵庫県生まれ。1994年から2年間、世界各国を旅行。旅行の絵と日記をまとめた『PRIVATE WORLD』(山と渓谷社)を出版し、絵の仕事を始める。2011年よりプライベートワークでハンドメイドの恐竜のヘッドピースを作り始める。2018年、COMME des GARÇONS HOMME PLUSがAWのメンズコレクションのショーにて、そのヘッドピースを採用。2021年、Virgil Ablohからの依頼で制作したマスク、ヘッドピースがOff-White/Fall 2021/Paris,Franceで使われる。絵本『死んだかいぞく』(ポプラ社)が、イタリアにてボローニャ・ラガッツィ賞2024特別部門「海」で特別賞(Special Mention of the 2024 BolognaRagazzi Awards for The Sea – 2024 Special Category)を受賞。2024年には、音楽劇『死んだかいぞく』が上演された。 何もうまくいかなくて、海外を放浪した2年間 ──下田さんはどんな人に影響を受けて、アートやデザインの世界に興味を持ったのでしょうか。 下田 子供のころは手塚治虫が好きでしたね。10代になってからは、ジョージ・ルーカスやスティーブン・スピルバーグの映画を意識して観るようになりました。『スター・ウォーズ』や『E.T.』とか、当時は「これが観たかったんだよ!」っていう感じで。 ──その後、美術系の学校に進まれますが、最初からアーティストを志していたわけではないそうですね。 下田 だって、なれると思わないじゃん! 子供のころは絵を描けば褒められたけど、美術の高校に行ったら、クラスで一番ビリで、勉強もできなくて……。クラスのみんなが美大を目指してるのに、ひとりだけ先生から美大進学の話を一回も聞かれないまま卒業したくらいだったので、絵で仕事ができるとはとても思えなかったです。 それで、会社員になったんですけど、全然うまくいかない。結局、会社をクビになったから、親のお金でデザインの専門学校に行かせてもらったものの、就職したデザイン事務所も1年でクビ。それからアルバイトをいろいろやってみたけど、それも全然続かない。本当に何をすればいいのかわかんなくなって、一度、働くということから離れてみようと思いました。 ──そこから、海外を放浪することになったと。 下田 最初は国内を自転車でブラブラ回ってたんですよ。まだ若かったから、人の家に泊めてもらったり、食べ物を食べさせてもらったり、アルバイトさせてもらったりしながら過ごしていたら、初めて貯金できて、100万円くらい貯まった。 ──すごいですね! 下田 それで、そのお金を持って海外旅行に行ったんです。なんとなく日記でも描きそうな気がしたので、スケッチブックと色鉛筆をカバンに入れて。中国からチベット、ネパール、インド、ヨーロッパなんかを回ったんだけど、時間を持て余してやることがなくなったときでも、日記帳に撮った写真を貼ったり、絵を描いたり、日記を書いたりしていました。学校の宿題の日記なんて一度もちゃんとつけたことないのに。旅行していた2年間で、出会った人たちの絵は500枚くらい描いたと思います。 下田さんが海外を旅したときの日記 ──下田さんの視点で旅の空気感がパッケージングされていて、スクラップブックみたいな作品になっていますね。中でも人との出会いは大きかったんですね。 下田 風景を描いてみたりもしたけど、人としゃべりながらその人の絵を描いたりするのが楽しくなって。そこで、「仕事にするのは無理だとしても、こういうことを一生続けていけたらいいな」ってなんとなく思うようになった気がします。 とにかく絵の仕事に専念してみようと「自称絵描きに」に ──ポートレートに関しては、このころからあまり作風が変わらないように思いますが、旅の中で生まれたスタイルなんですかね? 下田 そうですね。ずっと変わらない。持ち運びやすいし、すぐ描き始められるし、どこでも手に入るし、片づけもいらないから、色鉛筆は自分には合ってたと思います。人の描き方も、目の前に座ってもらっているから時間がかけられないし、向かい合ってずっとしゃべりながら描くから正面の顔ばっかりになって、こういう絵になった。 ──それがきっかけで、絵の仕事をされるようになったんですね。 下田 旅行から帰ってきて、写真や絵をまわりの友人などに見せていたら、人づてに週刊誌の連載の話をいただいたんです。もちろん、最初は絵だけじゃやっていけませんでしたよ。でも、絵を描くことで関わったデザイナーさんや挿絵を描いた小説家の方など、会う人たちがおもしろい人ばかりだったので、もっと絵の仕事をやってみたいと思うようになって。 それで、アルバイトの求人もなくなってきた30歳のタイミングで、絵の仕事だけで一度やってみようと思いました。ダメだったら、またバイトして考えようかな、くらいで。 ──「描きたい絵を描く」のと「仕事として絵を描く」のは違うと思いますが、「とにかく絵を仕事にする」という気持ちが大きかったのでしょうか。 下田 そうですね。絵の仕事ならなんでもよかったんですけど、きっかけが旅行中に描いた絵だったから、自分の描きたいものを作らせてもらえることも多かったです。小説の挿絵とか、題材があって「何を描こうか」って考える仕事も大好きですし。自分発信だけでやるほど中身もないから(笑)、両方できてよかったと思ってます。 ──自分から発信する場合、何かテーマや題材などはあったりするのでしょうか。 下田 作りたいものがあって、それをどうやってかたちにするか考えたり。たとえば、最初の絵本は、旅行中に描いた風景画をつなげていったらお話になりそうな気がして、絵本を作ってみたいと思って。とりあえず自分で1冊作ってみて、コピーして製本して出版社を回って、「これが作りたいんだけど、どうしたらいい?」って聞いて回りました。 ──物語を考えたりするのも好きなんですか? 下田 好きは好きだけど、その風景画の絵本のときは、とりあえず絵だけで作ってみて、本になることが決まったときに「文章どうしよう」って聞かれて。誰か文章を書ける人がつけてくれるもんだと思ってたら、「僕が書くの!?」みたいな(笑)。先に絵でお話を作っちゃったから、自分しかいないといえばいないんだけど、本当に何も知らないまま作ってたので。 欲しいものがなかったから、自分で作ることにした ──恐竜の被り物も、なんとなく興味の向くまま手を動かしたことが制作のきっかけらしいですね。 下田 2011年に、恐竜博に行ったのがきっかけで。久しぶりに見た恐竜の骨格標本がすごくカッコよくて、買い物をする気満々でミュージアムショップに行ったら、そのときは欲しいものが何もなくて、図録だけ買って帰ったんです。 家に帰ったら、絵を描くキャンバス用の布が丸めて置いてあって、なんとなくそれを切ってトリケラトプスの角とかを作ってみたんですよね。なんとなくだから、サイズも自分が基準になってて、なんか被れそうなものができ上がったから被ってみたら、「おお〜っ!!」と思って。2次元にはない、原始的な興奮を感じた気がしたんです。 ──絵では表現できない何かを感じた。 下田 しばらくは絵も描かずに、ずっと作ってましたね。 ──キャンバス地で恐竜の被り物を作るのも、意味やテーマはないんですね。 下田 そう。たまたま恐竜博に行って、布があって、ガムテープやホッチキスを使って形にしてみただけで。でも、作っているうちに、だんだん「中に何か詰めたほうがいいな」とか「ミシンを買ってみようかな」とか「身につけるっていうのがおもしろいな」とか思うようになって。だから、全部あとづけ。仕事につながるなんて思いもしなかった。 ──それを周囲の人が見てくれたことで、広がりが生まれたんですか? 下田 でも、最初はちょっと怖がられてましたよ。絵も描かずに急に恐竜を被り始めたから、本当に心配してる人もいて、「今だから言えるけど、あのころちょっと怖かったよ」みたいな(笑)。僕は僕でカッコいいものができたと思ってるから、毎日のように持ち歩いて被ったりしてたんだけど、たしかにちょっと怖いですよね。 ──ただ、中にはおもしろがってくれる人もいた。 下田 そう。たとえば、一緒に絵本を作る仕事で出会った谷川俊太郎さんは、わりと最初から率先して被ってくれました。それで谷川さんと会うときは一番新しい恐竜を持っていくようになったら、谷川さんが「これに詩を書くから、連載できる場所を探してきて」って言ってくれて。それがきっかけで雑誌の連載が始まって、世に出るようになりました。でも、撮影してくれた藤代冥砂さんもそうだけど、仕事というより単に楽しんでくれてたのかもしれない。 原点は、ひとりで行った映画館の暗闇 ──被り物以外にも舞台の美術や小道具、衣装を手がけられたり、活動の幅を広げられていますが、それぞれ向き合い方などは違ったりするのでしょうか。 下田 道具や材料が変わるだけで、一緒ですね。一生懸命やります。スタイルを変えたとか言われることもあるんだけど、全然変えてませんから。そのときの自分のブームによってやることが違ったり、いただいたテーマによってやり方を変えたりしているだけなんで。自分のスタイルみたいなものに特にこだわりがないというか、スタイルと呼べるほどのものを持ってない(笑)。 ──では、「こういうことをやってみたい」「こういう絵を描きたい」といった展望も特にない? 下田 ないですね。そういう作戦とか考えたほうがいいんだよな、本当は。でも、手を動かしていると何かがやってくる感じで。 ──恐竜との出会いはまさにインスピレーションが刺激された経験だと思いますが、同じようにインスピレーションを得た経験はほかにありますか? 下田 なんだろう、映画とかライブとか展覧会とか、いろんな本とか。小学生のときから、ひとりで映画館に行くのが許されてたんですよ。僕は落ち着きのない子供で、授業中にじっとしてられなかったりしたこともあったんですが、劇場や映画館は大好きで、そういうところでは静かに大人しくできた。あと、コンサートやお芝居は親に連れていってもらって、劇場で「ここは大人の場所だから、大人にしてなさい」と母親に言われたのをすごく覚えている。 まわりに子供がいない感じが妙に好きだったんですよ。友達と遊ぶのも好きだけど、ひとりで映画館に行って、暗闇の中で「落ち着く」とか思うような小学生でした。それが中学になると映画を観たついでにジャズ喫茶に寄ったりするようになって、高校になると洋書屋さんに立ち寄ってアートを見たりするようになった。そうやってひとりで観て、読んで、聴くことでふくらんでくるものがあって、いまだに創作の材料になっているような気がします。 ──10代で出会うものって、特別ですよね。 下田 やっぱり一番強烈なんだよなぁ。あのころいっぱい遊んでよかったと思う。当時、地元の神戸でRCサクセション、YMOのライブも観に行ったりしてました。一応学校ではまじめにやってたんですよ、まじめにやってるのに成績がビリだったっていうだけで。一番カッコ悪い(笑)。 創作は、自分の中の“好きな点”がつながることで動き出す ──「サボり」がこの企画のテーマなんですが、下田さんにとっては人生におけるサボりの時間が大きそうですよね。10代の過ごし方もそうですし、2年間海外にいたのも大きな意味でサボりといえそうです。 下田 まあ、学生時代はサボってたんでしょうね。だからこそ、あのころに観たものが深く刺さってる気がする。ずっと取っておいてあるんだよね、当時の映画やお芝居のチケット。今と違ってカッコいいでしょ。 当時のチケットの束 ──すぐに出てくるのがすごいです。 下田 宝物だもん。僕の札束だよ。たまんなくない? ──たまらないですね。このころが特別な時間だったことが伝わってくるというか。 下田 友達と行くこともあったけど、このチケットはだいたいひとりで行ったものだと思う。 ──ひとりだからこそ、自分の中で熟成されるようなこともありますよね。 下田 どうなんだろう。でも、たしかに自分の作るものも、何もないところから湧いてくるんじゃなくて、過去に観たものや、知ったこと、経験したことなんかが点としていっぱいあって、それが何かの瞬間にビャーッとつながる感じですね。そういう“好きな点”がいっぱいあるといいですよね。サボりながら、遊ぶようにその点を作ってこられたことは、自分にとってよかったと思います。 撮影=石垣星児 編集・文=後藤亮平
-

「うまくサボって、コンテンツ作りに効率と持続性をもたらす」橋本吉史のサボり方
クリエイターの活動とともに「サボり」にも焦点を当て、あの人はサボっているのか/いないのか、サボりは息抜きか/逃避か、などと掘り下げていくインタビュー連載「サボリスト~あの人のサボり方~」。 TBSラジオで数々の人気番組を立ち上げてきた、ラジオプロデューサーの橋本吉史さん。TBSラジオ退社後は、配信者やパーソナリティとして自らトークを繰り広げるなど、プロデュース業に留まらず幅広く活動している。そんな橋本さんに、クリエイターとしての原点や番組作り、幅広い活動の背景などを聞いた。 橋本吉史 はしもと・よしふみ 1979年、富山県生まれ。プロデューサー/配信者。2004年、株式会社TBSラジオ入社。『ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル』、『ジェーン・スー 生活は踊る』、『アフター6ジャンクション』など、数々の番組を立ち上げる。24年にTBSラジオを退社し、フリーランスのプロデューサーに。文化人として芸能事務所sai & co.に所属し、ラジオに限らずさまざまなコンテンツでラジオ体験をプロデュース、番組パーソナリティなど出演者として活動、ライブ配信者としてのプロジェクトも立ち上げるなど、活動の幅を広げている。 クリエイターとして必要なものは、すべて学生プロレスから学んだ ──橋本さんが手がけるラジオ番組からは、さまざまなカルチャーのエッセンスが感じられますが、ご自身はどんなカルチャーに影響を受けてきたのでしょうか。 橋本 僕は地方都市で生まれ育ったので、東京に比べれば遥かにカルチャー不毛の地ではありました。だから触れられるエンタメもある程度は限られていて。やっぱりテレビの影響は強かったですね。バラエティ番組が好きだったんですけど、今思えば、お笑いというよりも企画性に惹かれていたような気がします。 特に、裏方であるスタッフも前に出てくるようなチーム感のある番組に憧れていました。それってすごくラジオ的な構造でもあるので、そういう意味でも自分にとってのルーツかもしれないですね。 ──世代的に、インターネットもまだ広まっていませんでしたね。 橋本 そうですね。だから、雑誌や本からも影響を受けていました。『smart』っていうファッション誌で、なぜかジャーマン・テクノみたいなディープなカルチャーを知ったり、大槻ケンヂさんのエッセイに出会って、B級映画やプロレスのおもしろがり方といった、サブカルチャー的な視点を学んだり。あとは、地元にシネコンができたので、映画もけっこう観てましたし、ゲームの進化とともに人生を歩んできたので、ゲームもずっとやってましたね。 ──不毛の地出身とはいえ、幅広いカルチャーに触れられてきたんですね。 橋本 でも、大学で上京したら、やっぱり東京は格が違うと思いましたよ。中でも学生プロレスとの出会いは自分のキャリアにとって決定的だったというか、クリエイターとしてエンタメを作る上での価値観は、ほぼプロレスから学んだといってもいいくらいで。 たとえば、プロレスはお客さんを沸かせてナンボなので、まず試合をどう盛り上げるかというところから教わるわけですよ。いきなり必殺技を出しても盛り上がらないから、ちゃんと振りを入れるとか。お客さんを惹きつける試合の構築は、まさにエンタメの基礎だったなと思います。 ──学生プロレスにもプロ意識が求められる。 橋本 僕らはプロと違って、学園祭やお祭りで通りすがりの人を立ち止まらせなければならないんです。興味がない人の心をつかむのって、すごく難しいじゃないですか。だから、いかにインパクトを与えて、そこからどう惹きつけるか、プロ目線で考える必要があったんですよね。ウケないと、僕らもやっててキツいですし。 ──なるほど。そういった経験は、ラジオの世界でどう活きてきたのでしょうか。 橋本 それこそ、入社するといきなりプロの世界に飛び込んで、厳しい視線にさらされるわけじゃないですか。最初からプロの世界で通用する人なんてまずいないので、みんな打ちのめされるんですけど、僕はそこで落ち込んだり、苦労したりすることはなかったです。 そういうものだとわかっていたし、「どうやったら伝わるか」をずっと考えてきたので、ラジオの世界でも同じように考えることは、大変だけどつらくないというか、むしろ楽しいと思えた。そこはプロレスをはじめとするサブカルチャー的なベースが活きたと思いますね。 いいパーソナリティは、正直で、共感されやすい ──プロデューサーとして最初に立ち上げられた番組は『ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル』ですが、当時、宇多丸さんがパーソナリティのサブカル的な番組という企画を通すことにハードルなどはなかったのでしょうか。 橋本 TBSラジオにはそういう土壌があったので、大変ではなかったですね。そのころ、僕も担当していた『ストリーム』という昼のワイド番組に、吉田豪さんや町山智浩さんといったサブカルアイコンみたいな方々が出演していて、番組の聴取率もよかったんです。 サブカルとラジオって相性もよくて。ちょっと踏み込んだ時事評論とか、カウンターカルチャー的な要素もハマって、サブカルファンがラジオ好きになってくれた。それで、知名度が高いタレントさんを起用しなくても、リスナーとガッチリハマるおもしろい番組なら勝てるという自信をみんなが持つようになったんです。 ──そのタイミングで宇多丸さんと出会ったと。 橋本 そうですね。宇多丸さんは初めて会ったときからポテンシャルが高い人だというのは一発でわかったので、すぐに特番の企画を出してやってみたら、「宇多丸さん、おもしろいよね」って上の人たちも支持してくれて、レギュラー化できたんです。 当時は自分もプロデューサーになったばかりでイキっていたので、数字が取れるか、スポンサーについてもらえるかといったことよりは、とにかく宇多丸さんのポテンシャルを信じて番組として企画を当てていけば大丈夫だろうと思っていました。数字が下がると怒られはしましたが、今思えば局の理解があったからこそ続けられたんでしょうね。 ──その後もジェーン・スーさんなどをパーソナリティとして起用していきますが、「この人いけるな」と思うポイントなどはあるんですか? 橋本 これはラジオパーソナリティに限らないと思いますが、まず「正直な人」であることです。「正直な人」というのは、自分が思っていることをきちんと言葉にできて、それを「本当にこの人が言いたいことなんだな」と伝わる話し方ができる人のことなんですけど、上辺だけで話していない、“本当らしさ”というのは大切で。 もうひとつは、共感されやすいかどうか。リスナーがなんとなく抱えているような違和感を言語化できると共感を得やすいんですけど、その瞬発力が高い人は向いていると思いますね。 ──ほかにも、数々のラジオ番組を手がけてきて、実感されたことはありますか。 橋本 月並みですけど、リスナーの重要性ですね。最初は過激な情報や強い情報をぶつけまくって、それをおもしろがってもらえたらなと思っていましたが、だんだん「リスナーと一緒に場を作る」という感覚を持たないと、ラジオっぽくならないなと感じるようになりました。 やっぱり、リスナーに「参加している」という意識を持ってもらえたほうが、番組も長続きするんですよね。ラジオ番組はコンテンツでありながら、コミュニティでもあると思っていて。リスナーにはパーソナリティの話を聞きたいという欲求だけでなく、その場にいたい、その場の一員になって連帯を感じたいという気持ちがあるから、ラジオはインタラクティブにやるのが基本になっているんでしょうね。 ──番組に直接投稿するだけでなく、SNSにリアクションを書き込むといったかたちで番組に参加しているリスナーもたくさんいますよね。 橋本 そうですね。おかげでどんな人がどんなシチュエーションで、どんな思いで聴いているのか可視化されて、リスナーのイメージが浮かびやすくなりました。もちろんサイレントリスナーのことを大切にしながら、ですが。それで気づいたのが、ラジオは心地よさが大事だということです。家事や仕事をしながらラジオを聴いている人にとっては、ひたすらおもしろいだけだとちょっと疲れるんですよね。 だから、パーソナリティと一緒にいたい、その人の話を聞き続けたいと思ってもらうことも必要で。それって、トークの技術なんかとはまた別の要素ですよね。その点で、『たまむすび』という番組をやっていた赤江珠緒さんの「愛され力」はすごかったと思います。 「ラジオ的なもの」がどこまで広げられるか追求したい ──現在は独立されて活動の幅も広がっていますが、その活動イメージや、ラジオをはじめとする音声メディアに対する考え方などを聞かせてください。 橋本 先ほど話したように、ラジオには音声メディアだけでなく、コミュニティとしての側面などがあるわけですよね。だから、受け手との距離が近いコンテンツやファンと一緒に作るようなコンテンツなら、ラジオで培ってきたノウハウが活かせるんじゃないかと思っていて。それで、ある商品とそのファンをエンゲージさせる場を作るとか、そういったラジオ以外の仕事もやるようになりました。 それに音声メディア自体も、今やラジオやポッドキャストに限ったものではないと思うんです。YouTubeだって映像メディアではありますが、トークがベースのコンテンツがたくさんあるじゃないですか。そう考えると、音声メディアの領域ってかなり広いものだといえますよね。 ──たしかに、そう考えると活動領域も広がりますね。 橋本 そうなんです。僕がTBSラジオ時代に手がけた最後のプロジェクトのひとつに、『龍が如く』というゲーム内で、『アフター6ジャンクション2』というラジオ番組を流すというコラボレーションがあるんですけど、それってラジオじゃなくてゲームなわけですよね。でも、プレイヤーはゲームの中でラジオを聴いている。ということは、「ラジオ的なもの」はいろんな媒体の中に存在し、体験できるんですよね。 だったら、ラジオというものを因数分解しながらその構成要素を追求して、いろんなものに当てはめてみたい。それでどこまで行けるのか、どんな景色が見られるのか知りたい。そう考えたら「放送局にいる場合じゃないな」と思ったのが、独立のきっかけなんです。 ──ラジオ以外の場でラジオ的な空間や体験を作るという意味で、実際に活動されていることはありますか? 橋本 配信プラットフォームの「Twitch」で配信者として活動しているのも、そういった文脈から始めたことではありますね。今の若い子にとっては、ゲーム実況が深夜ラジオみたいな場になっていたりするんですよ。視聴者が悩み相談のコメントを書き込むなど、単にゲームの実況を聞くというよりは、ラジオパーソナリティみたいな存在として配信者と接していて。 個人が毎日のように生放送していて、そこにファンがついている。これってもうラジオ体験ですよね。配信者の振る舞いやコメントを拾ううまさなんかも、ほとんどラジオパーソナリティなんですよ。実際に配信者の方に話を聞いてみても、コミュニティを作ることが重要だと言ってました。だから、若い子はラジオなんか聴かない、ラジオはもう終わっていく、みたいに言われがちですけど、実はまったく終わってない。 ──「ラジオ的なもの」は常に求められ、存在している。 橋本 はい。電波で聴くのがラジオだという時代が終わっても、媒体やかたちを変えてラジオっぽいコンテンツは残っていくと思います。そのひとつが配信の世界だという仮説を実証するために、自分で配信することにしたんです。 もともと配信文化も好きで、一度ちゃんと学んでみたいと思っていたのでやってみたら、ラジオリスナーの人たちも集まってくれて、普通に楽しいですね。ラジオリスナーのコメントセンスや距離感も配信にぴったりで、予想どおりラジオ的な感覚で違和感なくやれています。いずれはタレントさんを立ててプロデュースしたりすることも考えていましたが、今は自分が楽しんじゃって、実験どころか「配信者としてやっていこう」みたいな感じになっちゃってます(笑)。 サボりは、コンテンツ作りにおける超重要テーマ ──橋本さんは趣味と仕事が近い位置にある方だと思いますが、サボることってありますか? 橋本 会社を辞めた今だから言えますけど、僕はもともとサボるのが大好きな人間なので、サボるために仕事をしていたようなところはありますね。仕事も好きですけど、遊ぶことも好きなので、無意味にダラダラ働くのがイヤで、サボるために効率を追求していた。いうなれば積極的なサボり、「ポジティブサボり」ですね。「漫然と仕事してたらサボれないじゃん!」みたいな。 ──ポジティブサボり、いいですね。見習いたいです。 橋本 ポジティブにサボり方を考えるのって、クリエイティブな行為だと思うんです。「ここを効率化すれば、この時間までに作業が終わって、別のことができるな」みたいに、時間の作り方を考えたりするので。それに、無駄を省く作業って、番組作りにおいてもプラスに働くんですよね。 一方で、僕もネガティブサボりをしてしまうことはあります。スイッチが入るまでなかなか動き出せないタイプだし、やるべきことをギリギリまで寝かせてしまうこともある。「やり始めたら、やる気も出るんだよ」って言われても、「いや、わかってるけど、『やる気が降りてくるの待ち』なときもあるじゃん!」みたいな(笑)。 ──やっぱり最初の一歩を踏み出すのが一番大変ですよね。 橋本 そうですよね。突然スイッチが入ってギュッと仕事をするときもあるから、できないときはやらなくてもいいかなと思いつつ、罪悪感は常にある。自分でもそれはよくないと思うんですけど、人間だからしょうがない。だって、サボりを知らない勤勉な人って、ちょっと人間味が感じられないじゃないですか。 キラキラした人のインタビューを読むと、「要はやるか、やらないか。成功できないのは、やらないヤツなんだ」みたいなことを言ってますけど、「本当かな?」って思いますよ。実際は「疲れた〜」とか「めんどくせー」とか思うこともあるんじゃないかな。 ──「好きなことをやっているから、仕事とも思わない」みたいな人はたまにいます。 橋本 僕も好きなことばっかりやっているので、仕事と遊びの境界線はないし、仕事してるのか、サボってるのかよくわからないこともあります。でも、好きなことをしていても、作業工程としては好きな作業と嫌いな作業があるわけで、好きな作業だけで仕事が埋まることはないじゃないですか。仕事は好きだけど、そのために朝早く起きるのはイヤだっていう気持ちは矛盾しないと思うんですよね。 ──たしかに、やりたいと思っていた仕事の中にも、やりたくないことはありますね。 橋本 そういう気持ちも隠さず、積極的にサボっているところを見せていったほうがいいですよね。普段は全然会社にいないのに、大事な仕事はビシッと決めるような先輩とか、僕はそういう人に憧れていましたから。「会社でデスクに座ってるだけじゃ、いいアイデアなんて出てくるわけないだろ」って言われて育った、最後の世代なのかな。 それに、ラジオ番組作りも、やっぱりサボりがないとダメなんですよ。お話ししたように、ラジオは聴いている人を疲れさせちゃいけないので。それは作る側も同じで、現場が疲弊していたら、コンテンツとしてサステナブルなものにならない。お互いに長く付き合っていくためには、適度に緩急をつけた、サボりの要素が入ったコンテンツにする必要があるんです。 ──なるほど、コンテンツにも「抜け」のようなものが必要だと。 橋本 そうですね。だから、「サボり」って超重要なテーマですよ。今の時代にこそ必要なものだと思います。 撮影=NAITO 編集・文=後藤亮平
-

「抜くときは抜いて、自分らしく楽しむ時間を作る」橋本和明のサボり方
クリエイターの活動とともに「サボり」にも焦点を当て、あの人はサボっているのか/いないのか、サボりは息抜きか/逃避か、などと掘り下げていくインタビュー連載「サボリスト~あの人のサボり方~」。 『有吉の壁』をはじめ、演出家・ディレクターとして日本テレビで多くの人気番組を手がけてきた橋本和明さん。2024年の独立以降は、テレビ番組や配信番組だけでなく、幅広いコンテンツに携わっている橋本さんに、その好奇心の源や、忙しいなかでのサボりについて聞いてみた。 橋本和明 はしもと・かずあき 1978年、大分県生まれ。東京大学教育学部を経て、東京大学大学院人文社会系研究科修了(社会学修士)。2003年、日本テレビ放送網株式会社入社。『有吉の壁』『有吉ゼミ』『マツコ会議』の企画、総合演出を務めヒット番組に。ほかにもドラマの演出・プロデュースや、映画監督なども務める。マツコ・デラックスをアンドロイド化した『マツコとマツコ』は、カンヌ広告賞でブロンズ賞を受賞。2023年、日本テレビを退社し、株式会社WOKASHIを設立。 原点は、大学時代に立ち上げたコント集団 ──橋本さんのルーツとして、大学の落語研究会での活動があるそうですね。 橋本 はい。東京大学の落語研究会でコントをやっていました。どうしてもコントがやりたくて、自分で「ナナペーハー」っていうコント集団を立ち上げたんです。作家の別役実さんのコントセミナーに通ったりして、自分で台本も書いて。とにかくお笑いがやりたかったので、「カジュアル兄弟」っていう恥ずかしいコンビ名で漫才もやってましたね(笑)。 ──大学時代はお笑いひと筋だった。 橋本 大学院に進んだのも、コントを続けるために大学生活を延ばそうという一心からで、お笑いへの熱量は当時から高かったと思います。学園祭でのライブにも力を入れていて、最初は20人くらいしか集まらなかったけど、客引きなどをがんばって盛り上げて、最終的には3日で1000人くらい動員できるライブにしていって。 学園祭でのライブが自分にとっての原体験なんですよね。お客さんが目の前で笑ってくれる、ライブを観て喜んでくれるって、やっぱり何事にも代えがたいことなんですよ。「生きててよかった」って本当に思うくらいで。芸人さんがお笑いをやめられないのも、すごくよくわかります。 ──そのまま芸人になるという道は考えなかったのでしょうか。 橋本 芸人になる勇気はなかったというか、自分がそこまでおもしろいとは思えなかった。同じ世代でお笑いをやっていた学生の中でも、かもめんたるや小島よしおさんがいたWAGEや、脳みそ夫さんなんかはプロになれると思っていたけど、自分は演者としては無理だなって。それで、テレビ局の入社試験を受けてみたら、たまたま日テレに拾ってもらえたので、運命だと思ってテレビの道に進みました。最初は報道採用だったんですけど。 ──報道だったんですね。意外です。 橋本 でも研修を受けてみて、やっぱり人間性的に報道は無理だなと。それで、人事に「報道じゃないと思うんで、舞台やりたいです」と言ったら、「甘えるな」ということで制作現場に配属されました。それでいつの間にかバラエティをやることになったっていう。これも巡り合わせですね。 準備を重ねた上で、予定調和が崩れる瞬間がおもしろい ──テレビ番組作りとなると、学生時代のライブとは違うと思いますが、ノウハウなどは現場で学んでいくものなのでしょうか。 橋本 そうですね、入社当時はまだテレビ界が近代化する前だったので……(笑)、ADとして徹夜で仕事するとか、きつい下積み時代がありました。それでも自分の企画をかたちにしたくて、企画書を山ほど提出して。2年目でようやく深夜番組の企画が通って、3年目でディレクターになって、7年目にゴールデンでレギュラー番組を担当するようになりました。 その後も、『ヒルナンデス!』の演出をやったり、『有吉ゼミ』を立ち上げたり、10年ぐらいはずっとバラエティ畑で。12年目でようやく『有吉の壁』というお笑いに特化した番組をやれるようになったんです。 ──『有吉の壁』まで「お笑い番組」と呼べるものは手がけられていなかったんですね。企画は出していたんですか? 橋本 めちゃくちゃ出してました。お笑い番組ってなかなか企画が通らないんですよ。『有吉ゼミ』が当たって、ようやく「そろそろこいつにお笑いやらせてやるか」と思ってもらえたんじゃないかな。でも、バラエティディレクターとして地肩を作る期間は必要だったと思います。 『有吉ゼミ』で初めて当たったのが、坂上忍さんが家を買う企画なんですけど、芸能人が本当に家を買うわけで、そこでリアルであることの大切さを実感しました。リアルなものをそのまま届けることで、バラエティとしての強度が生まれる。『有吉の壁』でも、その点は大切にしています。芸人さんたちがその場でネタを披露して、有吉(弘行)さんが即興で○×をつける。その様子を視聴者のみなさんにショーとして見せるって、リアルなことじゃないですか。 ──たしかに、芸人さんたちのリアクションや生き様なども含め、ドキュメンタリー的な魅力を感じます。 橋本 そうなんですよ。バラエティにおけるドキュメンタリー要素って年々強まっていて、ドキュメンタリー性がないものは観てもらえなくなってきてるんですよね。YouTubeやInstagramなどのあらゆる動画が視聴者の見る目や世界を変えたんだと思います。それによって、テレビが自ら現象を作って当てるようなことが難しくなり、リアルをいかに切り取って、人の感情を導くかという方向に舵を切るようになっていった。 そこで、観ている人の感覚をすくい取る能力がより重要になってくるんですけど、僕がずっと番組で伴走してきた有吉さんとマツコ(・デラックス)さんって、その天才なんですよ。ふたりとも台本がいらないタイプで、その場の肌感で流れを作ることができる。ふたりのそばにいるなかで、自分もそういった感覚が培われたというか、チューニングできるようになってきたところはあると思います。 ──では、台本や企画の狙いなどは用意しつつも、収録はその場の流れで進めていく、といった作り方が多いのでしょうか。 橋本 そうですね。『マツコ会議』なんかも、テーマについて調べたり、いろんな人に会ったり、準備に準備を重ねるのですが、収録では現場で起きたことに流されていました。マツコさんが、画面の端っこに映っていたこちらが意図しない人を「おもしろい」と言ったら、その流れに乗っていく。こちらが考え抜いて準備した予定調和が崩れていくからこそ、それを超えたものが生まれるんだと思います。 ──企画当初のビジョンに捉われると、それ以上のものは作れない。 橋本 そう、全部が崩れる瞬間が最高におもしろいんです。『有吉の壁』で、プールの水面に浮かんだゴザの上を走って、浮島で大喜利のお題に答えるというコーナーをやったんですけど、U字工事の益子(卓郎)さんがプールから上がってこない。みんなが「どうした?」って聞くと、結婚指輪を落としたと。 そうしたら、出演者がみんなで指輪を探し始めたんですよ、濁ったプールの底を足で探りながら。有吉さんも「指輪を見つけた人が優勝です」って言い出して、結果、パーパーのあいなぷぅが指輪を見つけるというミラクルを起こして優勝した。その瞬間、もとの企画とかそれまで獲得したポイントなんてどうでもよくなるんですよ。でも、結婚指輪をなくして焦る益子さんも、それをなんとかしなきゃと思う芸人さんたちの愛情も、全部リアルじゃないですか。あのときはすごいものが撮れたなと思いましたね。 答えのない問題と向き合う楽しさ ──独立後の活動について伺いたいのですが、やはりメディアなどの幅が広がると作る感覚も違うものですか。 橋本 全然違いますね。TikTokで『本日も絶体絶命。』っていうコント番組を始めたんですけど、10代のお客さんも多いなかで、最初の1秒半が勝負のコンテンツをどう作ろうか、参加してくれたハナコやかが屋、吉住と現場で議論しています。それで、振りの部分をバッサリ切って、何かが起こるところから始まるコントを作ってみたり。またそういう経験によって、テレビを作る上での視点も広がるんですよね。 ──いろんなルールの中で考えていくことで、引き出しも増えている。 橋本 そうなんです。いろんなルールを知って、いろんなテクニックを持っているほうが、これからの時代、絶対おもしろいと思うんですよ。バラエティの世界も、これからはコンテンツありきで進む、コンテンツファーストの時代になるはずなので、テレビマンとしての可動域を広げる必要が出てくる。独立してからの経験は、そのためのトレーニングになっていると思います。 ──逆にテレビマンとして鍛えてきたものが、ほかのメディアで活きていると感じることはありますか? 橋本 テレビで10年以上鍛えてきた力はすごく大きいです。特にたくさんのスタッフさん、タレントさんを活かしてプロのコンテンツを作ることって、テレビじゃないとできない経験なので。Netflixさんとお仕事してもAmazonプライムさんとお仕事しても、結局出てくるのはテレビ畑の人だっていう実感があるわけですよ。 そういう意味では、コンテンツメーカーとしてのテレビ局の未来って、全然暗いものじゃないと思います。マンガ業界はIP(知的財産)活用や海外進出など、マネタイズが多角化してより才能が発掘できるようになりましたが、テレビ業界も同じような進化をしていかなきゃいけないフェーズに差しかかっている。そこでテレビの真価が問われるようになったとき、多くの仲間と新しい表現に挑戦したいという気持ちはすごくありますね。 ──過渡期の中に身を置くことは不安や怖さもあると思いますが、橋本さんからはワクワクしたものを感じます。 橋本 楽しいですよ。日々いろんなお話をいただいて、「こんな宿題があるのか、こんなテーマがあるのか、どうしよう」って思いながら、答えのない問題と向き合っています。答えがないなかで第一投を投げることは怖くもありますが、見たことがないものを見ることができる楽しさもあって、刺激的なんですよね。 原点に立ち戻って、手作りで好きなことをやりたい ──さまざまなメディアでの展開のほかに、新たにユニットも始められるそうですね。 橋本 timeleszの佐藤勝利くんとダウ90000の蓮見翔くんと3人でコントユニットをやるんです。まずは『佐藤勝利のすべて』という、佐藤勝利がコントライブを作るまでのドキュメンタリー的なものをYouTubeでやって、実際に劇場でコントライブもやるっていう。これは仕事というより、好きな仲間と好きなことをしたいね、っていう話から始まった企画なんですけど。3人とも本当にお笑いが大好きで。 ──佐藤さんもお笑い好きなんですね。 橋本 そうなんですよ。普段、あまり表には出さないけどすごくお笑い好きで、自分でもやりたいってずっと言っていたので、こんな時代だし、やっちゃってもいいんじゃないかという話になって。今は3人で毎週朝10時から定例会議をやっています。スタイリストさんへの発注とかロケ場所の予約とかも勝利くんが自分で電話したりして、完全に手弁当です(笑)。 ──そんなに手作りなんですか? 橋本 そう、手作り。全部自分たちでやっています。テレビ局や配信プラットフォームに企画として持っていくと、仕事になっちゃうじゃないですか。でも、ここでは違うことをやりたい。再生回数も宣伝方法も考えず、やりたいこと、楽しいことをやりながら、だんだん仲間が増えていったらいいよね、って話しています。11月11日〜13日にニューピアホール竹芝で旗揚げのコントライブをやるんですけど、3人ともワクワクしながら中身を作っています。 だから、大学時代にコント集団を作ったっていう原点に戻ってるんですよね。ビジネスとして結果を出さなきゃいけない仕事が続いて、それはそれで楽しいんだけど、一方で自分が本当にやりたいこと、愛せるものを確立しておきたくて。それが今になって気の合う仲間とできるって、めちゃくちゃ贅沢なことだと思うんです。そのぶん、めちゃくちゃ大変ですけど。 ──でも、そういう熱量の高いコンテンツは時代にも合っている気がします。 橋本 今っぽいですよね。想いや熱量を応援してもらうっていう感覚がすごく強くなったと思います。ただ、YouTubeチャンネルもやるんですけど、再生回数競争に巻き込まれて実態を暴露したり、キツいことを言ったりしなきゃいけないような感じからも自由になりたいんです。 個人的にも、ギスギスしたものや、人間の本性を暴くようなものが苦手なんですよね。細々でもいいから、誰かを悪く見せることなく、仲間と楽しい場所を作って、応援してくれる人を増やしていきたい。そうやって生きていくことが自分の人生の目標というか、そういう場所にたどり着きたいと今は思っています。 サボって罪悪感を溜め込むからこそがんばれる? ──橋本さんのサボりについても伺いたいのですが、忙しいなかでついサボりたくなることはありますか? 橋本 昔からサボり癖はひどくて、できれば働きたくないと思うようなタイプなんですよ。休みの日は起きれなくてずっとゴロゴロしてたりしますし、夏休みの宿題は残り2日くらいまでやらなかったし。でも、サボるって罪悪感があるじゃないですか。その罪悪感を溜め込むことが僕にとっては大事なんですよね。 やっぱり人間って、サボるとそれを取り戻そうとがんばるじゃないですか。サボることは、がんばるための貯金になるんですよ。サボってサボって、自分を追い込んでようやくがんばれる。最後に帳尻が合っていればいいわけですから。 ──ダッシュするための溜めがサボりなんですね。サボりの反作用に自覚的な方の話はあまり聞いたことがなかったです。 橋本 だから、何をサボっているか、その実感だけは忘れないようにしています。「これとこれで人を待たせているけど、今日はやらずに映画を観に行こう」となっても、ちゃんとサボったことを覚えていて、翌朝急いでやれば許してもらえるだろう、みたいな。 でも、みんなそんなもんじゃないんですかね。リモート会議を仕切っているときも、画面をオフにしている人たちはそれぞれメシ食ったり、横になったりしながら聞いてるんだろうなって思ってます(笑)。でも、別にそれでいいというか。僕だって、横になってお菓子を食べながらVTRをチェックすることもありますから。 ──やることをやっていればいい。 橋本 多少サボっても、ここだけは押さえておかないと事故が起こる、人と揉めてしまう、失敗してしまう、といったポイントはわかっている。プロってそこが大事な気がします。逆に、サボってるという自覚がない人のほうがやりにくいこともありますよね。罪悪感もないまま、何も進めてくれなかったり……。 あと、サボってるときのほうがいろいろ思いつくんですよ。オンの状態で企画に意識が向きすぎても、いいアイデアって浮かばなくて。そこでいったん放置しておくと、シャワーを浴びたりしているときにふと思いつく。泳ぐのが好きで、無心で泳いでいるときに企画を思いつくことも多いです。やっぱり根を詰めるだけじゃなくて、抜くのも大事なんですよね。 撮影=石垣星児 編集・文=後藤亮平
-

「仕事もサボりも、その場に足を運んで体感したい」小西朝子のサボり方
クリエイターの活動とともに「サボり」にも焦点を当て、あの人はサボっているのか/いないのか、サボりは息抜きか/逃避か、などと掘り下げていくインタビュー連載「サボリスト~あの人のサボり方~」。 コント好きや演劇好きから一目置かれているイベント『テアトロコント』。そのキュレーションを手がけているのが、ユーロスペースの小西朝子さんだ。お笑い芸人や演劇人からの信頼も厚い小西さんのコント愛、演劇愛を伺いながら、そのアクティブなサボり方にも触れた。 小西朝子 こにし・ともこ 2015年、有限会社ユーロスペースに所属。東京・渋谷にある劇場「ユーロライブ」で開催されるコント公演『渋谷コントセンター』を担当。持ち時間30分でコント師と演劇人が競演するイベント『テアトロコント』のキュレーターを務めている。 公演の意義を熱弁したら、いつの間にか運営スタッフに ──小西さんがユーロスペースに所属し、コントライブを手がけるようになった経緯を教えてください。 小西 2014年の11月にユーロライブ(東京・渋谷にある劇場)が開館して、劇場主催の月例公演として『渋谷コントセンター』が始まったんですけど、それを普通に観に行っていたんです。劇場主催で、芸人さんの持ち時間が3〜5分ではなく30分というコンセプトがおもしろいし、いい試みだなと思っていました。でも、全然お客さんがいなくて。 それで、誰も気づいていないけど、劇場が主体となって発信して交流を生むことがいかに大事で、そうした場がいかに貴重か、といったことを小論文みたいにしたためた手紙をユーロライブに送ったんです。 ──すごい情熱ですね。 小西 当時読んだ、平田オリザさんの『芸術立国論』という本の影響などもあったと思います。そうしたら、社長の堀越(謙三)さんが読んで、連絡をくださって。30分という上演時間によるコントと演劇の違いは何か、コントと演劇を混ぜたらおもしろそう、といったことも手紙に書いたら、『渋谷コントセンター』と同じフォーマットで演劇も入れた公演をやってくれないか、みたいなことを言っていただいたんです。それがきっかけですね。 その公演が、『テアトロコント』なんですけど、最初は制作スタッフとしてテアトロコントだけを担当する感じだったのが、だんだん劇場のこともやるようになって、気がつけばユーロライブを運営している人になってしまいました(笑)。 ──最初からキュレーションなどもされていたのでしょうか。 小西 1回目は先に決まっていて、2回目からはキュレーションも含め好きにやらせてもらっていました。演劇のほうは、お笑い芸人を名乗っていないけど劇場でコント公演をしているような方々をブッキングして。最初のほうはただただがむしゃらでしたね。関係性のない方をゲストに呼んでアフタートークをお願いしたり、今だったら足踏みしてしまうような挑戦的だけど危なっかしいこともやっていました。 ──今はどんな基準でキュレーションをされているんですか? 小西 お笑いも演劇も、ファンの方ばかりじゃない場でも成立して、ウケることがひとつの基準ですね。あとは、新しいことをしていたり、そんなにお客さんを抱えていなかったりするような方もブッキングすることがあるんですけど、その基準を言語化するのはちょっと難しくて。私なりに「この人たちのものづくりは信頼できる」と思えるかどうかというか。強いて言葉にするなら、「人の意見やお客さんのウケに左右されず、自分がおもしろいと思うことをブレずに追求できているか」みたいなことかもしれません。 おもしろさを体感することが一番 ──ブッキングしたくなるようなおもしろい人たちは、どのように見つけているんですか? 小西 ひたすら劇場に観に行っています。それが一番おもしろさを体感できるので。特に信頼できる方から「おもしろいよ」と紹介されたものはできるだけ観るようにしていて。YouTubeなどの動画も観ますが、あまり集中力が続かないんですよね。ただ、YouTubeではたまに「コント」で検索して、芸人さんなのかどうかもわからないような人たちが上げているコントを観ることもあります。 ──キュレーターとして目をつけるポイントと、個人的なツボや好みに違いはあるのでしょうか。 小西 私は一緒かもしれないです。集客につなげるためにはバランスのいいブッキングをしたほうがいいかもと考えたこともありましたが、「それって私自身がやる意味があるのかな?」と思って。最近は自分の好みを判断基準にした、いわば偏ったブッキングのほうがいいと考えるようになりました。それぞれの価値観で選ぶキュレーターがいっぱいいることで、多様性も生まれるはずなので。 ──そのほうが「この人たちはおもしろいから観てほしい!」という熱も高くなるんでしょうね。 小西 はい。それが一番だし、たぶんそれしかできないなと。「おもしろいらしいです」って紹介するのが一番よくなくて、私がしっかり「おもしろいです」って言えないとお客さんにも悪いと思うんですよ。 ──お笑いも演劇も幅広く観られているなかで、最近の演劇シーン、コントシーンについてはどう見えているのでしょうか。 小西 テアトロコントを始めたときは、演劇とお笑いは別物だという壁があったように思いますが、最近はその壁がなくなってきている気がします。テアトロコントについても、以前は演者の方にそんなに興味を持たれてなさそうだなと感じることもありました。 でも最近は、演劇とお笑いの垣根を感じさせない方の話をよく聞くようになったんです。先日もアンパサンドさんという劇団と春とヒコーキさんというコンビに出てもらったんですけど、春とヒコーキさんがもともとアンパサンドさんを好きで観ていて、一緒になってうれしいと言ってくださいました。 さまざまな交流を生む場をつくっていきたい ──お笑いと演劇の交流について、テアトロコントをやっていて手応えや意義を感じられたことはありますか? 小西 そんなに大きな話ではないのですが、普段は積極的に演劇を観ないという芸人さんや、コントを観ないという劇団の方が、共演者の演劇/コントを観て、楽屋で少し話したりする。そういう交流から何か思ってもらえたら、一番うれしいですね。 特に演劇だとほかの組と一緒になる公演がそもそも少ないので、自分たちの上演を観たお客さんがほかの組の上演を観て別の反応をしていることが刺激になるみたいで。芸人さんのウケ方を目の当たりにして、「もっとウケたい」「もっと笑いを取り込みたい」と思って帰る方もいたりします。 ──30分上演するコントと演劇は何が違うのか、といった問いかけもありましたが、実際に同じ場で上演するなかで違いを感じることはあるのでしょうか。 小西 如実に違うのは、作る環境というか、文化ですね。演劇はやっぱりスタッフワークというか、照明、音響、制作、舞台美術、舞台監督といった役割込みで完成形に持っていく感じですが、芸人さんは本当に身ひとつなんです。単独公演では演劇寄りの制作体制でやっている芸人さんも、演劇とはまたちょっとやり方が違っていて。そこが近づくと、より多様な表現が生まれそうな気もするんですけどね。 ──テアトロコントについて、今後の展望などはありますか? 小西 テアトロコントは関西の劇団の方にもちょくちょく出てもらっていて、そういうご縁もあるので、関西でテアトロコントをやりたいなとは思っていました。コロナ禍になってその展望が一度潰えてしまったんですけど、また関西公演みたいなかたちでやれたらなと思っています。関東で活躍している方々にも参加してもらって、場所を超えた何かができたらいいですね。 ──コントと演劇という垣根だけでなく、地理的な垣根も引っかき回せたらおもしろそうですね。 小西 そうですね。お笑いでも劇団でも、関西の方って東京でもう一度売れないといけない、といったハードルがあるので、関東で認知を広めるお手伝いができたらいいですね。逆に、関東を基盤にしている方でもツアーができるような劇団じゃないと関西公演をやるような機会がないので、そのお手伝いもしたいですし。そういう活動をしていれば、地方で演劇やお笑いをやる人も増えるんじゃないかと思っています。 サボるために出かけるのか、サボるから出かけるのか ──小西さんは、やらなきゃいけないことを先延ばしにしてしまうようなことはありますか? 小西 テアトロコントの告知が迫ってきて、早くブッキングしなきゃいけないのに事務作業をやっちゃうようなことはあります。コントのことは置いておいて、とりあえずメールの返信をするとか。事務作業って、やればやるだけ進んで、仕事が消えていく感覚があるんですよね。 ──では息抜きみたいなことも意識するのでしょうか。 小西 やっぱり息抜きをしないと効率が悪くなってくることはありますね。そういうときは劇場とかじゃなくて、神社仏閣や史跡を巡ったりします。歴史が好きなので、本やドラマでポイントとなっていた場所に行くことが多いです。(NHKの大河ドラマ)『鎌倉殿の13人』に出てきた伊豆山権現に行ってみたり、読んでいた本で取り上げられた唐招提寺に行ってみたり。 ──いわゆる「聖地巡礼」的な。 小西 そうですね。劇場に行くのと同じで、実際に足を運んで体験することが私の中で一番大事なので。「寺が思ったよりデカい!」とかでもいいんですけど、その場で感じたこと、受け取ったものって、積み重なっていくような気がするんです。普通に温泉に行くのとかも好きですけどね。 ──日常的な小さな息抜きだと、どんなことが思い当たりますか? 小西 それも結局、どこかへ足を運ぶことかもしれないです。音楽のライブに行ったり、外でごはんを食べたり。もしかしたら、すごくサボりやすい人間なのかも。家に帰ると何もしないから、どこかへ出かけてるんじゃないかと思います。 ──それも嫌々だと続かないはずなので、やっぱり出かけること自体が好きなんでしょうね。 小西 そういえば、無理をしないことは大事にしてますね。「行きたい」ではなく「行ったほうがいい、行かなければならない」と思ってしまったことは、義務というか労働になってしまうので、やらないと決めています。 ──それは、絶対に観たほうがいい話題の映画でも、気分じゃないなと思ったら観ない、みたいなことですか? 小西 そうですね。ただ、トータルで「観たい」が大きくなるときもあるじゃないですか。乗り気ではなかったけど、観た人と「あの映画観ました」って話せるかなと思ったら「観たいかも」という気持ちが大きくなるとか。いろんな動機があるなかで、それでも「やらなければならない」と思っていたらやめる、という感じですね。 撮影=石垣星児 編集・文=後藤亮平
-

「仕事みたいに遊んで、遊びみたいに働く」林雄司のサボり方
クリエイターの活動とともに「サボり」にも焦点を当て、あの人はサボっているのか/いないのか、サボりは息抜きか/逃避か、などと掘り下げていくインタビュー連載「サボリスト~あの人のサボり方~」。 今回お話を伺ったのは、会社員として人気WEBメディア『デイリーポータルZ』の編集長を長年務め、2024年に独立し、デイリーポータルZ株式会社の代表として同サイトの運営を続けている林雄司さん。会社員時代から背伸びをしない等身大のビジネス書を手がけるなど、どこかサボりの香りがするクリエイターである林さんの「サボり観」を聞いてみた。 林 雄司 はやし・ゆうじ デイリーポータルZ株式会社代表。2002年に立ち上げたWEBメディア『デイリーポータルZ』をはじめ、『Webやぎの目』、『死ぬかと思った』などのサイトを運営。『世界のエリートは大事にしないが、普通の人にはそこそこ役立つビジネス書』(扶桑社)、『ビジネスマン超入門365』(太田出版)など、独自視点のビジネス書なども手がけている。 本当は「できませんでした」で終わりたい ──林さんは『デイリーポータルZ』を20年以上運営されてきましたが、独立による変化というのはやはり大きいのでしょうか。 林 単純に忙しくなったというのはありますね。編集が僕を入れてふたりになっちゃったんで、現場に同行するだけで1週間が終わっていく感じで。あと、営業もいないので、広告の引き合いなどがあっても対応が遅くなってしまったり、費用を安く言っちゃって後悔したり、そういうつらさもあります。 「いったん持ち帰ります」とか「僕はやりたいんですけど、上が……」とか、会社のせいにできなくなったんですよね(笑)。前は安めに言っちゃっても「上から言われまして」っていう言い訳で訂正できたのに、それが使えないのはけっこう厳しいなって思ってます。 ──誰かのせいにできないのは地味につらいですね。自分で会社をやるとなると大変なことも多いと思います。 林 でも、会社にお金が入ってくるのは、意外とうれしかったです。「もっと制作費を抑えればお金が余る」みたいな悪魔の誘い的な声が聞こえてきたりして、経営者がお金儲けに夢中になっていく気持ちがわかってきました。 ──では、『デイリーポータルZ』自体の変化について伺いたいのですが、WEBメディアとして、時代による変化をどのくらい意識されているのでしょうか。 林 けっこう意識してるつもりで、実際に変わってると思います。2000年代は、インターネットで『デイリーポータルZ』みたいな記事を読む人も少なかったんで、変わったことをやっていればいいというか、サブカルチャーな感じでしたね。「工作しようとしたけど、できませんでした! いや〜失敗、失敗」みたいな読み物も受け入れられていた。 でも、今は結果を求められるようになって、「できませんでした」って言ったら「なんで完成してないのに記事に載せてんだ、ちゃんとやれ」みたいに言われてしまう。今、YouTubeにも器用な人がいっぱいいるじゃないですか。下手な人がいないので、下手を売りにできなくなったというか。本当はね、失敗した人が落ち込んだりしてるところがおもしろいと思うんですけど、そういうのは受け入れられなくなった気がします。 ──たしかに、結果や情報が主体で、ドキュメント性の少ないコンテンツが多いかもしれません。 林 ホームセンターに行って材料買わなきゃいけないのにアイス食ってるとか、そういうのはないですよね。 ──「材料は100均で買えるよ!」でおしまいですもんね。実際に行ってみたらなかったりするんですけど。 林 ないんですよねぇ。まあ、僕も10秒ですごいものがバーンとできる動画とか、回ってくると見ちゃうんですけど。だから記事のほうでも、最近は「できない」で終わるものはなくなってきたと思います。ただ、「あんまりできるようになってほしくないなぁ」というのが正直なところで。ライターには得意なことばかりしないようにお願いすることもありますね。 ──では、逆に変わらず大事にしているようなことはありますか? 林 書き手のキャラクターが見えるようにはしています。人に読んでもらうために、入口は「すごく辛いカレーを出す店がある」といった“情報”にしましょうと言ってるんですけど、そこから「実家のカレーより辛い」とか、自分のことやよけいなことも書いて、書き手の存在を見せるようにしたい。そこはブレずにやってますね。 あと、ただ奇を衒(てら)うんじゃなくて、動機となるような軸があるかどうかは大事にしてます。以前、「豚の鼻を食べる」という企画があがったんですけど、企画したライターが特に豚の鼻に思い入れがあるわけでもなかったので、そういう場合は「じゃあやめよう」と言っています。逆にディズニーみたいな王道のテーマでも、ライターが個人的にすごく好きで、「ここが!」っていうポイントがあるなら扱ってもいいかなと思ってます。 やるべきことをすぐに始めたくない ──独自のおもしろさを追求して、記事として発信したりしていると、人から「楽しく働いている」と思われがちなんじゃないかと思いますが、実際のところどうなんでしょうか。 林 楽しく働くようにはしてます。本当に仕事してんのか遊んでんのかわかんないような感じで、なるべくやりたい仕事だけやるようにしていて。生意気ですね(笑)。でも、最初に「イヤだな」と思った仕事を、お金になるから、お世話になってるから、次につながりそうだから、みたいに考えて受け入れると、結局「うわ、やんなきゃよかった……」ってなるじゃないですか。だから、最初の直感は意外に正しいというか、大事にしてますね。 ──とはいえ、お仕事なので楽しいだけではないかと思いますが、現場や会議などで人と楽しくやるためのコツなどはありますか? 林 企画やアイデアにダメ出ししなきゃいけないときは、ひたすら低姿勢でお願いしてます。現場でも、思いつきで新しい提案をしてきた人に「却下」って言わなくちゃいけないときは、できるだけ冗談っぽく言うようにしてます。それくらいですかね。 ──林さんが機嫌よくやっていて、周囲の機嫌も損ねないようにしている。地味だけど、チームで動くときは大事なことかもしれませんね。 林 機嫌が悪い人がいたらイヤですよね。だから僕、お菓子買って行ったりしますよ。あと、撮影で集まっても20分ぐらいダラダラしゃべって、なかなか始めない。来てすぐ始めようとする人には「ちょっと待って。おしゃべりしましょう」って言いますから。「なに効率よくやってんだ」っていう(笑)。無駄話も大事にしてますね。 知りたいこと、わからないことは増え続ける ──「くだらないことをおもしろがって楽しむ」って、年齢とともにモチベーションが下がるというか、できなくなってきませんか? 林 そういうことはないですね。たぶん、自分には子供がいないし、介護もしていないので、くだらないことに時間を使えるのが大きいと思います。興味を持つ対象なども変わらずで。何かを知れば知るほど、またわかんないことが増えて興味を持ったりしています。 でも、下品な企画は恥ずかしくなってきたかもしれない。この前も検尿用の折りたたみ式のコップが売られているのを見て、「これで飲み会やったらおもしろいかな」と思ったんだけど、さすがにそういうことはやれなくなりました。「若かったらまだかわいげがあるけど、おっさんがやってたらキツいな、見たくないな」って。 ──たしかに、人からの見え方は変わっていくので、そういう意味で「いい年だから」とブレーキがかかることもありますね。 林 だから、僕が若いYouTuberだったら、きっと炎上してたと思います。ちょっと前に、交差点に布団を敷いて怒られたYouTuberがいたんですけど、僕、企画メモに同じこと書いてましたから。「本当にやらなくてよかったな〜」と思いました。 ただ今後、YouTubeは照れずにやってみたい気持ちもあります。無駄話的なものや、その場の雰囲気、行間的なものを伝えるのなら、動画がいいんじゃないかと。工作するつもりが、木材を買うのに右往左往してるだけの動画とかいいですよね。 ──ほかに今後やってみたいことなどはありますか。 林 笑い屋さんを呼んで、絶対に爆笑になるお笑いイベントをやりたいと思ってるんですよ。スベるのは恥ずかしいじゃないですか。でも、これなら何をやったってウケるので、気持ちがいいっていう。実際に笑い屋さんの事務所に電話してみたら、けっこう安くお願いできることがわかったので、演者からお金をもらえば成立するんじゃないかと思ってるんです。素人参加型のオープンなイベントにして、おもしろいことをやりたい人たちを仲間にできたらいいですね。 屋上でサボるのが好き 愛用の双眼鏡で東京を眺める林さん ──林さんの「サボり」について伺いたいのですが、サボりと聞いてどんなイメージが浮かびますか? 林 喫茶店にいる会社員のイメージ。僕は打ち合わせに行くと、絶対にまっすぐ帰らず喫茶店に入っちゃいますね。スマホを見ると負けた気がするので、ぼーっと外を眺めたり、ひたすらぼんやり過ごすんです。 あと、展望台にも登ります。「三軒茶屋に来たから、キャロットタワーに登ってみよう」とか。休みの日にわざわざ行かないけど行くとおもしろい場所って、サボるのにちょうどいいんですよ。渋谷に事務所があったときは、渋谷スクランブルスクエアの年間パスポートを買って、しょっちゅう屋上に行ってました。 ──展望台や屋上では何をしているんですか? 林 アプリで上空を飛んでいる飛行機がどこの会社なのかわかるので、それを調べたりしてます。あと、屋上が好きすぎて双眼鏡を買っちゃいました。星空を見るための、倍率が低くて視野が広い双眼鏡があって、それで東京を眺めるんです。 アプリで飛行機を特定する林さん ──サボりグッズを日常的に所持している方は初めてです。さすがですね。ほかにも携帯しているものはあるのでしょうか。 林 いろいろ持ち歩いてるんですよ。温度と気圧のログが取れる温湿度計とか、液体とか金属の温度が測れる温度計とか。あんまり使ってないんですけど、何か測りたくなったときに「持っておけばよかった〜」って思うのが癪(しゃく)なんで。前に、西陽に当たってすごく熱くなったゴミ箱があって、温度を測りたかったのに測れなかったのがすごく悔しくて。 もしものために携帯している温度計 ──サボってはいるけれど、ちゃんとネタにしている感じもしますね。 林 記事になるかはわからないけど、気になったことは調べちゃいますね。スクランブルスクエアの屋上から見たら、品川方面のビルの高さがみんな同じだったので調べてみたら、羽田空港があるから高さの制限があるとわかったり。そういう発見はメモしてます。 趣味は「一銭にもならない仕事」 ──著書の『ビジネスマン超入門365』でも、サボりのテクニックのようなものが紹介されていますよね。「どこかに直行したことにするときは、つじつま合わせの行き先をメモしておく」とか。こういったものは、どのくらいご自身の経験がもとになっているのでしょうか。 林 ほとんど自分が経験してることかな。「直行直帰」ってホワイトボードに書いたときは、ちゃんとウソを貫き通せるように設定を考えてました。人事の人が見てたりして、バレるとけっこうな怒られ方をするので……。でも、会社を辞めてみると、やっぱり会社員ってラクだったなって思うんです。だって、雇われてる側としては、最小の労力でお金もらうべきだし、なるべくサボったほうがいいですもんね(笑)。 ──では、もっとシンプルに息抜きや趣味として楽しんでいることはなんですか? 林 趣味ってあんまりないんですよ。全部が趣味みたいなものだけど、仕事に関わらないものがほぼないので。パソコンでゲームをやっても、トラックで荷物を運んだり、車を洗ったり、パソコンを直したりしていて、遊んでるときにやってることが全部仕事っぽくて。一銭にもならない仕事は楽しいですね。 ──「一銭にもならない仕事」って、もう趣味ですよね。 林 そうですね。知り合いの経営者も、スキマバイトアプリに登録してコンビニでバイトしてるって言ってました。現場で働くのが楽しいみたいで。僕も知らない業界のハウツー本が好きで、本当はSEOの本とか読めばいいのに、消防士のホースのたたみ方とか、料理の盛りつけマニュアルとか、体育教師の指導要領とかを読んでます。 ──趣味としての仕事って、大人のキッザニアみたいなものだと考えたら、ちょっと需要がありそうな気がします。 林 あったらおもしろいですよね。僕もドラッグストアの品出しとか、ちょっとやってみたい。『Airbnb』で趣味として人の家に泊まれるようになったので、次は趣味として人の仕事をやるようになってもおかしくないと思います。 ──サボりとはかけ離れてしまいましたが、興味深いです。ちなみに、あえてシンプルな趣味をあげるとしたら……? 林 古本屋に行くか、ミスドに行くぐらいですね。 ──サボってるときと変わらない(笑)。ありがとうございました。 撮影=石垣星児 編集・文=後藤亮平
-

「自分の中の衝動と向き合い、うまく付き合う」越智康貴のサボり方
クリエイターの活動とともに「サボり」にも焦点を当て、あの人はサボっているのか/いないのか、サボりは息抜きか/逃避か、などと掘り下げていくインタビュー連載「サボリスト~あの人のサボり方~」。 フローリストの越智康貴さんは、ショップを経営するほか、イベントや広告などでフラワーアレンジメントを手がけている。花の美しさを引き出す作品だけでなく、写真や文章でも注目を集める越智さんに、フローリストとしての考え方や、サボることの難しさについて聞いた。 越智康貴 おち・やすたか フローリスト/「ディリジェンスパーラー」代表。文化服装学院にてファッションを学んだのち、フローリストの道へ。2011年、ディリジェンスパーラーを開業。ショップ運営のほか、イベントや店舗、雑誌、広告などのフラワーアレンジメントを手がける。また、写真や文章の分野でも活躍している。 「向いてるな」という直感で花の道へ ──服飾系の学校を卒業されたのに、なぜフローリストの道を選ばれたのでしょうか? 越智 服飾の学校を卒業したら資格の専門学校に入学する予定だったんですけど、そのときに花屋でアルバイトをしていたんです。それで、「こっちのほうが向いてるな」と思って、すぐに独立しちゃいました。 当時は「手に職をつけなければ」という焦りがあって。それで、アパレル関係の会社に就職した友達などが、展示会やポップアップストアをやる際に「花を生けてよ」って頼んでくれるようになったこともあり、とにかく失敗してもいいから独立してやってみようと。そのまま10年以上が経ったという感じですね。 ──それでなんとかなるものなんですか? 越智 でも、最初の1年は本当に仕事がなかったし、請求書の作り方とかも何もわからなかったので、とにかく手探りのままなんとか生きてきました。4年ぐらいはショップの一部を間借りして花を売っていたんですけど、外に出る仕事が多くなってきたころに、「表参道ヒルズのコンペに参加しないか」とお声がけいただいて。そのコンペに参加して店を出すことになり、会社化したあたりからちょっと流れが変わってきました。 でも、会社を作ってからの1〜2年も大変でしたけどね。店の固定費が跳ね上がって、人も雇うことになって。人間と働くのがイヤで独立したのに、あれよあれよと人間、人間……ってなっちゃって(笑)。 「花で表現はしない。花は花でいい」 ──外でも花の装飾などをたくさんやられてきたとのことですが、お仕事としてのターニングポイントなどはありますか? 越智 手応えのある仕事をひとつやったというよりは、グラデーションのように変わっていった感じですね。僕、スタイルがどんどん変わっていくんですよ、会社の経営スタイルでも、外から来る仕事でも。だから、いろんな仕事が連鎖していって、実力もついていったし、評価していただけるようにもなっていったと思います。 ──経営スタイルはどう変わっていったのでしょうか。 越智 僕は既存のやり方に則らない方向でしか物事を考えられなくて。インディペンデントな花屋なのに商業施設に入ったのも、そういう店がほとんどなかったからなんです。インディペンデントな小規模の花屋さんって、センスのいいフローリストさんがオーナーで、隠れ家的にやっていることが多かったんですよね。 でも、自分はそういう方法だと長く続かない気がして、店舗に立つ頻度なども減らしていき、店と自分を分離するようになりました。やっぱり店ってお客様が作っていくものというか、自分がいなくてもお客様のニーズに合わせて物事を展開していけば、それがいつの間にかブランドになっていくと思うので。 ──越智さんらしさにこだわらないんですね。 越智 もちろん僕のアイデアもありますが、ルールを壊していく発想が多いので、どうしても定着するのに時間がかかるんですよ。透明の取っ手がついた花を入れるためのバッグがシグネチャー的に有名になったんですけど、それも最初はみんな「何これ?」みたいな反応でしたし。 あと、花屋の特徴として、花を買いに来てくださる方+それを受け取られる方、ふたりのお客様がいるんです。買いに来てくださるお客様は花を贈るお相手のことをわかっているようでわからない場合も多いので、「お相手に合うものを花で用意するとしたら何がいいだろう?」と考えたり、わりと翻訳的な仕事が求められる。それによって自分たちも助けられ、店として成長していったところもあります。 ──外で装飾のお仕事をされる場合、依頼内容や目的などはありますが、もう少し表現する要素が強いかと思います。そこの違いはあるのでしょうか。 越智 それもあまり自分の個性みたいなことは考えてなくて。花で表現したいことも特にないというか、表現媒介として花を使うっていうことをなるべく避けようと思ってるんです。花は花でいい。だから、花屋の場合と同じで、頼んでくれた方が言っていることを翻訳していくイメージですね。 もちろん、それでも自分の視点が反映されて、どうしてもスタイルみたいなものはできてしまいますが、本当はそれも避けたい。自分の持ち味みたいなものには興味がないので、仕入れなんかもスタッフに任せたりします。 「なんか違う」言葉にできない感覚をどう生み出すか ──ひとつのスタイルや自分にこだわらないとのことですが、ずっと花と向き合ってきたことで、植物に対する考えや捉え方などは変わってきていますか? 越智 そうですね。生花もやってるんですけど、その影響は強いです。花の個別性や、「そこにある見えないもの」を重視するようになりました。その場に花が一輪あることで雰囲気が変わる、その雰囲気をそのままパッケージしたいと思ったりするというか。すごく感覚的な話なんですけど、そういった人の感覚的なものに頼るようになってきました。「なんか違う」ことをやっていると、見た人も「この花屋さんはなんか違う」と思ってくれる。そういう言語化できないことを徹底的にやっています。 ──「なんか違う」を生み出せたかどうかが、越智さんの中でOKかどうかの基準になっているとか。 越智 なんか違わないとヤバいっていうか、そこに驚きとか喜びがないとつまらないなと思っていて。一見何も気にならないのに、大きく見ると今までにない印象が生まれるとか、目に見えないものをそこに生じさせるとか、そういうことができないかずっと考えています。まだ全然成功してないんですけど。すごくめんどくさい話してますよね(笑)。 ──いやいや(笑)。でも、なぜそういう考えなのかは気になります。 越智 自分の中に3方向くらいの衝動があって、それぞれが緊張状態にあるんですよ。まずルールに縛られず自由でいること。同時に博愛的であること。そこが自分にとっての喜びにつながっているんですけど、一方で物事を持続したり変えなかったりすることにも安心を感じる。独立したいけど、博愛的でいたい。新しいことをやりたいけど、変化したくない。そういう方向性の違う衝動が自分の中でぐるぐるしてるんですよね。 ──それが仕事や表現にも影響している。 越智 そうですね。サイコロの出目みたいにどんどん変わるので、スタッフも困ってるんですけど、みんな慣れてきて無視するようになりました(笑)。文章や写真の仕事をやっているのも、そういう自分の中のさまざまな衝動を逃すためなんです。花では自分を表現していないし、それだけだと過集中しちゃうので。だから、自分らしさは文章で表現すると決めています。 ──文章ではどんな活動をされているんですか? 越智 仕事として短い話やエッセイを書いたりすることもありますし、個人的な制作として小説を書くこともあります。花や写真では自分を表現したいと思っていないにもかかわらず、そのことにストレスも感じてるんですよね。頼まれた仕事だけが世に出ることで、それが自分らしさだと思われてしまうから。 ──自分を正しく理解してほしい、といった気持ちもあるんですか? 越智 理解してほしいとはあんまり思ってないですね。ただ、愛してほしい。「こんなことを考えてるよ」「こんなことをしたよ」「こんなところに行ったよ」って、愛してほしくて書いてるんだと思います。あと、文章では「こういうことってあるよね」「こういうのはわかるかもしれない」っていう、言葉にできていなかった体験を人と共有したい気持ちもあります。 ──文章について、何かやってみたいことなどはありますか。 越智 いくつか話が溜まってきていて、ちょっとずつ人に読んでもらったりしてるんです。それがもうちょっと溜まったら、本にできるといいですね。 猫は神様が作った最高傑作 ──頭の中も仕事も忙しいと、サボりたくなったりはしませんか? 越智 サボってると安心できない状態になってしまうので、本当にサボれないんですよ。そういうものが必要な人もいることは理解できるんですけど、自分にはちょっと当てはまらないというか。純粋に趣味といえるものもほとんど存在しなくて。美術を観るのも、映画を観るのも、本を読むのも好きなんですけど、全部「自分だったらこうする」とか、何か制作したい気持ちと切り離せないものなので。 ──仕事や制作と関係のない時間がほとんどない。 越智 でも、猫を飼い始めたんですよ。対象を決めて、そのために時間を使っているぶんには大丈夫なので、猫と遊んだり、猫の世話をしたりしている時間が、自分にとってはサボるということなのかもしれないです。本当に時間貧乏性なので、何かしてないとダメで。 ──猫と戯れている時間だけは、そこから解き放たれているんですね。 越智 友達と遊んでいても、頭の中はめちゃくちゃぐるぐるしてるんです。でも、猫は思考を追う必要がない。猫の性質や動いていることから受け取るものもありますし、めちゃくちゃ猫のことを文章にしたりもしてるんですけど、仕事が絡んでないというか、「かわいい、OK」みたいな感じで。だから、「猫は神様が今まで作ったもので一番完成度が高い」「猫がもたらすものは世界平和だ」と本気で思ってます。 あと、文章を書くこともけっこうリフレッシュになりますね。そのときだけは考えていることが外に出ていくから、デトックス的な感じかもしれないです。しかも、最終的に人に見せることができるのも、自分としてはうれしい。 ──コーヒーを飲むとホッとするとか、そういう些細なレベルのものはないですか? 越智 食べ物も全然興味がないんですよね。先日、京都に5日間いたんですけど、ずっと朝はベローチェでサンドイッチ、昼はベローチェでホットドッグ、夜はカロリーメイトでした。友達とごはんに行くと、ちょっとしたビストロとかに入るじゃないですか。そういうのも一切興味ないんですよ。お酒も飲みますけど、けっこう強いからあまり酔わないし、リラックスすることもなくて。 「動いてるほうがサボれるんです」 ──安らいだり楽しんだりする時間も広くサボりとして伺っているのですが、基本的に活動していたいということなんですかね? 越智 僕の場合、安心、安全みたいなものがエネルギーや闘争心とくっついてしまっていて、活動的であることに安心するんです。だから、物事の持続や、発展・拡大を実感することでリラックスしてる。動いてるほうがサボれるんです。喜びを感じるのはまた別の領域なんですけど。 ──仕事と趣味の境目がなくて、結果としてサボりを必要としていない方もいますが、それともまた違いますね。 越智 母親の影響もあるかもしれません。母子家庭で、母親がずーっと働いてる家だったんですよ。それが安心のかたちを作ってしまったと思いますね。ただ、経理の人が「休むのも仕事だから、本当に休めるときに休んでください」ってすごく言ってくれるので、「なるほど、仕事か」と物理的に休むようにはなりました。 ──ちなみに、睡眠はしっかり取るタイプですか? 越智 睡眠もヤバくて。寝たり起きたりみたいなことが多いですね。猫も平気で起こしてくるから。睡眠にアプローチするアロマオイルにハマったり、いろいろトライしてますけど、なかなか難しい。夜中に目覚めたら、夢で見たものを全部メモしようとしたり、「こういうふうに編集すればいいんだ!」っていきなり動画編集を始めたりしちゃう。「どうせしばらく眠れないから、無理に眠ろうとせずに仕事しよう」って。本当にヤバい(笑)。 ──やっぱり猫と遊ぶしかないですね。 越智 でも、つい「いつか死ぬんだよな……」ってなっちゃう。2匹いるので、今は夜中に追いかけっこ始めて走り回ったりするから「ええ加減にせえ」ってなるんですけど、それだけが心配ですね。 撮影=石垣星児 編集・文=後藤亮平
-

「前例に捉われず、自分たちが楽しめるかを考える」サリngROCKのサボり方
クリエイターの活動とともに「サボり」にも焦点を当て、あの人はサボっているのか/いないのか、サボりは息抜きか/逃避か、などと掘り下げていくインタビュー連載「サボリスト~あの人のサボり方~」。 ちょっと不気味で不思議な作風で、関西の演劇シーンで活躍している劇団「突劇金魚」のサリngROCKさん。最近では映画『BAD LANDS』での怪演も話題になった彼女に、劇団独自のスタイルやルーツ、サボりマインドについて聞いた。 サリngROCK さりんぐろっく 劇作家/演出家。2002年、劇団「突劇金魚」を旗揚げし、大阪を拠点に活動。2008年に第15回OMS戯曲賞大賞、2009年に第9回AAF戯曲賞大賞、2013年に若手演出家コンクール2012優秀賞を受賞。2023年には映画『BAD LANDS』にて俳優として映画デビューし、第78回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞を受賞した。 就活がイヤで劇団旗揚げ…? ──演劇と出合ったのは、高校時代に所属されていたという演劇部ですか? サリngROCK(以下、サリ) そうなんですけど、高校のときはあまり演劇を知らなくて。大学に入学するころに、演劇好きの先輩に連れて行ってもらった「惑星ピスタチオ」を観て衝撃を受けて、小劇場の作品を観るようになったんです。 惑星ピスタチオの舞台って、オブジェみたいな抽象的な舞台美術で、その中で宇宙を表現したりしてたんですよ。体ひとつで人物や物語を想像させられるのがすごいなって。演劇で想像力を掻き立てられるという体験が初めてだったので、すごくびっくりしたのを覚えてます。 ──そこから大学で劇団を立ち上げるようになったきっかけは? サリ 当時の演劇サークルでは、先輩たちが卒業のタイミングで劇団を作っていたので、前例があったんですね。もうちょっと演劇をやりたかったのと、なにより就職活動がめちゃめちゃイヤやったんで(笑)、だったら先輩たちみたいに同級生と劇団をやってみようと。私は演出がやりたかったんですけど、脚本を書く人が誰もいなかったので、自分で脚本も書いたのが最初の公演でしたね。 ──立ち上げ当初から、劇団としてのコンセプトやイメージなどは決まっていたのでしょうか。 サリ 子供のころからかわいいキャラクターより幽霊が好きだったり、ティム・バートン監督の映画が好きだったり、ちょっと不気味だったり、痛々しかったりするものに惹かれるんですよ。だから、そういうドロドロとしたものを入れた、ひと筋縄ではいかない舞台にしようとは思っていました。 ──実際に公演をやってみて、手応えはありましたか? サリ とにかくやりきれたというのが大きくて。やりきることを続ける、初期はそれだけやったと思いますね。若手のための演劇祭にもとにかく出場していたんですけど、そしたら、劇場のスタッフさんが選ぶ賞をもらえて、劇場が使える権利をもらったんです。それが人から認められたほぼ初めての経験だったので、「この方向でいいんや、間違ってなかった」みたいに思えた気がします。 ──そこから公演を打ち続けるなかで、ターニングポイントなどはあったのでしょうか。 サリ 28歳のときに、OMS戯曲賞という関西の劇作家が欲しがる戯曲賞で大賞をいただいたんですよ。そこから観に来る人もガラッと変わって、「どんなもんやねん」って批評的に観られるようになり、「脚本は独特でおもしろいけど、演出と俳優がめちゃめちゃダメや」といったことを言われるようになりました。特に演劇の勉強をしてきたわけではなかったので、やっぱり未熟やったんだと思います。 それで、「何がダメなの?」と思うようになったころ、今も一緒に突劇金魚をやってる山田蟲男くんが劇団に関わるようになったんです。山田くんのほうがわりとロジカルに技術的なことも考えているタイプで、だんだん「だったら、こうしたほうがいいんじゃない?」って提案してくれるようになって。彼の言うことに応えようと、薦められた本を読んだり、作品を観たりしながら技術を身につけていったことで、徐々にできることも増えてきた。そう思えるようになってきたのは、ここ最近の話なんですけど。 活動の軸は「楽しく生きていくこと」 ──劇団を続けることは簡単なことではないと思いますが、ひたすら試行錯誤を続けるうちにここまで来た、という感覚なんですかね? サリ それに近いと思います。技術を身につけて客観的にわかりやすくなった作品は評判もいいんですけど、私独特のヘンテコな要素が薄まると、それはそれで「前のほうがよかった」と言われたりもする。でも、そこは絶対両立できるはずなので、今もヘンテコだけど伝わりやすいラインを探してます。そういう目の前の課題をただやり続けてきたというか。 あと、今は劇団も山田くんとふたりでやってる状態なので、ふたりが納得すればいい。だから続けられてるところもあります。それを「劇団」って言っていいのかよくわからないんですけど。 ──1公演で俳優2チームのWキャストにするといった独自のスタイルも、その結果のひとつなのでしょうか。 サリ 山田くんがけっこう前例に捉われないアイデアを出してくるんです。大人数のキャストを2チームにするのもそうで、私が「そんなんやってる人おらんけど大丈夫なん?」って聞いても、「論理的に考えたら、このほうがうまくいくんや」みたいな。 結果的に、俳優さんがケガや病気になっても中止にしなくて済みますし、関係者が増えれば公演の宣伝をしてくれる人も増えるので、そういう意味でも助かっています。それに2チームあるだけで、俳優さんたちがそれぞれ勝手にがんばってくれるんですよ(笑)。 ──切磋琢磨する状況が生まれるんですね。関西の小劇場というシーンなどはあまり意識されていないんですか? サリ 同世代とは友達感覚はありますけど、横のつながりを意識するようなことはあまりないかもしれません。「アイツら、なんかヘンなことやってんな」って思われてるんじゃないですかね。前例や風習に捉われないという意味では、裏方の仕事など、当たり前に人に頼んでいた仕事についても一から検討して、自分たちでできることはやろうとするから、まわりから変わった目で見られている気がします。 ──劇団としてのあり方にも捉われていない印象ですが、活動のイメージも変わってきているのでしょうか。 サリ ふたりとも40歳を過ぎたので、劇団の核になるものについて改めて話し合うようになったんです。それで、劇団を続けるとか売れるとかじゃなくて、我々ふたりが楽しく生きていくことを軸にしようと話していて。 次はどこどこの劇場でやろうとか、東京にも行かないといけないんじゃないかとか、そういうことは無視しようと。できるだけしんどいことは無理してやらんとこうというか。「自分たちの人生のためになっているか」が基準としてはっきりしてきたので、結果として、私が全然演劇をやらなくなる可能性だってある。そうやって縛られずに考えられるようになったのはいいことやなと思いますね。 映画初出演で感じた、演劇との違い ──最近では映画『BAD LANDS』への出演の話題になりましたね。ただ、最初は監督からのオファーを断られていたそうですが……。 サリ でも、映画の現場はめちゃくちゃ楽しかったです。演劇では、お客さんにちゃんと声を届けるとか、顔が見えるように立つとか、役者+お客さんで演じるんですよ。そこが楽しみのひとつでもあるんですけど、映画では目の前の俳優さんと演技すればいいだけなのがめっちゃ楽しくて。もちろん、映画でもカメラの位置やいろんなことを意識しなければいけないんでしょうけど、初めての映画出演だったんで、そこは今回は無視させていただいて。 ──裏社会に生きる林田というキャラクターを演じる上で意識したことなどはありますか? サリ かたちから入ることってめっちゃ大事だと思うんです。かたちを心がけてたら、中身も寄っていくというか。それで、なるべく瞬きをしないようにしたり、口を半開きにしたり、ちょこまか動かないようにしていました。あとは基本的に演出どおりにやれば成立するものなので、ヘンなことをやろうとしたり、「ちゃんと演じたろう」みたいな欲は出さないようにしました。そういうのって、バレるんですよね。 ──こうした経験をきっかけに、演劇でも自ら演じる機会が増えるような可能性もあるのでしょうか。 サリ あるかもしれないですね。演出をやりながらだと難しいところもあるし、外部の作品に役者として出ることにもあまり興味がないので、どういうかたちかはわかりませんけど。ただ、山田くんとは「二人芝居やりたいね」といった話もしているので、役者としてのウェイトが大きい公演を、ふたりで演出しながらやってみたいとは思ってます。 時間が許すなら、イヤになるまでサボり続ける ──サリngROCKさんは、「サボりたいな」と思ったりすることはありますか? サリ 私の仕事の場合、みんなで仕事してる最中にひとりだけサボって抜け駆けするようなことはないんですけど、やらなきゃいけないことがあるのになかなかできない、みたいなことならめっちゃあります。でも、結局締め切りに間に合うんだったら、それも必要な時間というか。 「スマホを見なきゃもっと仕事が進んだのに」って思うよりも、「私はそこでスマホを見る人間だし、この作品はそんな人間が作ったものなんだ」って思っちゃうというか。そういう達観みたいなものはあるかもしれない。 ──やっぱりサボるときはスマホを見てしまうことが多いんですかね。 サリ そうですね。SNSとか、YouTubeとか。そういうときはもう飽きるまで見続けます。逆にそっちがイヤになるまでやっちゃったほうがいいんじゃないかなって。結局、スマホを見続けられてるってことは、その時間が許されてるってことなんで。ほんまにやんなきゃいけなかったら、やるじゃないですか。 ──そのほうがすっきり切り替えられそうですね。もうちょっとポジティブなサボりというか、アイデアにつながるリフレッシュとしてやっていることはありますか? サリ お風呂に入ってリラックスしたら新しいアイデアが湧く、みたいなことがあまりないので、映画を観たり、偉人たちの戯曲を読んだりしますね。インスピレーションを受けようと思って観たり読んだりするわけじゃないんですけど、人のアイデアに触れることで何か考えたり、受け取ったりすることが多い気がします。 ──より趣味に近いかたちで楽しんでいるものもあるのでしょうか。 サリ これも創作ではありますけど、絵を描くことですかね。時間ができたら絵を描きたい。でき上がったものがパッと一瞬で目に入るのが好きなんですよ。脚本は「完」って書くのが気持ちよくても、一瞬で全部は見られないので。ただ、もうちょっと本格的にやろうとしたら、絵を描く手が止まってしまいそうな気もするんですけど。 ──では、より仕事に関係なくリラックスしたり、楽しんだりできる時間は? サリ スーパーに行って野菜を選んでるときです。別に料理好きなわけじゃないんですけど、「今日は自炊する余裕があるんだ」とか「普通の日を過ごせている」って思えるのがうれしくて。だから掃除でもよくて、余裕を感じられることがうれしいというか。 あと、最近はユニクロのお店に行ったり、サイトを見たりするのがめっちゃ好きで(笑)。新商品が次々出るので、チェックするのが楽しい。好きなブランドと似合う服って違うんだということがようやくわかってきたので、ユニクロでいろいろな服を試してて……ってどうでもいいか(笑)。 ──いやいや(笑)、そういうささやかな楽しみも聞きたいんです。 サリ コラボものとかは大きい店舗にしかないので、わざわざ発売日に自転車で遠い店まで行ってるんですよ。発売日がいっぱいあるっていいですよねぇ。 撮影=石垣星児 編集・文=後藤亮平
-

「サボりたくなる人間だから、短歌を書いているのかもしれない」伊藤紺のサボり方
クリエイターの活動とともに「サボり」にも焦点を当て、あの人はサボっているのか/いないのか、サボりは息抜きか/逃避か、などと掘り下げていくインタビュー連載「サボリスト~あの人のサボり方~」。 歌人の伊藤紺さんは、心のどこかにある感情、情景が呼び起こされるような歌で多くの共感や支持を集めている。3作目となる歌集『気がする朝』も反響を呼んでいる伊藤さんに、短歌との出合いや、歌が生まれる過程、サボりと創作などについて聞いた。 伊藤 紺 いとう・こん 歌人。2016年に作歌を始め、2019年に『肌に流れる透明な気持ち』、2020年に『満ちる腕』を私家版で刊行する。2022年には、両作を短歌研究社より新装版として同時刊行。最新刊は2023年に発売された第3歌集『気がする朝』(ナナロク社)。 短歌と出合って、すぐに投稿を始めた ──短歌と出合ったのは、大学生のときだそうですね。 伊藤 最初は小学生か中学生のときに教科書で見た俵万智さんの歌だと思うんですけど、そのときは特にすごいと思ったりはしなかったんです。でも、大学4年生の年末に突然俵さんの歌を思い出して、「あれ? なんかわかるかも、いい歌かも」と思って、そのまま本屋さんで俵さんの『サラダ記念日』(河出書房新社)と、あと穂村弘さんの『ラインマーカーズ』(小学館)という歌集を買いました。 ──読んでみてどうでしたか? 伊藤 歌集って400首くらいの歌が載っているので、よくわからないものもあったんですけど、繰り返し読みたくなるほど「いいな」と思える歌もあって。それから短歌や歌人についてネットで調べて、佐藤真由美さんの『プライベート』(集英社)という歌集と出合いました。とっつきやすい言葉でリアルなことが書かれていて、すごくおもしろくて。そのあとすぐ、2016年元旦に短歌を始めました。 ──「おもしろい」から「やってみよう」までが早いですね。なんとなく詠み方などもつかめたのでしょうか。 伊藤 いや、何も考えてなかったです。かわいいイラストを見て自分でも描いてみたくなるのと同じような、軽い感じでしたね。なんでもすぐにやってみるタイプではあったので、なんとなく1首書いてみて。それが2首、3首と書くうちに「いいかも」と思えてきて、母に読んでもらったりしていました。 ──人に見せるのも早いですね(笑)。 伊藤 書いたその日には当時のTwitterにアカウントを作って、短歌を投稿し始めてましたから。ただ、当時は短歌そのものに愛を感じていたというよりは、「わかる/わからない」という基準で判断しているところが大きかったし、まだ趣味にも満たないマイブームっていう感じでしたね。 でも、歌人の枡野浩一(※)さんが早い段階で「いいね」してくださって、「あれ、才能ある……?」みたいな(笑)。枡野さんは特別うれしかったけど、そうでなくても反応をもらえること自体が当時のモチベーションの一部だったと思います。 (※)簡単な現代語で表現されているのに思わず読者が感嘆してしまう「かんたん短歌」を提唱するなど、若い世代の短歌ブームを牽引した歌人。 「若い女性の恋心」を詠んでいるわけではない ──歌人として活動していくようになったのは、どんなタイミングだったのでしょうか。 伊藤 短歌を真剣に書き続けている人はみんな歌人だと思いますし、「歌人になる」というタイミングはほぼ存在しないと思うんですけど、肩書を「歌人」だけにしたタイミングはなんとなくありました。それまではライターやコピーライターとしても活動していて、特に短歌では食べていけない気がしていたし、そもそも作家は精神的に苦しいだろうから、あんまりなりたいとは思ってなかったんです。 だけど、どんどん短歌だけが調子づいてきて、ほかの仕事とは違う早さでいろんなことが進んでしまって、「これなのか……?」って。今でもたまにコピーを書くことはありますが、「歌人・伊藤紺」として、自分の言葉で書くものだけ、ということにしています。 ──手応えのある歌ができた、といったことでもなく? 伊藤 その時々で「書けてよかったな」と思える歌はちょこちょこあるんですけど、あとから思うとそうでもなかったような気がすることもありますし、これといった歌があったわけではないと思います。ただ、最近はいいと思える打率が上がってきたというか、外さなくなってきたような感覚はありますね。 ──では、周囲の反響による手応えはあったのでしょうか。2019年には私家版(自主制作の書籍)というかたちで最初の歌集『肌に流れる透明な気持ち』を作られていますよね。 伊藤 第1歌集は300冊作ったらすぐ増刷になり、(私家版も扱う)書店にも置いてもらえて、思ったよりも反響があってうれしかったですね。読者の方の解釈を聞いたりするのも新鮮で楽しかった。でも同時に「若い女性の揺れる恋心」みたいなよくある言葉がひとり歩きすることがあって、抵抗もありました。自分はそういうつもりじゃなかったので。 ──ご自身の中ではどんな作品、作風だと認識されていたんですか? 伊藤 当時はあんまりわかってなかったですね。「なんか違う気がするな」っていうだけで。少し成長してある程度見えてきたのは、作品内での他者への特別な感情について、恋とか愛とか友情とかっていう仕分けをあんまり重視していないということです。「情」って言葉が近いのかな。人間でなくてもよくて、動物や植物に胸がきゅうっと動くのも全部一緒でいい。登場人物の設定などを詳細に書かなくてもいいから短歌がおもしろかったのに、「若い女性の恋」だけになっていくことに違和感があったんだと思います。 でもやっぱり「きみ」とか「あなた」って入っていたら恋の歌に見えやすいし、事実、私は「若い女性」だったし、今の話を聞いても「恋だ」と思う人もいるはずで、それはそれでもちろんいいんです。自分にできることは、そういう違和感に向き合って、描きたいものを明確にしていくことなのかなって。 ──そういった変化は第3歌集の『気がする朝』にも反映されているのでしょうか。 伊藤 そうですね。歌を作るにしても、本当に書きたいことか、立ち止まることが増えたように思います。歌の並べ方もそうで、編集の村井(光男)さんがいわゆる恋っぽい歌をひいおじいちゃんの歌の近くに置く案をくれたとき、すごく見え方が変わることに気づいて。それは大きな発見でした。 歌になるのは、自分にとって「真実らしきもの」 ──伊藤さんの場合、短歌はどういう流れで作られているんですか? 伊藤 自分にとっての真実らしいものが見つかると、それが歌になると思うんです。自分にとってはそれが情とか自由、命みたいなものだと思うんですけど。生活しているなかで、そういう真実のかけらみたいなものを見つけたらメモしておきます。短歌を書こうと思ってパソコンに向かったときは、そのメモから広げていくことが多いですね。 まずは短歌にしてみて、それを読んで「こういうことじゃないな」とかって思いながら、改行しては書き直していく。ちょっとずつ軌道を変えていったり、突然思いついた方向にガラッと変えていったりしながら、いいと思えるかたちになるまで書き続けています。 ──考えてみれば当たり前なんですけど、やっぱりパソコンで作るんですね。 伊藤 申し訳ない(笑)。 ──いえいえ、さすがに短冊に筆で書いたりしていないと思いますが、なんとなくアナログなイメージというか思い込みがあったので。改行しながら書き連ねていくことは、思考の痕跡を残すためでもあるのでしょうか。 伊藤 そうですね。行き詰まったら過去に書いたものやメモを見返して、いいと思えた要素を取り込んだりすることもあるので。けっこうしょうもないことも書いたまま残しているから、あとで見るとひどいなって思うこともあるんですけど、いいものだけ残そうとするとカッコつけちゃうんですよね。なんでもいいから書き続けることが大事というか。 ──以前は完成までたどり着けなかったメモが、時を経てかたちになる、といったこともありますか? 伊藤 ありますね。時間が経って自分が成長したことで書けるようになる場合もありますし、時間が空いたことで客観的に見直せるようになる場合もあります。たとえば、「机と宇宙」という言葉の感じが気に入っていても、何がいいのかわかっていないと、下の句にたどり着けなかったりする。でも、時間を置いてから見直すと、そのよさや言葉の結びつきがわかることがあるんです。 ──何かを感じたときにメモしておく習慣があると、自分の感動や感情に意識的になるし、その気持ちを思い出すこともできるんでしょうね。 伊藤 そう思います。なるべく新鮮な状態で言葉にしておくと、言葉を解凍したときに食べられる、みたいな。メモせずにあとから思い出して書こうとしても、感動が言葉にたどり着かなくなることもあるので。 今は小石のような真実が、いつか世間の真実になるかもしれない ──『気がする朝』のあとがきに、短歌を書くことは「日常の些細な喜び」ではなく、「100%の満足」だとあったのが印象的でした。日常の中で「真実らしいもの」を見つけていくこと自体が生きることだという意味でもあるのかなと思ったのですが、いかがでしょうか。 伊藤 そうですね。でも、真実らしいことでなくても「お茶がおいしい」とか「木漏れ日がきれい」とかで心が大きく動くこともあるし、そういうふうに楽しく生きてはいける気もする。短歌と生きることがイコールではないです。 『気がする朝』は「このところ鏡に出会うたびそっと髪の長さに満足してる」という歌で始まるのですが、この歌もひとつの真実らしいものが基盤になっていて、その発見が歌になっています。その真実は私がそのへんで拾ってきた小石のような真実なので、きっと理解しない人もいる、というかそっちが多数派でしょうね。逆に自分が多数派だったら書こうとも思わないのかもしれない。 ──そういった気づきから、「自分」というものを発見していく感覚はあるんですか? 伊藤 あまり自分で意識したり実感したりしたことはないんですけど、あるかもしれません。自分の言いたかったことや思ったことを短歌にして、それを何度も読んだりするのって、自己理解にもつながりますしね。 でも、その小石のような真実を「みんなも本当はこうなんじゃない?」ってどこかで思ってるんですよね。100年後、1000年後、世間一般の真実になっているかもしれないって。だから、「自分」を発見するということにもつながっているけど、自分の特異性というよりは、いつかどこかで誰かと共有でき得るものだと思っているかも。 ──みんなが気づいていないだけかもしれない。そんなふうに、伊藤さんの歌によって自分では意識していなかった感情に気づいた、という経験をした読者も多いのではないでしょうか。それって作家としてはうれしいことですよね。 伊藤 よく言われます。すごくうれしいですね。ただ、そう感じてもらうことが短歌を作る目的ではないので、自分にとっての山頂を目指して歩いていたら、給水スポットの人がすごく優しかった、みたいな感じというか。 ──なるほど。では、伊藤さんの中で今後目指したい山のイメージなどはあったりするのでしょうか。 伊藤 書きたいと思ったものを短歌にするという意味では、毎回山頂に登ったような気持ちで作品を作っていて、登りきったところでまだ山頂ではないことに気づいたり、別の山に登ってみたくなったりする感じなんですね。 それで今、ちょっと登りたい山があって、「5・7・5・7・7」ぴったりの定型に帰ってみようかなと思ってるんです。作品作りを積み重ねていくなかで、どんどん定型から外れてきたんですけど、『気がする朝』で自分のやりたいことがすごくできたので、勉強がてら定型に戻ってみたいなって。いざやってみるとどうしても外れてしまうので、今は難しいと思いながら向き合っているところです。 「ずっとサボってゲームしてます」 ──伊藤さんは、作業をしなくてはいけないと思いつつ、サボってしまうようなことはありますか? 伊藤 ずっとサボってますね。ゲームしちゃうんです。最近は、落ちてくる数字を小さくまとめていくゲームとか、ブロックをそろえて王様を助けてあげるゲームとか。サボりっていうか、気がつくと8時間くらいやっちゃうこともあります。作品を作ったり、本にしているときが一番逃げやすいので、『気がする朝』を出したあとはそんなにやらなくなったんですけど。 ──やっぱり、やらなきゃいけないことがあるからこそ、サボりも発生するんですよね。 伊藤 そうですね。ゲームをやることが楽しいわけじゃないのに、サボってる間は楽しくなるんですよ。でも、もうちょっとちゃんとしたサボりというか、スーパーで買い物するついでに散歩したり、喫茶店で本を読んだりしてリフレッシュすることもあります。 ──リフレッシュを挟むことで、作業が進展するようなこともありますか? 伊藤 けっこうあります。散歩から帰ったときにメモしたいようなことが出てきたり、行き詰まっていた原稿がはかどるようになったり。5日くらい外出しないこともあるんですけど、そんなときも家事をしたり、お風呂に入ったり、何か食べたり、そういうことをちょこちょこ挟んだほうが調子は出やすいですね。 ──ずっと家にいられるタイプなんですね。1時間おきとかにできそうな、気軽な息抜きもあったりしますか? 伊藤 詩集を読んだりしますね。好きな1節とか1ページだけ読んで本を閉じると、「いかんいかん」って書きたい気持ちが戻ってくることがあります。小説だと戻れなくなっちゃうので、つまみ読みできるような詩集がいいんです。Instagramとかも見ますけど、猫の動画をずっと見ちゃったりして、「いかんいかん」を20回くらい繰り返すことになるので……。 ──戻れない感じ、すごくわかります。そういうブレを断ち切って、ストイックに作品に向き合いたいと思ったりすることはあるのでしょうか。 伊藤 うーん……ありますけど、たぶんそういうことができる人間だったら、短歌を書いてないんじゃないかなって思います。もっとお金がいっぱいもらえる仕事に就いたほうがよさそうじゃないですか。もちろん、芸術や文化を愛している人の中にもストイックに動き続けられる人は山ほどいるわけですけど、自分の場合は短歌と出合う前にやりたかったことが本当はたくさんあった気がするので、そのうちのどれかをしているんじゃないかな。そうじゃないからここに来てしまった感じがします。 撮影=石垣星児 編集・文=後藤亮平
Daily logirl
撮り下ろし写真を、月曜〜金曜日に1枚ずつ公開
-
 村重マリア(Daily logirl #206)
村重マリア(Daily logirl #206)村重マリア(むらしげ・まりあ)2004年7月10日生まれ。山口県出身 Instagram:maria0710murashige X:@murashigemaria 妹の村重エリカと結成したバンドグループ「STRAWDAY」としても活動中 X:@STRAWDAY_OFCL Instagram:strawday_official 撮影=時永大吾 ヘアメイク=菅野綾香 編集=中野 潤 【「Daily logirl」とは】 テレビ朝日の動画配信サービス「logirl」による私服グラビア。毎週ひとりをピックアップし、撮り下ろし写真を月曜〜金曜日に1枚ずつ公開します。
-
 石川満里奈(Daily logirl #205)
石川満里奈(Daily logirl #205)石川満里奈(いしかわ・まりな)2005年8月12日生まれ。東京都出身 Instagram:marina__ishikawa812 X:@marina_is812 撮影=青山裕企 ヘアメイク=爽来 編集=中野 潤 【「Daily logirl」とは】 テレビ朝日の動画配信サービス「logirl」による私服グラビア。毎週ひとりをピックアップし、撮り下ろし写真を月曜〜金曜日に1枚ずつ公開します。
-
 向井怜衣(Daily logirl #204)
向井怜衣(Daily logirl #204)向井怜衣(むかい・れい)2007年6月25日生まれ。広島県出身 Instagram:rei_toy0625 X:@rei___mukai625 撮影=佐々木康太 ヘアメイク=爽来 編集=中野 潤 【「Daily logirl」とは】 テレビ朝日の動画配信サービス「logirl」による私服グラビア。毎週ひとりをピックアップし、撮り下ろし写真を月曜〜金曜日に1枚ずつ公開します。
Dig for Enta!
注目を集める、さまざまなエンタメを“ディグ”!
-
 14年間のアイドル人生で手に入れたふたつの宝物、髙木悠未が描く“なりたい自分”とは?
14年間のアイドル人生で手に入れたふたつの宝物、髙木悠未が描く“なりたい自分”とは?髙木悠未(たかき・ゆうみ) 1997年5月7日生まれ、福岡県出身。身長147cm。福岡を拠点に活動するアイドルグループ「LinQ」の現役メンバー唯一の1期生。アイドル活動と並行して、モデル、タレント、インフルエンサーとしても活躍している。2025年7月に自身初となる写真集『タカラモノ』(光文社)を発売。そして同年8月、福岡での卒業ライブをもってLinQを卒業することを発表した。 福岡を拠点に活動するアイドルグループ「LinQ」の1期生として活躍中の髙木悠未。中学1年生からアイドルの活動をスタートさせた彼女が、2025年夏に14年間のアイドル人生に幕を下ろすことを決意した。そこで今回、配信番組『LinQ・LinK』や『LinQのしゃべらんと知らんよ』などでLinQと親交が深いlogirlで、彼女の活動を追いかけ続けてきたテレビ朝日プロデューサー・鈴木さちひろが髙木悠未に独占インタビューを敢行。デビュー時から卒業を決意した現在の思い、そして初芝居を経験した舞台『灯籠』の秘話など、彼女が青春時代のすべてを捧げた“LinQ・髙木悠未”としての人生と、これから描いていく“髙木悠未”の新しい未来について語ってもらった。 ──お久しぶりです! シュッとしましたよね? 髙木 痩せましたね。あと、お姉さんになってません? 自分で言うのはあれやけど(笑)。ちょっと色気出てませんか? ──あ、いや……(笑)。 髙木 失礼〜(笑)! ちょっとでも色気ありません? 出てないかな〜♪って。 ──タレントさんの……?顔になりましたね。 髙木 きれい系になった? 垢抜けた? (周囲にいる当時関わったスタッフを見ながら)みんなも痩せすぎ……! ──そりゃ、LinQダイエットをしましたから。「カロリーなんて」(2011年)を毎日聴いて(笑)。 髙木 ちゃんと覚えてくださっているんですね! ──もちろんですよ! 髙木 あれ? でも、ライブ……あんまり……観たことないですよね(笑)? ──あ、気づかれちゃった。でもさ、ちょうどコロナだったじゃない? 髙木 コロナ前からもですけど!(笑) ──コロナ前だとアキバかなー。AKIBAカルチャーズ劇場でのライブに行ってる。 髙木 それめっちゃ前じゃないですか(笑)……8年前とか? ──コロナ前のライブなので(笑)、もちろん、絶えず観てますよ! 髙木 ありがとうございます! でもメンバーでもう知っている人いないですよね、誰も。 ──たしかに、番組をやっていたころのメンバーは、みなさん卒業しちゃったから。そして今回、髙木さんも卒業ということで。では、集大成のインタビューを始めますね。 髙木 (鈴木さんに)初めて、真正面からお話を聞いていただきますね(笑)。 ──そうだっけ? じゃあ……デビューのきっかけから聞いてみようかな(笑)。 髙木 ははは! っぽい、っぽい、取材っぽい(笑)。デビューのきっかけは中学1年生のころ、何気なく毎日授業を受けて、帰りの会をして……そのルーティンに「人生って毎日終わりに近づいているのに、このままでいいんだろうか?」という急な悟りを(笑)。そこから「自分の人生を派手にしたい」となって……イコール“芸能界”だったんです。 当時、兄がモーニング娘。さんを好きだったんですけど、私が「9期生オーディション」というのを受けたら、いい感じのところまでは行けて。それが悔しくて……じゃあ東京で認められないのなら、福岡でやってやる!となって。時代的には、「アイドル戦国時代」でもあったので。それで「福岡 オーディション」って調べてみたら、LinQが出てきたんです。しかも初期メンバー募集だったので、やってみようと思って。 ──グループに入って……最初のライブは天神ベストホールですか? 髙木 最初のライブはキャナルシティ博多です。からの、イムズホール(※)という。 (※福岡市中央区天神IMSビル9Fにあったキャパ約400人のイベントホール) ──あ、イムズホールのほうが先なんだ。 髙木 イムズホールがデビューの場所です。ベストホールでのライブは、その3〜4カ月あとですね。 ──ステージに初めて立ったときはどうでした? 髙木 当時アメーバブログというのがあったんですけど、それをデビュー前にやっていたんです。でも、アイドルをするという感覚はわからなくて。初めてステージに立ったときファンの方に「ゆうみ〜ん」って叫んでもらって……それで「すごい世界だ」と思って。自分はアイドルを見たこともないしライブへも行ったことはなかったんですけど、見ず知らずの人が「ゆうみ〜ん」って言ってくれる感覚に、なんだこれは!と思いました。 ──推されるみたいな? 髙木 うんうん。こういうのも、この活動を通しての出会いだなって。本来はお互いに出会うことはなかったわけで。ファンの方も中1の私と出会うことはなかったし、(私も)20〜40代くらいの方に出会うこともなかったし。これもご縁だな、と。活動をしながら、ご縁というのをすごく感じていました。 ──その後メンバーがいろいろと変わっていったけど、初期メンバーの中で印象に残っているメンバーとか、このお姉さんにいろいろ教えてもらったとかありますか? 髙木 そもそも年齢幅がひと回り違うグループだったんですよね。それがグループの色だったと思うし、LinQの強み。いろんな層のメンバーを好きになってもらうのは、すごくよかったなと思う。私も中学校では習わない、人生の経験をたくさんしている先輩と仕事をするという。もう仲間じゃないですか? ──なるほどね。 髙木 上下関係も学ぶし。いろんな人のいろんないいところを盗むと、最強の大人になれるんじゃないかなって、中1ながらに思っていました。 ──いい意味で厳しかった? 髙木 厳しいです! 上原あさみさんという初代のリーダーが、バリバリ体育会系で。そもそも「ハニーズ」という福岡ソフトバンクホークスのダンサーだったんですよ。もう、立ち姿から教えてもらっていました。お辞儀は90度!みたいな。だから、1期生はこうしてますね(笑)。今でも名残があります。 (と話して、90度のきれいなお辞儀を見せる髙木) ──もう、あの大人数でライブをやっているすごさに圧倒されるというか。 髙木 最初はレッスンも大変でしたね。集まることができるのが夜とかしかなくて。学校もあるし、バイトをしているメンバーもいたので。しかもほぼダンスも歌もやったことのない素人集団が、1カ月後に12曲のオリジナル曲を披露するという過酷な期間だったんですよ。毎日毎日レッスン場で。レッスン場も、コンクリート打ちっぱなしみたいな雑居ビルのようなところでやっていて。 でもそれも、今となってはいい思い出ですね。私たちは素人なんですけど、あさみさんはハニーズでの経験があるから、練習するときもイメージトレーニングが大事だとずっと言っていて。練習の質を上げるためのイメージトレーニングをしていたこと、今でも記憶しています。あさみさんには、ただ練習するんじゃなくて、イメージをする大切さも教えてもらいました。 ──悠未さんは当時中1だから学校もあったじゃないですか。学校とアイドル活動の両立は大変でした? 髙木 いーや、私は本当に両立できていない! 学校にも行きたくなくて。学校行くふりをして八十八ヶ所巡りをしてました(笑)。私の地元が、仏さん、お地蔵さんの街なんですよ。 ──これ使えるのかな(笑)。 髙木 これはよく話しているので大丈夫です(笑)。 ──ははは。さっきアイドル戦国時代と言っていましたけど、印象に残っているグループはありますか? ちょうどローカルアイドルブームでもありましたよね。 髙木 ひめキュンフルーツ缶さんとか、Dorothy Little Happyさんとか、あとは、東京女子流さんも。東京だけど世代の方のイメージだし。ひめキュンさんがけっこう、ご当地アイドル1位になっているイメージがあって。 ──ご当地アイドルだと、あとNegiccoとか……。 髙木 まなみのりささんも! あと、T-Palette Records(※)に所属していたからバニラビーンズさんも。あとlyrical schoolさんにアプガ(アップアップガールズ(仮))さん。その時代は、みんながむしゃらにやっていましたね。 (※タワーレコード内に設立されたアイドル専門のレコードレーベル) ──T-Paletteといえば、デビューするときはどうでした? 髙木 初めて東京に来たときの記憶は残っていて。ご当地ブームというのもあったし、福岡ブランドだし、「福岡=かわいい」みたいなイメージが先行していて。お客さんも初めてなのにけっこう来てくれたし。あと、私はロリ系だったから……(笑)。 ──はははは! 髙木 ちっちゃいから、めちゃくちゃロリ系で(笑)。東京の人にめちゃくちゃ刺さって。人気メンバーだったのを覚えています(笑)。 ──たしかに、売りにしていましたもんね。よくMCで「幼い私を……」とか。 髙木 そうそう! しかも姉さんたちからも「これ言ってみたら?」って頭に叩き込まれながら(笑)。大人の好きな言葉を言っていこう!みたいなしつけはありましたね(笑)。 ──(笑)。デビューを経て、ライブもどんどん大きくなっていきますよね。本当に大きなライブをやったという意味だとZepp Fukuoka(『LinQ 1st Anniversary Live@Zepp Fukuoka 2012.4.17<豚骨革命!濃すぎたらごめんたい!>』/2012年)かな。このときはどうでした? 髙木 Zeppでやったとき……本当にがむしゃらだったな。初めての大きな会場で、どんな気持ちやったんやろ。集客っていうよりも「いいものを作るぞ」の時間をいっぱい過ごしていた気がするけど。今になると集客とかどうなったのかなって。満員だったのかな……。 演出でフライングハートという、上からハートを降らせるみたいな。そういう演出をまだやったことがなくて、そういう演出にもお金をかけられるので、演出にこだわっていたイメージがあります。 ──そして次に、さらに大きな福岡市民会館。 髙木 『~楽詣~(たのしもうで)あけましておめでとうございマ・シ・テ』(2013年)ね! あさみさんの最後のライブ! ──『楽詣』はどうでした? なかなかの大きな会場で。 髙木 LinQの全盛期だったかも、と今でも思うぐらい一番集客もできたし、キティちゃんを呼んだりして派手にできていた。みんなで太鼓もやったりして。メンバーが多いぶん、いろんな役割ができるから……太鼓メンバーとかダンスメンバーとか。幅広いLinQを見せられたライブでした。 ──太鼓、ありましたね! 髙木 しかもお正月なのに、お客さんがたくさん来てくれて感動しました! ──そこからいろいろ経て、『TIF(TOKYO IDOL FESTIVAL)』でも東京に来たりするじゃないですか。東京のライブで印象に残っているものはあります? 髙木 2周年のときに、福岡と東京を画面でつなぐ、みたいなライブがあったんですけど。そういうのって大所帯じゃないとなかなかできなくて。「私たちLinQです!」というのを、全国3カ所ぐらいでできるのがLinQの強みだったんですよね。それを福岡と東京とで画面でつないでコラボできたのが思い出というか、話題性もあってよかったのかなって。新しい取り組みでしたし。 ──なるほど。現在も東京と福岡を行き来していると思うんですけど、東京の思い出ってありますか? 髙木 東京の最初の思い出は、こんな満員電車に乗ったことない!かな。駅員さんが人を人と思わないぐらい押しつぶしているし、福岡と東京の違いを満員電車で、初めて経験して。東京の最初の印象は、人の多さですね。あと、東京のアイドルさんは福岡と違って戦いに来ている感があって。 福岡はいい意味でも、悪い意味でも、平和っていうか……うーん、自分のスタイルで、ファミリー感でやっていこうというのがスタイルで。でも東京は上京してきた人たちもいるし、ここでやるしかないという覚悟が全然違う。でも、LinQは福岡で自分のスタイルでの戦いをやっているからこそ、大らかで純粋な雰囲気があって、それが東京の刺さる人には刺さっていたのかなって。純粋な何にも染まっていない感じが。 ──それはTIFに行くと感じていたりしてました? 髙木 はい、感じます! TIFは、1年の活動の集大成と思っていて、あそこに入るのも限られた人数だし……100組ぐらい。ゆうたら甲子園みたいな。あそこに行くのを目指しているアイドルさんもいっぱいいるし。TIFで、こういうアイドルさんが流行っているんだなというのを、自分でも知るきっかけになるし。 あと10年前と今のTIFで明らかに違うのは、昔は目立ってなんぼ、個性強めでとにかく破天荒なグループがいっぱいいました。今は令和キュルキュル、衣装もみんなカラフルでリボンがバリでかいとか。流行りものには、一貫性がある気はするんですけど。 ──なるほど。福岡のアイドルグループでよく交流するグループはいますか? 髙木 福岡は入れ替わりがいっぱいあるから。私の関わったグループだと、今はもう誰もいないかもですね。HKT48さんも入れ替わっているし、HRには友達がいたぐらいだったんですけど。QunQunさん(現QunQun☆RiniU)さんも変わったし。あと、流星群少女さんも、今はないですね。 ──活動をしていくなかで、LinQは大胆に構成が変わりましたよね。そのときはどうでした? 髙木 あれは6年の壁……。3年、6年、9年って壁があると思うんですけど、その壁がやってきて。そのころ、グループ自体も少しマンネリ化していたのもあって、解散じゃなくて“解体”というものをLinQはしているんです。今となっては、すごくよかったと思います。事務所が「IQプロジェクト」というかたちを作って……それまでLinQというグループしかなかったところへ、LinQから派生してできたユニットだったりとか、OGメンバーの舞台だったりとか、いろいろと活動の場を広げたんです。 九州の大きなエンタメプロジェクトが“解体”以降、すごく盛り上がってきたような気がしているし、今では小学生低学年からのLinQ KIDSというものもできています。育成を担当しているのが、1期生の上原あさみさんで、同期メンバーでも、裏方に回って違うかたちで、違う目標でやっている元メンバーも多くて。 私がここまでLinQを続けてきた理由には、こういうふうに仲間がまだ近くにいて、違うかたちで一緒にやっていることもあります。私も責任を感じていたから、LinQで少しでも上へ行けるように、もうちょっとがんばってみます、みたいな。今はそれぞれの役割で、同じ事務所の仲間として盛り上げているイメージですね。 ──それこそ最初は最年少で始まって、気づいたら最年長になっていたという。 髙木 そうです! でも、最年少も最年長もどっちも経験できるっていうのは、けっこう貴重な経験だと思っていて……どっちの気持ちもわかるんで(笑)。でも最年長になってみて、中学生のころ「自分は天才」と思っていたけど違っていたんだなって、お姉さんたちに自分を活かしてもらっていたことに気づいて。「とりあえずあとはうちらでやっとくけん」、「悠未は自由におること」って。でも私はそのときは勘違いをしてたから……。自分がLinQを盛り上げてるんじゃなかった、活かしてもらってたんだなって、今になってめっちゃ思います。 だから、お姉さんたちにやってもらっていたことを今度は自分がやりたいと思っていて。ただ自分もまだプレイヤーだから、後押しだけじゃなくて、うまく自分が出るところと、チームでの役割というものを意識してやっている感じです。 ──その意識を持っているなかで、今回卒業を決めたきっかけはなんですか? 髙木 きっかけは、中高生メンバーが9割を占めたグループになっていたこと。私の中で毎年LinQをこういうグループにしたいという目標もありながら、後輩も増えて、毎年教えなきゃいけない1年にもなっていて。良い意味でも悪い意味でも、なかなか前に進めないみたいな。新しいメンバーが入ってきてくれたからがんばるぞ!という気持ちでやってはいるんですけど、触れていると、本当に世代が変わったんだなと、心から思って。 自分が今できることは、自分が経験してきたことを今のメンバーに教えて、LinQを長く続けてもらってLinQの歴史を塗り替えてくれるようにすること。だからそのために、私も今のメンバーにいろいろと伝授する役割に、いつの間にかシフトチェンジしていた。2年ぐらい前から……そのあたりも、理由ですね。同期もどんどんいなくなって。まだ同期がいっぱいいたら、もうちょっと続けられたかもしれないけど。やっぱり世代交代のタイミングかもしれないなって思えたし、自分の20代残りの時間を、アイドルというひとつの武器を下ろしてみて、違う魅力をつける期間にしたいなとも思いました。 ──後輩メンバーに、こんなことを期待したいというのはありますか? 髙木 LinQの歴史が長いぶん、先輩方の想いというのを持ってくれているのはうれしいんですけど、それだとLinQのカバーグループになってしまうから、自分らのLinQにしてほしくて。私の想いとかじゃなくて、自分らで作っていってほしいと、言っていますね。どうしても、昔のLinQを知っているファンは「なんか違うんだよな」って、やっぱり見えちゃうと思うし。今のメンバーは、いつまでもそう思われちゃうのはかわいそうだなって。ポテンシャルはあるんだから、自分らのLinQを作っていってほしいと思っています。 ──なるほどね。ちょっと脱線しますが、悠未さんはテレビ朝日の番組にも出てくださったじゃないですか。『関ジャニの仕分け∞』はどうでした? 髙木 今でも、あのときの自分はすごかったなって思って(笑)。あり得ない奇跡が起きて。あのプレッシャーのなか、しかもドラマーのシシド・カフカさんに『太鼓の達人』で、パーフェクトで……。練習では一度も……知ってますよね? 私が練習でできていなかったのを見てましたよね? ──見てましたよ(笑)。 髙木 なのに、あれは不思議で仕方ない。今でも不思議。本番にただただ強かったという。だって、まわりの大人たちが「え?」ってなってましたよね? ──なってた(笑)。 髙木 記憶がないですもん、ざわざわしてた。 ──ライブアイドルって本番に強いんだなって思いました。この前出演した『踊る!さんま御殿!!』(日本テレビ)もそうですけど、出た反響はどうでした? 髙木 やっぱり全国放送の影響力ってすごいなと思いました。普段テレビで見ている人たちと実際に一緒の空間で収録すると刺。激がすごい。入る隙もないぐらいトークが飛び交ってるから、すげえって(笑) ──でも、ちゃんと爪あとを残してましたよね? 髙木 あれ(実際は)6回振ってもらって、結果3カットだけ。前半は緊張しちゃって。でも緊張していたら二度とチャンスがないから、その緊張も途中からは意外と楽しめていて「なんか楽しいかも!」って。 ──やっぱり本番に強い(笑)。あとlogirlでは、番組『LinQ・LinK』とか、生配信の番組もあったり。何か覚えている企画とかありますか? 覚えていないかもだけど(笑)。 髙木 覚えてますよ〜! logirlは──今日も取材に来るまでの道のりで「なつかしい〜」と思いながら大江戸線に乗ってきて、思い出してました。ひとりでテレ朝に来るという環境も(そういう動きは)福岡ではできなくて、自分の中ではいい経験の時間だったんです。 あと、トーク力も。わからないながらに「これを言ったら大人が笑った」とか「これは笑わないんだ」とか、大人の顔色をめっちゃ見ながら正解とか不正解を探していたlogirlでした(笑)。しかも芸人さんとかとも絡ませてもらう時間も多かったから、本当に修行させてもらった感じです。 ──あとプライベート案件になるけど。このときの記憶はありますか? (と、写真を見せる:ももいろクローバーZのメンバーと一緒に撮った写真) 髙木 わあ、なつかしい〜! 初めて人を見て鳥肌が立ちました。ももクロさんのZeppツアーだと思うんですけど、初めて鳥肌が立ったし、このライブを観て、よりがんばりたいと思ったので記憶にあります。 ──百田夏菜子さん推しでしたよね? 髙木 はい、今でも。ライブ映像を観ています。ももクロさんはずっと『@JAM EXPO』に出られていて、この間もフィナーレのステージを観たんですが、ずっと変わらず愛され続ける人たちはすごいなって。 ──そうですよね。あと舞台『灯籠』(2015年)に出演してもらったじゃないですか。あれはどうでした? ※【カタオモイ.net】プロデュース公演『灯籠』 髙木 『灯籠』! この間も見返したんですよ! 井之脇海さん……めっちゃ……すごいですよね! この間も、当時来てくれていたファンの方と物販で盛り上がりました(笑)。「井之脇海さんすごいよね」「俺も思っとったけど、誰も共有する人いない」って。 ──見返してるの!? 髙木 見返してますよ、何回も! もう一回やり直したい……。あの経験が今の私の、第一の殻破りをしてくれた。表現ってこんなに幅があるんだって。普段まわりにはメンバーしかいなくて、LinQっていう小さな視野でしかなかったので。違う方々と関わることで、すごく視野が広がりましたね。 ──初のお芝居? 髙木 めちゃくちゃ初のお芝居だし、今見たら本当に恥ずかしいぐらいで。ごめんなさいという感じ(笑)。 ──本番公演をやっていくなかで、回を重ねるごとに悠未さんの演技が上達していったんですよ。客を前にすると一気に変わる。僕らも観ていて「ライブアイドルってそういうことなんだね」って。 髙木 本当に!? それはアイドルの経験が活きていたってこと? ──うん、客が入ると全然違う。 髙木 それタイムリーで褒めてほしかった……(笑)。ずっと自信がないままで。今もゲネプロの映像を観て、もっとできたなって。ばり早口だったし、今見える自分へのアドバイスがある。今までやってきたものの経験が何かに活きるってことですね。 ──めちゃくちゃ活きてますよ! 髙木 2191回でした、センターでステージに立っていたのは。いい経験。 ──「いろんなチャレンジをしたい」と言ってましたけど、卒業後はどんなことをやっていきたいですか? 髙木 拠点はどうするの?って、よく聞かれるんです。もうちょっと若かったら東京でチャレンジしたいと思ったんですけど。私が福岡を拠点にしたいと思った理由は、年齢もあるんですけど、逆にせっかく14年間、福岡でいろいろと築いてきたし、その経験は何にも変えられないものだと思ったから。地方に東京のタレントさんが来ることもすごく多いので、そこで絡んで「福岡におもしろい子がいた」って。こっち(東京)に来て埋もれるよりも、たぶん印象が強くなると思ったんですよね。「九州におもしろい子がいる」というフレーズでタレント活動をやりたいなと思っています。 ──目指す方向はタレントさん? 髙木 そうですね、マルチな。SNS系が好きなファン層もつけたいけど、メディアのほうでもファン層が広がったら最強になるんじゃないかなって。SNSもここ数年力を入れてやってきたので。観ている人には、テレビの画面もスマホの画面も同じレベルに見えているらしく。だからどっちも最強になれたらいいなって思っています。 ──こんな人になりたいっていうロールモデルはありますか? 髙木 大泉洋さん! やっぱり、絶対的な地元があって、東京は出稼ぎみたいだと言える人。地元でも愛されると思うし、結局は地元に持って帰るから。それが自分のスタイルになればいいなと思っています。 ──なるほど。ソロ(のアーティスト)活動は? 髙木 ソロ活動は、今は特に考えていないです。したいと思ったら、もっとストイックにならないと……だし、今なっていないってことは、やりたいことじゃないんだろうなって思っています。 ──ここが私の魅力なんだというところはありますか? 髙木 私はアイドルということでごまかしてきたものがめっちゃあると思うんですよ(笑)。ごまかすというか……アイドルだから許されてきたというか。それがなくなるので、新しい武器を身につけなければと思うけど。地方タレントだと、人間力というか「この生き方かっこいい」というのが長くファンでいてくれるファン層になるのかなと思うので。人間力を磨きたいと思っています。この人の生き方がかっこいいと思ったら、女性の方々にも応援してもらえるだろうし。息を長くしたいという感じです。 ──そのひとつが、趣味のバイクだったりします? 髙木 そうですね。バイクも最初は興味がなかったんですけど、『東京卍リベンジャーズ』を観て、マイキーのバブかっこいいなと思って(笑)。これからどういうことをしていくかという戦略会議で、釣り女子とかゴルフ女子とかたくさんある中で、バイクってあんまおらんと思うって。しかも自分の小柄というのも、ギャップになって生きるかもしれんって。バイク好きな人とアイドル好きな人って近い人が多いかもしれないと思って……それでバイク女子。 実際に自分もすごく興味があったので。車の免許は持っていないけど、バイクの免許は取りました。前にバイクのイベントへ出たときも「バイクに乗っている女の子だ」って言ってもらえたし。あと、バイク女子でフォロワーがめっちゃ多い人もあんまりいないから「いいかもしれん!」って、いい意味でビジネス脳も働かせながら(笑)。 ──なるほど。好きなことが仕事になるのはいいですよね。卒業ライブのことについても伺います。こんなライブになったら……というのはありますか? 髙木 私は創立メンバーなので“創立メンバーの卒業”でしかできない、OGメンバーを34人呼ぶということを7月5日に実現できるようになったんです。これまでの卒業メンバーが60人ぐらいいるんですけど、そんなに来てくれることもびっくりだし、みんなそれぞれ人生のシフトを変えているなかで、あのときの青春を一夜思い出そうと。 たぶんLinQにも感謝しているから、来てくれるのかなって。私もみなさんがいたから今まで続けようと思ってこられた感謝の会、同窓会みたいな。LinQのファンの方も、今のファンと昔のファンが共通している「LinQで好きだったもの」が融合する日になればいいなって。7月5日は、けっこう力を入れてますね。 メンバーにも10年ぶりに踊る人もいるし。衣装も引っ張り出してきて「入らんよー」というLINEをしながら(笑)。あと、若いころぶつかってきたメンバーもいるんですけど、今はもう時効だよねって感じで。和解できている時間もすごくよくて。お互いに反省していた部分も、大人になってわかるから、めっちゃ泣くと思います。 ──楽しみですね。最後に応援してきてくれたファン、今応援してくれているファンに向けて、ひと言もらえますか? 髙木 この活動をしていなかったら出会えていなかった人たち、ファンの方もだし関係者の方もいっぱいいると考えると、私の宝物だなと思えたのが「出会い」だったんですよね。あと「経験」。これが私の14年の宝物だなと思えた部分だったんです。せっかく出会えたご縁だから、今後も悠未ちゃんを応援したい、活力をもらえるという存在、Win-Winな関係でいたいと思うから、これからもどうぞよろしくお願いいたします! 取材・文=鈴木さちひろ 撮影=まくらあさみ 編集=宇田川佳奈枝
-
 なぜガンダムは長く愛されるのか?サブスク時代のアニメ新常識とムーブメント──DJ・KO KIMURA×アニメ評論家・藤津亮太
なぜガンダムは長く愛されるのか?サブスク時代のアニメ新常識とムーブメント──DJ・KO KIMURA×アニメ評論家・藤津亮太KO KIMURA 木村コウ(きむら・こう) 国内ダンスミュージック・シーンのトップDJ。クラブ創成期から現在までシーンをリードし、ナイトクラブでの活動のみならず、さまざまなアーティストのプロデュース、リミックス、J-WAVE『TOKYO M.A.A.D SPIN』(毎月第1金曜日27:00〜29:00)にてラジオDJとしてなど、国内外で活躍中。2025年、DJキャリア40周年を迎えた 藤津亮太(ふじつ・りょうた) アニメ評論家。地方紙記者、週刊誌編集を経てフリーのライターとなる。主な著書として『「アニメ評論家」宣言』(2003年/扶桑社、2022年/ちくま文庫)、『アニメと戦争』(2021年/日本評論社)、『アニメの輪郭』(2021年/青土社)などを出版。最新刊は2025年3月刊行の『富野由悠季論』(筑摩書房)。 目次2025年春アニメの注目作品は?サブスク時代に感じるアニメの当たり前作品が増えるにつれて、観ない理由を探す時代に愛され続けるガンダムの魅力とは?社会現象を巻き起こす名ゼリフ 2025年春アニメの注目作品は? ──前回から1年ぶりの対談になります。また春アニメの時期がやってきましたが、今年も豊富なラインナップです。さっそくおふたりの注目作を伺えますでしょうか? 木村 最近は、おじさんが活躍するアニメを好きになってしまいますね(笑)。 藤津 『片田舎のおっさん、剣聖になる』は評判いいんですよ。 木村 勢いでどんどん話が進んでいくから観やすいですよね。再放送の作品もありますが、次シリーズを予定しているから予習っぽい感じなんですかね? 藤津 『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』も7月に新シリーズ『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』を放送するし、『その着せ替え人形は恋をする』も、この次があるので新作に向けての“つなぎ”ですね。 ──藤津さんはどうですか? 藤津 オリジナルを中心に上げると『アポカリプスホテル』と『LAZARUS ラザロ』は、タイプは違う作品ですけどツカミはじゅうぶん強く、オリジナルアニメのおもしろさ──デザインやアイデアのユニークさを含めた目新しさ──を実感しています。『アポカリプスホテル』は人類が地球からいなくなっちゃってロボットだけがホテルを守っていて、そこに宇宙人がやってくるという設定。コメディではあるんだけれどもロボットが来るか来ないかわからないお客さんをずっと待っているという、ちょっと物悲しい要素が軸にあることで、すごく独特な味になっていますよね。 『LAZARUS ラザロ』は渡辺信一郎監督のアクションモノ。しかも『ジョン・ウィック』のアクション監督が協力していて、普通のアニメよりも、手の動きや足さばきとかが複雑で細かく、本当のアクションスターがやっているような仕上がりです。しかも主人公は驚異的身体能力があるのでパルクールみたいな動きができるという設定で、アクションだけでも話が持つというか、番組のウリとして成立しているんですよね。 木村 音楽とかもちゃんとしていて、海外で売るために作ったのかなあと観ながら考えていました。 藤津 もともと勧進元がカートゥーン ネットワークなので、そういう意味では海外の企画なんです。プロデューサーはJoseph Chou氏で、最近だと神山健治監督の『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』(2024年)をプロデュースしています。もともとはアメリカで働いていて、OVA『アニマトリックス』のプロデュースとかをしていたんです。その方が日本で会社を作り、プロデュースと実制作を手がけています。渡辺さんにアクションモノをやりませんか?とだいぶ前に声をかけたのもChouさんだと聞きました。そういう流れの中の企画なので、海外へのアプローチも最初から頭に入っていると思います。 木村 『サムライチャンプルー』(2004年)や『カウボーイビバップ』(1998年)とかも海外でのウケがいいですよね。 藤津 そうそう、海外で愛されています。映画『ブレードランナー 2049』(2017年)に合わせて短編『ブレードランナー ブラックアウト2022』(2017年)を監督したり、クランチロールなどでリリースされた『ブレードランナー』のシリーズ作品にクリエイティブプロデューサーでも参加していて、海外との関係性がけっこう深いんですよね。 木村 日本は“クールジャパン”と言ってアニメでアプローチしてはいるけど、10年前ぐらいはなかなか反応がないなと思っていたけど、今になってちゃんと反応がありますね。アニメだけでなく音楽も。YOASOBIやAdoはどっちかというとアニメの主題歌で向こうでウケた感じがありますもんね。 藤津 アニメとセットで認識が広がった感じですね。 木村 逆に、『LAZARUS ラザロ』は海外の音楽がそのまま鳴っているみたいなのもおもしろいですし。 藤津 『怪獣8号』はOP/EDに洋楽アーティストに書き下ろしでお願いをしていて。それには関係者のいろんなご苦労があったみたいですけど(笑)、そういうこともやれるような環境になってきたということですよね。向こうでもメリットがあるし、日本の視聴者も新鮮な気持ちになりますし。 木村 自分がDJだから気になるのかもしれないけど、音楽が違うとまた雰囲気がガラリと変わるから。あと、国でいうと中国と一緒になってきている作品も多いなと思っていて。それは中国が売る市場として大きいからもあるんでしょうけど。ただ『薬屋のひとりごと』はあっちからすると中国じゃないって言われているんですよね? 藤津 あれは中華「風」ファンタジーなんですよ! そんなに多くはないんですけど、日本の中で少女小説を中心に中華風ファンタジーのジャンルが成立していて、アニメ化された作品でいうと『十二国記』(2002年)とか『彩雲国物語』(2006年)とか。どちらも放送がNHKですね。あと少女マンガ原作だと『ふしぎ遊戯』(1995年)とか。 聞くところによると『薬屋のひとりごと』は、韓流ドラマファンも観ている人が多いらしいです。壬氏さまがわりと早い段階で猫猫にデレているんですけど、僕はもう少し緊張関係というかお互い嫌味なやりとりを延々とやっていてほしいなと思っていたのに……。それを女性ファンに言ったら、韓流ドラマの文脈で楽しんでいる人もいるから、お互い好きだということがハッキリわかっていたほうが盛り上がるんだという解説を受けて。そうか、そういうものなのかと(笑)。 木村 はははは、おもしろい! 藤津 そういう文脈で観ている人がけっこういると思うので、想像以上に視聴者の年齢層が広いみたいですよ。 木村 ストーリーもおもしろいし。そういえば15年くらい前にアニメ系の友人と話をしていたときに、その当時アニメを“難し系“と”空気系“で区別し出していて、世の中の大多数のアニメファンが“空気系“のほうに流れていってるので残念と話をしていて、当時、僕は“空気系“より圧倒的に“難し系“のほうが好きだったのでそれ推しだったのですが、今になって“難し系“を観なくなってきた気がして、いろいろ考えさせられます。 サブスク時代に感じるアニメの当たり前 ──今年の春アニメは、難し系と言われる作品がわりとあるような。 木村 たとえば『鬼人幻燈抄』は難し系に入るのかも。鬼が出てくる作品は昔からあるのに、『鬼滅の刃』の影響で定型が決まってしまって。もし『鬼滅』の前に放送されていたら、また反応が違っていたんでしょうけど。 藤津 鬼って、普通に怖く演出しようとするとストライクゾーンが狭くなっちゃうんでしょうね。しかも、ひとつ強い作品があると見る側も意識が引っ張られちゃいますよね。難し系でいうと『ムーンライズ』(Netflix)は原案が冲方丁(うぶかた・とう)さんで、がっつりSF。過去と未来が行ったり来たりしながら進んでいく語り口も特徴的で、難しいのは難しい。でもアクションシーンも多いし、WIT STUDIO制作なので絵のパワーがあって、牽引力は強いです。 木村 最近は軽いストーリーが多くて、女子高生の日常とか。 藤津 軽いっていう意味でいうと、今回ど真ん中なのが『ざつ旅-That's Journey-』と『mono』かな。『ざつ旅-That's Journey-』は思いつきで旅をするというだけの内容なんですが、観光案内的なおもしろさがありますよね。ほかの地方の人間からすると「こんなものあるんだ」と、ちょっと驚けるような、地方にしかないちょっとおもしろいものも出てくる。 木村 町おこしの一環としてやっている感じもありますよね。そういえば僕の地元の岐阜県の陶芸アニメもちょい前にあったような……。 藤津 多治見でやっていた『やくならマグカップも』(2021年)ですね。15分アニメなんだけど、後半は役者さんが現地で陶芸体験をしたりする、実写映像がついていて。 木村 そうそう! あとは前回もお話しした『聲の形』(2016年)とかね。舞台は僕の地元なんだけど、商店街に行くと、そのキャラクターを使ったチラシがあって。「このキャラクターを使うのに100万円かかった」と店主が言うんですよ(笑)。 藤津 『聲の形』はプロジェクトが大きいので、大変だったと思いますよ。 木村 あと新海誠監督の『君の名は。』は飛騨高山の町おこしになっていましたし。 藤津 岐阜でいうと、今回は『ウマ娘 シンデレラグレイ』のカサマツトレセン学園になっているのが、笠松町の笠松競馬場で。 木村 そうなんですね。実は『ウマ娘』は1クールで観るのをやめてしまって。僕はおじさんだから、かわいいところについていけなくて(笑)。 藤津 ああ、でも『ウマ娘』って、シリーズが続くにつれて、かわいい要素が減ってスポ根度合いが上がっていくんですよ。もともとはレースが終わったらライブをやるという設定があったんですけど、今はそのシーンがなくはないけど、アニメ的にはメインではない状況です(笑)。『ウマ娘』がおもしろいのは、史実をもとにレースシーンが構築されているので、運命のいたずらを導入しやすいんですよ。普通のフィクションでそれをやると「そこでこの展開ってあざとくない?」となるけど、思いどおりにいかないことが実際にあった、ということがベースになっているので、リアリティが保証された上で、ストーリーにドラマチックさが出るんです。 木村 リアリティ要素が増しているんですね。 ──今の話を聞いたら、『ウマ娘』を最初から観直したくなりました。ちなみに、今回『恋するワンピース』が深夜枠に移動となり、一部で話題になっていましたね。 木村 配信で観られるから、子供向けアニメも深夜にやってもいいだろうとなったのかな。これは深夜にやるやつ?夕方にやったほうがいいんじゃないの?と思ったり。 藤津 昔は時間帯で視聴者のセグメントを分けていたんです。たとえば深夜に起きているのは若者で、朝早く起きているのはお母さんと子供とか。今やタイムシフトで見るのが当たり前になっちゃったので、そのセグメントが無効化してきているんですよね。昔は小学校高学年ぐらいの子が夕方のアニメを見てアニメファンになっていくという回路が多かった。今はタイトルを検索して配信で観られちゃうので、たまに「子供のお前が見るには大人向けすぎるんじゃないかな?」という作品も混ざってくる可能性も(笑)。別回路ができちゃっているんですよね。 昔は小学生のころは大人向けで観られなかったけど、中学生になったら深夜アニメを録画して観るようになったという、階段を登るみたいにちょっとずつ大人っぽいものを観ていくような感じだった。けど、今はもっと自由に観られる時代になっているんですよね。それはそれで今の時代のアニメの楽しみ方ではあるけれど、同時に、ミスマッチが起きる可能性があり得るよなって。 ──TVerやサブスクと、いつでもアニメを観られる環境が増えましたもんね。 木村 そうですね。配信だと最近は30秒スキップやOP/EDをスキップする効果があったりして。作品によってはスキップされないようにわざわざ絵を変えていたり、主題歌と主題歌の間でストーリーを入れていたりと工夫していて。 藤津 エンディングはスタッフのクレジットが載るので、自動的に飛ばされるとつらい。誰が担当してたんだっけ?と確認できなくて。設定で変えられるけど、デフォルトだとそうなっちゃう。映画もエンドロールを飛ばそうとするじゃないですか。 木村 そこ飛ばすのは寂しいですよね。この人が作っている作品だからこうなのかとかがあるから。そして話は飛びますが最近は音楽の制作をしているところがだいたい決まってきているので、タイアップでつけたみたいな感じが見えてしまうことも……。商業っぽさを感じて、逆に入っていけないものがあって。 藤津 大人の都合が見えちゃうとノリきれないんですね(笑)。テレビの話に戻ると、僕は東京工芸大学という学校で少しだけ教えているんですけど、毎年生徒にどういう試聴環境なのかの簡単なアンケートを取っています。それでいうとここ何年か傾向がはっきりして、基本的にひとり暮らしの人はテレビを持っていないから、タブレットかパソコンで観ている。実家で暮らしている子は、居間にテレビがあって録画機や再生機がある。じゃあ果たして、今この若い世代が大人になって家族を持ったとき、その居間にテレビを置くのかどうかという問題が見えるんですよ。 木村 買わないんじゃないですか? それかモニターとしてテレビを買う人はいるかもです。 藤津 そうなんですよね。あと、留学生の子が「うちの家は居間にテレビがありますが、誰もテレビを見ません」と。要は子供が成長すると自分用のテレビを部屋に置くか、PCやタブレットなりで各自が自分の機器で観ている。居間のテレビはよほどのことがない限りつけなくなるみたいで。ここから20年ぐらいテレビを持たない家がすごく増える可能性があるなあと。 木村 チャンネルの取り合いがないんですね……。よりいっそうネットの配信が重要になってきますよね。そうなるとその配信形態に合ったフォーマットが必要になってくるというか。音楽の場合だと、10年以上前にアメリカのスタンフォード大学で、レコードとデジタルデータのMP3の音はどっちがいいかというアンケートを取ったみたいで。そのころからもうほとんどの人が音楽をiTunesとかで聴いているからMP3のような圧縮音源に慣れちゃっていて。だから、若い子はレコードよりもデジタル圧縮音源のほうがいいと答えたみたい。なじみがあるから、そっちのほうがいい音だって。だからアニメもそのうち同じような感じになるのかも。最近は1.5倍速とかで観ている人も多いと思うので、それで本当のアニメの作家性というものが全部見られるかはわからないですけど。 藤津 ただ、内容をチェックするぶんにはいいのかもしれないですが。 作品が増えるにつれて、観ない理由を探す時代に ──タイパを重視する時代でもあり、視聴の簡略化が目立ってきていますからね。最近だと事前情報だけで観る観ないを判断する“ゼロ話切り”という言葉も聞きます。実際、どう思いますか? 木村 僕は、1話だけでも観てほしいかな。 藤津 最近は作品数が多いので、観ることにもなるべく努力しないといけなくて。2000年代初頭の時点であるアニメ誌の編集さんが言ってたんですけど、今や“観ない理由”を探す時代になったんだと。昔は観る理由を探していたけど、観ない理由を探すと。それが“ゼロ話切り”という言葉に置き換わったのかなって。 ──なるほど。時代によって視聴者の意識も変わってきますよね。作品のジャンルでいうと、一時期は異世界転生モノが増えていましたが、その時代の日本社会とも関係があったのでしょうか? 貧困などの問題でほかの人生を歩みたいという願望を異世界転生モノに重ねている人もいるという記事を読みまして。 木村 もちろん、人生うまくいかないこともあると思うんですけど──ここ数十年で世の中が変わっていてよりいろいろと抑圧されていることもあるし、それで自分が本当にやりたいことをやりたいという気持ちが異世界転生モノに惹かれるということになるかもしれないですね。 藤津 もともと異世界転生モノは、なろう系(※)なんていわれたとおり、小説投稿サイトを中心に広がっていって、当初の読者は氷河期世代が中心だったはず。その世代の「思いどおりにいかなくてつらいなあ」っていう気持ちを受け止めるフィクションだったと思うんです。そうしてその結果、あのジャンルが大量に生まれて、いろんなメディアに出ていったことで、今度は小学生とかも読むようになって。浸透と拡散とでもいえばいいんでしょうかね。スタートは世代の置かれている環境が反映されていたんだろうと思うんですけど、それがジャンルになってしまうと間口が広くなって、いろんな作品が出てきて、当初のターゲットとも異なる子供も読むようになっちゃう。『転生したらスライムだった件』なんかは今や小学生のファンがすごくいるんですよね。国作りの話だから、彼らはあの作品を『三国志』みたいな感覚で読んでいるんですよ。 (※小説投稿サイト『小説家になろう』発の原作の作品) 木村 短いエピソード内で事件とかいろんなことが起こりまくって、刺激が強いんですよね。子供たちも「次は何をやるだろう?」ってのめり込む。『片田舎のおっさん、剣聖になる』も同じで、どんどんいろんなことがあって、次の展開を楽しみだと思わせてくれる。ただ、あまりにもアニメの作品数が多すぎて……いい意味ですけど。これは数を作らなきゃいけなくて業界にプレッシャーがかかっているんですか? 藤津 難しいんですよ。制作会社は基本的には制作を請け負う側なので。『鬼滅』以降、原作側がアニメ化に対してのモチベーションが上がっているんですよね。一方で企画は、10倍の予算で1本作るよりは、10分の1の予算で作ったほうが絶対にリスクヘッジができるので「数は力」みたいなところがあって。だからお金を回している側からすると、数を減らす理由がないんですよね。しかも、原作元も意欲があるから。ただ作る側が過剰に大変だということに…… 木村 そうなんですね。あと、前は少女マンガが原作のアニメがけっこうあった気がしましたけど。 藤津 前期だと『ハニーレモンソーダ』がそうですね。今回だと『謎解きはディナーのあとで』が「ノイタミナ」でアニメ化されています。これは小説原作ですが、キャラクターデザインや雰囲気は、コメディ寄りの少女マンガといったテイストで。気取った警察の警部の声優は宮野真守さんで。しかも、おもしろいほうの宮野さんでやっている。だから少女マンガそのものではなくても、「少女マンガっぽいもの」へのニーズはあると思うんですよね。 木村 やっぱり女性のアニメ視聴層は、パーセンテージ的に多いんですか? 藤津 多いと思います! あくまで傾向で例外もあると思うんですが、女性ファンって好きになると友達を誘いがちなんです。なので、熱気が盛り上がるときはS字曲線なんですよ。ちなみに下がるときは逆のプロセスになるので、そちらも早くて(小声)。 あの子が離れたなら私も離れようかなって。あくまで一般論的で例外もあるでしょうけど、マクロで見ると女性はそういう行動を取りがちのようです。男性は友人に布教しても、そこまでではないんですよね。わりとバラバラというか、“分子間力”が弱い感じ。女性は“分子間力”が強くて、「一緒に楽しもうよ!」となって塊が生まれる。だから女性ファンがつくとグッと温度が上がる。そういうことで女性ファンが目立って見えるというのがあるかもしれません。 木村 だいたい女の子のほうが先にハマって、そのまわりの男の子が釣られてハマっていく時期には女の子はもう飽きているという(笑)。男性のほうがハマっていったらわりと長く続ける人が多いのかなって。おもしろいものを見つけようという意識は女性のほうがすごい感じがしますね。 愛され続けるガンダムの魅力とは? ──おもしろい傾向ですよね。話は変わるのですが、前回の春アニメ対談の際に、春アニメといえば『ガンダム』とふたりともおっしゃっていました。今春は新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』がスタートしています。さらに先日、藤津さんが『富野由悠季論』も刊行されましたので、ガンダム作品についてもたっぷり聞いていけたらと思っています。 藤津 ようやく映画『機動戦士Gundam GQuuuuuuX Beginning』(2025年)と違う展開に。1クールだけという噂がありますが、これからどうなっていくのか楽しみですね。 木村 ガンダムなのに1クールって珍しいですよね。 藤津 その前の『機動戦士ガンダム 水星の魔女』(2022年)も結局2クールだったので、短かったんですよね。それまでは基本は1年ベースで作ってきたので。 木村 『機動戦士ガンダム00』(2007年)も途中で一回終わって、またやっていましたね。 藤津 あれはもともと1年の企画なんだけど、だんだん求められるものが高度になってきたので連続で制作するとすごく大変になっちゃう。なので、半年ブレイクを入れましょうとなったみたいです。 木村 そのころから、長い作品は途中で休むようになりましたよね。1クールとか2クール休んで。 藤津 分割4クールとか分割2クールといったパターンですね。やっぱり1年間は大変みたいで……マラソンなのでね。庵野秀明監督は「テレビシリーズというのは穴の開いた船みたいなもので。出航した瞬間から水が溜まり始めるから、沈むまでに目的地にたどり着けるかどうかが勝負。なのでダメージコントロールをしていかないと」みたいな話をされていて。なので、1年作り続けるってそれぐらい大変なんですよね。 木村 ただ、今回は12話で収めちゃうのはなかなか厳しいですよね。世界観も広がっているので。ファーストガンダム(『機動戦士ガンダム』/1979年)と同じだけど、違う話。頭から設定が変わっているから。あとは若き日のシャア少佐(シャア・アズナブル)の声が変わった時点で、だいぶ印象が違いますよね。 藤津 シャアっぽいお芝居ができる若手の方を選んだって感じですよね。 木村 サンライズにはないスタジオカラーっぽさが入っていて、新しい感じなのがおもしろいです。あとオリジナルストーリーだから、先がわからないところも。 藤津 オリジナルってそこがおもしろいところでね。あと、今回スタジオカラーが制作の中心なのがインパクトがある。サンライズといえばガンダムの会社で、ある時期までは社内である程度キャリアを積んできた人がガンダムの監督をやるということが普通だったわけで。たとえば、『機動戦士ガンダムSEED』(2002年)の福田己津央さんはサンライズの中で設定制作という仕事をやって、そのあと、演出家になり監督作『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』(1991年)をヒットさせた上での『ガンダム』でした。ある意味満を持しての登板ですよね。それで実際に実績を出したという。 そのあとから風を変えに行って、サンライズでは演出家にはなっていなかった水島精二さんとか長井龍雪さんとか、サンライズに縁はあっても、生え抜きという感じではない人を監督にするようになった。さらにはゲーム会社レベルファイブの日野晃博さんをシリーズ構成に起用したこともあった。あの時期は、次に進んだなという印象でした。『水星の魔女』もその延長線上の印象です。さらに今回の座組は『ガンダム』をどうやって長く生きたタイトルにしていくかというときに、サンライズはある意味ガンダムのプロデュースをすればいい。業界全体で見て、そのとき一番おもしろい人に作ってもらうということを考えているのかなと。 木村 だいぶ変わってきましたもんね。特に『新機動戦記ガンダムW』(1995年)あたりからは、もう全体が変わってしまって。僕は好きなんですが。 ──映画『機動戦士Gundam GQuuuuuuX Beginning』は情報がないままでしたけど、観たときの印象はどうでした? 藤津 僕は前半のインパクトがすごすぎて、後半のマチュ(アマテ・ユズリハ)が出てきてからの記憶が飛んでしまいました(笑)。あと劇伴と効果音が元のシリーズと同じなのもインパクトが強かった。 木村 効果音、気になりましたよね! ちゃんとうまく使っていましたし。 ──キャラクターデザインはどうでした? 木村 後期の『新世紀エヴァンゲリオン』を彷彿させましたね。 藤津 竹さんというイラストレーターにお願いされてるんですけど、思いきったなと。記号化されたタイプの方だからリアリティが求められる世界観になじむか不安だったけど、動き出して声がつくとその世界にいるような感じになりました。アニメ化にあたって、斜めのアングルとか、影のつけ方を工夫して実在感が感じられるようにする調節をしているのもうまくいっているのかなと。木村さん、メカはどうでした? 木村 違和感はなかったですけど、細身で鋭角な感じが大河原邦男さんのデザインではなくて、全体がスタジオカラーのセンスだなと思って観ていました。 そうだ、ガンダムシリーズでずっと気になっていたんですけど、『GQuuuuuuX』って英語が不思議ですよね。たとえば、エグザベ・オリベというキャラクターがいますけど、スペイン語だと“シャビエル”で、英語だと“ザビエル”とかで。けど“エグザベ”はどこの言葉?みたいな……。 藤津 今となってはわりと忘れられちゃっているんですけど、最初『ガンダム』の設定では国家がなくなって「地球連邦」になったことで、人種もある程度混合されているんですね。だから言語もいろいろ変わっているであろうことが想定されていたっぽい。もちろん1970年代の作品なのでそこまで徹底はされていないですが。それがシリーズを制作していく過程で、だんだん現実味を増していくにあたって、用語も全部英語だったり、ドイツ語が入ってきたりした。でも富野監督自身は、いろんな固有名詞のモジリを使ったりして世界観を作ってる。「レコンキスタ」じゃなくて「レコンギスタ」にする、とか。だから「出雲(いずも)」じゃなくて「イズマ」にしたりするのは、ちょっと富野さんらしさに通じるものを感じる言葉遣いでもありますね。 木村 そうだったんですね。これは何語だろうな?といろいろと考えたりしていて(笑)。 社会現象を巻き起こす名ゼリフ ──そんな背景があったんですね……勉強になります。著書『富野由悠季論』では印象的な「富野ゼリフ」にも触れていらっしゃいます。記憶に残るセリフはありますか? 木村 やっぱりファーストガンダムの「坊やだからさ」かな。 藤津 『GQuuuuuuX』で、シャアがホワイトベースのブリッジを破壊するとき「運がなかったのだ」みたいなことを言うんです。最初の『機動戦士ガンダム』では、シャアは「私もよくよく運のない男だ」と言ってるんです。そのセリフの本歌取りとして『GQuuuuuuX』のセリフがあるのかなと。ちなみに、もともとの「運がよかった」のセリフは、脚本にはないので、富野さんが絵コンテで書いているセリフだと思うんです。そもそも敵・連邦軍の「V作戦」の秘密兵器であるホワイトベースを見つけちゃったんだから、本当はシャアは運がいいはず。なのにそれをわざわざ「よくよく運のない男だ」と。その持って回った感じが、少なくとも最初の『ガンダム』のシャアなんですよね。そこからすると、もういっぺんひねった結果、『GQuuuuuuX』で、ひねりのないストレートな発言になっているのがおもしろいですね(笑)。 ……なので印象に残るセリフというと、第1話最後の「認めたくないものだな」もそうなんですが、この持って回ったシャアのセリフはまず頭に浮かびますね。富野ゼリフは耳に引っかかる言葉遣いが多いですよね。 木村 今の時代でも、なんかの拍子で使われることもありますからね。 藤津 一定世代までは、歌舞伎とか大衆演劇、その流れにある時代劇が基礎教養だったと思うんですよ。『国定忠治』の「赤城の山も今宵限り」とか『忠臣蔵』の「殿中でござる」とか。 ──白浪五人男の「知らざあ言って聞かせやしょう」とか。 藤津 ある時期まではドリフ(ザ・ドリフターズ)とかがコントでパロディで使っていたりもしたので、歌舞伎を見たことがなくても「そういうものがあるんだなあ」と漠然とではあるけれど、教養として受け止めていたんですよね。それがどこかで『ガンダム』に置き換わったような印象です。 ──アムロ・レイが殴られたときのセリフとかも、コントで使われちゃう時代ですからね。 木村 自分たちはファーストガンダムの影響を受けて育ってきていますけど、今の人たち、若い子たちはそうじゃないから。昔だと『スター・ウォーズ』とか『ターミネーター』とかの映画を元にした社会現象みたいなのがあったんですが、今は世の中すべてがそれになっちゃうことってあまりないですよね。今の子たちは『鬼滅』とかなのかな? 藤津 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(2020年)は興行収入400億円ぐらいなので、当時10歳ぐらいだった子にはでかいムーブメントに見えていたと思います。あと、今10代後半〜20代前半ぐらいだと『ハリー・ポッター』の存在感がすごかったはず。ただ、今のほうがコンテンツの数自体が多いので、昔のように大人が巻き込まれるほどではないのかも。 木村 大人にはでかく見えないけど、子供たちにとっては大きかったんでしょうね。自分たちも子供のころに見ていたものは、すごいものに見えましたもんね。 藤津 ですが、昔よりも国民的大ヒットは生まれにくくなってきていると思います。そこは昔と今との違いかもです。 木村 名ゼリフみたいなものも、大人たちは気づいていなくて。だけど若い子たちの間では名ゼリフになっていくのかなって。 藤津 『鬼滅』で、冨岡義勇(とみおか・ぎゆう)が言っていた「生殺与奪の権を他人に握らせるな!!」とかは、おそらくその世代の子供たちだと何も言わずに通じているはずなんですよね。今の20歳ぐらいの子になるかな。彼らが40歳ぐらいになるころは、そのあたりがもっと広がっていてもおかしくないかなって。だから時間の問題じゃないですかね。 僕自身の肌感覚でも最初の『機動戦士ガンダム』がこんなに一般的にネタにされるようになってきたのは『∀ガンダム』(1999年)が終わったあとぐらいの印象なんです。21世紀になってから一般性を帯びてきて、風景になってきたというか。それまではマニアックなお遊びみたいだった。 ──この対談を読んで『GQuuuuuuX』だけでなく、これまでのガンダムシリーズも観ようと思う読者がいると思います。これからチャレンジしてみようかなと思っている人に、最低限ここを観ておいたらいいというシリーズがあれば伺いたいなと。 木村 『GQuuuuuuX』を観るんだったら、ファーストガンダム(『機動戦士ガンダム』)は観ないと。どこが変わったのかがわからないと思いますね。 藤津 『機動戦士ガンダム』は全43話あるから、その中でも絞るなら第39話「ニュータイプ、シャリア・ブル」、第41話「光る宇宙」かな。そこを観ておくと、元ネタがわかる。 ──ファーストガンダム以外は? 木村 バトルという点では『機動武闘伝Gガンダム』(1994年)かな。ただ、ガンダムバトルでも少し違うし参考にはならないかもです(笑)。 藤津 ガンダムではないんですが、監督である鶴巻和哉さんの作風を知りたかったら、『フリクリ』(2000年)と『トップをねらえ2!』(2006年)かな。両方とも6話ずつなので観やすい。特に『トップをねらえ2!』は、前に『トップをねらえ!』(1988年)という作品があった上で鶴巻さんがどう捻ったかがポイントなので、これはけっこう『ガンダム』と『GQuuuuuuX』の関係と似ているところがある。あ、似ているという意味では『ガンダム』の第1話も必要かな。完コピ具合の驚きも含めて。そうなると、第1話、第39話、第41話かな。 木村 始めを知っていると楽しめますよね。ミノフスキー粒子のこととか、ファーストガンダムを踏襲していますし。あとは、『機動戦士Ζガンダム』(1985年)と『機動戦士ガンダムΖΖ』(1986年)ではニュータイプの苦悩なども出てきますから。ニュータイプを知っておかないと、話がわからなくなってくるので、勉強してもらいたいですね。 藤津 だから今回、ニュータイプをテーマにしてやるんだって驚きました。大変なところに手を突っ込んできたなと(笑)。 撮影=Jumpei Yamada 取材・文・編集=宇田川佳奈枝
-
 永野芽郁が演じることをやめない理由「お芝居は“生きがい”に近いもの」
永野芽郁が演じることをやめない理由「お芝居は“生きがい”に近いもの」永野芽郁(ながの・めい) 1999年9月24日、東京都出身。朝のNHK連続テレビ小説『半分、青い。』(2018年)、『ハコヅメ~たたかう!交番女子~』(2021年/日本テレビ)など話題作に多数出演。近年の出演作に映画『はたらく細胞』(2024年)、配信ドラマ『晴れたらいいね』(2025年/テレビ東京)など。現在、TBS4月期日曜劇場ドラマ『キャスター』に出演中。 X:@mei_nagano0924 Instagram:mei_nagano0924official 2024年7月に俳優として15周年を迎えた永野芽郁。朝ドラヒロインを経て数々のドラマや映画で役を演じ、俳優として魅力を増し続けている彼女が、2025年5月16日より公開される映画『かくかくしかじか』で主人公・林明子を演じる。本作は漫画家・東村アキコの自伝的作品であり、学生時代から9年間にもわたる恩師との日々を描いた物語。映像化を断り続けていた東村を動かしたのは、永野芽郁と恩師・日高先生を演じる大泉洋の存在だ。“このふたりでなければ成立しなかった(東村)”と奇跡の映画化が実現した本作を通して、永野芽郁が作品に捧げた想いや、演じることで大切にしていることや信念などを知ることができた。なぜ人は永野芽郁に魅了されるのか?──その理由が明らかになる。 (※本取材は2025年2月に実施) 目次東村アキコ先生から受け取った“人生のバトン”永野芽郁にとっての“恩師”と呼べる人 どんなにしんどくても「終わらないものはない」役者を辞めようと思ったとき、いつも作品が引き止めてくれた 東村アキコ先生から受け取った“人生のバトン” ──漫画家・東村アキコさんが自身の実話をもとにして描かれたマンガ『かくかくしかじか』が、連載終了から10年の時を経て、ついに実写映画化されます。原作をお読みになって、どんな印象を持ちましたか? 永野 初めて原作を読んだとき、中盤まではただただ笑っていたんです。「こういう日常ってあるよね」とか、おもしろいエピソードも随所にちりばめられていて「こんなことが起こる!?」と楽しく読んでいたんですが、物語が進むにつれてだんだんと心が引っ張られていきました。人との出会いで人生って大きく変わったりするなとも思いましたし、大切な人に伝えなきゃいけないことって、やっぱり伝えたいと思ったときに伝えなきゃいけないんだなとも思い、気がついたら泣いていました。それが東村先生の実話というのが、なによりすごいなって感じました。 ──今作は完璧なかたちでの実現は不可能だろうという理由から、映像化を断り続けてきた東村さんが「永野芽郁さんが明子をやってくださるのなら」と快諾されたと聞きました。作品のオファーを受けたときのお気持ちと、実際に演じられてから気持ちの変化はありましたか? 永野 東村先生の人生を描いた作品に、私が携われると決まったときはただただ光栄でしたが、それと同時に緊張もありましたね。東村先生が過ごしてきた時間を壊してしまうかもしれない、というプレッシャーもあったので「どうしようかな」という気持ちは、撮影前から終わったあとも抱いていました。でも、現場には常に東村先生がいてくださったので、大泉洋さん演じるスパルタな絵画教師・日高先生とのかけ合いだったり、明子の動き方だったり、どうしたら明子らしさが出るかなと思ったときに、いつもその場でアドバイスをいただけました。友達とカラオケで盛り上がるシーンでも「私はこうやってノッていたんだよ」と直接教えてくださったので、東村先生に明子像を作ってもらえた感覚があります。あとは、常に大泉さんが日高先生として向き合ってくださっていたので、私はみなさんに身を任せる気持ちで撮影に臨んでいました。 ──今回、東村さん自らが脚本を手がけられたことも大きなポイントですね。原作との違いは感じましたか? 永野 原作と脚本でもちろん違う部分もありましたが、先生が物語として脚本に参加されながらも、生身の人間が演じるにあたって「こうしたほうがよりおもしろくなる」とか「ふたりのよさが伝わるんじゃないか」と、試行錯誤して何度も脚本を調整してくださりました。そのため、原作との違いに驚くことはなく、すんなりと読んではいたんですけど、日高先生が明子へ檄を飛ばすように発する「(絵を)描け!」という言葉がより心に残るような脚本になっていた印象です。完成した映画を観終わったあとに、あの「描け!」が頭の中で思い出されただけで、なんかグッときて泣きそうになりました。誰かのひと言で突き動かされる瞬間って、誰にでもあると思うので、とても素敵な作品になったと思います。 ──明子は思ったように絵が描けなくて落ち込んだり、精神的に絵と向き合うことが難しくなったりすると、日高先生が決まって「描け!」とひと言、喝を入れる。その言葉は非常にシンプルなんだけど、物語が進むに従って深みが増していきますよね。 永野 そうなんですよね! シンプルな言葉でも人に伝わることってあるんだなって思います。 ──永野さんはこれまでにも『俺物語!!』(2015年)、『マイ・ブロークン・マリコ』(2022年)、『はたらく細胞』(2024年)など、マンガ原作の作品に多数出演されています。今回は原作・東村先生が書かれた脚本や、目の前にいるご本人など、役を作るにあたって何が一番の指針になりましたか? 永野 映画なので割合的には脚本を軸にする部分が一番大きかったですけど、東村先生がいろんな思いを抱えながらかたちにされたマンガ原作のひとコマひとコマや、物語の流れは常に研究していました。それでいて、私からすれば明子が大人になった東村先生ご本人が目の前にいてくださるので、「こういう動きをしたほうが、今の東村先生に近いかな」とひっそり観察してお芝居に反映させました。 ──東村先生は「明子はかなり難しい役だと思う。ふわふわしただけの女の子ではないから」「でも、芽郁ちゃんなら絶対にうまく演じられると思った」と話していましたが、永野さんは明子という人物に対してどんな印象をお持ちですか? 永野 明子は飄々(ひょうひょう)としていて「なんとかなるでしょ!」と思える楽観的な強さがありつつ、意外と繊細な印象があります。どうして先生は、私だったら演じられると思ってくださったのかをまだ聞けていないんですけど、でも先生がそうって言ってくださることがすべてだと思ってがんばりました。 永野芽郁にとっての“恩師”と呼べる人 ──今作は東村さんの9年間にわたる実話の物語ということで、永野さんは明子の高校時代から漫画家としてデビューされるまでをおひとりで演じられました。 永野 出演のお話をいただいたときに、まず不安に思ったのが年齢の変化だったんですよ。高校生から大人になるまでを演じるのは、朝ドラ(『半分、青い。』/2018年)以来なんです。明子の高校時代はノーメイクでナチュラルにやればなんとかなるかなと思いつつ、じゃあメイクを濃くしたから大人に見えるのか?といったらそういうわけでもない。かといって、メイクをしなかったら高校時代との変化が難しいということで、衣装やヘアメイクもそうですし、歩き方や姿勢、声のトーンなどを関(和亮)監督と細かく話し合いながら調整していきましたね。 ──綿密に役を作られていく中で、明子がご自身の中に入ってきたと思えた瞬間はありましたか? 永野 先生が実際にマンガを描かれるとき、椅子の上に足を乗せるんです。最初は「それって描きづらくないのかな?」と思っていたのですが、いざ自分がやってみたら、慣れない姿勢だからかなり描きづらかったんですけど、カメラが回っていないときに、トーン貼りをやっていたら「あ、自然に椅子に足を乗せてる」と思って。そのときに明子の雰囲気をつかめているのかもしれないと思いました。 ──改めて、明子と日高先生の関係についても教えてください。 永野 明子が高校3年生のときに「美大に行くために絵の勉強をしなきゃ」と思って通い始めたのが、日高先生の絵画教室。当時は「怖い」「なんだ、この人は」という印象しかなかったですけど、時間が経つにつれて、恩師だと思うんですよね。誰もがあとになって気づくこととか、大人になって理解したり、その時間に寄り添えたりすることってあると思うんですけど、まさにそれを象徴するふたりだと思いました。 ──撮影現場の雰囲気はいかがでしたか? 永野 大泉さんとは現場でずっとしゃべっていましたね。常に現場の雰囲気を明るくしてくださっていました。ただ、ドライで撮影の段取りが始まるとガラッと空気が変わって、急に怖い先生になるんです。普段の優しくてみんなを盛り上げてくれた大泉さんと、心はまっすぐで優しいけど一見とても怖く見える日高先生とのギャップがすごくて、常に大泉さんの放つ空気に引っ張ってもらいながら撮影していました。 ──今作は笑えるシーンから泣けるシーンまで、明子と日高先生の関係性が見られる名場面がたくさんあります。その中で永野さんが印象に残っているシーンは? 永野 完成した映画を観て、強く印象的に残ったのは明子と日高先生がバス停で出会う場面。その場はあまり考えずに撮っていたんですけど、こんなに印象に残るものなんだなって観終わってから思いました。そのバス停で明子は、つかなければよかったと思う嘘をついてしまうのですが、あのバス停が始まりであり通過点でもあるので、私の中で心に響きましたね。 ──明子にとっての日高先生のように、永野さんご自身も怖いけど好きだと思える恩師はいますか? 永野 中学時代の先生が、当時は怖くて苦手だったんです。何をやっても注意され、ひと言しゃべるだけで怒られるみたいな感じでした。ただ、卒業が近くなって最後にみんなで出し物をやる機会に、先生が「あなたが学年みんなをまとめなさい」と言ってくれたことがありました。当初は「なんで私?」と不思議だったんですけど、先生は私のことを信頼してくれていて、だからこその厳しさだったんだなって感じました。そこからいい先生だなと思えるようになって、今でもご飯に行く仲なんですけど、当時の話をすると先生は「芽郁には厳しく怒りすぎたな。今も反省してる」と言っていて。私は「アレはアレでおもしろかったね!」と言って、今では笑い話になっているんです。明子と日高先生の関係性とは違いますけど、きっとこの人が恩師なんだろうなと思います。 ──金沢や宮崎など地方ロケが多かったそうですが、振り返って印象に残っていることはありますか? 永野 撮影をした金沢美術工芸大学は、東村先生の母校なんです。撮影時には旧校舎が取り壊されることが決まっていたんですけど、最後にということで、協力してくださって。先生が過ごされた地で撮影できて、エネルギーをもらいましたし、ありがたかったですね。そのあとに「金沢のおいしい回転寿司屋さんがある」と聞いて、みんなで食べに行き、それもすごく楽しかったです。金沢には2、3日しかいなかったんですけど、いい思い出ができたなと思います。 宮崎には長い時間滞在していたんですけど、あの穏やかな雰囲気にみんなが引っ張られていました。それとまわりは穏やかなのに絵画教室の中は張り詰めた空気が漂っているという対比が、おもしろかったです。宮崎には先生のご親族や親戚の方もたくさんいらっしゃるので、代わる代わるみなさんが現場に来てくださって、「この感じ懐かしい!」「そんなこともあったな!」なんて言っていたぐらい、マンガと同じ風景がたくさん出てくるので、それぞれの地にこの作品は助けられたなと思います。 ──ちなみに、作品の中で「タイムマシンがあったら、昔の私に竹刀をお見舞いしたい」という明子のナレーションが流れます。もし永野さんが過去に戻れるなら、このときの自分に喝を入れたいと思う場面はありますか? 永野 小学生のころに映画の撮影をしていたときに、マネージャーさんに「芽郁ちゃん、楽屋でテレビばっかり見てないで、ちゃんと台本を読みなさい」と言われたんです。ただ私はセリフを覚えてきていたので「なんで覚えているのに読む必要があるんだろう?」と思っていたら、母親から電話がかかってきて「芽郁、台本を読みなよ」と言われたんです。 ──お母さんに関しては、永野さんが事前に台本を読んでいたことを知っていたんじゃないですか? 永野 母親はいまだに言うんですけど、私が台本を読んでる姿を一回も見たことないらしいんですよ。それもあってみんながすごく心配になっちゃったみたいで。そのあと、マネージャーさんが「台本を読みなさい」と言って、しばらくして戻ってきたら私が寝てたみたいで(笑)。 ──ははは! テレビを観るよりもひどくなってるじゃないですか。 永野 起きたらみんなにすごく怒られました。あのときに寝ないで、嘘でも台本を開いておけばよかったのになっていうのは思います。 ──でも、ちゃんと覚えていたわけですよね。 永野 そうなんです、ちゃんと覚えていたんです! でも、あのころは自分も子供だったので「覚えたもん!」でしかなかったんですけど、もうちょっと台本を一生懸命読み解くとか、いろいろやれることはあったかもしれないのに、「読んだら?」と言ってくれた親切さを無視して寝るなんて、すごく子供らしいことをしていたなって(笑)。当時の自分に「もうちょっと、ちゃんとやりなさい!」と喝を入れたいですね。 ──先ほどお母さんは永野さんが台本を読む姿を見たことがない、とおっしゃいましたけど、人前でセリフを覚える様子を見せないのは、永野さんのポリシーなんですか? 永野 台本を持ち帰って家で仕事をするのが好きじゃないです。でも、昔は学校が終わって母が仕事から帰ってくるまでの間に台本を読んでいましたね。あとは、オーディションで台本を読まなきゃいけないときは、家を出る前に携帯で写真を撮っておいて、オーディションに向かう電車内でその画面を見続けていました。自分なりに時間を費やして覚えていたんですけど、それを母がたまたま見てなかっただけだと思います(笑)。 どんなにしんどくても「終わらないものはない」 ──もうひとつ作中の場面をピックアップすると、明子は絵を描きたいけど、何を描けばいいのかわからなくて筆が進まないシーンがありました。永野さんご自身はお芝居をされる上で、考えすぎてどうしたらいいのかわからなくなった経験はありますか? 永野 私はあまりないです。お芝居に関しては、現場に行ったら監督だけでなく、脚本家さんやプロデューサーさん、また共演者の方など味方をしてくれる人がたくさんいたり、助言をしてくれる人も大勢いるので、「ここはどうしよう?」みたいなことは基本的にはないです。ただ、唯一『半分、青い。』のときだけは、10カ月以上も撮影をしていたので、自分なのか役なのかがわからなくなったんです。それは最初で最後の体験でしたね。 そのときはセリフをしゃべっている自覚もないし、自分の感情が動いている感覚もなくて、「え? 今、涙が流れてたの?」と自分で自分に驚きました。もはや別世界に行ったような気持ちだったんです。がんばっているのに、そのがんばりが伝わっている気もしなくて、「どうしよう……」と暗闇の中で過ごしているような、不安な感覚が長い間ありました。その経験をしていたからこそ、今回の「自分の描きたいものがわからないから描けない」と悩み、もがいている明子の姿はすごく共感しましたし、でき上がった作品を観てそのシーンで思わず涙が出ました。自分にとって大きな壁じゃないはずなのに、なぜか大きくて固い壁に感じて、どう壊せばいいんだろうっていうのは、誰にでもあることだなと思って、泣きましたね。 ──大きな壁が立ちはだかったとき、どのようにご自身を奮い立たせていますか? 永野 いい意味で「終わらないものはない」と言い聞かせています。今がしんどくても、この状況を乗り越えられる自信がなくても、絶対に大丈夫だって。時間は必ず進むし、終わらないものはないと思っているから、それでどうにかこうにか乗り越えてきましたね。 ──先ほど「スタッフさんや共演者の方々がまわりにいるから、お芝居で悩むことはない」とおっしゃいましたが、最初からそう思えていましたか? 永野 小学生でこの仕事を始めたので、最初は何も考えずに過ごしていたんですけど、この仕事に対して自覚を持ったときには、すでに座長が真ん中に立っていらっしゃり、サポートするように共演者がまわりを囲んでいました。さらに、それをいい方向に持っていくために、監督やスタッフのみなさんが常に現場のムードを作っていく姿を見て「あ、ひとりじゃないんだな」と実感しました。「自分が座長という立場で現場に入るときも、座長を支える立場で入るときも、どんなときでも自分は助けてくれる人たち、支えてくれる人たちに感謝を持ちながら頼ろう」と思ったのが、始まりだったと思います。 ──その考えに至ったのは、何歳のころですか? 永野 中学生のときには思っていましたね。当時、出会った先輩方の姿がとても大きかったんだと思います。 役者を辞めようと思ったとき、いつも作品が引き止めてくれた ──永野さんは女優を辞めようと思ったことが、過去に2度あったそうですね。きっと肉体的、精神的にもいろいろなしんどい経験があったと思いますが、それでも「お芝居が楽しい」「この仕事を続けたい」と思えたのは? 永野 私がこの世界に残った理由は、いつも作品が引き止めてくれたからなんですよね。1度目はしんどいから辞めたかったというより、高校受験のタイミングで「一生の職にするのは難しいのかもしれないな」と思い、「辞めようと思う」と家族や会社の人に話していたときに『俺物語!!』のヒロインに決まり、「これは辞められないぞ」となりました。 2度目は、小さいころからずっとお芝居をがんばったし、もう辞めようと思ったときに「最後に朝ドラのオーディションを受けてみない?」と言われて挑戦したら『半分、青い。』が決まりました。運なのか縁なのか、常に作品に引き止めてもらってきたんです。だからこそ、その作品に対して「恩返し」といったらおこがましいですけど、「この作品にすべてを懸けてみよう」と思ってなんとかやってきました。そのおかげで、今はすべてのお仕事を純粋に楽しめています。振り返ると、当時は楽しいよりも「続けるきっかけをもらえたからがんばらなきゃ」という感じで、がむしゃらにやっていた感じでしたね。 ──昨年はデビュー15周年を迎えられました。長く続けようと思ったというより、続けていたら15周年を迎えていた、という感覚なのかなと思います。 永野 まさに、気づいたら15年も経っていましたね。小中学生のころは、今みたいな仕事の仕方をしていなかったので、これだけの仕事が自分にある未来を想像していなかったです。忙しくなってからはギュッとしているので、仕事がなかった期間をカウントしなければ15年も経ってないかもしれないですけど、気づいたら「あ、そんなに経ってましたか?」って感覚です。私もそんなに長いことお芝居を続けてこられたんだなと感慨深いですね。 ──映画の話に戻りますが、『かくかくしかじか』の映像化を東村さんが何度も断ってきたのは、日高先生との日々に涙を流しながら心血を注いで描かれたこともそうですし、日高先生がすでにお亡くなりになっていることも含めて、それを映像作品に残すことにいろいろな感情があったのかなと思います。でも、映画を拝見したときに、お芝居を通して日高先生のことも、東村さんが日高先生と過ごした時間も肯定しているように見えたんです。特に今作において、お芝居はその人の人生や一緒に過ごしたことを肯定する行為に思えました。 永野 この作品は、東村先生の過ごしてきた時間だったり日高先生への思いを消化したり消化しきれなかったり、いろんな感情の中で描かれたと思います。そのなかで、東村先生が映画化を承諾してくださり、私はその気持ちに応えたかったです。今言ってくださったように、東村先生ご自身の人生を肯定して、またここから東村先生の新しい章が始まるみたいな感覚になってくださったらいいなと感じています。実際、東村先生からは「もうこれ以上のものはない」とお言葉をいただけたので、先生の人生のひとつにこの映画が入ったらいいなと思います。 ──ちょっと大きな質問なんですけど、永野さんにとってお芝居を言葉にするとなんですか? 永野 演じること自体は“ただただ偽り”ではありますけど、台本の中にいる登場人物たちにとってはそれが人生。そして私が生きていて一番やりたいと思うことも、一番続けたいって思うこともお芝居。大きな言い方をすると、私にとっては、もう生きる上で絶対的に必要なことだし生きがいに近いものです。きっとこれからも続けていくだろうし、続けていく努力をしていきたいと思います。 ──最後に、この映画を通して永野さんが観客に伝えたいことは? 永野 明子は日高先生に対して言えなかったことがあって、いまだに「あのときに言えばよかった」と後悔しています。だからこそ、やっぱり自分の大切な人に伝えたいと思ったことは今伝えるべきです。自分の気持ちを言葉にして大切な人に届けることが、どれだけ大切なのかが、この映画を観ればきっと感じてもらえると思います。映画を観終わったあとに、大切な人に「いつもありがとね」って言ってくれたらいいなって思います。 映画『かくかくしかじか』2025年5月16日(金)より全国ロードショー 出演:永野芽郁、大泉 洋 原作:東村アキコ 監督:関 和亮 脚本:東村アキコ、伊達さん 主題歌:MISAMO「Message」(ワーナーミュージック・ジャパン) 音楽:宗形勇輝 制作プロダクション:ソケット 製作:フジテレビジョン 配給:ワーナー・ブラザース映画 原作クレジット:「かくかくしかじか」東村アキコ(集英社マーガレットコミックス刊) (C)東村アキコ/集英社 (C)2025 映画「かくかくしかじか」製作委員会 取材・文=真貝 聡 編集=宇田川佳奈枝
BOY meets logirl
今注目の「BOY」をピックアップし、撮り下ろし写真を公開
-
 越山敬達(BOY meets logirl #058)
越山敬達(BOY meets logirl #058)越山敬達(こしやま・けいたつ)2009年4月21日生まれ。東京都出身 Instagram:keitatsu_koshiyama_official 映画『国宝』大垣俊介(幼少期役)で出演中 EBiDAN NEXTとしても活動中 撮影=Jumpei Yamada 編集=宇田川佳奈枝 【「BOY meets logirl」とは】 今、注目の「BOY」をピックアップし、撮り下ろし写真を公開します。
-
 八村倫太郎(BOY meets logirl #057)
八村倫太郎(BOY meets logirl #057)八村倫太郎(はちむら・りんたろう)1999年7月28日生まれ。神奈川県出身 Instagram:rintaro_watwing X:@Rintaro_watwing 2025年9月6日〜全国25カ所を回るWATWING LIVE TOUR『honest』開催決定 撮影=矢島泰輔 編集=高橋千里 【「BOY meets logirl」とは】 今、注目の「BOY」をピックアップし、撮り下ろし写真を公開します。
-
 齋藤璃佑(BOY meets logirl #056)
齋藤璃佑(BOY meets logirl #056)齋藤璃佑(さいとう・りゅう)2004年6月16日生まれ。秋田県出身 Instagram:saitoryu_616_official X:@saitoryu616 1st写真集 『All Light!』6月6日発売 写真集『All Light!』発売記念イベントを東京(6月7日)、大阪(6月8日)で開催 Vシネクスト『爆上戦隊ブンブンジャーVSキングオージャー』阿久瀬錠役で出演(5月1日〜期間限定上映) 『爆上戦隊ブンブンジャー』ファイナルライブツアー2025(3月〜5月/全国9都市で開催中) 撮影=井上ユリ 編集=宇田川佳奈枝 【「BOY meets logirl」とは】 今、注目の「BOY」をピックアップし、撮り下ろし写真を公開します。
若手お笑い芸人インタビュー連載 <First Stage>
「初舞台の日」をテーマに、当時の期待感や反省点、そこから得た学びを回想。そして、これから目指す自分の理想像を語る、インタビュー連載
-
 栗谷が「幸せな朝」を迎えても勢いの衰えない強運コンビ・カカロニの次なる展開とは?|お笑い芸人インタビュー<First Stage>#36
栗谷が「幸せな朝」を迎えても勢いの衰えない強運コンビ・カカロニの次なる展開とは?|お笑い芸人インタビュー<First Stage>#36カカロニのふたりは、なぜか、朗らかとしている。そして、自信に満ちている。撮影中の佇まいを見てそう思った。 彼らがまとう、余裕のオーラ。その秘密を知りたくなった。 芸人の初舞台について聞くインタビュー連載「First Stage」。今回はカカロニのふたりに、テレビでの初舞台や、ブレイクの舞台裏を話してもらった。そこで見えてきたのは、チャンスをものにするための徹底的な準備と、幸運を信じる前向きな姿勢だった。 【こちらの記事も】 人気コンビ・カカロニの半年遅れのファーストステージと、波乱のセカンドステージ|お笑い芸人インタビュー<First Stage>#36 目次「グレープカンパニーは各々なんです」コロナ禍のサッカーテレビに出た時期がたまたまよかった僕らは幸運である 「グレープカンパニーは各々なんです」 左から:栗谷、すがや ──2016年に結成したカカロニは、その後すぐに人力舎を退所してフリーになった。 すがや そうですね。1年間くらいですけどラスタ原宿を中心に、寄席にけっこう出てました。よかったのは、あの時期に栗谷さんが「カッコつけるキャラやってるけど、俺、本当はこういうこと思ってないんだよね」って言い出したことで。 ──どういうことですか。 すがや 「俺は落とし方とかは考えるけど、実践はできないんだよ。勇気がないから」って言われたんです。 栗谷 「そういう俺の性格で、漫才をやったほうがいいんじゃないか」って提案しました。それでナルシストにネガティブな要素を入れたらウケたんです。あと俺と組む前のすがやはずっとボケをやっててツッコミに慣れてなかった。だから俺がまっすぐナルシストすぎると全力でツッコまなきゃいけなくて、しんどかったんです。でもそれもネガティブ要素を入れれば、俺で落とせるようになる。 ──コンビの課題を一気に解消する提案だったと。その後どうやってグレープカンパニーに入るんですか。 栗谷 2016年の『M-1(グランプリ)』決勝で、「カミナリさんおもしれぇ!」ってなって、グレープカンパニーを知って。そこからサンドウィッチマンさんいる事務所じゃん、ここ行きたいってなって、メールを送りましたね。 すがや それまでは浅井企画のオーディションを受けてたんですけど、グレープにメールを送ってから数カ月後に「今ならオーディションできます」って返信があったので、浅井にはお断りを入れて。それでわりかしすぐ所属させてもらいましたね。 ──そもそも2016年のグレープカンパニーは、芸人ですらピンとこない事務所だったんですね。 すがや そうですね、カミナリさんもライブシーンで会うことってなくて、いきなり出てきた感じで。サンドさんも売れすぎてもはや事務所名で把握してなかったですし、永野さんもすでに入ってたんですけど事務所は意識してなかった。あ……でも(お見送り芸人)しんいちさんがいたから、グレープの名前は知ってたんだ。 ──2016年のしんいちさんとは知り合ってた? すがや しんいちさんとバイト先が一緒だったんですよ。まぁでも今の歌ネタをやる前のしんいちさんの事務所に行こうとはなかなか……(苦笑)。 栗谷 それまで腐っても人力舎とワタナベにいたんで、無名すぎる事務所はっていうのもありましたよね。今でこそ(東京)ホテイソン、ティモンディ、ランジャタイ、わらふぢ(なるお)さんとかいるけど、当時はサンドさん以外、誰もいなかったから。 ──その面々で一致団結してグレープカンパニーもここまで大きく……。 すがや 力を合わせた記憶はまったくない(笑)。 栗谷 各々がんばってた。グレープカンパニーって各々なんですよ。 コロナ禍のサッカー ──実際所属してどうでしたか。 すがや 「なんていい事務所なんだ!」って思いました。グレープの芸人がちょっと不満に思ってることも、いや、ワタナベと人力舎に比べたらだいぶ恵まれてる(笑)。めちゃめちゃオーディション多いですし。 栗谷 コロナ以降はYouTubeでネタが見られるようになったんで、オーディション自体減ってるんですけど、コロナ前はオーディションだけで忙しい時期とかあって。テレビにはまったく出てないし金も稼げてないのに、オーディションのはしごでした。月20日オーディション入ってた。 すがや 養成所の生徒向けに、オーディションでのハマり方で授業できるくらい必勝トークルートができ上がってました。 栗谷 こいつがここで暴露して俺がブチギレるとか。それで『ゴッドタン』の「この若手知ってんのか!?(2020)」もうまくいったんで。 ──オーディション地獄があったからこその成功だった。 すがや 俺らの感覚からすると地獄でもなかったんですよ。前の事務所ではチャンスすらもらえなかったから。 栗谷 売れてる感覚すらあったよな。売れてない芸人はテレビ局なんか行けないじゃないですか。でも今くらい行ってた(笑)。 すがや オーディションも二次、三次まであったし。 栗谷 夢に向かってがんばってる感じがあったよね。あれは青春だった。 すがや やっと軌道に乗ってきた手応えもあったし。テレビに出るまでではないけど、スタッフには気に入ってもらえて最終まで残るんですよ。だから一個番組に出たら、ほかのところも急に使ってくれるようになって。 ──おもしろいと思っても実績がないなかなかとキャスティングしづらい。そんなときにひとつハネると一気に連鎖する。それにしてもふたりになってからはわりとトントン拍子ですけど、うまくいかない時期はありましたか? 栗谷 コロナ禍ですね。なんにもなくなったじゃないですか。テレビに出てる人すら仕事がなくなって、再放送が流れてるみたいな。それだったらテレビにまだ出てない人はもう無理じゃんって。ずっと家にいてけっこう病んじゃって、とりあえず解散しようって思いました。 すがや それは初めて聞いたな(笑)。なんで解散の話しなかったんだろう。 栗谷 コロナ禍に事務所で久しぶりにネタ見せやりましょうってなって、すがやと前日にネタ合わせしたんですよ。そしたらこいつがサッカーボールを持ってきて、急にパスし始めて。 すがや ちょっと蹴ろうよって。 栗谷 それが楽しくて。で、じゃあちょっと……またがんばるかって(笑)。 すがや はははは(笑)。僕は僕で、家にこもっててしんどかったんで、ボール蹴りたかったんですよ。ネタ合わせよりも、一回リフレッシュしたかった。 栗谷 久々に外で笑ったな、笑顔になったなって思って、やっぱ悪くないなって。その直後に『ゴッドタン』に出られたんで解散しなくてよかった。 テレビに出た時期がたまたまよかった ──カカロニがテレビに現れたのは、コロナ禍だったんですね。 栗谷 コロナ禍に出られたのはラッキーでした。僕らふたりともひな壇に座って「ちょっとちょっとー!」って前に出られるタイプじゃないから。 ──たしかにテレビ収録も演者同士距離を取らなきゃいけないから、人数も限られてましたもんね。 栗谷 出演者が減ったぶん、1組を深掘りするようになった時期だったんで、ありがたかったです。僕は自分から行ける芸風じゃないんで。『ウチのガヤが(すみません!)』とか昔は30人とか出てたじゃないですか。それが5組くらいになったら、1組10分くらいプレゼンできるようになって。そこで掘ってもらって初めて僕はキャラを出せる。それでコロナが終わったら先輩にも知ってもらえてるから、『アメトーーク!』に出てもイジってもらえて。 ──ちなみにテレビの初舞台は『ゴッドタン』ですか? 栗谷 コンビでは『有ジェネ(有田ジェネレーション)』ですね。あれは2018年か。 ──ふたりが最も敬愛するくりぃむしちゅー有田(哲平)さんの番組。 栗谷 めっちゃ緊張しました。 すがや 大部屋の楽屋だったな。 栗谷 いろんな人にあいさつして、この人は返事しねぇんだなとか思ってましたね。 すがや 『有ジェネ』はみんなレギュラー外されたくなくてバチバチだったからね(笑)。 栗谷 今はみんな優しいですけど、当時はめっちゃ怖かった。 ──ネタの手応えはどうでしたか? 栗谷 あんまりよくなかったですね。ちょうどオーディションに呼ばれまくってた時期なんで、ネタをこねくり回してたんですよ。同じ番組に同じネタは持っていけないので毎回、進化版を出さなきゃいけなくて。 ──進化版なら、よりおもしろくなる気がするんですけど……。 栗谷 いや、スタッフさんに向けた進化版なんで、ちょっとわかりづらくなってるんですよ。初見の人にはもっとわかりやすいのを出したい。なので、これ伝わりづらいだろうなって思いながら本番やってました。 ──憧れの有田さんとの初対面はどうでした? すがや ずっと『オールナイトニッポン』を聴いてたから、有田さんがグイグイ来られてもあんま喜ばないのもなんとなく知ってて、ざっとあいさつしました。でもその時期、有田さんの番組の前説もちょこちょこあって、顔合わせる機会があったんです。僕たちがドッキリをかけられてる映像を有田さんが見てたこともあって、勝手に縁を感じてました。 栗谷 僕は今も『(全力!)脱力タイムズ』にカリスマ3(ぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1、リンダカラー∞・Denとのユニット)で、2週に1回お会いしてますから。 すがや 僕も半年に1回くらい『くりぃむナンタラ』に呼んでもらってますし、前編でも言いましたけど、有田さんとプライベートでゲーム大会してるんで夢のようです。 僕らは幸運である ──カカロニ、順風満帆ですね。 栗谷 もちろん不安はありますけど、そうですね。 すがや 僕らは幸運であるということは、もう知ってるので。 栗谷 不安はありつつも大丈夫かもっていう自信はありますね。事務所もちゃんと仕事入れてくれるし、バラエティの現場でも誰かが僕のことなんとかしてくれますし(笑)。去年まではずっと不安で、今年になってようやく楽しいです。 すがや 僕はわりとずっと楽しいですけどね。 栗谷 いや、もちろん楽しいは楽しいですけど……前は「この『アメトーーク!』ハネないと次はない……」って思って緊張してたんです。今はなんとかしてもらえる状況ができたので。 ──栗谷さんは2024年末に恋人ができたことを発表して、公私ともに順調ですもんね。 栗谷 2年前まで女性とまともにしゃべれなかったのに、番組でマッチングアプリをやったのをきっかけにここまで来られましたね。 ──どうやって苦手意識を克服したんですか。 栗谷 マッチングしたら1回は必ずランチするって決めて、60人ぐらいの女性と会ってたらだんだん楽しくなってきました。でも、なかなかモテないキャラという芸風があったんで、彼女作ったら仕事なくなるかもっていう不安はあって。いいなって思う子がいても、仕事を失ってまで付き合えないやって。 ──今の恋人は、その不安も払拭するほどの出会いだったんですね。 栗谷 そうですね。去年の夏に出会ったんですけど、めちゃくちゃ楽しくて。どうやらこれ彼女できても仕事なくならないっぽいぞって秋くらいに確信して、11月に付き合って。 ──どういう方なんですか。 栗谷 2歳年上で、僕が失敗してもなんでも笑って楽しくしてくれる。全部受け止めてくれる優しい人ですね。こんな幸せでいいんかって思います。結局仕事も減らず、なんなら増えてるぐらいですし。 すがや 大変なのは漫才だけですね(笑)。前編でも言いましたけど、栗谷さんに彼女ができて、今までの漫才ネタは全部使えなくなったんで。 栗谷 でもそこもラッキーで、俺が童貞卒業したと同時に、今度はこいつのポンコツがバレ始めた。今までポンコツの部分は隠してくれてたんですよ。 すがや 栗谷さんのキャラを見せたいのに、僕が目立つとブレるんで。 栗谷 いやぁ隠しきって、今このタイミングでバレるって本当に俺たちは運がいいです。だからこの先も大丈夫じゃないですかね。 文=安里和哲 撮影=青山裕企 編集=後藤亮平 カカロニ 栗谷(くりたに、1989年9月5日、神奈川県出身)と、すがや(1991年3月5日、東京都出身)のコンビ。2016年に結成し、2017年にグレープカンパニーに所属する。2020年には『ゴッドタン』の企画「この若手知ってんのか!? 2020」の“今の時代に売れそうな新世代芸人”部門で2位に入り、ブレイク。栗谷は、すがちゃん最高No.1(ぱーてぃーちゃん)とDen(リンダカラー∞)とのユニット「カリスマスリー」でも活動する。サッカー好きで知られるすがやは、2018年のサッカーW杯「日本対セネガル戦」をゴールネット裏で観戦している際、セネガル選手のシュートをヘディングした映像が話題になった。 【後編アザーカット】
-
 人気コンビ・カカロニの半年遅れのファーストステージと、波乱のセカンドステージ|お笑い芸人インタビュー<First Stage>#36
人気コンビ・カカロニの半年遅れのファーストステージと、波乱のセカンドステージ|お笑い芸人インタビュー<First Stage>#36ナルシストキャラなのに、繰り出すセリフはネガティブ。カカロニ栗谷の「ネガティブナルシスト」はひとつの発明だった。コロナ禍に現れた新種は、あっという間にお笑いファンのハートをつかんだ。 学生時代はともにサッカーに励みながら、くりぃむしちゅーに憧れたカカロニ。彼らがコンビを組み、初舞台を踏むに至るヒストリーを紐解くと、鼻っ柱の強い栗谷の、漢気が見えてきた。 若手お笑い芸人インタビュー連載<First Stage> 注目の若手お笑い芸人が毎月登場する、インタビュー連載。「初舞台の日」をテーマに、当時の高揚や反省点、そこから得た学びを回想。そして、これから目指す自分の理想像を語ります。 目次栗谷は小6まではイケメンで“俺様キャラ”だったすがやは、くりぃむしちゅーと友達だった担任に背中を押されて芸人の道へ……栗谷、不遇の養成所時代キレる栗谷、人力舎も速攻で辞める 栗谷は小6まではイケメンで“俺様キャラ”だった 左から:栗谷、すがや ──「ネガティブナルシスト」で知られる栗谷さんですが、2024年末に初めての恋人ができたことを所属事務所のホームページでお知らせして話題になりましたね。 弊社所属タレント カカロニ栗谷からのお知らせ 栗谷 「幸せな朝」を迎えさせていただきました。 すがや でも、それでカカロニの持ちネタは全部成立しなくなったんです(笑)。これまではナルシスト×ネガティブな童貞キャラだったんですけど、お客さんも「彼女いるじゃん」っていうのがよぎる台本になっちゃったので。 栗谷 だから作り直してるところです。前は僕がボケで、すがやがツッコミでしたけど、それも入れ替えて。 ──栗谷さんの「幸せな朝」は、カカロニというコンビを抜本的に変える出来事だったと。それなら事務所ホームページで知らせるのも納得です(笑)。でもなぜ女性と縁がなかったんですか。 栗谷 僕はずっと一軍だったんですよ。小中高、体育祭のリレーはずっとアンカーでしたし。小学6年生まではけっこうイケメンで、わがままな俺様キャラで。でもそのころ、鼻の骨が1本足りないことがわかって顔の手術をしたら、顔が変わっちゃってブサイクになっちゃって。それで女子に無視されるようになったんです。女子に嫌われたら、男友達からも距離取られるようになっちゃって。 ──それはつらい……。 栗谷 でも俺も学校の友達をちょっと下に見てたんですよ。サッカーのクラブチームに入ってたんで、学校のヤツらとはつるまない、みたいな。なので運動神経はいいんだけど、「何してるかわからないヤツ」みたいな扱いになってたのが中学時代ですね。 ──高校は? 栗谷 僕が通ってた厚木北高校って、中学でクラブチームに行ってた子が集まる学校だったんですよ。だから最初から友達がいっぱいいたし、先輩も俺のこと知ってくれてたんで、人間関係を作る必要がなかった。入学早々、3年生の教室呼ばれて「みんなの前でなんかやれ」みたいな。 ──イジられキャラだった? 栗谷 いや、普段はイジるほうが多かったですよ。 すがや たしかに栗谷さんの気質はイジる側ですね(笑)。 栗谷 当時は狩野英孝さんが出てきたり、出川(哲朗)さんが再ブレイクしたりして、イジられる側もすごいっていう風潮がもうあったんですよ。バナナマンの日村(勇紀)さんもブサイクイジりされておもしろかったし。「イジるほうが上/イジられるほうは下」っていう意識はなかったですね。 ──学生のときからお笑いは好きだったんですか。 栗谷 そうですね、中学のときには芸人になりたいなと思ってました。サッカーやってるせいで、夜は早く寝なさいっていう家庭だったんで、親の目を盗んでバラエティ番組観てましたね。『ワンナイ(R&R)』、『内P(内村プロデュース)』、『(くりぃむしちゅーの)たりらリラ〜ン』(のちに『くりぃむしちゅーのたりらリでイキます!!』に改名)、『くりぃむナントカ』……。くりぃむしちゅーさんは特に好きでした。 すがやは、くりぃむしちゅーと友達だった すがや 僕もくりぃむさん、大好きでした。テレビもそうですけど、やっぱり『(くりぃむしちゅーの)オールナイトニッポン』ですね。中3の夏に始まってハマって、それきっかけでTBSラジオの『JUNK』も聴くようになって、お笑いにずっぽり。僕もずっとサッカーやってたんですけど、高3の冬にくりぃむさんのANNが終わるってなって、「よし、芸人になろう」と思いました。 ──かなり飛躍があるように感じるんですけど(笑)。 すがや ラジオを聴きすぎて、くりぃむさんと友達になったような錯覚を起こしてたんです(笑)。なんなら友達としゃべってる時間より、ラジオを聴く時間のほうが長かった。ラジオが終わって、この人たちに会えなくなるのはイヤだから、芸人になれば会えるぞってことです。 ──なるほど(笑)。実際に共演の機会もありますか。 すがや 番組でもたまにご一緒させてもらいますし、今は有田(哲平)さんとプライベートでゲーム大会とかして遊んだりしてます。 ──本当に友達になった……! すがや 友達っていうと恐れ多いですけど(苦笑)。でも夢のようです。リスナーだった当時の自分に教えてあげたい。 ──高3で芸人になろうと思って、すぐ養成所に行ったんですか? すがや いや、くりぃむさんのANNが終わったのが高3の冬で、いきなり「受験辞める」って親に言い出せなかったんで、大学には行くことにしました。バイトでお金貯めて、3年生のときに養成所入って。その1年で無理そうだったら就活しようって。なんだかんだ逃げの手は残しておいて(笑)。それで最初はワタナベコメディスクールに行きましたね。 ──養成所はどうでした。 すがや 200組くらいいたんですけど、ハガキ職人をやってたおかげで、最初は上のクラスに行けましたね。相方が「俺は島田紳助になる」ってトガり散らかしてるのに、「ネタはお前が書いてくれ」っていう変な子で。 栗谷 ネタ書かない島田紳助さんはあり得ないって。 すがや 最初のライブでは、舞台裏で女芸人に「全然目見て話してくれないじゃん」ってイジられてふてくされて、ネタ合わせしてくれなくて(笑)。たぶん、栗谷さんと同じで女性が苦手な人だった。でも、そこをネタ書かない上に、女子に免疫がないことをイジられてふてくされちゃう人とは、コンビ続けられないなって思いましたね。そのあとは今、モンローズっていうコンビをやってる宮本(勇気)と、ベアードノーズっていうコンビを組んで卒業しました。 ──ベアードノーズは何年くらい活動したんですか。 すがや 4年くらいですね。見た目はちょっとシュッとしてたから、それなりに笑ってもらえたんですけど、テレビのオーディションでは手応えがまったくなくて解散しました。仲悪いとかではなかったんですけどね。そのあと栗谷さんと組みました。 担任に背中を押されて芸人の道へ…… ──おふたりが合流する前に、栗谷さんの経歴を聞かせてください。 栗谷 高校卒業したらNSCに入ろうと思ってたんですけど、なかなか言い出せないうちに大学も指定校で決まっちゃって。 すがや スポーツ科だったから内申点が取りやすかったんですよね。 栗谷 そうそう。でも担任の先生だけには「お笑いやりたい」って言ってて。その先生は『(痛快なりゆき番組)風雲!たけし城』に出たことがあって、たけし軍団にもスカウトされたらしくて。 ──そんな先生が身近なところに。 栗谷 すごくおもしろい先生でした。それで「栗ちゃん、お笑いやりたいんじゃないの? がんばりなよ」って背中を押してくれて、三者面談でも「お父さん、悟史くんはお笑いやりたいんですよ」って言ってくれて。父親が「いや、お笑いなんて……」って言っても「一回やらせてあげてください」って説得してくれて。結局、推薦が決まってた大学にも、校長先生と一緒に謝りに行ってくれて、それで1年間お金貯めて、NSCに行きました。 ──NSCはどうでした? 栗谷 1週間で辞めました。 すがや 先生があそこまでしてくれたのに(笑)。 栗谷 有吉(弘行)さんがブレイクしたときだったんで、自分もいけると勘違いして、同期に毒舌でバーッて言ってて。当然それがウケなくて、この状態でネタ見せして「つまんないヤツじゃん」って思われたらいよいよヤバいなと思ったら怖くて行けなくなっちゃいました。 ──担任の先生はそのこと知ってるんですか。 栗谷 いや、言えないです。あれ以来会えてないんで、一回謝りたいし、感謝も伝えたいですね。 ──ぜひそうしてください。その後、栗谷さんはどうするんですか。 栗谷 20歳になるんだし、やったことないことやってみようと思って、ヤンキーになってみました。近くのコンビニに小学校のとき仲よかったヤンキーの子たちがたまってたんで、「仲間に入れてくんない?」って。 ──歓迎してくれた? 栗谷 俺がおもしろいっていうのも伝わってたんで、普通に入れてくれましたね。ずっと駐車場でくっちゃべって、ダーツ行ったり、ボーリングしたり、ほかの人が車イジってるの見たりして。その間はお笑いは何もしてなかった。 ──いずれ芸人に戻る気はあったんですか。 栗谷 それはありましたね。でもヤンキーも楽しそうだった。で、ある程度遊んで満足したんで、工場で1年間働いて貯めたお金で(スクール)JCA(人力舎の養成所)に行きました。人力舎ってみんな仲がいいイメージがあるじゃないですか。おぎやはぎさん、アンタッチャブルさん、(東京)03さんの雰囲気ですよね。みなさん好きでしたし。 栗谷、不遇の養成所時代 ──じゃあ栗谷さんの芸人としての初舞台は、人力舎時代ですか。 栗谷 そうっすねぇ。でもその前にまたいろいろあって……。僕がJCAに入った年に、本来あった2クラスに加えて、「阿佐ヶ谷クラス」っていうのが新しくできたんです。そこに配属されたんですけど、授業初日に講師の方が「このクラスは実験クラスです。1年間何もしなかったらどうなるか見てみます」って言い出して。 すがや 60万円払ってるのに(笑)。 栗谷 最初はボケだろうなって思いましたけど、本当に誰も教えてくれなくて。で、夏に初めてのネタ見せがあったんですけど、当然誰もうまくいかなくて、講師が「このクラスはダメです。このままだったらライブやりません」って言い出して。 ──そんな理不尽な……。 栗谷 しかも、僕だけ呼び出されて「こいつらやる気ないから、お前が辞めさせろ。そうしないとライブやらせないよ」って。 すがや 栗谷さんが同期にリストラを告げたんですよね。 栗谷 うん、それで「ちゃんとやるならやる、やらないなら辞めてくれ」ってはっきり言って辞めてもらいました。で、ようやく9月に初ライブでしたね。そのネタはウケたんですよ。そのときの相方は、ソニーで2年くらいやってた経験者だったんでネタが作れて、みんなより完成度も高かった。「おやじ狩り」のネタでしたね。僕が親父役で「金出せよ」って言われるんだけど、変なものをどんどん出すモノボケみたいなネタで。 ──当時はコントだったんですね。 栗谷 人力舎だしコントかなって。でも当時はフリーライブに出ちゃいけないルールがあって、かといって事務所ライブも月1〜2回しかない。『キングオブコント』で結果を出さないとK-PROにも呼ばれないし、当時はネタ番組が軒並み終わって、お笑い氷河期みたいになってたんで。そんななかでも同期のトンツカタンとかは2年目で『おもしろ荘』に呼ばれてたから、オーディションにすら行けない俺らは絶対売れないってことで解散しました。 すがや その解散のタイミングが、僕の解散と同じ時期だったんで、組むことになったんですよ。 キレる栗谷、人力舎も速攻で辞める ──もともとふたりは知り合いだったんですか。 栗谷 いや、全然。共通の知り合いがいて、「ちょうど解散したヤツいるから会ってみれば」ってところからです。 すがや 新宿のベローチェで、ふたりっきりで会いましたね。 ──本当にお互いのこと何も知らない状態で。 すがや 最初、趣味の話したかな? どんな芸人が好きかとか、どんなネタやりたいのかとか。あと、ふたりともサッカーやってたっていうのは教えてもらってたので、その話。そういえば、組む前に一回、フットサル大会出たよね。 栗谷 優勝したんだよな。 すがや その景品でワールドカップ予選のチケットをもらったんだ。チームメイトがMVPになったんですけど、その人が気遣って「お前らで見てこいよ」って言ってくれたんです。 ──最初は友達みたいな感じでスタートした。でもふたりとも当時は人力舎とワタナベで他事務所だったんですよね? すがや まずは僕が人力舎に行くことになりました。ワタナベに栗谷さんが入るのは難しそうだけど、人力舎は行けそうな雰囲気があったから。 栗谷 それでいったん預かりになったんです。でもなかなかライブに出られなかったんですよ。当時あったじゃないですか、事務所移動したら半年間活動しちゃいけないっていう謎ルール。 すがや そんなところだけ若手芸人にも芸能界のルールが適用されるんだって(笑)。 栗谷 なので初舞台はコンビになってから半年後でしたね。 すがや 初舞台はわりとうまくいったんですよ。ナンパの成功数で競って、負けたほうが一枚ずつ服を脱いでく設定のコントで、栗谷さんが男前キャラのまんま、どんどん裸になっていく。 栗谷 あのネタがめっちゃウケた記憶がありますね。 すがや でもその次のライブで事務所を辞めましたけど。だから人力舎のライブは2回しか出てないんです。 ──何があったんですか。 すがや 出番直前に栗谷さんがマネージャーとケンカして辞めることになったんです。 栗谷 半年出してもらえなかったのに、ネタやる直前に「このネタおもしろくなかったら、もう来なくていいから」って言われたんですよ。それも舞台袖で。そのまま舞台出ていってウケたんですけど「辞めます!」って言って、それで終わり。 すがや 完全にふてくされた栗谷さんが、カツラ脱いで、去っていきましたね。 栗谷 あれに関してはこっちに完全に非はなかった。まぁもうその人はいないんですけど。「ピンだったら残っていいよ」みたいな、すがやに対してすごい失礼な感じだったんすよ。いや、お前らがすがや連れてきていいって言ったのに、そんな言い方ないだろって、すげぇムカついたんですよね。 すがや 止めてくれたマネージャーもいたんです。その人は「私が担当するんで」って泣きながら止めてくれて。だから俺は「面倒見てくれるって人もいるから残ってもいいんじゃないの」って言ったんだけど、栗谷さんは辞めるって聞かなくて。しかもそのとき栗谷さんが「栗谷だけピンで残るならいいよ」って言われてたことを、俺は知らなかったんです。 栗谷 別に隠してたつもりもないですけど。怒りがピークに達して感情的になったから説明してないだけです。 すがや 今でこそ感謝してますけど、当時は何も言ってくれないから「意地張って辞めなくてもいいのに」って思ってました。まぁあそこで辞めて、結果よかったんですけどね。 文=安里和哲 撮影=青山裕企 編集=後藤亮平 カカロニ 栗谷(くりたに、1989年9月5日、神奈川県出身)と、すがや(1991年3月5日、東京都出身)のコンビ。2016年に結成し、2017年にグレープカンパニーに所属する。2020年には『ゴッドタン』の企画「この若手知ってんのか!? 2020」の“今の時代に売れそうな新世代芸人”部門で2位に入り、ブレイク。栗谷は、すがちゃん最高No.1(ぱーてぃーちゃん)とDen(リンダカラー∞)とのユニット「カリスマスリー」でも活動する。サッカー好きで知られるすがやは、2018年のサッカーW杯「日本対セネガル戦」をゴールネット裏で観戦している際、セネガル選手のシュートをヘディングした映像が話題になった。 【前編アザーカット】 【インタビュー後編】 栗谷が「幸せな朝」を迎えても勢いの衰えない強運コンビ・カカロニの次なる展開とは?|お笑い芸人インタビュー<First Stage>#36
-
 賞レースでも活躍し、ブレイク間近と話題のコンビ・ひつじねいりが抱く焦燥と野望|お笑い芸人インタビュー<First Stage>#35
賞レースでも活躍し、ブレイク間近と話題のコンビ・ひつじねいりが抱く焦燥と野望|お笑い芸人インタビュー<First Stage>#35細身の元慶應ボーイ・細田が並べ立てる屁理屈に、ふくよかな男・松村が濃厚な関西弁で熱くツッコむ。東と西の笑いが融合したしゃべくり漫才が魅力のコンビ・ひつじねいり。 前回の『M-1グランプリ』では惜しくも準決勝敗退。しかし確実に認知を広げ、活躍の場は広がっている。 はたから見ているとのぼり調子なひつじねいりだが、本人たちの自覚は違うようだ。死屍累々の芸人界でひと旗あげるべく、がむしゃらに戦う彼らの現在地を聞いた。 【こちらの記事も】 紆余曲折を経て主役の座が見えてきたコンビ・ひつじねいりの期待にあと押しされた初舞台|お笑い芸人インタビュー<First Stage>#35 目次ひつじねいりには、何かが足りんライブシーンに居座ってしまったテレビで傭兵として爆死したい ひつじねいりには、何かが足りん 左から:松村祥維、細田祥平 ──ネタ作りはどうしてますか? 松村 細田が0→1を出して、台本を持ってくるんですけど、一言一句決まってるわけじゃないんで、僕が編集する感じです。前のコンビではネタ作りしてましたけど、僕はゼロからイチを生み出すのが苦手やなと思ったんで、このかたちになりましたね。 細田 最初のころは(松村が)遠慮じゃないけど気を遣って、台本をまんまやってくれてて。でもこれじゃM-1勝てんぞってなって、気になるとこを言ってくれるようになりましたね。 松村 組んで1年くらいは細田の発想にシンプルにツッコむみたいな感じで。それがちょっと戦うには弱いなってなってから、お互いの違いを乗せたかたちになってきた。 細田 あと今年になって、ラジオを通して外部の意見をくれる人を募りました。2年くらい前に、ふたりで詰めるやり方だと、天井このへんかなぁって。 松村 今、3人いますね。ひとりはガッツリお笑いの作家さんですけど、あとは別の畑の方です。ネタの種だけあるときに、「どういう拾い方がいいですかねぇ」って聞いたりして。 ──客観的な視点を入れているというのは意外です。どのネタもふたりの人柄(ニン)が立ってるので気づきませんでした。 松村 組むときの目標として、M-1で決勝行きたい、優勝したいっていうのがはっきりあったんで、そこに行けない間はずっとテコ入れは繰り返すでしょうね。 ──昨年のM-1では初めて準決勝に進出しました。着実にステップアップしてる印象があるんですが。 松村 やってることは間違ってはないんでしょうけど、決勝に届かないってことは単純なウケ以外の部分で、何かが足りんってことでしょう。だったら何かやらんとあかん。まぁ落ちても「なんでやねん!」とはならないですけど。 ──その足りない「何か」って、現状ではなんだと思いますか? 細田 ネタの切り口、設定のところがまだ弱いのかなと。今まではふたりの人間性と対照性を見せてきましたけど、それだけだとまだ足りない。 ──昨年末のM-1敗者復活戦は初めての舞台でしたが、いかがでしたか。 細田 勝つかもとは思ったんですけど、まぁ勝ったところで……とは思いましたね。 松村 決勝行ったとて、令和ロマンにボコボコにされてたから。 細田 たぶん損してたと思うんで、結果、勝ち上がれなくてよかったです(笑)。 ライブシーンに居座ってしまった ──近年マセキ芸能社では、おふたりより芸歴の長いモグライダーやハンジロウといった中堅や、同世代のきしたかのが活躍されています。やや遅咲きの面々を見ていて、自分たちもまだまだ間に合うぞって背中を押されるところはありませんか。 松村 いや、普通にめっちゃ焦りますよ。子供のころテレビで見てたスターは20代後半だったんで、僕らみたいに30代半ばでお金はギリギリ、テレビもちょっとしか出てないってヤバいなと思います。SMAにいたときにバイきんぐの小峠(英二)さんにお世話になってて、今もたまに飲ませてもらうんですけど、あの人が『キングオブコント』で優勝したのが、36歳のときなんです。 ──松村さんは今年37歳になるから、小峠さんがチャンピオンになったときを超えると……。 松村 そうなんですよ。当時のバイきんぐさんって、死ぬほど遅咲きで苦労人っていう扱われ方だったじゃないですか。それでも36歳やったっていうのがヤバくて。あんなに苦労人やって言われてた、つるっぱげのおじいちゃんが報われたのに、俺はまだ報われてない。 ──たしかにそう聞くと焦るのもわかります。 松村 それこそ前編でも話題になったストレッチーズって、2022年に『ツギクル(芸人グランプリ)』で優勝して、M-1も準決勝まで行ってるんすよ。俺らより前に「次はストレッチーズの時代や!」ってなってたんです。でも、ちょうど昨日(高木)貫太を飲みに誘ったら「行きてぇけど……金がない」って言うんですよ。 ──なんと……。 松村 僕もびっくりっすよ。さすがに「今日俺がおごったるわぁ。俺の金で飲め!」って言っちゃいましたね。自分らより先にガッと行きかけてたヤツらが金ないのは焦ります。 ──ちなみにマセキだと、どのあたりの芸人がバイトを辞めて芸人仕事だけで食べていけてるんですか。 松村 僕らとサスペンダーズがギリギリで食えてる。 細田 カナメ(ストーン)さんも食えてるはずだけど、借金が(笑)。 松村 吉本(興業)だけですよ、若手でもたくさん食えてるのは。僕らがガッと上行って、仲間をフックアップできる立場になれればいいですけどね。ライブシーンでいうと、僕らってもうだいぶおじさんなんでいい加減上がらないといけないんですけど、実は下もあんまり育ってないんですよ。次の若手があんまり出てきてないから、僕らが中心に居座ってしまってる。吉本はそのへんもうまく回ってるんですけどね。 細田 僕はライブシーンがどうこうっていうより、自分のことで精いっぱいですね。 松村 細田はこの世代の中で一番熟してないんですよ。この芸歴ではありえんパフォーマンス。コイツだけマジで大学生みたい。 細田 本当にそうなんですよ。僕はしゃべりもステージングも全然ダメで……。ここから僕らが勝ち上がるために必要なものを考えると、僕の足りてないところばっかりなんです。 松村 これは自分らのラジオでもしゃべってることなんすけど、細田は青臭いまんま、ここまで来てる。たぶんコイツはお笑いを頭の中でだけやってきたんやなって。でも今は本人が意識して成長しようとしてるぶん、まわりの先輩も「最近の細田、接しやすくなったな」って徐々に認められてきてますけど。 細田 年齢的にも芸歴的にも、かわいげを出すとかってやり方はギリギリアウトなんですけどね……。 松村 20代前半のヤツ育ててるみたいな気分ですよ(笑)。 ──松村さんは相方として、細田さんの青臭さに気づいてたはずですよね。なんでここまで放置したんですか? 松村 もちろん気づいてましたよ! でも自分でなんとかすると思ってたんです。なのに、いよいよなんともならんから! 組んで3〜4年目までは我慢してたんです。でもこれはいよいよあかんわって。僕らほんまにずっとジタバタしてますね。 テレビで傭兵として爆死したい ──今後はどんな活躍のビジョンを描いてますか? 細田 僕はずっとおもしろいことを言ってカッコいいと思われたいんです。だから学生気分でやんなって言われるんでしょうけど。 ──前編では「『火花』憧れはもうない」って言ってましたけど、まだ引きずってる……? 細田 そうかもしれないですね。僕は足りてないところを宿題としてまじめにやっていって、その先でおもしろいこと言いたい。 松村 細田はまだまだ自分磨きで必死なんですよ。自分がちゃんと磨けてないから、具体的に何になれるかまだわかってない(笑)。 細田 でも僕、めっちゃまじめなんで、一個一個がんばるのは性に合ってます。 松村 こっちは次の課題を毎回提示せなあかんので大変ですよ(笑)。「これできた! ハイ次これ!」ってずっとやってるんで。最近だと『大喜る人たち』でも「MCをやるんじゃなくて、お前もやる側に回れよ!」って。この見た目は絶対大喜利できると思われるんで。 まぁ僕だけでも先に売れればいいんですけどね。そしたら「コイツ、ヘンなヤツなんですよ」って紹介できるじゃないですか。そのために「プレイヤーとしていろんなことできますよ」ってことで、いろいろやってます。サツマカワ(RPG)さんと、ストレッチーズの貫太とやってる『トゥリオのKOC優勝への道』ってPodcastもやってるし、『こちら幡ヶ谷待機所』っていうYouTubeチャンネルをスタミナパン・トシダと、大仰天・田口とも組んでますし。 ──YouTubeやPodcastで活動の幅を広げている松村さんは、テレビよりネットのほうに活路を見出している? 松村 いや、本当はいっぱいテレビに出たいですよ。ウエストランドの井口(浩之)さんと仲いいんですけど、あの人みたいにレギュラー番組はあんまなくても、この人おったら全部おもろなるなって芸人になりたい。 あと、芸人のおもちゃになりたいですね。子供のころからずっとイジられてやってきたんで、そういうところを見せていきたい。きしたかのさんとかって、ネタが高野(正成)さんの説明書になってるじゃないですか。ああいうネタも必要やなって思います。そんで、食べたいもの食べられて、いくらでもおごれるくらい稼ぎたい。 ──テレビで活躍したいんですね。 松村 めちゃめちゃテレビ至上主義です。YouTubeは結局ナメちゃうっていうか。テレビってどんだけしんどいことになっても、結局、一番影響力がある。だから、そこで自分も戦っていきたいんですよ。ルールとかコンプラはどんどん厳しくなるんでしょうけど、その網目をくぐっていきたいですね。 どうせ僕らはテレビにフィットできない側の人間ですけど、若い子らはそのへんうまいことやるじゃないですか。その手前でがんじがらめになった僕は、わめき続けたい。最後まで「女がめっちゃ好きやねん!」って叫び続けたい。テレビでまだこんなん言ってるでって呆れられたい。 細田 僕らってさらば(青春の光)さんとかAマッソさんみたいに、自分らの国を作っていくタイプではなくて、もらった仕事を一個ずつこなしていく傭兵タイプだと思うんです。だからどんな仕事もスケジュールが空いてたら行きます。 松村 傭兵として戦いますよ。僕らはどうせ爆売れはしないんで。 ──今回はブレイク直前のひつじねいりさんの焦燥を聞けて、貴重なインタビューになった気がします。 松村 ブレイクできるかほんまにわからないですからね。このFirst Stageさんがストレッチーズを取材したのってちょうど『ツギクル』優勝して、M-1準決勝行ったタイミングですよね。そう考えると、僕らも踏ん張らなあかんと思いますよ。 ──テレビで活躍するふたりを見たいです。 松村 早くボロ雑巾になりたいです。 細田 もっと働きたいですね、働かせてください。 文=安里和哲 撮影=青山裕企 編集=後藤亮平 ひつじねいり 細田祥平(ほそだ・しょうへい、1991年11月30日、埼玉県出身)と松村祥維(まつむら・よしつな、1988年7月2日、大阪府出身)のコンビ。2019年に結成し、2023年には『ツギクル芸人グランプリ』で準優勝する。『M-1グランプリ2024』では初めてセミファイナリストとなった。大喜利ライブ『大喜る人たち』のMCとして、お笑いファンの信頼も厚い。 【後編アザーカット】
focus on!ネクストガール
今まさに旬な、そして今後さらに輝いていく「ネクストガール」(女優、タレント、アーティスト等)を紹介していく、インタビュー連載
-
 休日にはあえてグルテンを摂取!──女優・鳴海唯の「チートデイ」
休日にはあえてグルテンを摂取!──女優・鳴海唯の「チートデイ」#21 鳴海 唯(後編) 旬まっ盛りな女優やタレントにアプローチする連載「focus on!ネクストガール」。 鳴海唯(なるみ・ゆい)。2019年、NHK連続テレビ小説『なつぞら』で、テレビドラマ初出演を果たす。2021年『偽りのないhappy end』で映画初主演。その後、大河ドラマ『どうする家康』(2023年・NHK)、ドラマ『Eye Love You』(2024年・TBS)、映画『赤羽骨子のボディーガード』(2024年)、ドラマ『七夕の国』(2024年・ディズニープラス)などへの出演を重ね、今夏、NHK連続テレビ小説『あんぱん』に、今田美桜演じる「若松のぶ」の同僚「琴子」役として出演。 インタビュー【前編】 目次余命宣告を受けた女性、感情を吐き出すシーン──難しい役に直面する日々休日にはあえてグルテンを摂取! ひとり旅にも行きたい刑事や弁護士、特殊な職業を演じてみたい 余命宣告を受けた女性、感情を吐き出すシーン──難しい役に直面する日々 ──これまでいろいろな作品に出演されてきたと思いますが、その中で特に印象に残っているものはなんですか? 鳴海 最近だと、やっぱり『あんぱん』が一番ホットですね。でも、印象に残っているという意味では、『わかっていても The Shapes of Love』(2024年/ABEMA)という、横浜流星さん主演のドラマですね。その作品で私は、余命宣告を受けた女性の役を演じさせていただいたんです。 その役は、必然的に命と向き合わなければならないキャラクターだったので、演じる上で本当にたくさんのことを考えましたし、それを経験したことが自分の中ではすごく大きな糧になっていて……。 もちろん私自身は実際に余命宣告を受けたことはないので、どこまでいっても埋められない差はあるんですけど、だからこそ、その中で「どう向き合っていくか」という難しさに直面しました。この経験を通じて、私自身、役への向き合い方が大きく変わったと思います。だから『わかっていても』は、すごく印象深い作品ですね。 ──そういう壁にぶつかったときは、どう乗り越えていくんですか? 鳴海 自分の人生と全然違う役柄に出会うと、やっぱりすごく難しいなって思いますし、「どうすればいいんだろう」って悩みます。でも、その壁を乗り越えたときに、またひとつ自分が成長できたような気がするんですよね。 だから、自分が取り組みやすい、演じやすい役ばかりじゃなくて、苦手意識のあるキャラクターにも、どんどん挑戦していきたいなと思っています。 ──なるほど。その意味では、先日、NHKで放送された村上春樹さん原作のドラマ『地震のあとで』(第2話「アイロンのある風景」)に出演されましたよね。あれは難しい作品だったと思いますが、どうでした? 鳴海 役がすごく難しくて、ずっと悩んでいました。撮影が終わっても、「これでよかったのかな」と、思い続けていました。 もちろん、正解がない作品だと思うので、正解を求めること自体が違うのかもしれないんですけど……どうしても正解を求めてしまう自分がいて。放送を終えて、視聴者の方から感想をいただいたときに初めて、「わからないままでいいのかもしれない」と思えたんです。 正解が出ないなかで悩み続けることって、その作品とひたすら向き合っている証拠だと思うので、正解が出るかどうかじゃなく、向き合っていた“時間”のほうが大事なんだなと……そういうことを視聴者の方々の感想から教えてもらいました。 ──堤真一さんと共演されていましたが、現場でお話はされましたか? 鳴海 はい。私が演じたキャラクターは、けっこう感情を吐き出すようなシーンがあって、そのときは堤さんが本当に静かに寄り添ってくださいました。監督ともアプローチについて話しながら撮影に臨んでいたんですけど……堤さんは細かくお芝居について話すというよりは、すごく自然に気持ちを引き出してもらえるような関わり方をしてくださって。 実は私、小学生のころから「好きな俳優さんは誰ですか?」と聞かれたら「堤真一さんです」と言っていたくらい、ずっと憧れていたんです。しかも堤さんは私と同じ兵庫県西宮市の出身で地元のスターでもあるので、いつか共演できたら……と思っていた夢が今回実現しました。 撮影中は悩む時間もありましたけど、堤さんとは地元トークで盛り上がったりして……「あそこの公園わかる!」みたいなお話もできたんです。東京にいるのに、地元にいるような感覚でお話しできて、とても楽しかったです。お芝居の面でも、本当にたくさん引っ張っていただきました。 休日にはあえてグルテンを摂取! ひとり旅にも行きたい ──地元トークができるのっていいですよね。ところで、少し仕事からは離れますが、最近ハマっていることや気になっていることってありますか? 鳴海 最近ハマっているのは、休みの日に「あえてグルテンを摂取しに行く」ことなんです(笑)。今、普段はグルテンフリーをゆるくやっているんですけど、完全に摂らないでい続けるというのは無理なので、次の日に撮影がないときは「今日は小麦を摂るぞ!」って決めて、気になるパン屋さんを調べて行くんです。 今はそれがすごく楽しみで……パン屋さんまで散歩して、近くのカフェでカフェラテを買って、公園で座ってのんびりするというのが最近のリフレッシュ方法ですね。ひとりでパンを食べたり、トンカツを食べたり……そういうのが今のささやかな楽しみです。(小麦を)ごほうび感覚にすると、適度に距離感が出ることで、より好きになって。 ──いわゆるグルテンフリー版「チートデイ」的な感じですね! 鳴海 そうです(笑)。おっしゃるとおり、チートデイですね。 ──グルテンフリーを始めて、何か変化はありましたか? 鳴海 そうですね。わかりやすく体重が減りましたし、朝の目覚めもすごくよくなりました。よく「本当に効果あるの?」って言われるんですけど、実際にやってみたら本当でした。おもしろいくらい、如実に効果が出ます。 ただ、普段パンを食べていない状態で久しぶりに小麦を食べると、そのあとすごく眠くなるんですよね。だから仕事に集中したいときは、お米を食べるようにしています。 ──なるほど。今後やってみたいことって何かありますか? 鳴海 私、ひとり旅が好きなんですよ。今年は(忙しくて)ちょっと行けそうにないんですけど……去年や一昨年は海外に行っていて。国内旅行は飛ばして、海外にばかり行っていたんです。でも最近は、時間があまりないなかで「どこか行きたいな」と思ったときに「国内旅行もいいな」と思うようになってきて。やりたいことっていうほどではないかもしれないですけど、今は国内旅行をしたい気持ちが強いです。 ──行ってみたい場所はありますか? 鳴海 今は三重県の伊勢神宮に行きたいです……というか、伊勢神宮の手前にある参道で、赤福のぜんざいを食べたいという(笑)。 東京から三重って絶妙に行きづらくて、なかなか友達とも計画が立てられないんですよね。大阪に帰ってくると、つい実家で過ごしてしまうので、やっぱりなかなか予定に組み込めなくて。なので「ちゃんと見に行くぞ!」って決めないと、きっと実現できないなと思っています。 刑事や弁護士、特殊な職業を演じてみたい ──三重、近いうちに実現するといいですね……あと、今後演じてみたい役柄はあります? 鳴海 今までは、自分に近い等身大の役が多かったんですけど、最近は特殊な職業の女性を演じてみたいなと思っていて。実はこの前、とあるそういう感じの役をやらせていただいたんです。その役づくりをしていく中でのプロセスが、すごくおもしろくて。 『あんぱん』だと土佐弁がそうだと思うんですけど、そういう役づくりで必要になる要素があると、自然と役と向き合う時間が増えるんですよね。いつも以上に役と向き合わないといけない。準備をしっかりしないといけないから、役やセリフが自分の中にどんどん染み込んでくる、血肉になっていく感じがあって、それが好きなんです。 これからも、そういう特殊な職業の役に挑戦してみたいです。刑事とか弁護士とか、以前からやってみたいと思っていた役にも……実は今後挑戦させていただく予定があるので、夢がひとつ叶ってうれしいですね。絶対、大変じゃないですか(笑)。もちろん大変だとは思っているんですが、限られた時間の中でどこまで取捨選択して準備できるか、挑戦していきたいと思っていますし、大人の女性の役柄を演じていけたらいいなとも思っています。 ──ありがとうございます。最後に、鳴海さんが出演する『あんぱん』の見どころを教えてください。 鳴海 私は『高知新報』という新聞社のパートに出演しているんですけど、そこは戦後最初のパートになるんですね。なので、すごく自由と活気にあふれていて、熱量の高い場面が続きます。ドラマの制作の方からも「開放感のある、明るいシーンにしたい」と最初に言われていたので、そういうエネルギーを意識しながら演じていました。 それと、(若松)のぶと(柳井)崇の恋が大きく進展するパートでもあるし、私が演じる琴子は、そのふたりの恋のキューピッド的な存在でもあるので、琴子の“愛あるおせっかい”によって、ふたりの恋がどう動いていくのか……ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。 ──視聴者が思っているもどかしさを、全部代弁してくれるようなキャラクターですよね。 鳴海 そうなんです(笑)。『高知新報』のシーンは、ちょうど作品としては折り返し地点に入っているところなので、最初から観てくださっていて(のぶと崇の関係性が)「もどかしい!」と思っている方には、「ようやく動く!」と思っていただけるんじゃないかなと思います。 取材・文=鈴木さちひろ 撮影=時永大吾 ヘアメイク=丸林彩花 編集=中野 潤 ************ 鳴海 唯(なるみ・ゆい) 1998年5月16日生まれ。兵庫県出身。2019年、NHK連続テレビ小説『なつぞら』で、テレビドラマ初出演を果たす。2021年『偽りのないhappy end』で映画初主演。その後、テレビCMや大河ドラマ『どうする家康』(2023年/NHK)、ドラマ『Eye Love You』(2024年/TBS)、映画『赤羽骨子のボディーガード』(2024年)、ドラマ『七夕の国』(2024年/ディズニープラス)などへの出演を重ねる。2023年には写真集『Sugarless』を発売。今夏、NHK連続テレビ小説『あんぱん』に、今田美桜演じる若松のぶの同僚「琴子」役として出演。
-
 気鋭の女優・鳴海唯──『なつぞら』でデビューし『あんぱん』に出演。朝ドラへかける想い
気鋭の女優・鳴海唯──『なつぞら』でデビューし『あんぱん』に出演。朝ドラへかける想い#21 鳴海 唯(前編) 旬まっ盛りな女優やタレントにアプローチする連載「focus on!ネクストガール」。 鳴海唯(なるみ・ゆい)。2019年、NHK連続テレビ小説『なつぞら』で、テレビドラマ初出演を果たす。2021年『偽りのないhappy end』で映画初主演。その後、大河ドラマ『どうする家康』(2023年/NHK)、ドラマ『Eye Love You』(2024年/TBS)、映画『赤羽骨子のボディーガード』(2024年)、ドラマ『七夕の国』(2024年/ディズニープラス)などへの出演を重ね、今夏、NHK連続テレビ小説『あんぱん』に、今田美桜演じる若松のぶの同僚「琴子」役として出演。 目次#21 鳴海 唯(前編)憧れが生まれたのは11歳──行動に移したのは19歳『なつぞら』出演で、街中でも声をかけられるように共演者とのチームワークで臨んだ『あんぱん』 憧れが生まれたのは11歳──行動に移したのは19歳 ──まずは、デビューのきっかけからお伺いできればと……。 鳴海 小学校のときにドラマ『のだめカンタービレ』(2007年/フジテレビ)を観て女優という職業を知って、私もこういうお仕事をしてみたいと思ったんです。ただ、そこから10年くらいは行動に移さずにいて、気がついたら大人になっていました。 11歳くらいのときに憧れが生まれて、実際に行動に移したのは19歳のとき。映画『ちはやふる―結び―』(2018年/東宝)のエキストラに参加させていただいたのがきっかけですね。そこで「やっぱりこのままでは後悔する」と思って、大学を辞めて養成所に入ろう!と決めて、東京に出てきました。 ──なるほど。大学を辞めるという決断は、かなり大きなハードルだったのではないですか? 鳴海 本当に親不孝なことをしてしまったなと思ってはいます。入ってすぐに辞めてしまったので……。 でも、この思いは今に始まったことではなくて、11歳のころからずっと心の中で沸々と、くすぶっていたんです。それが『ちはやふる』への参加をきっかけに、もう抑えきれないほどあふれてしまって……居ても立ってもいられなくなって、行動に移すしかありませんでした。 ──なるほど。最初のお仕事はなんでしたか? 鳴海 たしか最初は、ミュージックビデオだったと思います。セリフはなかったんですけど、初めてカメラの前に立たせてもらったとき、「どこを見ればいいのかわからない」と思いました。カメラが目の前にあるのに、「カメラを見ないでください」と言われて……「どういうことだろう?」と、そんなことを考えながら撮影に臨んでいました。 カメラを向けられる緊張感や、メイクをしてもらうことへの違和感など、すべてが新鮮で、そうしたフレッシュな感覚をそのまま受け止めながら撮影に臨んでいた記憶があります。 ──セリフのあるお仕事の最初の印象はどうでしたか? 鳴海 その当時は、役づくりがどういうものかということすらわかっていなくて……いただいた台本をただ覚えて、それを一生懸命カメラの前で演じるということで精いっぱいだったような気がします。それでも「お芝居って楽しいな」と思えたことは、今でも覚えています。 結果的に作品として最初にメディアに出たのは『なつぞら』(2019年/NHK)なんですけど、実はその前に撮影した初めての作品があったんです。その作品で出会った仲間たちとは今でも会いますし、自分にとっては本当に大切な出会いでした。 一番最初に行った現場で出会った友達が今でもがんばっている姿を見ると勇気づけられるし、自分も「がんばろう」と思わせてもらえるんです。今もよくご飯に行って、思い出話をしたりしています。 ──それはどなたですか? 鳴海 配信ドラマ『妖怪人間ベラ〜Episode0〜』(2020年)という作品でご一緒した、北原帆夏ちゃんと横田愛佳ちゃんです。1年に1回は集まって、近況報告をしています。 それと別の現場でも、大友花恋ちゃんや森田想ちゃんと再会する機会があって、彼女たちとも『ベラ』で一緒だったんですよ。そうやって初めての作品で出会った人たちと、現場でまた会えるのはすごくうれしいです。最近も(森田)想ちゃんと現場でお会いしたので、そのことを伝えたりしました。 『なつぞら』出演で、街中でも声をかけられるように ──映像として世に出たのは『なつぞら』が先になったとのことですが、ご自身で試写などで初めて観た出演映像作品も『なつぞら』だったんですか? 鳴海 そうですね。自分自身が出演した作品を最初に観たのは『なつぞら』でした。 ──『なつぞら』の出演は、オーディションだったんですか? 鳴海 はい。オーディションです。 ──そのオーディションの印象はいかがでしたか? 鳴海 まず、「受けさせてもらえるチャンスがあるんだ」と驚いたのを覚えています。当時は、本当に受かるなんて思っていませんでした。 友達に家に泊まりに来てもらって、夜遅くまで相手役を手伝ってもらったりして……今までで一番時間をかけて取り組んだオーディションでした。本当に一生懸命だったと思います。 ──実際に受けてみてどうでしたか? 鳴海 自分自身の手応えは特に感じなかったんですけど……当時、ドラマや映画で観ていた女優さんたちが目の前にいらっしゃって、そんな体験も初めてで。オーディションとはいえ、そういった方々とお芝居ができたことがすごくうれしかったです。「楽しかったなー」と思いながら(オーディション会場の)NHK放送センターから帰った記憶がありますね。 ──『ちはやふる』ではエキストラというかたちで共演した広瀬すずさんと、今度は別のかたちでお会いしたわけですが、どんな気持ちでしたか? 鳴海 そうですね。高校生のころの自分に教えてあげたいくらい……本当に夢みたいな瞬間でした。 『なつぞら』を経て感じた、スクリーンやテレビの外から観ていた憧れの方々と共演させていただく喜びみたいなものを、それこそ『なつぞら』以降、たくさん経験させていただくことになるんですけど、たぶんその最初の体験ですね。 ──よく朝ドラに出演すると、街中で声をかけられるようになるって聞くんですけど……実際どうでしたか? 鳴海 『なつぞら』での出演は本当にちょっとだけだったので、そこまで声をかけられることはなかったです。でも、地方で仕事をしていると、「明美(役名)ちゃんだよね?」と声をかけていただくこともあって、朝ドラの影響力って本当にすごいなって、改めて感じました。あのドラマをどれだけの人が楽しみにしているのかが、実感できた瞬間でしたね。 ──映像作品に出演するようになってからの、身近な人や友人からの反応はどんな感じでしたか? 鳴海 父はもう、私が映ってさえいればなんでもうれしいっていう感じで(笑)。どんな作品に出ても喜んでくれるんですけど、特にNHKの作品だとすごく楽しんで観てくれている印象があります。だからNHKの作品に出ると、親孝行がまたひとつできた!っていう気持ちになるんですよね。 そういう意味では今回、『あんぱん』に出演できたことも、おばあちゃんや親にちょっとでも孝行できたかな、という気持ちになりました。 共演者とのチームワークで臨んだ『あんぱん』 ──その『あんぱん』ですが、撮影現場で何か印象に残ったことはありました? 鳴海 そうですね、『あんぱん』の1週間は、まず月曜日にリハーサルをして、火曜日から金曜日は、だいたい朝8時くらいから撮影が始まるんです。毎日NHKに通って撮影をするという流れが、ほかのドラマとは全然違っていて。 普段は時間も毎日バラバラだし、行く場所も変わるんですけど、朝ドラの撮影はルーティンがしっかり決まっていて、それがすごく身体に染みついた感じでした。その感じがすごく不思議で……ああ、これが朝ドラに出演しているっていうことなんだなと思いながら、撮影をしていました。 普段は作品が終わってもそこまで寂しくなるタイプじゃないんですけど、『あんぱん』は参加期間が3週間と短かったものの、毎日同じ現場に通っていたので、終わったときにはすごく寂しくて……。あのルーティンがなくなるのが寂しいな、と。 ──『あんぱん』での役づくりで、特に意識したことはありますか? 鳴海 私が演じる琴子のキャラクターは、一見すごく明るいんですけど、脚本を読んだときにすごく魅力的だなと思ったのと同時に、彼女がどうして明るく振る舞っているのか……その背景が気になったんです。だから、ただ明るいだけじゃなくて、なぜそう振る舞っているのかを丁寧に掘り下げていくことで、もっと人間らしい深みのあるキャラクターにできるんじゃないかと思って……一番そこを意識して向き合いました。ただ明るいキャラクターというだけで終わらせないようにする点には、すごく気をつけましたね。 あとは、やっぱり土佐弁が難しかったんですよね。普段セリフを覚えるときは、単に言葉を覚えるだけなんですけど、今回は「言葉」も「音」も覚えなきゃいけなくて、いつも以上に……覚えるまで2倍くらいの時間がかかりました。すごくハードルは高かったんですけど、この作品に出ている方はみんな同じ経験をしていると思うので、「大変なのは自分だけじゃない!」と思えて、それを励みにがんばれた気がします。 ──共演者の今田美桜さんや津田健次郎さんらとは、現場でどんな感じの……。 鳴海 私が参加した『高知新報』でのパートは、北村匠海さん、今田さん、津田さん、倉悠貴さん、そして私の5人で、基本的に物語が進んでいくんです。現場では今田さんと北村さんがよく前室にいらっしゃって、自然とコミュニケーションも生まれて、いろんな話をしました。 芝居の話ももちろんしましたけど、全然関係ない話もたくさんしましたね。特にご飯の話題が多くて、「今日は何を食べようかな」とか、メニューを見ながら「このデリバリーがおすすめだよ」とか(笑)。 そういう日常的なやりとりを通じて、自然と仲よくなっていった感じですね。だから撮影が進むにつれて、チーム感みたいなものが、どんどん強くなっていきました。もちろん、それぞれの撮影日は違っていたりして完全に一緒に動いていたわけじゃないんですけど、前室の空気みたいなものは、きっと画面にも映っている瞬間があると思います。 取材・文=鈴木さちひろ 撮影=時永大吾 ヘアメイク=丸林彩花 編集=中野 潤 ************ 鳴海 唯(なるみ・ゆい) 1998年5月16日生まれ。兵庫県出身。2019年、NHK連続テレビ小説『なつぞら』で、テレビドラマ初出演を果たす。2021年『偽りのないhappy end』で映画初主演。その後、テレビCMや大河ドラマ『どうする家康』(2023年/NHK)、ドラマ『Eye Love You』(2024年/TBS)、映画『赤羽骨子のボディーガード』(2024年)、ドラマ『七夕の国』(2024年/ディズニープラス)などへの出演を重ねる。2023年には写真集『Sugarless』を発売。今夏、NHK連続テレビ小説『あんぱん』に、今田美桜演じる若松のぶの同僚「琴子」役として出演。 ▼『logirl』でマンガ連載(『テレビドラマのつくり方』)をしている、『妖怪人間ベラ〜Episode0〜』で監督を務めた筧昌也さんへのコメントを求めると「筧さん、私が新しい作品に出るたびに連絡をくださるんですよ。またご一緒したいです!と言っているものの、なかなかタイミングが合わなくて……がんばっていれば、きっとまたすぐに作品でお会いできると思うので、これからもよろしくお願いします!」 【インタビュー後編】
-
 趣味は編み物と映画鑑賞──『おいしくて泣くとき』ヒロイン・當真あみのプライベート
趣味は編み物と映画鑑賞──『おいしくて泣くとき』ヒロイン・當真あみのプライベート#20 當真あみ(後編) 旬まっ盛りな俳優にアプローチする連載「focus on!ネクストガール」。 當真あみ(とうま・あみ)。2020年に沖縄でスカウトされ、『妻、小学生になる』(2022年/TBS)でテレビドラマ初出演を果たす。その後、「カルピスウォーター」の14代目イメージキャラクターに就任、また、『パパとなっちゃんのお弁当』(2023年/日本テレビ『ZIP!』朝ドラマ)や『どうする家康』(2023年/NHK)、『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』(2023年/日本テレビ)など、ドラマへの出演を重ねる。2025年4月4日公開の映画『おいしくて泣くとき』では、複雑な家庭環境下にあるヒロイン・夕花を演じている。後編では、プライベートに関することを聞いてみた。 インタビュー【前編】 目次手芸屋で毛糸を物色、俳優仲間と映画館へ上京後も送ってもらっていた“実家の味” 手芸屋で毛糸を物色、俳優仲間と映画館へ ──プライベートなことも伺いたいのですが、最近ハマっていることはありますか? 當真 映画鑑賞はずっとしています。あと、去年ハマり出したのは、カメラと編み物ですね。編み物は、空いている時間に少しずつ編んで、いろいろと作ったりしています。 ──素材も自分で買いに行ったり? 當真 はい。手芸屋さんへ行って、毛糸を物色したりとか。 ──今まで編んだ中で、一番うまくできたものはなんですか? 當真 ニット帽ですね。けっこううまくいって。夏場は、麦わら帽子になるような素材で、帽子を作ったりもしていました。 ──映画は今、どれくらいのペースで観ていますか? 當真 今年も1月中に3本は観ました。まだまだ観たい作品があって、もうすぐ上映が終わるのかなとか、早く行かなきゃと思っている作品も、今、3つぐらいあります。少なくとも月に1本以上は確実に観たいなと思っています。 ──映画館に行って観るんですか? 當真 そうですね、映画館がすごく好きで。家で観ていると、ちょっと飽きちゃったり、気が散ることもあるのですが、映画館だと大きなスクリーンにすごい音響だったり、本当にその空間がすごく好きなんです。 ──今まで観てきた映画の中で、すごく好きな作品、もしくはこの作品に出ているこの俳優の演技に憧れる、というのはありますか? 當真 お芝居でいうと、杉咲花さんです。昨年観た『52ヘルツのクジラたち』(2024年)と、おととし観た『市子』(2023年)での杉咲さんのお芝居が本当にすごくて……誰かの人生を追いかけて見ているような、そういうリアルなお芝居というか。リアルだし、言葉の一つひとつに、しっかりと伝わってくる強さがあって、そういう相手に届ける力がすごく強い女優さんだなと思いました。 ──お仕事をするなかで、仲よくなった俳優さんはいますか? 當真 『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』というドラマで仲よくなった友達とは、ずっと一緒にいます。みんな映画を観るのが好きなので、最近は一緒に。それこそ『室町無頼』も一緒に観に行きました。共通の好きなものを持っている人がいるのって、すごくいいなと思いながら過ごしています ──今後、やってみたい役柄はありますか? 當真 今、高校卒業間近で、これまでは学生役をいただくことが多くて、今後はさらに先にある大人としての仕事とか、今の学生のさらに先のところで一生懸命にがんばっているような役に挑戦できたらなと思っています。 ──社会人の役などですかね? 當真 そうですね。学生の役では、自分が経験したものだったり、知っている感情をつなぎ合わせて演じていたんですけど、その先となると私もまだ経験したことがないから、たぶんすごく難しいだろうなと思うんです。でもそこを探しながらやるのがすごく楽しいだろうなと思っていて、挑戦してみたいですね。 ──高校を卒業して、成人して、何かが変わる実感はあったりしますか? 當真 成人してですか……まったくないです(笑)。18歳になったからって遅くまで出歩くわけでもないですし、結局あまり変わらないかなというのが大きくて。ただ、学生でも子供でもないというところを意識して、しっかり気持ちを切り替えてかないといけないなとは思っています。 上京後も送ってもらっていた“実家の味” ──俳優以外で、今後やってみたいお仕事はありますか? 當真 ドラマや映画の宣伝で出演するバラエティ番組などで、全然違うジャンルなのに、おもしろくできる俳優さんがいるじゃないですか。すごく明るいキャラクターが出ている感じの……。私は(バラエティでは)うまくしゃべれないぐらいに緊張するので、それをなくせたらなと思っています。 ──書く仕事などは、興味があったりしますか? 當真 あまり考えたことはなかったですね。それよりは、最近カメラを持ち始めてずっと撮っているんですけど、写真を撮るのがすごく楽しくて。その流れで何か挑戦できるものがあったらいいなと思います。 ──写真を撮るときには、ご自分が撮られるときの経験が活きていたりしますか? 當真 いや、まったくないですね(笑)。撮っている対象も友達ばかりですし。画面を通して見ると、また違う人に見えてくるのがおもしろくて、そこはどこかお仕事で活かせたら楽しいだろうなと思います。 ──最後に、改めて映画『おいしくて泣くとき』の見どころを伺えれば。 當真 そうですね。心也くんと夕花の初恋、ラブストーリーではあるんですけど、それだけじゃなくて、ふたりを囲む世界にいる人たちの愛がたくさん感じられる作品だと思います。たとえば30年も相手を思い続ける心也くんの想いや、子供に対する心也くんのお父さんの想いなど、深い気持ちをすごく感じられる作品ですし、人の気持ちの強さ、尊さを感じていただけたらなと思います。 ──タイトルにもつながる、當真さんご自身の「食の思い出」はあったりしますか? 當真 あまり外に出て食べるということをしないのですが、お母さんやおばあちゃんの料理はすごく好きですし、東京に来てからも作った料理を実家から送ってもらっていたことがあって。ハンバーグとか、自分が本当に好きな食べ物を送ってもらっていて、仕事が終わったあとに食べるとすごく体に染み渡りました。ずっと食べてきたものを食べるとすごく安心して、おいしくて。泣くまではいかないんですが、ほっとする料理が身近にあるのは、本当にうれしいことだなと思いました。 取材・文=鈴木さちひろ 撮影=時永大吾 編集=中野 潤 ************ 當真あみ(とうま・あみ) 2006年11月2日生まれ。沖縄県出身。『妻、小学生になる』(2021年/TBS)でテレビドラマ初出演。その後も『パパとなっちゃんのお弁当』(2023年/日本テレビ『ZIP!』朝ドラマ)や『どうする家康』(2023年/NHK)、『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』(2023年/日本テレビ)、『さよならマエストロ~父と私のアパッシオナート~』(2024年/TBS)など、ドラマへの出演を重ねる。Netflix映画『Demon City 鬼ゴロシ』が配信中。2025年4月4日公開の映画『おいしくて泣くとき』では、複雑な家庭環境下にあるヒロイン・夕花を演じている。
エッセイアンソロジー「Night Piece」
気持ちが高ぶった夢のような夜や、涙で顔がぐしゃぐしゃになった夜。そんな「忘れられない一夜」のエピソードを、オムニバス形式で届けるエッセイ連載
-
 定期的に見る夢がある、「何も変わらない」と罪悪感を抱えた夜(二瓶有加)
定期的に見る夢がある、「何も変わらない」と罪悪感を抱えた夜(二瓶有加)エッセイアンソロジー「Night Piece〜忘れられない一夜〜」 「忘れられない一夜」のエピソードを、毎回異なる芸能人がオムニバス形式でお届けするエッセイ連載。 二瓶有加(にへい・ゆうか) 1995年10月20日生まれ、東京都三鷹市出身。2016年にダンス&ボーカルグループ「PINK CRES.」のメンバーとしてデビューし、2021年まで活動。2022年にYouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』の出演をきっかけにブレイク、現在は女優・タレントとして活躍中。2025年7月10日(木)〜7月16日(水)は、草月ホールにてミュージカル版『武士の献立』に出演。2025年8⽉より東京建物 Brillia HALLを⽪切りに、⼤阪、京都、愛知、熊本など全国5カ所にて上演される、舞台『ぼくらの七⽇間戦争2025』に出演。 Instagram:@niheiyuka.official X:@niheiyuka1020 YouTubeチャンネル『二瓶有加ch』:@niheiyuka1020 定期的に見る夢がある。 自分の心のしこりとなっていることの夢。 夢の終わりはいつも同じで、その問題がおとぎ話のようにハッピーエンドを迎え、そこで目が覚める。 あぁ……現実はまだ何も変わってないんだ。 この日は、夕方には仕事が終わり、帰宅後すぐに昼寝をしてしまっていた。 少し寝るつもりだったのが、気がつけば24時前。 最近はダラダラと続く雨が降っていて、室内に干した洗濯物の影響で、部屋全体がじめっとしている。こんな時間まで寝てしまった……やることを何もやれていない、という軽い罪悪感を抱える。 まぁまぁ嫌な目覚めだった。 あのときと今とでは、自分を取り巻く環境がだいぶ変わった。 自分の部屋を借りて、自分の好きなものに囲まれて、広くはないけど、狭すぎない。ひとりで住むにはじゅうぶんな快適さがある1Kの部屋で、ひとり暮らしをしている。 あのとき、私は自分が手にしたい夢を追うことに精いっぱいで、いつかその夢を叶えて、好きな部屋をひとりで借りて、好きなものに囲まれて生活をすることが目標だった。 今現在、やっとひとり暮らしが始められたというのに、ひとりベッドの上でぼーっとしている自分を客観的に見つめると、なんだか妙に切なくて、寂しさに押しつぶされそうになる。 あのとき、私は25歳だった。 20歳から25歳までアイドルとして駆け抜けた。 私はいわゆる、「人気メンバー」ではなかったけど、好きな歌とダンスを踊って、ステージに立つと目の前でファンの方が応援してくれる。そんな充実感で、なんだかんだとても幸せだった。 しかし、24歳の誕生日を迎えた瞬間、急な不安が自分を襲った。 「来年、私25歳なんだ……。20代半ばに突入する。 25歳を迎えたとき、きっと過ぎる時間の速さをもっと実感して、きっと、もっと焦ってしまうだろう。 若さって永遠じゃないんだ……」 20代、若さを武器に仕事をしていた私は、 若さがなくなることへの不安感を初めて覚えた。 そんななか、世間はコロナ禍に突入。 仕事はもちろん全部ストップ。ライブも、ファンの方との握手会も、全部なくなった。 ステージで歌って踊っていた自分の日常が、急に奪われた。そんな気持ち。 毎日実家のベッドで死んだように寝て、起きるだけ。 もうすぐ25歳だというのに、ひとり暮らしをする経済力もなければ、いつまでもこの家の末っ子として、出されたご飯を食べて、家の手伝いもせずに寝る。 家事もろくにできない。 なんなら母の手料理にケチもつける。 最低な甘ったれ。 誰かが用意してくれたステージがなければ、 自分は何もできない、ただの情けない大人だということに気がついた。 悔しかった。情けなかった。 そして、このままじゃいけないという焦燥感に襲われた。 だめだ、動かなきゃ。やらなきゃ。 思い描いてた理想の大人になりたい! そんな想いが自分を突き動かした。 そこから流れるように解散が決まり、 無観客で解散ライブ。 アイドルである夢の時間が終わったのか、終わってないのか、 曖昧な気持ちを抱えたまま、 ソロとしての活動が始まった。 そのあとは転がっていくように、 日々求められることに応えるのに必死で、 とにかく毎日もがいていたら、29歳になっていた。 気がついたら、ひとり暮らしをしていて、 気がついたら、あと数カ月で30歳になろうとしている。 あのとき思い描いてた 【理想の大人】に私はなれているのだろうか……。 初めて焦りを覚えた24歳の夜を一緒にお祝いしてくれたのは、10代からずっと一緒だった親友ふたり。気がつけばふたりは結婚をして、今は子育て真っ最中。 3人で誕生日会を開くことも、もうここ数年していない。 みんな前に進んでる。 私、側から見れば進んでるのかもしれないけど、 今日も自分の心のしこりとなっていることの夢を見て起きて、同じことで落ち込んでる。 自分だけ取り残された、そんな気持ちがただただズンと心を重くする。 そんななか、なんとなく、自分のグループ時代の映像が観たくなってYouTubeを開いた。 自分が思ってたより、幼い自分がそこには映っていた。 今の私から、当時の自分やグループを客観的に見たとき、当時は思わなかった感情があふれてきた。 ここからは自画自賛になるが、 「このとき、ここの歌がうまく歌えないって思ってたけど、全然上手に歌えてたじゃん!」 「人気ないしなぁ……なんて自信なかったけど、こんなにお客さん笑顔でいてくれてたじゃん」 「太ってるから恥ずかしい……なんて思ってたけどお肌ピチピチで、若さあふれててかわいかったじゃん!」 「てか、曲もダンスも最高! このグループ最高だったじゃん!」 ふと、思った。 当時の自分が、今の自分のように、 自分で自分を認めてあげられてたらよかった。 それと同時に、今の自分に足りないのは、 【自分で自分を認めてあげられない力】 だと思った。 「振り返れば、自分はちゃんとやってきた。 あのときの自分より、ちゃんと今の自分は成長してる。私、大丈夫。よくがんばってる」 自分にそう言い聞かせるだけで、 強くなれた気がした。 さっきまで、罪悪感を抱えたこの夜の時間が、 捉え方次第で、自分自身を癒やす、いい夜に変わった。 いつか、今の私も過去になる。 過去になってから、 「あのときはがんばってたなぁ」と過去の自分を認めるのではなく、 今の私を今、認めてあげよう。 そんなふうに思った。 文・写真=二瓶有加 編集=宇田川佳奈枝
-
 踏み込めないまま大人になったふたり、“あーちゃん”と距離が近づいた夜(金井 球)
踏み込めないまま大人になったふたり、“あーちゃん”と距離が近づいた夜(金井 球)エッセイアンソロジー「Night Piece〜忘れられない一夜〜」 「忘れられない一夜」のエピソードを、毎回異なる芸能人がオムニバス形式でお届けするエッセイ連載。 金井 球(かない・きゅう) 2001年9月の新宿に生まれる。寿司屋のバイトを「賄いに寿司が出ない」という理由で辞めたこともあったが、最近は執筆やZINE制作、Podcast番組『ラジオ知らねえ単語』の制作・出演、演技など、精力的に活動の幅を広げている。 X:@tiyk_tbr Instagram:@tiyk_tbr note:@tiyk_tbr 正直、踊ることがおもしろいみたいなフェーズはとっくに終わっていて、それでもあーちゃんとわたしは踊りをやめたくないから踊っていた。 わたしたちにできる踊りのレパートリーは、とっくに尽きていた。左右に揺れる/お尻を振る/腕を広げる/肩をくねらす。義務感とかではなかった。いつでもやめられる踊りを、踊りをやめたくないという明確な意思を持ってやめなかったふたり。左右に揺れる/お尻を振る/腕を広げる/肩をくねらす。はじめて、わたしたちはいまどうしようもなく姉妹だなと思った。 意外だと言われることが多いのだけど、わたしには妹がいる。あーちゃんという、髪がピンクの4歳下の妹だ。意外だと言われることが多い、というのは、自認がどうとかではない。本当に、いままで100人と兄弟構成を当て合って、100人がわたしに妹がいること、わたしが長女であることを見抜けなかった(わたしにはそれを褒め言葉だと思っている節がある)。 わたしのあざとかわいさがそう思わせるのか、面倒見のよくなさが一瞬でにじんでしまうのかはわからないけど、とにかくわたしは世界中の初対面のだれからもお姉ちゃんだと思われたことがない。正直、自分でも自分の中に姉らしさみたいなものをひとつも見出せない。 一度、あーちゃんの18歳の誕生日のプレゼントを買うために、自分でもなかなか入れないデパコス売り場に行った。「妹のプレゼントを買いたいんですけど……」と、はじめて話したBAさん(ビューティーアドバイザー)に伝えたとき「自分がかなり自覚的に姉をやりにいっている」ということにすぐ気がついてしまったくらい、わたしは日頃まったく姉じゃない。 あーちゃんとわたしは父親が違う。 そんなに意識せず生活してこられたけれど、そういうこともあってか、わたしたちの間には少し不思議な距離感があると思う。趣味はまったく被っていない。洋服もシェアしない。子どものころはよくケンカをしていた気がするけど、ある程度大きくなってからは一定の距離を保って暮らしていた。 そういえば、あーちゃんの友だちと話したことがない。真夜中のキッチンで恋バナをしたこともない。父からはよく「仲がいいんだか悪いんだか、わかんないね!」と言われるが、仲はよくも悪くもないと思う。干渉しない。そんなルールがあるみたいに、わたしたちはお互いに踏み込まないまま、同じ部屋で大きくなった。 離れて暮らすようになってからは、頻繁に連絡を取り合うこともない。姉らしくきょうだいを溺愛するまわりの姉たちに憧れては少しまねをしてみるが、やはりそこまでの熱はない。照れくさいのかもしれない。きっと、あーちゃんだってわたしに溺愛されることなんて望んでいないのではないか、と思うけど本当の気持ちはわたしにはわからない。友だちじゃないし赤の他人じゃない、家族と言い合うのは恥ずかしい。ママの血と家だけがわたしたちをつないでいると思う。わたしたちはそれでいい。一緒にご飯を食べても、銭湯に行っても、この距離感が縮まることはないのだろうと思う。 2月のことだ。餃子パーティーをしたいというママの提案によって、あーちゃんとわたしはママの家に遊びに行った。18時、先にあーちゃんと合流してスーパーで食材を買っているとき、そういえばあーちゃんのことをわたしは「あーちゃん」としか呼んだことがないと気がついた。それに、ママの家をあーちゃんと訪ねたのははじめてだった。 みんなで作ったママの餃子を食べながら、19歳になったあーちゃんの成人式が、もう来年に迫っていることを話した。 「あーちゃん。振袖は、わたしも着たおばあちゃんのお下がりを着るのが絶対いいよ!」姉らしいことを言ってみて、「あらまあ姉ですね〜」と思った。わたしが姉らしさをものにすることはきっと一生できないんだろう。 食事が終わって、しばらく布団に横になったあと、おもむろに立ち上がったわたしはリビングへ向かった。半分くらい残していた缶ビールを飲み干すとすごく気分がよくて、好きな曲を流してみる。人の家で好きな曲を流すのはビールを飲み干すことより気分がいい。電影と少年CQに合わせてでたらめに踊っていると、あーちゃんがそれに続いて、次にママが続いて踊り始めた。3人は、わたしのiPhoneからシャッフル再生で流れてくるどんな曲調にも合わせて踊った。肩が触れそうになるたび爆笑しながら踊った。 30分くらい経ったあたりでママはお風呂に入るからと踊りをやめて、リビングにはあーちゃんとわたしふたりだけになった。左右に揺れる/お尻を振る/腕を広げる/肩をくねらす。おもしろくないのにやめたくない。 わたしたち、おもしろくないのに、やめたくない。 いまこの瞬間、この世界で心がつながっている唯一の人間だと思った。どっちが上とか下とかはなく、なんか人間同士として姉妹だった。 ママがお風呂から上がって布団に横になりはじめても、わたしたちはふたりきりで、いつでもやめられる踊りを踊った。左右に揺れる/お尻を振る/腕を広げる/肩をくねらす。そんななか。革命が起きる。あーちゃんが手を拳銃の形にしてこちらに向けてきたのだ。頭のうしろのほうで爆発音がした。 左右に揺れる/お尻を振る/腕を広げる/肩をくねらすしかなかったわたしたちの世界に、とつぜん具体的なイメージが持ち込まれて、あろうことかその銃口は、ずっと一緒にたのしく踊っていたわたしに向けられている。すごくおかしかった。笑いすぎて涙が出る。笑いながら泣きながら、向けられた銃口によって、また少しずつ、一度近づいたはずのわたしたちが、いままで保たれてきた距離感に戻っていく感覚があった。 拳銃を突きつけたまま、突きつけられたまま、わたしたちは踊り続けた。 しばらくしてあーちゃんが踊りながら寝室に帰っていって、それで、わたしたちの夜は終わった。 文・写真=金井 球 編集=宇田川佳奈枝
-
 悔しくてノートに怒りをぶつけた、いろいろな感情が交錯する夜(箭内夢菜)
悔しくてノートに怒りをぶつけた、いろいろな感情が交錯する夜(箭内夢菜)エッセイアンソロジー「Night Piece〜忘れられない一夜〜」 「忘れられない一夜」のエピソードを、毎回異なる芸能人がオムニバス形式でお届けするエッセイ連載。 箭内夢菜(やない・ゆめな) 2000年6月21日生まれ、福島県出身。2017年8月、「ミスセブンティーン2017」でグランプリを受賞し、雑誌『Seventeen』の専属モデルとしてデビュー。2018年、ドラマ『チア☆ダン』(TBS)でドラマ初出演、2019年には映画『雪の華』で映画初出演を果たす。以降、ドラマ『ゆるキャン△』シリーズ(テレビ東京)、『3年A組-今から皆さんは、人質です-』(日本テレビ)、『明日、私は誰かのカノジョ』(MBS・TBS)『マイ・セカンド・アオハル』(TBS)などに出演。また、バラエティ番組『世界の果てまでイッテQ!』(日本テレビ)の「出川ガールズ」としても活躍。 Instagram @ yumenayanai_official 「夜」 私にとっては“敵”のようにも感じる。 普段は前向きでポジティブな私を、 ネガティブに変えてしまうような気がするから。 なぜなのだろう。 「夜」の自分は自分自身でも理解ができないほど、いろいろな感情が入り交じる。 私自身が矛盾する。 そんな「夜」ばかりだ。 私は毎日、無意識にひとりで反省会をしてしまう。 今日はうまく発言できなかったな…… あのタイミングでこう言っとけばよかったな…… あの人に嫌われていないかな…… うまくみんなの輪に入れてなかったな…… もっとああすればよかった。 もっとこうすればよかった。 でも、今日これを言えたからスッキリした! 自分の気持ちはやっぱり素直に言うようにしよう! みんなに褒めてもらえたのうれしかったな〜。 今日のお昼ご飯おいしかったな〜。 浮き沈みが激しいとは、私のことをいうのだと思う。 そして時々、そんなことを考えているうちに、どんどん考え事のスケールが大きくなっていく。 自分は、人生を生きていく上で何をしたいんだろう。 今の現状に満足しているのかな。 将来、自分はどうなりたいのかな。 人生においての優先順位ってなんだろう。 もしも明日地球が滅びるってなっても、後悔しないかな。 もう、キリがない。 21歳の夏、とある夜 いつものように反省会をしていた。 この何気ない、何か嫌なことがあったわけでもない日に、私は突然爆発した。 なぜか「怒り」が強かった。 でも、この怒りをどこにぶつければいいのかわからず、私は無我夢中で、ひたすらノートに自分の思いを殴り書きした。 その筆圧は、紙を破く勢いだった。 「思うままに、直感でやりたいことをやればいいものを、なぜこんなにもいろいろな思考が入るんだろう。言葉を選びすぎて、結局何を言いたいのかわからなくなってしまう。質問されたことから脱線してしまう。 そして結局伝わらない。 これはどうしたら改善できるの? 私の頭の中のことを代弁してくれる小人でもいればいいのに。 自分がどうしたいのかも理解できていない。 どうしたいのかくらい、自分で決められるようになってくれ……。 人に合わせることばかりじゃなく、 自分の思いを話さないとどんどんおかしくなるぞ。 はぁ、何も考えたくない。 何にも追われたくない。 自分から逃げたい。 自分にもいいところはたくさんあるんだから。 自分に甘いのを乗り越えればもっとできるはず。 支えてくれる人、アドバイスをくれる人、怒ってくれる人、背中を押してくれる人は幸せなことにたくさんいるんだから。 逃げずに自分自身が自分のことを支えてあげたい。認めてあげたい」 そんな内容だった。 自分がわからなくて、ムカついて、悔しくて、涙でぐしゃぐしゃになりながら書いた。 私は「言葉」をうまく人に伝えることが苦手で、とてもとても時間がかかる。 心で思っていること。 自分の意思、意見。 これがスパッと言えるようになったら、どんなに楽だろうか。 声にできない悩みが少しずつ溜まっていって、キャパオーバーになってしまったんだと思う。 まだ芸能界に入りたてで、この世界の難しさと厳しさに耐えることで必死だった17歳のころ、 「何があっても、どんな状況でも、笑顔でいないといけない仕事を、夢菜はしているんだよ。だから、家族に何かあってもテレビの前では笑顔でいなさい。それがプロだからね」 と、母から教わったこの言葉を、私はふと思い出した。 17歳のころは、なんでそんなことを言うの? と、その言葉の重みを感じることはできていなかったが、21歳の私は、その言葉で何度も立ち直ることができていた。 私はこの仕事が好きだし、いくつになってもやっていたい。 そう思える仕事に出会えたことは本当にありがたいことだし、今まで続けられているのもまわりの人が支えてくれているから。 見てくれている人がいるから。 そう思うと、少し涙が落ち着いた。 そして私は肩に力を入れず、楽にこの世界で生きていく方法を考えた。 職場での自分、ひとりのときの自分 家族の前での自分、友達の前での自分 このいろいろな自分を、使い分けることができたらいいのではないか。 でも、これってもしかしたら今まで意識していなかっただけで、普段からしていることなのではないかな。 そうも思えた。 よし、これから意識してみよう。 まずは、身近なところから。 と、いろいろなタイプの「自分」を使い分けてみると、 本当に少し楽になった気がした。 私は、出会う人、一人ひとりにいい顔をしようとしすぎていたんだ。 いろいろな自分も、結局は私自身の中に存在するものだから。 偽りでもなんでもない。 もっと気楽に「楽しむ」ようにしてみよう、そう思い、実践できたとき、頭が軽くなった気がした。 前よりも人と話せるようになった。 あの日 たくさん泣いてたくさん考えて、自分の中のモヤモヤと葛藤して、でも自分は嫌いになりたくなくて、いろいろな感情が交互にあふれてこぼれた夜。 つらかったけど、いい気づきになった。 ある意味、自分を知り、向き合えたいい夜だった。 きっとこの先も悩み、小さな細かい分かれ道を迷い続けて生きていくと思うけど、 ネガティブになりがちな「夜」も自分と向き合い、守ってあげられる時間にしてあげようと思う。 文・写真=箭内夢菜 編集=宇田川佳奈枝
文野紋のドキュメンタリー日記 ~現実(リアル)を求めて~
人生を変えた一本、退屈な日々に刺激をくれる一本、さまざまな愛に気づく一本など──漫画家・文野紋によるリアルな視点、世界観で紹介するドキュメンタリー映画日記
-
 4年ごとに人類が抱く夢、映像美を追求したスポーツの記録──市川崑『東京オリンピック』
4年ごとに人類が抱く夢、映像美を追求したスポーツの記録──市川崑『東京オリンピック』文野紋のドキュメンタリー日記 ~現実(リアル)を求めて~ 人生を変えた一本、退屈な日々に刺激をくれる一本、さまざまな愛に気づく一本など── 漫画家・文野紋によるリアルな視点、世界観で紹介するドキュメンタリー映画日記 1964年8月21日、ギリシャ・オリンポスの丘で点火されたオリンピックの火は日本へ向かった。 『東京オリンピック』は、1965年3月に公開された1964年の東京オリンピックの公式記録映画である。監督は『ビルマの竪琴』(1956年)や『炎上』(1958年)などで知られる鬼才・市川崑。 東京オリンピックの公式記録映画でありながら市川の「単なる記録映画にはしたくない」という理念のもと作られた本作は、「芸術か? 記録か?」と政治問題にまで発展する議論を巻き起こし、国内動員2000万人超えの大ヒットを記録し、数々の映画賞を受賞した。 本作の特徴はなんといってもその映像美、芸術性にあると思う。スポーツの祭典であるオリンピックの記録映画でありながら、冒頭の真っ赤な太陽の画など、抽象的なショットがたびたび映し出される。 「とにかく、単なる記録映画にはしたくなかったですね。自分の意思とかイメージというものを重く見て、つまり創造力を発揮して、真実なるものを捉えたい、と。」 (「公益財団法人日本オリンピック委員会」インタビューより引用) 市川は本作の制作にあたり、記録映画であるにもかかわらず緻密なシナリオを制作し、スタッフには絵コンテを描いて説明するなど、演出に強くこだわったという。100台以上のカメラ、200本以上のレンズ。世界で初めての2000ミリの望遠レンズまでも使用された。それらを用いて撮影された映像は、選手の肉体美のみならず、内面までも映し出す。 (C)フォート・キシモト 選手の強張った表情が、額を流れる汗が、彼らがオリンピックというものに向ける大きな感情を如実に表現する。 そして市川らのカメラが捉える対象は、選手だけに留まらない。 ケガをした選手を運ぶ救護班。 グラウンドの整備をするスタッフ。 思わず競技に見入ってしまう審判。 休憩中、競技が始まって、思わず仲間たちと顔を見合わせニヤリと笑う警備員たち。 アメリカ人選手とドイツ人選手による一騎打ちとなった棒高跳びのシーンでは、各国の応援をする観客たちのリアルな表情が対比するように映される。 太ったおじさんの二重あごのアップ……ではなく、息を呑む観客の喉元が、こだわり抜かれた映像技術で映し出される。 彼らもまた、東京オリンピックの参加者のひとりである。 また、本作では、ハードル走のシーンで選手が先行しているかわかりづらいであろう真正面からの画角を採用するなど、スポーツ観戦としての正確性より芸術性を重視した挑戦的なカメラワークを採用している。そのため、映像作品としても非常に完成度が高い。 監督である市川は、もともとスポーツというものにはそれほどの関心がなく、本作の総監督の打診もそのことを理由に一度保留にしていたほどだ。そして、自身がスポーツに疎いからこそ「スポーツファンだけの映画にしない」とスタッフ全員に徹底して伝えたという。 市川はスポーツに対し、たとえばその勝敗などよりも、そこに関わっている人間たちのドラマや心の機微に関心があったのだろう。 そのため本作は記録映画としては不十分ではないかという批評を受けることがある。冒頭でも述べたように、当時は「芸術か? 記録か?」と政治問題にまで発展する議論が巻き起こった。試写会で本作を鑑みたオリンピック担当大臣(当時)の河野一郎は、「記録性を無視したひどい映画」と本作を激しく批判し、文部大臣(当時)の愛知揆一もまたこれに同調した。 しかし翌年1965年、『東京オリンピック』が劇場公開されると当時の興行記録を塗り替える大ヒットとなった。 「オリンピックは人類の持っている夢のあらわれである」 冒頭の字幕だ。 本作は、オリンピックのために解体される東京の街を映したシーンから始まる。聖火リレーのシーンで映されるのは沖縄の「ひめゆりの塔」、広島の「原爆ドーム」。市川はのちに「どうしても広島の原爆ドームからスタートさせたかったんです」と語る。 1945年8月6日、市川の母を含む家族8人全員が広島に住んでおり、被爆している。当時東京で暮らしていた市川も原爆投下から数日後に広島へ向かい、その凄惨さを目の当たりにしていた。 オリンピックの理念のひとつに世界平和がある。のちのインタビューで市川はこの世界平和という部分に着目してシナリオを制作したと語っている。 東京オリンピックには、実は1940年にも一度開催が予定されていたが日中戦争の勃発などにより幻となったという経緯がある。戦後復興と高度経済成長を世界にアピールしたい日本にとって、1964年の東京オリンピックは絶好の機会であった。 本作は 「人類は4年ごとに夢をみる この創られた平和を夢で終わらせていいのであろうか」 という言葉で締めくくられる。 森達也をはじめ、さまざまなドキュメンタリー監督がドキュメンタリーにおいて作り手の視点は重要である、という趣旨の発言をしている。ドキュメンタリーとは事実の記録に基づいた作品のことであり、一般的に「意図を含まぬ事実の描写」であると認識されることが多いが、それを撮影、編集し作品として仕上げている以上、制作者の意図や思想、視点が入り込むことになる。 私はドキュメンタリーのおもしろさはこの制作者の視点にあると思っている。制作陣がどういう感情を持ってその対象を観測していたかの記録であり、そしてその視点を我々視聴者が追体験できるという意味で、ドキュメンタリーは非常に価値のあるものだと感じている。 自分がいつかスポーツマンガを描くのなら、私はこういった制作者の視点が、制作者が何に魅力を感じているのかが如実に伝わるような作品が作りたい。 本作はそう強く思える、市川の視点が十二分に込められた素晴らしいスポーツドキュメンタリーだ。 文野 紋(ふみの・あや) 漫画家。2020年『月刊!スピリッツ』(小学館)にて商業誌デビュー。2021年1月に初単行本『呪いと性春 文野紋短編集』(小学館)を刊行。同年9月から『月刊コミックビーム』(KADOKAWA)で連載していた『ミューズの真髄』は2023年に単行本全3巻で完結。2024年7月、WEBコミック配信サイト『サイコミ』連載の『感受点』(原作:いつまちゃん)の単行本を発売。2025年1月から、『週刊SPA!』(扶桑社)にて『トムライガール冥衣』(原作:角由紀子)の新連載がスタートしている。 『東京オリンピック』 Blu-ray&DVD発売中 発売・販売元:東宝 (C)公益財団法人 日本オリンピック委員会
-
 俳優・東出昌大が導く「生きている意味」
俳優・東出昌大が導く「生きている意味」文野紋のドキュメンタリー日記 ~現実(リアル)を求めて~ 人生を変えた一本、退屈な日々に刺激をくれる一本、さまざまな愛に気づく一本など── 漫画家・文野紋によるリアルな視点、世界観で紹介するドキュメンタリー映画日記 「あいつ、鉄砲の免許持ってて狩猟してるんだよ」 サバイバル登山家・服部文祥の言葉からすべては始まった。 『WILL』は映像作家・エリザベス宮地によるドキュメンタリー映画で、俳優・東出昌大の狩猟生活を追った作品だ。 東出昌大は映画『桐島、部活やめるってよ』(2012年)での俳優デビューから数々の映画やドラマに出演するなど人気の俳優だ。個人的な話になるが、私は東出が将棋棋士・羽生善治を演じた映画『聖の青春』(2016年)をきっかけに、最近では『Winny』(2023年)や『福田村事件』(2023年)などの東出の出演作を観ては彼の魅力に感嘆するいち映画ファン、東出ファンである。彼は世間的に見ると常軌を逸したような、独特な人間を演じるのがうまい。 しかし一般的にはやはり東出といえば、2020年の離婚騒動をはじめとしたスキャンダルのイメージが強いだろう。その後、「山ごもり」が報道され賛否両論となっていたころ、東出は2023年11月放送のABEMAのバラエティ番組『チャンスの時間』に出演した。映画に出演している姿以外ほとんど彼について知らなかった私は、そのあきらめきったような厭世的な様子に少しだけ衝撃を受けた。騒動の印象と端正な顔立ちから、いわゆるチャラい、器用なタイプかと想像していたが、なんとも生きづらそうな人だ、と思った。 俳優・東出昌大はなぜ狩りをするのか。 「カメラ回してもらっても、たぶん僕500時間ぐらい一緒にいないとわからないから」 「カメラ前で主張したいこととかもないし……」 実は本企画は、一度頓挫している。事務所の許可が降りなかったのだ。しかしその半年後、宮地のもとに東出から連絡が届く。2021年10月、再びのスキャンダルにより事務所を離れることになったという。事務所NGがなくなったことで本企画は再び動き出し、宮地は狩りをする東出にカメラを向けることになる。 (C)2024 SPACE SHOWER FILMS 東出は狩猟について「悪」であると語る。 「混沌とすることが、常にまとわりついていて、でも、近くに命があるから……考え続けるし……」 なぜ自身が「悪」と定義する狩猟を、つらい思いを抱えながらも続けるのかと尋ねられた東出はたどたどしく答え、頭を抱える。東出は何に葛藤し、何に悩んでいるのか。きっと自分でもわかっていないのだろう。わからないから狩猟をしているのだろう。東出にとって狩猟は、自身(人間)の根源的な罪を心に刻む、ゆるやかな自傷行為なのかもしれない。 「忙しい中でよくわかんないコンビニ飯食って感謝もしないよか、呪われてるっていう実感持ちながら、そこに張り合い持ってアレの分も……って思ってもらったほうが……とかなんのかな。わからん」 東出から紡ぎ出される言葉はいつも正直で真摯だ。 私は大阪府貝塚市の精肉店を迫ったドキュメンタリー映画『ある精肉店のはなし』(2013年)を見たことをきっかけに、狩猟や屠殺(とさつ)について興味を持ち、関連のドキュメンタリー映画や書籍を読み漁っていたことがある。そうしていわゆる「食育」について学んでいると、「命をいただいている自覚を持って感謝して生きる」といった結論にたどり着くことが多い。それはもちろん間違いではないし、人間として生きていく以上そうして合理化するしかない。だが、屠殺の職に就いているわけでもない「忙しい中でよくわかんないコンビニ飯を食っている」自分にとってその結論は本当に実感を持った正しいものなのだろうかと思う。 もっとわかりやすくいうと、ものすごく耳障りがいい「命への感謝」という概念に違和感があった(これは私が普段食に対して命を実感する生活をしていないことに起因しているため、その結論を出している人たちを批判するものではない)。 東出は自身の銃で鹿を仕留めたとき、ひと言「うぃ〜」と言った。ドキュメンタリーのカメラが回っているにもかかわらず、俳優という世間からわざわざボロを探して叩かれるような人生を送っているにもかかわらず、だ。東出はこのことを振り返って、なんて軽薄なんだと思ったけど、すごくうれしかったから、と語る。こういう素直さは東出の魅力のひとつだ。 作中全編を通して感じることだが、改めて、東出は人間離れした男前である。189cmの長身に、考えられないくらい小さな頭。目鼻立ちもハッキリしており、端正。誰がどう見ても男前なのだ……一般人として生きていけないくらいに。猟友会の中にいる東出は正直、イケメンすぎて浮いている。作中でも狩猟仲間から親戚を紹介され「芸能人」として求められることに苦悩するシーンが映されている。 (C)2024 SPACE SHOWER FILMS スキャンダルや本作中での言動を考えると、東出は本来「芸能人」に向いている性質ではないのだろうと思う。実際、最初はバイト感覚でモデルの仕事をしていたという。だが東出の生まれ持った圧倒的なオーラは、彼が一般人になることを許さない。そして、そのことに葛藤し、もがき苦しんだ東出はよりいっそう俳優として唯一無二な魅力的な存在になっていく。俳優という職業は人生経験が糧になる。彼にしか演じられない役柄が存在する限り、東出は映画界から求められ続けるだろう。 東出は『世界の果てに、ひろゆき置いてきた』(2023年/ABEMA)の仕掛け人である高橋弘樹プロデューサーとの対談で、俳優の仕事について次のように語る。 「僕の場合は(高橋さんと違って)人が用意した台本でやる。たしかにそれはあるんですけど、“僕の35年の人生があって台本をどう読むか”だから。そこに僕のオリジナリティがまた生まれるんです」 「でも役者の仕事はめちゃくちゃ疲弊するんです。磨耗する、削られる。ちょっと休むとまた欲が出るんです。(中略)また身を粉にするように削られるようにやりながら挑戦したいという欲が生まれる」 2022年、東出が出演する映画作品『福田村事件』の撮影が始まる。監督は、『A』(1998年)、『A2』(2001年)、『FAKE』(2016年)など数々のドキュメンタリー作品でも有名な、森達也だ。東出はオファーを受ける前から森の作品のファンだったという。正義や悪や人間は簡単なものじゃない、虐待事件を起こした側にも家族があり愛がある──そういった森の作品に共感し出演を決めたという。私自身も森の作品には感銘を受け、トークショーにも足を運ぶようなドキュメンタリーファンのひとりだ。東出のこの感覚には非常に共感する。 私は普段はマンガの仕事をしているが、時々、自分には作品を発表する素質がないような気がして何も書けなくなってしまうことがある。なにも自分や自分の作り出したキャラクターの価値観が絶対的に正しいだなんて思っていない。何が正しいことなのかを悩みながら、悩んでいるからこそ生きているし、物を作っている。しかし世間が見るのは「完成品」であり「商品」である。当たり前に自分が作ったものが倫理的に正しくないと指摘されることがある。私の作品を見ることで不快になった(=不幸になった)と言われることがある。これ自体は物を作って発表している以上、仕方のないことだ。折り合いをつけていくしかない。 ただ、私はそういう正しくなさも含めて人間(キャラクター)であり、愛らしさであり、それが滲み出ているものが、それを丸ごと抱きしめてあげたくなるようなものが愛しい作品であると思っている。自分はそういった「抱きしめてあげたいような気持ち」に出会うために生きているような気がする。 調子がいいときはそう思えているのだが、物作りをしているとどうしようもない不安に駆られる瞬間がある。自分の考える「愛らしさ」は世間にとって害であり、自分が物を作り自分の価値観を訴えることは多くの人を不快にする行為なのではないか。そうやって価値観を開示したときに人を幸せにできるか否かこそが物作りをすることに必要な素質の有無なのではないか。正直に自分を開示することは世間から愛されるコツだが、開示して出てくるものが世間とズレていたらもうどうしようもないのではないか。 東出は私にとって非常に「愛らしい」存在だ。 東出はきっと、本当に「こういう人」で、それを我々にある程度素直に開示してくれている。何度世間を賑わせて、叩かれて、殺害予告が届いても。 彼の過去のスキャンダルが倫理的に正しかったかというと、うなずくことはもちろんできない。内容はまったく違うが、個人的には本作を観たときの感覚は圡方宏史監督の『ホームレス理事長』(2014年)を観たときに近い。罪は罪だし行為に対して正しいとも思わないけれど、人間が真摯に生きる姿は惹かれるものがある。そして、「自分はやっぱり人間という生き物が好きだな」と思う。 東出は語る。 「──仕事だったり狩猟だったり、人との出会いだったりっていうのを本気でやってると、何か生きててよかったって僕自身思う瞬間もあれば、生きててよかったって(あなたの)おかげで思いましたって言ってくれる人の言葉があったり、生きててよかったとか、どうしようもなく愛おしいっていう気持ちなんだ、とか。それは物に対しても人に対しても作品に対しても。そういうときに、なんか、生きている意味ってあるんだろうな」 さまざまなスキャンダルやバッシングを受け続けた東出の口から、たどたどしい言葉で紡がれる「生きている意味」は必見だ。 文野 紋(ふみの・あや) 漫画家。2020年『月刊!スピリッツ』(小学館)にて商業誌デビュー。2021年1月に初単行本『呪いと性春 文野紋短編集』(小学館)を刊行。同年9月から『月刊コミックビーム』(KADOKAWA)で連載していた『ミューズの真髄』は2023年に単行本全3巻で完結。2024年7月、WEBコミック配信サイト『サイコミ』連載の『感受点』(原作:いつまちゃん)の単行本を発売。 (C)2024 SPACE SHOWER FILMS 出演:東出昌大 音楽・出演:MOROHA 監督・撮影・編集:エリザベス宮地 プロデューサー:高根順次 製作・配給・宣伝:SPACE SHOWER FILMS
-
 ファッションが持つ力を信じる、最前線の美しさに込めたメッセージ──関根光才『燃えるドレスを紡いで』
ファッションが持つ力を信じる、最前線の美しさに込めたメッセージ──関根光才『燃えるドレスを紡いで』文野紋のドキュメンタリー日記 ~現実(リアル)を求めて~ 人生を変えた一本、退屈な日々に刺激をくれる一本、さまざまな愛に気づく一本など── 漫画家・文野紋によるリアルな視点、世界観で紹介するドキュメンタリー映画日記 服を作ることは罪でしょうか? 本作はその疑問に真っ向からぶつかる日本人デザイナーを追った作品だ。 『パリ・オートクチュール・コレクション』。 オートクチュールとは「高級仕立服」という意味のフランス語で、『パリ・オートクチュール・コレクション』は、パリ・クチュール組合に加盟する限られたブランド、または招待されたブランドしか参加できない格式高いコレクションである。 本映画は、同コレクションに日本から唯一参加するブランド「YUIMA NAKAZATO(ユイマ ナカザト)」のデザイナーである中里唯馬に密着したリアル・ファッション・ドキュメンタリーである。 映画『燃えるドレスを紡いで』 唯馬は国内外で活躍する日本のトップデザイナーのひとりだ。ベルギーの名門アントワープ王立芸術アカデミー出身である彼の卒業コレクションは、インターネット上で回り回って世界的ヒップホップグループであるThe Black Eyed Peasのスタイリストの目に留まった。同グループの世界ツアー衣装のデザインを手がけたことをきっかけに、唯馬は対話から服を作っていけるオートクチュールに惹かれていった。 その後、唯馬は2009年に前述のブランド「YUIMA NAKAZATO」を設立。日本人では森英恵以来ふたり目となる『パリ・オートクチュール・コレクション』のゲストデザイナーに選ばれている。そんな輝かしい経験を持ち、ファッション業界の最前線を走る唯馬にはひとつの関心事があった。 「衣服の最終到達地点を見たい」 映画は、唯馬がアフリカ・ケニアへ旅立つシーンから始まる。アフリカ・ケニアのギコンバはメディアを通してしばしば「服の墓場」と表現されることがある。 映画『燃えるドレスを紡いで』 チャリティ団体や回収ボックスに寄付された古着がその後どのような道をたどるかご存じだろうか。昨今ファストファッションの流行などにより先進国での衣類の生産量や購入料は実際に必要とされている分よりも遥かに多いとされる。流行のデザインの安価な服をワンシーズンのみ着用するために購入する、ということも珍しくないだろう。そういった服を善意から、廃棄ではなく前述のような手段で寄付というかたちで手放すこともあるだろう。しかし現実には、回収量が必要量を上回っていたり、質などの問題で再利用できなかったり、ニーズに合っていなかったりと問題が多く、運ばれてくる古着のうちそのまま売り物になるのは20%ほどで、ゴミ同然のものも多いという。 ケニアの街の人々は口々に言った。 「服はじゅうぶんにある。もう作らないでほしい」 そうして弾かれたり売れ残ったりしたゴミ同然の古着は「服の墓場」である集積場に廃棄される。ケニアには焼却炉はない。集積場には生ゴミなども廃棄されており、プラスチックゴミの自然発火も相まって、街に入った瞬間から腐敗臭が立ち込めるという。 色とりどりの衣類等のゴミが地平線まで積み重なり、その中を子供たちが歩く様子は我々が想像すらしたことのないような光景でまさに圧巻。37年間、このゴミ山で暮らしているという女性の姿も映し出される。風でゴミたちが巻き上がる。 唯馬は、服の墓場を見て「美しい」とつぶやいた。 唯馬は『さんデジオリジナル』(山陽新聞)のインタビューでそのときのことを振り返り「不快だという思いもあるんですけど、それだけではない何かがあるな……と」、「適切な言葉が思いつきませんでした」と述べている。この「美しい」という言葉には我々には想像もつかないくらいたくさんの感情が込められているのだろう。 安価な服はポリエステルを主としている上、さまざまな原料が混ぜられているので、そう簡単にリサイクルすることはできない。 新しい服を作ることに魅力を感じ、生業としている唯馬にとってケニアでの光景は大きな葛藤を産むものだった。唯馬は「なぜ自分は服を作るのか」と自問自答した。唯馬の動揺がスクリーン越しに強く伝わってくる。 このとき、すでに次のパリコレクションまでの猶予は2カ月ほどしかなかった。この現実を知り、強い落ち込みを感じているのに、それを無視してまったく別のコレクションを発表することなどできない。 その後、唯馬たちはケニア北部のマルサビット地方を訪れる。マルサビット地方ではひどい干ばつが続いており、家畜が死に、食糧危機にも悩まされていた。そんな場所で唯馬が出会ったのは、羊の皮を縫い合わせた服や色とりどりにビーズを使った装飾品を身につけておしゃれを楽しむ現地の女性たちの姿であった。深刻な食糧危機に悩まされるこの地域でも、人々はおしゃれを楽しんでいたのだ。 映画『燃えるドレスを紡いで』 唯馬は彼女らから人が装うことの根源的な意味を考えるヒントを得て帰国し、パリコレクションに向けての制作に入る。 映画の後半では、帰国からパリコレクションまで約2カ月間の奮闘が描かれている。ケニアで売られていた古着の塊を持ち帰った唯馬は、さまざまなハプニング──SDGsとも関係のないものも含めた本当にさまざまなハプニングに見舞われながらも、より美しいコレクションを作るために妥協なしで服作りを進める。 この後半の物語によって、本作はSDGsに関する啓蒙映画という枠にとどまらず、むしろ中里唯馬というひとりの人間の生き様を映した映画になっていると思う。 服の過剰生産に対する問題提議を新しい服を作るという方法で行うのは、一歩間違えたら矛盾と捉えかねられない難しい活動だ。実際、唯馬も社内ミーティングで「(パリコレクションのような消費を促すことが目的の場に)関わっている以上、すでに加担してしまっている」、「そういう中で何を言っても、言い訳にしか聞こえないだろう」と言葉にしている場面があった。しかし、唯馬は方向性を固めてからは、ただひたすら美しさに重点を置き、ストイックにそれを追求していく。 唯馬はきっと芸術、特に美しい衣服の持つ力を心の底から信頼しているのだろう。 唯馬は「オートクチュールはF1レースみたいなもの」だという。技術を集結させ最も美しいものを発表する場だ、と。しかしF1レースで培われた技術は10年後には公道を走る車に応用される。かつては男性のものだったパンツスーツが今は女性の装いとして当たり前のものになっているように。最前線で美しいものを発表することが、人々の装いを、そして価値観までを変えることができる、服の持つ美しさにはその力があると信じているのだろう。 趣味程度だが、私は美術館やギャラリーで絵画や現代アートを見ることが好きだ。それらの作品の中には、戦争や政治、環境問題などに対するメッセージや主張が込められたものが多い。そして、それらはただ単純に文字や言葉での主張ではなく、絵画や彫刻などの美しく心が惹かれるようなかたちに昇華されている。 なぜ人は、理路整然とした言葉や理屈ではなく、美しさを通じて何かを主張しようとするのだろうか。その答えは簡単にわかることではないが、パリコレクションという大きな舞台の本番の直前まで美しさにこだわり、追求し、微調整を続ける唯馬を見ていると、我々もまた美しさの持つ可能性を信じずにはいられなくなる。美しさは時に言葉よりも鮮明に、そして強く物事を主張することができる。 映画『燃えるドレスを紡いで』 「デザイナーにはこれだという主張が必要だけど、彼(唯馬)は常に何か言いたいことがあった」 作中で唯馬について述べられていることのひとつだ。 何かどうしても言いたいことがある人が、美しさの持つ力を圧倒的に信じることで、世の中のデザインや芸術というものはでき上がっているのかもしれない。 『燃えるドレスを紡いで』は環境問題やファッション業界について知ることができるのはもちろんのこと、中里唯馬という人間のかっこいい生き様をのぞける貴重な作品だ。 文野 紋(ふみの・あや) 漫画家。2020年『月刊!スピリッツ』(小学館)にて商業誌デビュー。2021年1月に初単行本『呪いと性春 文野紋短編集』(小学館)を刊行。同年9月から『月刊コミックビーム』(KADOKAWA)で連載していた『ミューズの真髄』は2023年に単行本全3巻で完結。2024年7月18日、WEBコミック配信サイト『サイコミ』連載の『感受点』(原作:いつまちゃん)の単行本が発売予定。 映画『燃えるドレスを紡いで』 出演:中里唯馬 監督:関根光才 プロデューサー:鎌田雄介 撮影監督:アンジェ・ラズ 音楽:立石従寛 編集:井手麻里子 特別協力:セイコーエプソン株式会社 Spiber
マンガ『テレビドラマのつくり方』筧昌也
もっとドラマが楽しめる? 映画・ドラマ監督/脚本家の筧昌也が描く、テレビドラマづくりの裏側、こだわり、人間模様——
-
 #37「ドラマと映画、サントラ作りの違いとは?」|マンガ『テレビドラマのつくり方』筧昌也
#37「ドラマと映画、サントラ作りの違いとは?」|マンガ『テレビドラマのつくり方』筧昌也マンガ『テレビドラマのつくり方』筧昌也 もっとドラマが楽しめる? 映画・ドラマ監督/脚本家の筧昌也が描く、テレビドラマづくりの裏側、こだわり、人間模様——
-
 #36「ドラマのサントラ『劇伴』の発注は難しい」|マンガ『テレビドラマのつくり方』筧昌也
#36「ドラマのサントラ『劇伴』の発注は難しい」|マンガ『テレビドラマのつくり方』筧昌也マンガ『テレビドラマのつくり方』筧昌也 もっとドラマが楽しめる? 映画・ドラマ監督/脚本家の筧昌也が描く、テレビドラマづくりの裏側、こだわり、人間模様——
-
 #35スピンオフ「差し入れ道、すなわち『差道』」|マンガ『テレビドラマのつくり方』筧昌也
#35スピンオフ「差し入れ道、すなわち『差道』」|マンガ『テレビドラマのつくり方』筧昌也マンガ『テレビドラマのつくり方』筧昌也 もっとドラマが楽しめる? 映画・ドラマ監督/脚本家の筧昌也が描く、テレビドラマづくりの裏側、こだわり、人間模様——
マンガ『ぺろりん日記』鹿目凛
「ぺろりん」こと鹿目凛がゆる〜く描く、人生の悲喜こもごも——
林 美桜のK-POP沼ガール
K-POPガチオタク・林美桜テレビ朝日アナウンサーの沼落ちコラム
-
 推し活歴15年…恩人との再会で感じた“続けること”の大変さと幸せ|「林美桜のK-POP沼ガール」第20回
推し活歴15年…恩人との再会で感じた“続けること”の大変さと幸せ|「林美桜のK-POP沼ガール」第20回「林 美桜のK-POP沼ガール」 K-POPガチオタク・林美桜テレビ朝日アナウンサーの沼落ちコラム 久しぶりすぎるコラムの更新になってしまいました。 最近はというと……最近というかずっとですが、仕事内容もあまり変わらず、もともとプライベートでは推し活以外は家にこもっているので、大きな変化はなく。 「最近どう?」って聞かれると、 「ちょっといいウイスキーにコーラを注いでコークハイにすると、ド○ターペ○パーみたいな味になるっていう発見がありました! 割合は1対1です」 っていう会話しかできないくらいになってます。要は、何もないってこと。 停滞気味の私を救ってくれた「韓国ドラマ全話鑑賞」 毎年ですが、真夏に入るまではなんだかいろいろ停滞気味。 特に誕生日付近。歳を取ることの重みがどんどん増している。 急に先を思い悩んで、人生このままじゃまずいんじゃないか?と考え込み、でも行動に移す元気もなく、体調も上向かず、人との会話でもパッとしたことが言えないし、思いつかない。全部がぎこちない!! ふぅ〜〜〜。 でもこんなときこそ、韓国ドラマに救われます。 韓国ドラマを「全話観きる」ことが、私に達成感を与えてくれる。 仕事も勉強も人間関係も日常生活も、完璧にこなすことがいつも以上に難しくなっているときに、よくやるメンタル向上術です。 韓国ドラマを一気観することだけは完璧にできる。 この“完璧”を積み重ねると、私の場合「やり遂げた」という自信につながって、少しずついろいろよくなっていくような気がしてます。 そんな最近、一気観したドラマは 『悪縁』 『弱いヒーロー Class2』 『運の悪い日』 ちょっと蒸し暑くなってくるころは、スリリングでドロッとしたドラマが最高。 特に『運の悪い日』はおもしろかったです。韓国のウェブトゥーン(*1)が原作のようなんですが、それも読もうかなと思うくらい。 結局一番怖いのは人間だな……と痛いくらい再確認するような内容です。ヒヤッとするシーンの描き方がリアルで引き込まれました。 皆様もぜひご覧ください。 あ、もしよろしければ、この記事の冒頭に出てきたド○ターペ○パー風コークハイとともに(笑)。 『ドリームハイ』の現場で15年ぶりに再会した恩人 ……ここからが本題なんです。 読んでくださる皆様の受け取り方まで考えを及ばさず、一方的にしゃべるように書いちゃってます。申し訳ございません。 本当にあんまり人としゃべってなくて……しゃべりたかったみたいです。 2025年を振り返るときにこれは絶対思い出すだろうなという、印象深い出来事がありました。 4月に開催されたショーミュージカル『ドリームハイ』(*2)の劇場で、15年ぶりくらいにお会いした方がいらっしゃったんです。 母の知り合いなのですが、私が高校時代に「一生のお願いだから、どうしても韓国で開催されるサイン会に参加してみたい」とダダをこねたとき、母が頼ったSE7ENさん(*3)のファンの方です。 当時は今のように、何をどうしたら韓国でアーティストを観ることができるのかの情報がSNS上にあふれているわけではなく、韓国のアーティストを応援するのなら、その道を切り拓くくらいの意志と決意がないと難しいものだったと思います。 情報を得るには詳しい人を伝って知るしかない、根気のいる作業が必要でした。 その時代に熱心に韓国まで行ってアーティストを応援していた方は、本当にすごいと思います。失敗や悔しい思いをした方もたくさんいたはず。 母が頼ったその方は、嫌な顔ひとつせず、新参者の私たち親子にいろいろなことを教えてくださいました。 韓国のおすすめ滞在場所、CDの買い方、サイン会への参加の仕方……。 きっと苦労して得た情報だったはず。 その方のおかげで、無事に韓国のサイン会に参加することができました。 月日が流れてなかなかお会いできずにいましたが、『ドリームハイ』の現場で偶然お会いできたんです。 お顔を見た瞬間、高校時代の記憶がブワッと。 なんていうんでしょう……15年ほど続けている“推し活”という人生が一周した感覚、ひとつ区切りができた感覚っていうのかな。 そして、感動したんです。 変わらずSE7ENさんを応援されていることに。 誰かを応援し続けることって、そんなに簡単なことじゃないんですよね。 この話はアーティストにはまったく関係なく、応援する側に限った話ですが。 幸せな瞬間は本当にたくさんあるんですが、お金の面で悔しい思いをすることもありますし、応援が難しくなってしまうような大きな出来事があったり、まわりの現実主義者から厳しいことを言われて傷ついたり……。 “長く続ける”って難しい。 私も、昔たくさんいたはずの推し活仲間は、ずいぶん減りました。 私の場合は、母がとても協力的でいてくれたこと(ありがとう)。 そして「継続は力なり」。何かを継続することだけが私にできる唯一の特技なので、今まで推し活が続けられているのかなぁとも思います。 きっとその方も、お会いできていなかった15年でいろいろな出来事があったと思いますが、それを乗り越えて今も変わらずいらっしゃって、本当に幸せな表情をされていたことに、なんだか勇気をもらいました。 このままで大丈夫だと、自分の生き方が肯定されたような感じ。 やっぱり推し活で得られるものってあまりにも大きくて、 どれだけ落ち込んでいてもアーティストのパフォーマンスを見たら心が照らされるし、笑顔に救われるし、何事も自分のことよりずっとうれしいし、がんばっている姿に励まされて生きる活力をもらえる。 自分自身や身近な人にはどうしたって満たせない、心の一部を熱く輝かせてくれる。 今、人生を振り返っても思い出すのは、推し活で幸せだったシーンばかり。幸せのすべて。 ファンのために活躍し続けてくれて、推し活を続けさせてくれてありがとう(泣)。 『ドリームハイ』の帰り道、母にこんな支離滅裂感情をぶちまけるくらいにはハイになった出来事でした。 ミュージカルのクオリティも圧巻! そしてショーミュージカル『ドリームハイ』、素晴らしかったです。 日韓のレジェンドたちが息を合わせて作り上げていくプロフェッショナルな演技、パフォーマンスは圧巻。 その様子を1秒も逃さずリアルで見られるわけですから、ミュージカルってやはりいいですね。 ミュージカルは、昔、明治座で『光化門恋歌』を観て以来だったのですが(またいつかこの話もしたい)、改めてミュージカルの素晴らしさに触れた素敵な機会になりました。ハマりそう……。 林美桜のチョアチョア♡メモ* 1/ウェブトゥーン 韓国発のデジタルマンガ。スマホなどで読みやすいように、縦スクロール形式で公開されています。 *2/ショーミュージカル『ドリームハイ』 2011年に韓国・KBSで放映された、若者たちが芸能学校で夢を追う姿を描いた音楽ドラマを舞台化。2023年に韓国で初演、2025年4月に日本でも上演されました。ショーとミュージカルが融合した新感覚舞台。 *3/SE7EN(セブン) 2003年にデビューした、韓国出身の男性ソロシンガー。歌とダンスに定評があり、日本やアジア各国でも活躍しています。 文=林 美桜 編集=高橋千里
-
 『2025 パク・ヒョンシクFANMEETING [UNIVERSIKTY]』レポート|「林美桜のK-POP沼ガール」特別編
『2025 パク・ヒョンシクFANMEETING [UNIVERSIKTY]』レポート|「林美桜のK-POP沼ガール」特別編「林 美桜のK-POP沼ガール」 K-POPガチオタク・林美桜テレビ朝日アナウンサーの沼落ちコラム 『2025 パク・ヒョンシクFANMEETING [UNIVERSIKTY]』に行ってきました!! パク・ヒョンシクさんは韓国の俳優・歌手。アイドルグループ「ZE:A」でデビュー後、時代劇『花郎<ファラン>』、ラブコメディドラマ『力の強い女 ト・ボンスン』や『SUIT/スーツ~運命の選択~』などに出演し、演技力にも定評があります。 今回は特別編として、本イベントのレポートをお届けします。 神々しいオーラで登場!素敵な歌唱パフォーマンスも 真っ暗な会場で、すべての光を集めながら登場した 真っ赤なスーツに身を包む、金髪のパク・ヒョンシクさん。 (C)PARKHYUNGSIK JAPAN OFFICIAL なんだこの比率は……顔が小さすぎる。 赤だ。え? 金だ? 天使……いや、神が降臨したのか? パク・ヒョンシクさんという神々しい存在に、まったく脳の処理が追いつかない。 会場にいらっしゃったSIKcretのみなさんも「は!? え?」と驚いているように感じました。 (C)PARKHYUNGSIK JAPAN OFFICIAL まずは一つひとつの言葉を大事に、すらっと長い手で曲調を表現しながら、日本のカバー曲を披露くださいました。 温もりある、伸びのいい歌声。 曲間には、立っているだけの時間をすべて意味のあるものにする表情も。 俳優さんとしての魅力もひしひしと感じるパフォーマンスに魅了されました。 (C)PARKHYUNGSIK JAPAN OFFICIAL パク・ヒョンシクさんと大学生活を楽しもう! 素晴らしい歌声で幕を開けたファンミーティングは [UNIVERSIKTY]の名のとおり、 パク・ヒョンシクさんと一緒に大学生活を楽しむ、というコンセプト。 学科別に、ヒョンシクさんのいろいろな姿を見ることができました。 (C)PARKHYUNGSIK JAPAN OFFICIAL ここで語り尽くしたいほどすべてが楽しい内容だったのですが、 中でも、演劇科。 ヒョンシクさんがカメラの前でひとり芝居。 かなり接近するシーンもあり、最高以上でした。 レポート執筆のため、CSで流れる映像をお先に確認させていただきましたが、 会場で見たあの瞬間をもっと超高画質で、もちろんカメラマンさん目線の映像で観ることができます。 大変貴重です。とても近かったです。観る方は心してご覧くださいませ!! 会場のみなさんと団結して“厳しい監督”を演じたのも、大切な思い出になりました。 ヒョンシクさん主演の最新ドラマ『埋もれた心』(ディズニープラス)とはまた違った姿を堪能できましたよ。 調理科では、 最高のMC・古家(正亨)さんとのかけ合いでたくさん笑って、トークで引き出されるさまざまな表情にこちらまでニッコリ。 古家さんが映りのバランスを考えて、スマホを上下逆に構えて撮影している優しさにもご注目ください!! ファンミーティングでしか見られない生バンドを携えての歌唱は、やはり圧巻でした。 お忙しいなかにも関わらず、本当にいつ練習したんでしょう……。 飛びそうなくらい軽やかに高くスキップしながら歌われているお姿、妖精のようでした。 ファンミだけじゃ物足りない!スペシャルコンテンツも ぎゅっとした内容のレポートになってしまいましたが ここでお知らせがございます。 6月21日(土)午後3:00~午後5:00 CSテレ朝チャンネル1 <独占放送>2025 パク・ヒョンシクFANMEETING [UNIVERSIKTY] https://www.tv-asahi.co.jp/ch/contents/variety/0794/ ファンミーティングの様子が放送されます!! 独占インタビュー含め、なんと2時間。たっぷりお楽しみいただけます♪ (C)PARKHYUNGSIK JAPAN OFFICIAL そしてもうひとつお知らせです。 6/20(金) 『大下容子ワイド!スクランブル』(テレビ朝日)のフラッシュニュース枠で パク・ヒョンシクさんのインタビューが放送されます。 時間は11時25分ごろを予定しております。 (ニュース番組ですので、緊急で何か発生した場合などは放送されない場合もございます) さらに、テレビ朝日公式YouTube『ANNnewsCH』では ロングバージョンのインタビューも公開されますので、ぜひご覧いただけるとうれしいです。 https://youtube.com/@annnewsch ヒョンシクさんはファンミーティング後、お疲れなのにもかかわらず、疲れた顔をひとつも見せず、丁寧に質問に応じてくださいました。 日本語も瞬時に理解して反応くださいました。 (C)PARKHYUNGSIK JAPAN OFFICIAL お話しされるお言葉にあふれる、ヒョンシクさんらしい愛嬌とユーモアのセンス。 短い時間の中でも、観てくださるファンのみなさんを一番に想って、いつでも楽しませたいという情熱的で優しいお人柄が感じられました。 ぜひたくさんの方に観ていただけるとうれしいです。 文=林 美桜 編集=高橋千里
-
 神保町の韓国書籍専門店CHEKCCORIを訪問!経営者・金 承福「行動ひとつが自分を変える」|「林美桜のK-POP沼ガール」マレジュセヨ編
神保町の韓国書籍専門店CHEKCCORIを訪問!経営者・金 承福「行動ひとつが自分を変える」|「林美桜のK-POP沼ガール」マレジュセヨ編「林 美桜のK-POP沼ガール」 K-POPガチオタク・林美桜テレビ朝日アナウンサーの沼落ちコラム 林美桜が話を聞きたい“韓国カルチャー仕事人”に突撃取材する「林美桜のK-POP沼ガール・マレジュセヨ編」。 第2弾は、最近K-BOOKがマイブームである林の強い要望で、神保町で韓国語原書書籍・韓国関連本を専門に扱う書店「CHEKCCORI(チェッコリ)」を営む、金 承福(キム・スンボク)さんが登場! 出版社の社長も務める金さんのキャリアにも興味津々。林は、いったいどんな学びを得るのか? CHEKCCORIが作り出す「韓国文学を通じたコミュニティ」 林 美桜(以下、林) 営業時間外にもかかわらずお店を開けていただいて……本当にありがとうございます! まず店内がとても明るい雰囲気で、入った瞬間にとてもワクワクしました。 金 承福(以下、金) こちらこそありがとうございます。CHEKCCORIに来てくれてうれしいです! この場所ができてから、今年で丸10年になるんですよ。 林 10周年、本当にすごい。おめでとうございます。 金 なんだか100年くらいやっているような感覚です(笑)。 林 アハハハ! そのくらい、この場所でいろんなことを経験されているということですよね。そもそも韓国書籍専門店をオープンされた経緯を伺ってもよろしいですか? 金 まず私たちは、2007年に「クオン」という韓国文学を出版する出版社を作ったのですが、以前は今よりも韓国の本を取り扱っている書店はずっと少なかったんです。 韓国語を学び始める人も増えていたので、そういった方々が原文で韓国語の本を読む機会が少ないのは残念にも感じていました。であれば、自分たちで書店を作ってしまおうと思い立ったんです。 林 金さんは、いつから本がお好きだったんですか? 金 子供のころ、母が毎日おもしろいお話を聞かせてくれていたんですね。でもあるとき、それらは母の自作ではなく本から仕入れた物語だということを知った私は、まだ字が読めない年齢にもかかわらず「私も聞くだけじゃなく、本を読んでみたい!」と言って、文字を教えてほしいとせがみました。 林 すごい熱意! お母様はどんなお話をされていたんですか。 金 冒険物語とか、偉人伝が多かったです。そういった物語を通じて、新しい世界に飛び込むことに魅了されたことで本の魅力に目覚め、大きくなってからは詩人を志すようになり、韓国の芸術大学へ進みました。 林 ご自身で詩を書いていたこともあるんですね。そこからどのように、日本で出版社を立ち上げたのでしょうか? 金 当時、韓国の若者の間で留学ブームが起こって。特に私たちの世代にとって日本カルチャーは憧れの対象でした。今、日本の若い方たちが韓国カルチャーに対して抱いている気持ちに近いものだったと思います。 また、そのころは村上春樹や江國香織など、日本文学の注目度が高い時期でもありました。大学の先輩が、吉本ばななの『キッチン』を韓国語に翻訳してくれたノートを、みんなで回し読みしていたこともあったんですよ。それくらい人気があって、本好きとしてはぜひ日本に行かなければと決意し、大学に留学しました。 卒業後は日本の広告代理店に入社したのですが、やはり文学への愛は変わらなかったので出版社を作ろうと。ただ、イチから本を作ることは最初の段階では難しかったから、版権仲介のかたちで事業をスタートさせました。自分たちで新しく本を出すようになったのは、2011年になってからですね。 林 そしてクオンの記念すべき第1弾作品になったのは……。 金 『菜食主義者』(著:ハン・ガン/訳:きむ ふな)です。人間の内面を繊細に描く内容で、国を問わず文学が好きな人なら誰もが入り込んでしまう物語だと思い、一作目に選びました。 ただ、せっかく素晴らしい作品でも、読んでもらえなければそのよさを伝えることができない。最初にお話ししたとおり、当時はどこの書店も韓国文学の棚がない状況でしたから、まずは手に取ってもらえる機会を作ろうと思いました。そこで、私たちだけでなくいろんな出版社が韓国文学を出せるような環境を作る取り組みも始めたんです。 林 日本の韓国文学を取り巻く環境から変えようと。 金 そのとおりです。結果的に、今ではたくさんの韓国文学が日本語に翻訳され、人気を博すようになりました。『菜食主義者』著者のハン・ガンさんも本作で、2016年にアジア人で初めてブッカー国際賞を、そして2024年にはノーベル文学賞を獲得し、世界的に知られる作家となりましたね。 彼女の受賞が発表されるや、たくさんの方がCHEKCCORIへお祝いに駆けつけてくださったときは、「やはりいいものは、ゆっくり時間がかかっても必ず魅力が伝わるんだな」と感じてすごくうれしかったです。 林 今のお話を聞いて、クオンで新たな作品を発信するとともに、CHEKCCORIという場所で、韓国文学を通じて人と人がつながるコミュニティも作られているのだなと感じました。 金 そうですね。ここでは本を売るだけでなく、著者を招いたトークショーや楽器の演奏、映画やドラマの話をするイベントなどを週に2~3回は行っています。人の話を聞ける、そして自分の話もできる場所ですね。 お客様からの寄せ書きもたくさん! 林におすすめ!「シンクン」(=胸キュン)する韓国文学は? 林 最近はどんな本が人気なのですか? 金 K-POPファンの方にも来ていただけるようになったので、推しが読んでいる本が気になって……という声をよく聞きます。そのほか内容については、日本・韓国問わず、癒やしを与えてくれる本が好まれる傾向にあると感じます。林さんも、そういうテーマに関心がありますか? 林 癒やし、求めてますね(笑)。最近31歳になったのですが、働き方やひとりの人間としての生き方について悩むことも増えてきて、漠然とした不安に襲われることもあるんです。 金 それなら、2024年の本屋大賞で翻訳小説部門に輝いた『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』(著:ファン・ボルム/訳:牧野美加/集英社)をオススメしたいです。この本の主人公も、林さんと同じくバリバリ働く女性なのですが、あるとき燃え尽きてしまって「何をすればいいんだろう」という状態になってしまうんです。 そんななかで彼女は、本屋を開くことになる。そこに集う優しい人たちと交流していくうち、心に変化が生まれていくといったストーリーです。大きな出来事は起こらないけど、些細なことがゆっくりと進んでいく様子が描かれています。 林 それは癒やされそう!! すぐにでも読んでみたいです! 金 林さんは韓国語を勉強されているということなので、原書と日本語版を読み比べてみるといいと思いますよ。ここに来ている多くのお客さんもそういう方法で勉強しているし、私自身も日本語を学んでいたときにそのようにしていたんです。 林 なるほど! でも、小説を原書で読めるか不安です……。 金 この本はあまり難しすぎない表現で書かれているから、きっと大丈夫です。それに、先に日本語版で内容をインプットしてから原書を読むと、イメージしやすくなりますよ。「この表現、韓国語だとこうなるんだ!」っていう発見が楽しいですし、読み終えたあと「韓国語の本が読めた」と大きな自信につながるはずです。 林 たしかに、そうやって考えるとなんだかできそうな気がしてくるし、やってみたくなります! そして今感じたのですが、このように、本を前にお話ししながらオススメしていただくって、すごく特別な体験ですね。まさに、先ほど金さんがおっしゃっていた「人の話を聞ける、そして自分の話もできる場所」としての魅力を実感しました。 金 人と話すことで思いがけない本との出会いもありますし、そういった体験をみなさんに提供できればと思っています。ほかにも、興味のあるトピックや読んでみたいジャンルはありますか? 林 やっぱり、キュンとするような恋愛模様が描かれた物語も読みたいです。「胸キュン」って、たしか韓国語で「シンクン(심쿵)」っていうんですよね。 金 そうそう。ただ、うーん……いわれてみると、韓国ってドラマは「シンクン」する作品が多いんですが、意外と小説はそこまで多くないのかも。 林 えっ、そうなんですか! 金 なので、なかなか難しいのですが……『アンダー、サンダー、テンダー』(著:チョン・セラン/訳:吉川凪/クオン)は、私の中で「シンクン」ですね。これも主人公が30代女性なのですが、高校時代の友人の動画を撮り溜めているんです。その中で、青春時代に好きだった人の話も出てきて、それがすごくいい話なんですよ。 林 気になります~! こちらも今日、購入します(笑)。 翻訳者を育成するコンクールも開催! 林 クオンさんとCHEKCCORIさんでは、翻訳者の発掘や育成も行っていらっしゃるんですよね。 金 プロから直接学べる『チェッコリ翻訳スクール』という講座を設けたり、『日本語で読みたい韓国の本 翻訳コンクール』をK-BOOK振興会と開催しています。コンクールの受賞作品は、実際にクオンから出版されるんですよ。 第1回の受賞者である牧野(美加)さんも、今すごく活躍される翻訳者になられていて、先ほどご紹介した『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』の訳も手がけられているんです。 林 デビューまでサポートされているんですね。そうやって翻訳者の方が羽ばたくことで、日本での韓国文学界も豊かになっていく。 金 コンクールの翻訳対象となった作品に『ショウコの微笑』(著:チェ・ウニョン/訳:牧野美加、横本麻矢、小林由紀/クオン)があるのですが、212人の応募作が集まったんですね。 それについて著者のチェ・ウニョンさんが、「韓国語の『ショウコの微笑』はひとつしかない。だけど、日本語の『ショウコの微笑』の物語は212篇もあるんです」とおっしゃっていたことがすごく心に残っています。それこそが翻訳の素晴らしさだなと。 林 とても素敵な言葉……。また、そういった環境を整えられているのも、クオンさんが出版から書店まで行われているからこそだと思います。 金さんが31歳のとき、悩みは多かった? 金 ここまでのことは、とてもできないと最初は思っていましたが、経験を積み重ねていくうちに「自分たちはできるんだ」ということに気づいていって、今に至っています。 林 今日お話を伺って、金さんのバイタリティに感銘を受けました。私自身、今31歳で「何かやらなきゃ」と焦りつつ、頭で考えてばかりで行動に移せないので、すごく刺激になります。金さんも、私の年齢のときは悩むことが多かったですか? 金 もちろんありましたし、今も悩むことはあります。でもそれ以上にやりたいことがいっぱいでしたし、それが必ずしもお金にならないことでも、興味があるからとりあえずやってみるという考え方はずっと変わりません。 今振り返ってみると、その行動一つひとつが今を形作っているような気がしているんですよね。なので、頭で考えることがすべてではないと思います。 それに30歳でも40歳でも、新しいことに挑戦している人はいっぱいいますから、焦る必要はないですよ。そう思えたら、難しく考えずにとりあえずやってみようと感じられるじゃないですか。 林さんはせっかく韓国文学に関心を持って、今日ここへ足を運んでくれたんだから、これをきっかけに何か始めてみてもいいかもしれない。それくらいの気持ちで、まずは行動してみることが重要だと思います。 林 本当にそのとおりですね。韓国文学の発信という分野を開拓されて、人々に一歩踏み出すチャンスも届けている金さんの言葉だからこそ、よりいっそう刺さります。 金 ぜひ私たちと一緒に、何かやりましょう。アナウンサーさんだから、この場所で朗読会をやっていただくとか。すごくピッタリだと思いますよ。 林 うれしい……! 自分では考えてもみないことでしたが、そういったところから世界が広がっていくような予感がします。ぜひ、これからもよろしくお願いします! 韓国版の「指切りげんまん」。ふたりの約束が叶う日も近いかも? 林美桜の取材後記 金さんのお話に没頭した帰り、電車の窓に映った自分の顔が、充実感にあふれていてびっくり。久しぶりに見た表情でした。 それくらい、金さんから元気をいただいたんです。お話しさせていただけばいただくほどに、心が充電されていく新しい感覚でした。 今回の取材を通して、金さんのみなぎるパワーや行動力の源には「韓国文学」があるのではと感じました。 韓国文学にたくさん触れていらっしゃる金さんは、たくさんの世界、考え方をご存じです。 私は何かに行き詰まると、自分の世界だけで完結して限界を迎えてしまいますが、金さんにはその限界がまったくありませんでした。 「これがダメでも、こっちにはもっと楽しいことが!」「あっちもどうかしら?」と、限界突破!な考えがとめどなくあふれてきます。 それも、そのすべてがはつらつとしていて、ワクワクするような!! 「悩んでないでやってみようよ!」と、いくつもの出会ったことのない未来の扉を開いていただきました。 CHEKCCORIは本当に何時間でもいたくなる空間でした。ご紹介いただいた韓国文学を読むのが楽しみです。また新しい世界が見つかりそう! いつか朗読会もさせていただきたいので、韓国語もがんばります! 店舗情報 CHEKCCORI 東京都千代田区神田神保町1-7-3 三光堂ビル3階 https://www.chekccori.tokyo/ 文=菅原史稀 撮影=MANAMI 編集=高橋千里
奥森皐月の喫茶礼賛
喫茶店巡りが趣味の奥森皐月。今気になるお店を訪れ、その魅力と味わいをレポート
-
 カボチャのムースがピカイチ!喫茶店の未来を考える「カフェ トロワバグ」|「奥森皐月の喫茶礼賛」第10杯
カボチャのムースがピカイチ!喫茶店の未来を考える「カフェ トロワバグ」|「奥森皐月の喫茶礼賛」第10杯先月、友達と名画座に行ってきた。期間限定で上映している作品がおもしろそうだと誘われ、私も興味があったので観ることに。同じ監督の作品が2本立てで楽しめて、大満足で映画館をあとにした。 2本分の感想が温まっている状態で、その街でずっと営業している喫茶店に行った。けっして広くないお店のカウンターであれこれ楽しく映画のことを話していると、店の奥にいた男女のお客さんの声が聞こえてきた。どうやらそのふたりも私たちと同じ映画を観ていたそうだ。 その街での思い出を、その街の喫茶店で話している客が同時にいて、これこそ喫茶店のいいところだよなと感じた出来事だった。 「3つの輪」を意味する店名とロゴマーク 今回は神保町駅から徒歩1分というアクセス抜群の場所にある「カフェ トロワバグ」を訪れた。 大きな看板と赤いテントが目印の建物の、地下へ続く階段を降りていく。トロワバグとはフランス語で「3つの輪」という意味だそう。輪が3つ連なっているロゴマークが特徴的だ。 店内に入るとまず目に入るのは、かわいらしいランプやお花で飾られたカウンター。お店全体はダークブラウンを基調としていて、照明も落ち着いている。大人の雰囲気をまとっていながらも、穏やかな時間が流れている空間だ。 昼過ぎではあったが、若い女性のグループからビジネスマンまで幅広い客層のお客さんがコーヒーを飲んでいた。独特なフォントの「トロワバグ」が刻まれたお冷やのグラスでテンションが上がる。カッコいいなあ。 横型の写真アルバムのような形のメニューが素敵。一つひとつ写真が載っていてわかりやすく、メニューも豊富だ。 コーヒーのバリエーションが多く、サンドウィッチ系の食事メニューや甘いものなど全部おいしそうで、どれにしようか悩む。喫茶店ではあまり見かけないような手の込んだスイーツも豊富で、すべてオリジナルで手作りしているそうだ。 いつかホールで食べ尽くしたい「カボチャのムース」 今回は創業から一番人気でロングセラーの「グラタントースト」と「カボチャのムース」と「トロワブレンド」をいただくことにした。結局、人気と書かれているものを頼みたくなってしまう。 グラタントーストにはサラダもついている。ありがたい。 ハムやゴーダチーズなどの具材が挟まれたトーストに、自家製のホワイトソースがたっぷり。ボリューミーだけれど、まろやかで優しい味わいなのでもりもり食べられる。 クロックムッシュを置いている喫茶店はたまにあるが、「グラタントースト」というメニューは案外見かけない。わかりやすい名前と誰もが虜になるおいしさで、50年近く愛されているのだという。 カボチャのムースがこれまたおいしい。おいしすぎる。カボチャそのものの甘さが活かされていて、シンプルながら完璧な味。なめらかな舌触りで、少し振りかけられているシナモンとの相性も抜群。添えられているクリームはかなり甘さ控えめで、ムースと食べると食感が少し変わる。 カボチャのムースがある喫茶店は多くないだろうが、トロワバグのものはピカイチだと思う。いつかお金持ちになったらホールで食べ尽くしたい。食べ終わるのが名残惜しかった。 ブレンドは苦味と酸味のバランスが絶妙で、食事にもケーキにも合う。 まろやかで甘みも感じられるので、コーヒーの強い苦みや酸味が苦手という人にも飲みやすいのではないかと思う。 喫茶店が50年も残り続けているのは「奇跡的」 カフェ トロワバグについて、店主の三輪さんにお話を伺った。 オープンしたのは1976年。お母様が初代のオーナーで、娘である三輪さんが2代目として今もお店を継いでいるそうだ。学生時代からお店で過ごし、お母様とともにお店に立たれている時代もあったとのこと。 地下のお店なのでどうしても閉塞感があり、当時はタバコも吸えたので男性のお客さんが多かったそうだ。しかし、禁煙になってからは女性客も増え、最近は昨今の喫茶店ブームで若いお客さんも多いという。 女性店主ということもあり、なるべく華やかでかわいらしさのあるお店作りを心がけているそう。たしかに、テーブルのお花や壁に飾られている絵は店内を明るくしている。 客層の変化に合わせて、メニューも少しずつ変わったとのことだ。パンメニューの中にある「小倉バタートースト」は女性に人気らしい。 若い女性のグループが食事とスイーツをいくつか注文し、シェアしながら食べていることもあるそうだ。これだけ豊富なメニューだと誰かと行ってあれこれ食べてみたくなるので、気持ちがよくわかった。 落ち着きのある魅力的な店内の内装は、松樹新平さんという建築家さんが手がけたもの。特徴的な柱やカウンター、板張りの床などは創業以来変わらず残り続けている。 喫茶店というものは都市開発やビルのオーナーの都合などで移転や閉店をしてしまうことが多い。そのため、50年近く残り続けているのは奇跡的だ。 松樹さんは今でもたまにトロワバグを訪れることがあるそうで、自分のデザインのお店が残り続けていることを喜ばしく思っているそうだ。店内のあちこちに目を凝らしてみると、歴史が感じられる。 店主とお客さん、お互いの「様子の違い」にも気づく これまでにも都内の喫茶店を取材して耳にしていたのだが、三輪さんいわく喫茶店の店主は“横のつながり”があるそうだ。お互いのお店を訪れたり、プライベートでも交流したり。 先日閉店してしまった神田の喫茶店「エース」さんとも親交があったそうで、エースの壁に吊されていたコーヒーメニューの札をもらったそう。トロワバグの店内にこっそりと置かれていた。温かみがあって素敵だ。 神保町にはかなり多くの喫茶店が密集している。ライバル同士でお客さんの取り合いになっているのではないかと思ってしまうが、実際は違うようだ。 たとえばすぐ近くにある「神田伯剌西爾(カンダブラジル)」は現在も喫煙可能なため、タバコを吸うお客さんが集まっている。また「さぼうる」はボリューミーな食事メニューがあるため、男性のお客さんも多い。 そしてトロワバグさんは女性客が多め。このように、時代の流れによってそれぞれの特色が出て、結果的に棲み分けができるようになったとのことだ。 街に根づいている喫茶店には、もちろん常連さんがいる。常連さんとのコミュニケーションについて、印象的なお話を聞いた。 たとえば三輪さんの疲れが溜まっていたり、あまり元気がなかったりするときに、常連さんは気づくのだという。それは雰囲気だけでなく、コーヒーの味などからも違いを感じるのだそう。きっと私にはわからない違いなのだろうが、長年通っているとそういった関係が構築されていくようだ。 反対に、お客さんの様子がいつもと違うときには三輪さんも気づく。「コーヒーを1杯飲むだけ」ではあるが、それが大切なルーティンでありコミュニケーションであるというのは喫茶店ならではだ。喫茶店文化そのもののよさを、そのお話から改めて感じられた。 2号店「トロワバグヴェール」を開いた理由 実は、トロワバグさんは今年の6月に2号店となる「トロワバグヴェール」をオープンしている。同じ神保町で、そちらはコーヒーとクレープのお店。 週末のトロワバグはお客さんがたくさん来店し、外の階段まで並ぶこともあるという。そこで、せっかく来てくれた人にゆっくりしてもらいたいという思いがあり、2号店をオープンしたそうだ。 また、現在のトロワバグのビルもだんだんと老朽化してきていて、この先ずっと同じ場所で営業するというのはなかなか難しいのが現実だ。 その時が来たらきっぱりとお店をたたむという考えもよぎったそうだが、喫茶店業界では70代以上のマスターが現役バリバリで活躍している。それを見て三輪さんも「身体が元気なうちはお店を続けよう」と決心したそうだ。 結果として、喫茶店の新しいかたちを取ることになった。元のお店を続けながら2号店を開く。 古きよき喫茶店は減っていく一方のなか、トロワバグがこの新しい道を提案したことによって守られる未来があるように思える。 三輪さんは喫茶店業界の先を見据えた営業をされていて、店主仲間ともそのようなお話をされているそうだ。私はただ喫茶店が好きで足を運んでいるひとりにすぎないが、心強く思えてなんだかとてもうれしい気持ちになった。 最終回を迎えても、喫茶店に通う日々は続く 時代の変化に伴いながら、街に根づいた喫茶店。神保町という街全体が、多くの人を受け入れてきたということがよくわかった。 喫茶店のこれからを考える三輪さんは、これからのリーダー的存在であろう。大切に守られてきたトロワバグからつながる「輪」を感じられた。神保町でゆっくりとしたい日には、一度は訪れていただきたい名店だ。 昨年12月に始まったこの連載だが、今月が最終回。私も寂しい気持ちでいっぱいなのだが、これからも喫茶店が好きなことには変わりない。 今までどおり喫茶店に日々通って、写真を撮って記録していく。いつかまたどこかで、みなさんに素晴らしいお店を紹介したい。そのときにはまた読んでね。ごちそうさまでした。 カフェ トロワバグ 平日:10時〜20時、土祝日:12時〜19時、日曜:定休 東京都千代田区神田神保町1-12-1 富田ビルB1F 神保町駅A5出口から徒歩1分 文・写真=奥森皐月 編集=高橋千里
-
 贅沢な自家製みつまめを味わう。成田に佇む“理想の喫茶店”「チルチル」|「奥森皐月の喫茶礼賛」第9杯
贅沢な自家製みつまめを味わう。成田に佇む“理想の喫茶店”「チルチル」|「奥森皐月の喫茶礼賛」第9杯これまでに行った喫茶店とこれから行きたい喫茶店の場所に、マップアプリでピンを立てている。ピンに絵文字を割り振ることができるので、行った場所にはコーヒーカップ、行きたい場所にはホットケーキ。 都内で生活をしているため、東京の地図にはコーヒーカップの絵文字がびっしりと並んでいる。少しずつ縮小していくにつれ、全国に散り散りになったホットケーキのマークが見える。 いつか日本地図を全部コーヒーカップの絵文字で埋め尽くしたいなぁと、地図を眺めながらよく思う。 そのためには旅行をたくさんしてその先で喫茶店に行くか、喫茶店のために旅行するか、どちらかをしなければならない。どちらにせよ遠くまで行ったら喫茶店に立ち寄らないのはもったいないと思っている。 旅行気分で、成田の喫茶店「チルチル」へ 今回はこの連載が始まって以来一番都心から離れた場所に行ってきた。JR成田駅から徒歩で12分、成田山新勝寺総門のすぐそばのお店「チルチル」さんだ。 ずっと前から SNSや本で写真を見ていて、いつか行ってみたいと思っていた喫茶店。取材させていただけることになり、成田という土地自体初めて訪れた。 駅から成田山までの参道にはお土産屋さんや古い木造建築の商店などが建ち並んでおり、成田の名物である鰻(うなぎ)のお店も軒を連ねていた。 賑やかな道なので、体感としては思ったよりもすぐチルチルさんまで行けた。よく晴れた日で、きれいな街並みと青空が最高だった。旅行気分。 レンガでできた門に洋風のランプ、緑色のテントがとてもかわいらしい外観。 この日は店の外に猫ちゃんが4匹いた。地域猫に餌をあげてチルチルさんがお世話をしているそうで、人慣れしたかわいらしい猫たちがお出迎えしてくれた。 製造期間20日以上!とっても贅沢な手作りのみつまめ 店内に入り、思わず息を飲んだ。ゴージャスかつ落ち着きのある「理想の喫茶店」といってもいいような空間。 木目調の壁、レトロなシャンデリア、高級感のある椅子やソファ。天井が高いのも開放的でよい。装飾の施されたカーテンや壁のライトは、お城のような華やかさがある。 メニューは喫茶店らしさにこだわっているようで、コーヒー・紅茶・ソフトドリンク・ケーキ・トーストとシンプルなラインナップ。 レモンジュースやレモンスカッシュは、レモンをそのまま絞ったものを提供しているそう。写真映えするのでクリームソーダも若い人に人気なようだ。 ただ、チルチルのイチオシ看板メニューは、手作りのみつまめだという。強い日差しを浴びて汗をかいてしまっていたので、アイスコーヒーとみつまめを注文した。 店内の椅子やソファに使われている素敵な布は「金華山織」という高級な代物だそう。しかし布の部分は消耗してしまうため、定期的にすべて張り替えているとのこと。お値段を想像すると恐怖を覚えるが、ふかふかで素敵な椅子に座ると、家で過ごすのとは違う特別感を味わえる。 アイスコーヒーはすっきりしていておいしい。ごくごくと飲んでしまえる。ちなみにシロップはお店でグラニュー糖から作っているものだそう。甘いコーヒーが好きな人にはぜひたっぷり使ってみてもらいたい。 そして、お店イチオシのみつまめ。「手作り」とのことだが、なんと寒天は房州の天草を使った自家製。さらに「小豆」「金時」「白花豆」「紫豆」の4種類の豆は、水で戻すところから炊き上げまですべてをしているそうだ。完全無添加で、素材の味が存分に活かされたとにかく贅沢なみつまめ。 粉寒天や棒寒天で作るのとは違って、天草から作る寒天は磯の香りがほのかにする。また食感もよい。まず寒天そのものがおいしいのだ。 また、お豆は何度も何度も炊いてあり、とても柔らかい。甘さもほどよく、豆だけでもお茶碗一杯食べたくなるようなおいしさ。花豆はそれぞれ最後の仕上げの味つけが違うそうで、紫花豆は黒砂糖、白花豆は塩味。すべて食べきったあとに白花豆を食べると異なる味わいが楽しめるので、おすすめだそう。 このみつまめすべてを作るのには20日以上かかるとのことだ。完全無添加でこれほど時間と手間がかかっているみつまめは、ほかではないだろう。一度は食べていただきたい。 1972年に創業。店名は童話『青い鳥』から お店について、店主のお母様にお話を伺った。 「チルチル」は1972年11月に成田でオープン。当初は違う場所で、ボウリング場などが入っているビルの中で営業していた。 夜遅くもお客さんが来ることから夜中の0時までお店を開けていたため、毎日忙しく、寝る暇もなかったらしい。当時は20歳で、若いうちから相当がんばっていらしたそう。 2年後の1974年12月25日から現在の成田山の目の前の場所で営業がスタート。もとは酒屋さんが使っていた建物だそうで、1階はトラックが停まり、シャッターが閉まるような造りだったらしい。そこに内装を施して喫茶店にしたため、天井が高いようだ。 店名の「チルチル」は童話の『青い鳥』から。繰り返しの言葉は覚えやすいため、店名に選んだらしい。かわいらしいしキャッチーだし、とてもいい名前だと思う。 「チルチル」の文字はデザイナーさんに頼んだそうだが、お店の顔ともいえる男女のイラストは童話をモチーフにお母様が描いたもの。画用紙に描いてみた絵をそのまま50年間使い続けているとのことだ。今もメニューやマッチに使われている。 記憶にも残る素晴らしいデザインではないだろうか。おいしいみつまめも、トレードマークの看板イラストも作れる素敵な方だ。 「お不動さまに罰当たりなことはできない」 成田山のすぐそばで喫茶店を営業するからには、お不動さまに罰当たりなことはできない、というのがチルチルのポリシーらしい。 お参りをしに来た人がゆったりとくつろげて、「来てよかったな」と思ってもらえるようにやってきたそう。お参りをしてからチルチルに立ち寄る、というルーティンになっているお客さんも多いらしい。 店内は何度か改装をしているが、全体の造りや家具は50年間ほとんど変わりがないとのこと。椅子やテーブルはお店に合わせて職人さんに作ってもらったもので、細やかなこだわりを感じられる。 お店の奥のカウンターとキッチンの棚もとても素敵だ。これも職人さんがお店に合わせて作ったもの。喫茶店の特注の家具は、たまらない魅力がある。 随所にこだわりが光る「チルチル」は、50年間大切に守られてきた成田の名所のひとつであろう。 素通りするわけにはいかないので、成田山のお参りももちろんしてきた。広い境内は静かで、パワーをもらえるような力強さもあった。 空港に行く用事があっても「成田」まで行こうと思うことがなかったため、今回はとてもいい機会であった。成田山に行き、帰りに「チルチル」に寄るコースで小旅行をしてみてはいかがだろうか。 次回もまたどこかの喫茶店で。ごちそうさまでした。 チルチル 9時30分〜16時30分 不定休 千葉県成田市本町333 JR成田駅から徒歩12分、京成成田駅から徒歩13分 文・写真=奥森皐月 編集=高橋千里
-
 40年前から“映え”ていたクリームソーダにときめく。夏の阿佐ヶ谷は「喫茶 gion」で|「奥森皐月の喫茶礼賛」第8杯
40年前から“映え”ていたクリームソーダにときめく。夏の阿佐ヶ谷は「喫茶 gion」で|「奥森皐月の喫茶礼賛」第8杯「奥森皐月の喫茶礼賛」 喫茶店巡りが趣味の奥森皐月。今気になるお店を訪れ、その魅力と味わいをレポート 暑さが一段と厳しくなってきたので、大好きな散歩も日中はほどほどにしている。 昼間に家を出ると、アスファルトの照り返しのせいかフライパンで焼かれているようだ。寒さより暑さのほうが苦手な私は、夏の大半は溶けながらだらりと過ごしてしまう。 しかしながら、夏の喫茶店は大好き。汗をかきながらやっとお店に着いて、冷房の効いた席に座るときの幸福感は何にも変えられない。冷たいドリンクを飲んで少しずつ汗が引いていくあの感覚は、夏で一番好きな瞬間だ。 阿佐ヶ谷のメルヘンチックな喫茶店 今回訪れたのはJR阿佐ケ谷駅から徒歩1分、お店が建ち並ぶ駅前でひときわ目立つ緑に囲まれたレトロな外装の喫茶店。阿佐ヶ谷の街で40年近く愛されている「喫茶 gion(ぎおん)」さん。 実はこのお店は、私のお気に入りトップ5に入る大好きな喫茶店。中学生のころに初めて行ってから今日まで定期的に訪れている。取材させていただけてとてもうれしい。 店内はかわいいランプやお花や絵で装飾されていて、青と緑の光が特徴的。いわゆる「喫茶店」でここまでメルヘンチックな雰囲気のお店はかなり珍しいと思う。 どこの席も素敵だが、やはり一番特徴的なのはブランコの席。こちらに座らせていただき、人気メニューのナポリタンとソーダ水のフロートトッピングを注文した。 ブランコ席は窓に面していて、この部分だけ壁がピンク色。店内中央の青色を基調とした空気感とはまた違う、かわいらしさと落ち着きのある空間だ。 店先の木が窓から見える。今の季節は緑がとてもきれいだ。 焦げ目がおいしい!一風変わったナポリタン ここのナポリタンは、一般的な喫茶店のナポリタンとは異なる。大きなお皿にナポリタン、キャベツサラダ、そしてたまごサラダが乗っている。店主さんいわく、このたまごサラダはサンドイッチに挟むためのものだそう。それを一緒に提供しているのだ。 まずはナポリタンをいただく。ハムが1枚そのまま乗っている見た目がいい。このナポリタンは色が濃いのだが、これは少し焦げるくらいまでしっかりと炒めているから。麺にソースがしっかりとついていて、香ばしさがたまらなくおいしい。 次にキャベツと一緒に食べてみると、トマトのソースが絡んで、シャキシャキとした食感が加わり、これもまたいい。 最後にたまごサラダと食べると、まろやかさとナポリタンの風味が最高に合う。黒胡椒も効いていて、無限に食べられる味だ。ボリュームたっぷりだがあっという間に完食した。 トーストもグラタンもお餅も少し焦げ目があるくらいが一番おいしいので、スパゲッティもよく炒めてみたところおいしくできたから今のスタイルになったそうだ。 ただ、通常のナポリタンなら温める程度でいいところを、しっかり焼くとなると手間と時間がかかる。炒めてくれる店員さんに感謝だ。ごく稀に、焦げていると苦情を入れる人がいるそう。そこがおいしいのになあ。 トロピカルグラスで飲む、おもちゃみたいなクリームソーダ これまた名物のクリームソーダ。 正確にいうと、gionで注文する場合は「ソーダ水」を緑と青の2種類から選び、フロートトッピングにする。すると、丸く大きなグラスにたっぷりのクリームソーダを飲むことができる。このグラスは「トロピカルグラス」というそうだ。 gionさんのまねをしてこのグラスを使い始めたお店はあるが、このかわいいフォルムはオープン当初から変わらないとのこと。「インスタ映え」という言葉が生まれる遙か前からこの「映え」な見た目のクリームソーダがあったのは、なんだか趣深い。 深く透き通る青と炭酸のしゅわしゅわ、贅沢にふたつも乗った丸いバニラアイス。どこを切り取ってもときめくかわいさだ。 見た目だけでなく、味もおいしい。シロップの風味と炭酸に、バニラ感強めのアイスが合う。「映え」ではなくなってくる、アイスが溶けたときのクリームソーダも好きだ。白と青が混じった色は、ファンシーでおもちゃみたい。 内装から制服までこだわった“かわいい”世界観 お店について、店主の関口さんにお話を伺った。 学生時代に本が好きだった関口さんは、本をゆっくりと読めるような落ち着いた場所を作りたかったそうで、20代はとにかく必死で働いてお店を開く資金を貯めていたとのこと。 1日に16時間ほど働き、寝るためだけの狭い部屋で暮らし、食べ物以外には何もお金を使わず生活していたとのことだ。 そしてお金が貯まったころから1年かけて東京都内の喫茶店を300店舗ほど回り、どんなお店にしようかと参考にしながら計画を練ったそう。 お店を開くにあたって、設計から何からすべてを関口さんが考えたそうで、1cm単位で理想の喫茶店になるように作って、できたのがこの喫茶 gion。 大理石の床、板張りの床、絨毯の床、どれも捨てがたいと思い、最終的には場所ごとに変えて3種類の床になったらしい。贅沢な全部乗せだ。ブランコはかつて吉祥寺にあったジャズ喫茶から得たエッセンス。 オープン時には資金面でそろえきれなかった雑貨やインテリアも少しずつ集めて、今のお店の独特でうっとりするような空間になっていったようだ。 白いブラウスに黒のリボン、黒のロングスカートというgionの制服も関口さんプロデュース。手書きのメニューもキュートで魅力的だ。 ご自身の好みがはっきりとあり、それを実現できているからこそ、調和した世界観になっているのだとわかった。お店のマークも、関口さんの思い描く素敵な女性のイラストだという。ナプキンまでかわいい。 「帰りにgionに寄れる」という楽しみ 喫茶gionのもうひとつの魅力は、午前9時から24時(金・土は25時)まで営業しているところ。モーニングが楽しめるのはもちろん、夜も遅くまで開いている。阿佐ヶ谷には喫茶店が多くあるが、たいていは夕方〜19時くらいには閉店してしまう。 私は阿佐ヶ谷でお笑いや音楽のライブに行ったり、演劇を観に行ったりする機会が多い。終わるのは21時〜22時が多く、ちょうどお腹が空いている。ほかの街なら適当なチェーン店に入るのだが、阿佐ヶ谷に限っては「帰りにgionに寄れる」という楽しみがある。 ナポリタン以外にもピザやワッフルなど、小腹を満たせるメニューがあってありがたい。夜のgionは店先のネオンが光り、店内の青い灯りもより幻想的になる。遅くまで営業するのはとても大変だと思うが、これからも阿佐ヶ谷に行ったときは必ず寄りたい。 夏の阿佐ヶ谷の思い出に、gion 関口さんの理想を詰め込んだメルヘンチックな喫茶店は、若い人から地元民まで幅広く愛される名店となった。 阿佐ヶ谷の街では8月には七夕まつりも開催される。駅前のアーケードにさまざまな七夕飾りが出される、とても楽しいお祭りだ。夏の阿佐ヶ谷を楽しみながら、喫茶gionでひと休みしてみてはいかがだろうか。 次回もまたどこかの喫茶店で。ごちそうさまでした。 喫茶 gion 月火水木日:9時〜24時、金土:9時〜25時 東京都杉並区阿佐谷北1-3-3 川染ビル1F 阿佐ケ谷駅から徒歩1分、南阿佐ケ谷駅から徒歩8分 文・写真=奥森皐月 編集=高橋千里
奥森皐月の公私混同<収録後記>
「logirl」で毎週配信中の『奥森皐月の公私混同』。そのスピンオフのテキスト版として、MCの奥森皐月が自ら執筆する連載コラム
-
 涙の最終回!? 2年半の思い出を振り返る|『奥森皐月の公私混同<収録後記>』第30回
涙の最終回!? 2年半の思い出を振り返る|『奥森皐月の公私混同<収録後記>』第30回転んでも泣きません、大人です。奥森皐月です。 この記事では私がMCを務める番組『奥森皐月の公私混同』の収録後記として、番組収録のウラ話や収録を通して感じたことを毎月書いています。今回の記事で最終回。 『奥森皐月の公私混同〜ソレ、私に教えてください!〜』の9月に配信された第41回から最終回までの振り返りです。 月額990円ですが、logirlに加入すれば最新回までのエピソードがすべて視聴できます。過去回でおもしろいものは数えきれぬほどあるので、興味がある方はぜひ観ていただきたいです。 「見せたい景色がある」展望タワーの存在意義 (写真:奥森皐月の公私混同 第41回「タワー、私に教えてください!」) 第41回のテーマは「タワー、教えてください!」。ゲストに展望タワー・展望台マニアのかねだひろさんにお越しいただきました。 タワーと聞いてやはり思い浮かべるのは、東京タワーやスカイツリー。建築のすごさや造形美を楽しんでいるのだろうかとなんとなく考えていました。ところが、お話を聞いてみるとタワーという概念自体が覆されました。 かねださんご自身のタワーとの出会いのお話が本当におもしろかったです。20代で国内を旅行するようになり、新潟県で偶然バス停として見つけた「日本海タワー」に興味を持って行ってみたとのこと。 実際の画像を私も見ましたが、思っているタワーとはまったく違う建物。細長くて高い、あのタワーではありません。ただ、ここで見た景色をきっかけにまた別のタワーに行き、タワーの魅力にハマっていったそうです。 その土地を見渡したときに初めてその土地をわかったような気がした、というお話がとても素敵だと感じました。 たとえば京都旅行に行ったとして、金閣寺や清水寺など名所を回ることはあります。ただ、それはあくまでも京都の中の観光地に行っただけであって「京都府」を楽しんだとはいえないと、前から少し思っていました。 そこでタワーのよさが刺さった。たしかに、その地域や都市を広く見渡すことができれば気づきがたくさんあると思います。 もちろん造形的な楽しみ方もされているようでしたが、展望タワーからの景色というものはほかでは味わえない魅力があります。 かねださんが「そこに展望タワーがあるということは、見せたい景色がある」というようなことをお話しされていたのにも感銘を受けました。 いわゆる“高さのあるタワー”ではないところの展望台などは少し盛り上がりに欠けるのではないか、なんて思ってしまっていたけれど、その施設がある時点でその景色を見せたいという意思がありますね。 有効期限がたった1年の、全国の19タワーを巡るスタンプラリーを毎年されているという話も興味深かったです。最初の印象としては、一度訪れたところに何度も行くことの楽しみがよくわからなかったです。 でも、天気や季節、建物が壊されたり新しく建築されたりと常に変化していて「一度として同じ景色はない」というお話を聞いて納得しました。タワーはずっと同じ場所にあるのだから、まさに定点観測ですよね。 今後旅行に行くときはその近くのタワーに行ってみようと思いましたし、足を運んだことのある東京タワーやスカイツリーにもまた行こうと思いました。 収録後、速攻でかねださんの著書『日本展望タワー大全』を購入しました。最近も、小規模ではありますが2度、展望台に行きました。展望タワーの世界に着々と引き込まれています。 究極のパフェは、もはや芸術作品!? (写真:奥森皐月の公私混同 第42回「パフェ、私に教えてください!」) 第42回は、ゲストにパフェ愛好家の東雲郁さんにお越しいただき「パフェ、教えてください!」のテーマでお送りしました。 ここ数年パフェがブームになっている印象でしたが、流行りのパフェについてはあまり知識がありませんでした。 このような記事を書くときはたいていファミレスに行くので、そこでパフェを食べることがしばしばあります。あとは、純喫茶でどうしても気になったときだけは頼みます。ただ、重たいので本当にたまにしか食べないものという存在です。 東雲さんはもともとアイス好きとのことで、なんとアイスのメーカーに勤めていた経験もあるとのこと。〇〇好きの範疇を超えています。 そのころにパフェ用のアイスの開発などに携わり、そこからパフェのほうに関心が向いたそうです。お仕事がキッカケという意外な入口でした。それと同時に、パフェ専用のアイスというものがあるのも、意識したことがなかったので少し驚かされました。 最近のこだわり抜かれたパフェは“構成表”なるものがついてくるそう。パフェの写真やイラストに線が引かれていて、一つひとつのパーツがなんなのか説明が書かれているのです。 昔ながらの、チョコソース、バニラソフトクリーム、コーンフレークのように、見てわかるもので作られていない。野菜のソルベやスパイスのソースなど、本当に複雑なパーツが何十種も組み合わさってひとつのパフェになっている。 実際の構成表を見せていただきましたが、もはや読んでもなんなのかわからなかったです。「桃のアイス」とかならわかるのですが、「〇〇の〇〇」で上の句も下の句もわからないやつがありました。 ビスキュイとかクランブルとか、それは食べられるやつですか?と思ってしまいます。難しい世界だ。難しいのにおいしいのでしょうね。 ランキングのコーナーでは「パフェの概念が変わる東京パフェベスト3」をご紹介いただきました。どのお店も本当においしそうでしたが、写真で見ても圧倒される美しさ。もはや芸術作品の域で、ほかのスイーツにはない見た目の豪華さも魅力だよなと感じさせられました。 予約が取れないどころか普段は営業していないお店まであるそうで、究極のパフェのすごさを感じるランキングでした。何かを成し遂げたらごほうびとして行きたいです。 マニアだからとはいえ、東雲さんは1日に何軒もハシゴすることもあるとのこと。破産しない程度に、私も贅沢なパフェを食べられたらと思います。 1年間を振り返ったベスト3を作成! (写真:奥森皐月の公私混同 第43回「1年間を振り返り 〇〇ベスト3」) 第43回のテーマは「1年間を振り返り 〇〇ベスト3」ということで、久しぶりのラジオ回。昨年の10月からゲストをお招きして、あるテーマについて教えてもらうスタイルになったので、まるまる1年分あれこれ話しながら振り返りました。 リスナーからも「ソレ、私に教えてください!」というテーマで1年の感想や思い出などを送ってもらいましたが、印象的な回がわりと被っていて、みんな同じような気持ちだったのだなとうれしい気持ちになりました。 スタートして4回のうち2回が可児正さんと高木払いさんだったという“都トムコンプリート早すぎ事件”にもきちんと指摘のメールが来ました。 また、過去回の中で複雑だったお話からクイズが出るという、習熟度テストのようなメールもいただいて楽しかったです。みなさんは答えがわかるでしょうか。 この回では、私もこの1年での出来事をランキング形式で紹介しました。いつもはゲストさんにベスト3を作ってもらってきましたが、今度はそれを振り返りベスト3にするという、ベスト3のウロボロス。マトリョーシカ。果たしてこのたとえは正しいのでしょうか。 印象がガラリと変わったり、まったく興味のなかったところから興味が湧いたりしたものを紹介する「1時間で大きく心が動いた回ベスト3」、情報番組や教育番組として成立してしまうとすら思った「シンプルに!情報として役立つ回ベスト3」、本当に独特だと思った方をまとめた「アクの強かったゲストベスト3」、意表を突かれた「ソコ!?と思ったランキングタイトルベスト3」の4テーマを用意しました。 各ランキングを見た上で、ぜひ過去回を観直していただきたいです。我ながらいいランキングを作れたと思っています。 ハプニングと感動に包まれた『公私混同』最終回 (写真:奥森皐月の公私混同最終回!奥森皐月一問一答!) 9月最後は生配信で最終回をお届けしました。 2年半続いた『奥森皐月の公私混同』ですが、通常回の生配信は2回目。視聴者のみなさんと同じ時間を共有することができて本当に楽しかったです。 最終回だというのに、冒頭から「マイクの電源が入っていない」「配信のURLを告知できていなくて誰も観られていない」という恐ろしいハプニングが続いてすごかったです。こういうのを「持っている」というのでしょうか。 リアルタイムでX(旧Twitter)のリアクションを確認し、届いたメールをチェックしながら読み、進行をし、フリートークをして、ムチャ振りにも応える。 ハイパーマルチタスクパーソナリティとしての本領を発揮いたしました。かなりすごいことをしている。こういうことを自分で言っていきます。 最近メールが送られてきていなかった方から久々に届いたのもうれしかった。きちんと覚えてくれていてありがとうという気持ちでした。 事前にいただいたメールも、どれもうれしくて幸せを噛みしめました。みなさんそれぞれにこの番組の思い出や記憶があることを誇らしく思います。 配信内でも話しましたが、この番組をきっかけにお友達がたくさん増えました。番組開始時点では友達がいなすぎてひとりで行動している話をよくしていたのですが、今では友達が多い部類に入ってもいいくらいには人に恵まれている。 『公私混同』でお会いしたのをきっかけに仲よくなった方も、ひとりふたりではなく何人もいて、それだけでもこの番組があってよかったと思えるくらいです。 番組後半でのビデオレターもうれしかったです。豪華なみなさんにお越しいただいていたことを再確認できました。帰ってからもう一度ゆっくり見直しました。ありがたい限り。 この2年半は本当に楽しい日々でした。会いたい人にたくさん会えて、挑戦したいことにはすべて挑戦して、普通じゃあり得ない体験を何度もして、幅広いジャンルを学んで。 単独ライブも大喜利も地上波の冠ラジオもテレ朝のイベントも『公私混同』をきっかけにできました。それ以外にも挙げたらキリがないくらいには特別な経験ができました。 スタートしたときは16歳だったのがなんだか笑える。お世辞でも比喩でもなくきちんと成長したと思えています。テレビ朝日さん、logirlさん、スタッフのみなさんに本当に感謝です。 そしてなにより、リスナーの皆様には毎週助けていただきました。ラジオ形式での配信のころはもちろんのこと、ゲスト形式になってからも毎週大喜利コーナーでたくさん投稿をいただき、みなさんとのつながりを感じられていました。 メールを読んで涙が出るくらい笑ったことも何度もあります。毎回新鮮にうれしかったし、みなさんのことが大好きになりました。 #奥森皐月の公私混同 最終回でした。2021年3月から約2年半の間、応援してくださった皆様本当にありがとうございます。メールや投稿もたくさん嬉しかったです。また必ずどこかの場所で会いましょうね、大喜利の準備だけ頼みます。冠ラジオは絶対にやりますし、馬鹿デカくなるので見ていてください。 pic.twitter.com/8Z5F60tuMK — 奥森皐月 (@okumoris) September 28, 2023 『奥森皐月の公私混同』が終了してしまうことは本当に残念です。もっと続けたかったですし、もっともっと楽しいことができたような気もしています。でも、そんなことを言っても仕方がないので、素直にありがとうございましたと言います。 奥森皐月自体は今後も加速し続けながら進んで行く予定です。いや進みます。必ず約束します。毎日「今日売れるぞ」と思って生活しています。 それから、死ぬまで今の好きな仕事をしようと思っています。人生初の冠番組は幕を下ろしましたが、また必ずどこかで楽しい番組をするので、そのときはまた一緒に遊んでください。 私は全員のことを忘れないので覚悟していてください。脅迫めいた終わり方であと味が悪いですね。最終回も泣いたフリをするという絶妙に気味の悪い終わり方だったので、それも私らしいのかなと思います。 この連載もかれこれ2年半がんばりました。1カ月ごとに振り返ることで記憶が定着して、まるで学習内容を復習しているようで楽しかったです。 思い出すことと書くことが大好きなので、この場所がなくなってしまうのもとても寂しい。今後はそのへんの紙の切れ端に、思い出したことを殴り書きしていこうと思います。違う連載ができるのが一番理想ですけれども。 貴重な時間を割いてここまで読んでくださったあなた、ありがとうございます。また会えることをお約束しますね。また。
-
 W杯で話題のラグビーを学ぼう!破壊力抜群なベスト3|『奥森皐月の公私混同<収録後記>』第29回
W杯で話題のラグビーを学ぼう!破壊力抜群なベスト3|『奥森皐月の公私混同<収録後記>』第29回季節の和菓子が食べたくなります、大人です。奥森皐月です。 私がMCを務める番組『奥森皐月の公私混同』が毎週木曜日18時にlogirlで公開されています。 このブログでは収録後記として、番組収録のウラ話や収録を通して感じたことを奥森の目線で書いています。 今回は『奥森皐月の公私混同〜ソレ、私に教えてください!〜』の8月に配信された第36回から第40回までの振り返りです。 月額990円ですが、logirlに加入すれば最新回までのエピソードがたくさん視聴できます。『奥森皐月の公私混同』以外のさまざまな番組も、もちろん観られます。 「おすすめの海外旅行先」に意外な国が登場! (写真:奥森皐月の公私混同 第36回「旅行、私に教えてください!」) 第36回のテーマは「旅行、教えてください!」。ゲストに、元JTB芸人・こじま観光さんにお越しいただきました。 仕事で地方へ行くことはたまにありますが、それ以外で旅行に行くことはめったにありません。興味がないわけではないけれど、旅行ってすぐにできないし、習慣というか行き慣れていないとなかなか気軽にできないですよね。 それに加え、私は海外にも行ったことがないので、海外旅行は自分にとってかなり遠い出来事。そのため、どういったお話が聞けるのか楽しみでした。 こじま観光さんはもともとJTBの社員として働かれていたという、「旅行好き」では済まないほど旅行・観光に詳しいお方。パッケージツアーの中身を考えるお仕事などをされていたそうです。 食事、宿泊、観光名所、などすべてがそろって初めて旅行か、と当たり前のことに気づかされました。 旅行が好きになったきっかけのお話が印象的でした。小学生のころ、お父様に「飛行機に乗ったことないよな」と言われて、ふたりでハワイに行ったとのこと。 そこから始まって、海外への興味などが湧いたとのことで、子供のころの経験が今につながっているのは素敵だと感じました。 ベスト3のコーナーでは「奥森さんに今行ってほしい国ベスト3」をご紹介いただきました。海外旅行と聞いて思いつく国はいくつかありましたが、第3位でいきなりアイルランドが出てきて驚きました。 国名としては知っているけれど、どんな国なのかは想像できないような、あまり知らない国が登場するランキングで、各地を巡られているからこそのベスト3だとよく伝わりました。 1位の国もかなり意外な場所でした。「奥森さんに」というタイトルですが、皆さんも参考になると思うので、ぜひチェックしていただきたいです。 11種類もの「釣り方」をレクチャー! (写真:奥森皐月の公私混同 第37回「釣り、私に教えてください!」) 第37回は、ゲストに釣り大好き芸人・ハッピーマックスみしまさんにお越しいただき「釣り、教えてください!」のテーマでお送りしました。 以前「魚、教えてください!」のテーマで一度配信があり、その際に少し釣りについてのパートもありましたが、今回は1時間まるまる釣りについて。 魚回のとき釣りに少し興味が湧いたのですが、やはり始め方や初心者は何からすればいいかがわからないので、そういった点も詳しく聞きたく思い、お招きしました。 大まかに海釣りや川釣りなどに分かれることはさすがにわかるのですが、釣り方には細かくさまざまな種類があることをまず教えていただきました。11種類くらいあるとのことで、知らないものもたくさんありました。釣りって幅広いですね。 みしまさんは特にルアー釣りが好きということで、スタジオに実際にルアーをお持ちいただきました。見たことないくらい大きなものもあるし、カラフルでかわいらしいものもあるし、それぞれのルアーにエピソードがあってよかったです。 また、みしまさんがご自身で○と×のボタンを持ってきてくださって、定期的にクイズを出してくれたのもおもしろかった。全体的な空気感が明るかったです。 「思い出の釣り」のベスト3は、それぞれずっしりとしたエピソードがあり、いいランキングでした。それぞれ写真も見ながら当時の状況を教えてくださったので、釣りを知らない私でも楽しむことができました。 まずは初心者におすすめだという「管理釣り場」から挑戦したいです。 鉄道好きが知る「秘境駅」は唯一無二の景色! (写真:奥森皐月の公私混同 第38回「鉄道、私に教えてください!」) 第38回のテーマは「鉄道、教えてください!」。ゲストに鉄道芸人・レッスン祐輝さんをお招きしました。 鉄道自体に興味がないわけではなく、詳しくはありませんが、好きです。移動手段で電車を使っているのはもちろん、普段乗らない電車に乗って知らない土地に行くのも楽しいと思います。 ただ、鉄道好きが多く規模が大きいことで、楽しみ方が無限にありそう。そのため、あまりのめり込んで鉄道ファンになる機会はありませんでした。 この回のゲストのレッスン祐輝さん、いい意味でめちゃくちゃに「鉄道オタク」でした。あふれ出る情報量と熱量が凄まじかった。 全国各地の鉄道を巡っているとのことで、1日に1本しか走っていない列車や、秘境を走る鉄道にも足を運んでいるそうです。 「秘境駅」というものに魅了されたとのことでしたが、たしかに写真を見ると唯一無二の景色で美しかったです。山奥で、車ですら行けない場所などもあるようで、死ぬまでに一度は行ってみたいなと思いました。 ベスト3では「癖が強すぎる終電」について紹介していただきました。レッスン祐輝さんは鉄道好きの中でも珍しい「終電鉄」らしく、これまでに見た変わった終電のお話が続々と。 終電に乗るせいで家に帰れないこともあるとおっしゃっていて、終電なんて帰るためのものだと思っていたので、なんだかおもしろかったです。 あのインドカレーは「混ぜて食べてもOK」!? (写真:奥森皐月の公私混同 第39回「カレー、私に教えてください!」) 第39回は、ゲストにカレー芸人・桑原和也さんにお越しいただき「カレー、教えてください!」をお送りしました。 私もカレーは大好き。インドカレーのお店によく行きます、ナンが食べたい日がかなりある。 「カレー」とひと言でいえど、さまざまな種類がありますよね。日本風のカレーライスから、ナンで食べるカレー、タイカレーなど。 近年流行っている「スパイスカレー」も名前としては知っていましたが、それがなんなのか聞くことができてよかったです。関西が発祥というのは初めて知りました。 カレー屋さんは東京が栄えているのだと思っていたのですが、関西のほうが名店がたくさんあるとのことで、次に関西に行ったら必ずカレーを食べようと心に決めました。 インドカレーにも種類があるらしく、たまにカレー屋さんで見かける、銀のプレートに小さい銀のボウルで複数種類のカレーが乗っていてお米が真ん中にあるようなスタイルは、南インドの「ミールス」と呼ばれるものだそうです。 今まで、ミールスは食べる順番や配分が難しい印象だったのですが、桑原さんから「混ぜて食べてもいい」というお話を聞き、衝撃を受けました。銀のプレートにひっくり返して、ひとつにしてしまっていいらしいです。 違うカレーの味が混ざることで新たな味わいが生まれ、辛さがマイルドになったり、別のおいしさが感じられるようになったりするとのこと。次にミールスに出会ったら絶対に混ぜます。 ランキングは「オススメのレトルトカレー」という実用的な情報でした。 レトルトカレーで冒険できないのは私だけでしょうか。最近はレトルトでも本当においしくていろいろな種類が発売されているようで、3つとも初めてお目にかかるものでした。 自宅で簡単に食べられるおいしいカレー、皆さんもぜひ参考にしてみてください。 9月のW杯に向けて「ラグビー」を学ぼう! (写真:奥森皐月の公私混同 第40回「ラグビー、私に教えてください!」) 8月最後の配信のテーマは「ラグビー、教えてください!」で、ゲストにラグビー二郎さんにお越しいただきました。 9月にラグビーワールドカップがあるので、それに向けて学ぼうという回。 私はもともとスポーツにまったく興味がなく、現地観戦はおろかテレビでもほとんどのスポーツを観たことがありませんでした。それが、この『公私混同』をきっかけにサッカーW杯を観て、WBCを観て、相撲を観て、と大成長を遂げました。 この調子でラグビーもわかるようになりたい。ラグビー二郎さんはラグビー経験者ということで、プレイヤー視点でのお話もあっておもしろかったです。 ルールが難しい印象ですが、あまり理解しないで観始めても大丈夫とのこと。まずはその迫力を感じるだけでも楽しめるそうです。直感的に楽しむのって大事ですよね。 前回、前々回のラグビーW杯もかなり盛り上がっていたので、要素としての情報は少しだけ知っていました。 その中で「ハカ」は、言葉としてはわかるけれど具体的になんなのかよくわからなかったので、詳しく教えていただけてうれしかったです。実演もしていただいてありがたい。 ここからのランキングが非常によかった。「ハカをやってるときの対戦相手の対応」というマニアックなベスト3でした。 ハカの最中に対戦相手が挑発的な対応をすることもあるらしく、過去に本当にあった名場面的な対応を3つご紹介いただきました。 どれも破壊力抜群のおもしろさで、ランキングタイトルを聞いたときのわくわく感をさらに上回る数々。本編でご確認いただきたい。 今年のワールドカップを観るのはもちろん、ハカのときの対戦相手の対応という細かいところまできちんと見届けたいと強く感じました。 『奥森皐月の公私混同』は毎週木曜18時に最新回が公開 奥森皐月の公私混同ではメールを募集しています。 募集内容はX(Twitter)に定期的に掲載しているので、テーマや大喜利のお題などそちらからご確認ください。 宛先は s-okumori@tv-asahi.co.jp です、たくさんのメールをお待ちしております。 logirl公式サイト内「ラジオ」のページでは毎週アフタートークが公開されています。 最近のことを話したり、あれこれ考えたりしています。無料でお聴きいただけるのでぜひ。 (写真:『奥森皐月の公私混同 アフタートーク』) 『奥森皐月の公私混同』番組公式X(Twitter)アカウントがあります。 最新情報やメール募集についてすべてお知らせしていますので、チェックしていただけるとうれしいです。 また、番組やこの収録後記の感想などは「#奥森皐月の公私混同」をつけて投稿してください。 メール募集! 今週は!1年間の振り返り放送です!!! コーナーリスナー的ベスト3 奥森さんへの質問、感想メール募集します! ▼奥森!コレ知ってんのか!ニュース▼リアクションメール▼感想メール
宛先は s-okumori@tv-asahi.co.jp メールの〆切は9/19(火)10時です! pic.twitter.com/nazDBoFSDk — 奥森皐月の公私混同は傍若無人 (@s_okumori) September 18, 2023 奥森皐月個人のX(Twitter)アカウントもあります。 番組アカウントとともにぜひフォローしてください。たまにおもしろいことも投稿しています。 キングオブコントのインタビュー動画 男性ブランコのサムネイルも漢字二文字だ、もはや漢字二文字待ちみたいになってきている、各芸人さんの漢字二文字考えたいな、そんなこと一緒にしてくれる人いないから1人で考えます、1人で色々な二文字を考えようと思います https://t.co/dfCQQVlhrg pic.twitter.com/LMpwxWhgUF — 奥森皐月 (@okumoris) September 19, 2023 『奥森皐月の公私混同』はlogirlにて毎週木曜18時に最新回が公開。 次回は、なんと収録後記の最終回です。 番組開始当初から毎月欠かさず書いてきましたが、9月末で番組が終了ということで、こちらもおしまい。とても寂しいですが、最後まで読んでいただけるとうれしいです。
-
 宮下草薙・宮下と再会!ボードゲームの驚くべき進化|『奥森皐月の公私混同<収録後記>』第28回
宮下草薙・宮下と再会!ボードゲームの驚くべき進化|『奥森皐月の公私混同<収録後記>』第28回ドライブがしたいなと思ったら車を借りてドライブをします、大人です。奥森皐月です。 私がMCを務める番組『奥森皐月の公私混同』が毎週木曜日18時にlogirlで公開されています。 このブログでは収録後記として、番組収録のウラ話や収録を通して感じたことを奥森の目線で書いています。 今回は『奥森皐月の公私混同〜ソレ、私に教えてください!〜』の7月に配信された第32回から第35回までの振り返りです。 月額990円ですが、logirlに加入すれば最新回までのエピソードがたくさん視聴できます。『奥森皐月の公私混同』以外のさまざまな番組ももちろん観られます。 かれこれ2年半もこの番組を続けています。もっとがんばってるねとか言ってほしいです。 宮下草薙・宮下が「ボードゲームの驚くべき進化」をプレゼン (写真:奥森皐月の公私混同 第32回「ボードゲーム、私に教えてください!」) 第32回のテーマは「ボードゲーム、教えてください!」。ゲストに、宮下草薙の宮下さんにお越しいただきました。 昨年のテレビ朝日の夏イベント『サマステ』ではこの番組のステージがあり、ゲストに宮下草薙さんをお招きしました。それ以来、約1年ぶりにお会いできてうれしかったです。 宮下さんといえばおもちゃ好きとして知られていますが、今回はその中でも特に宮下さんが詳しい「ボードゲーム」に特化してお話を伺いました。 巷では「ボードゲームカフェ」なるものが流行っているようですが、私はほとんどプレイしたことがありません。『人生ゲーム』すら、ちゃんとやったことがあるか記憶が曖昧。ひとりっ子だったからかしら。 そんななか、ボードゲームは驚くべき進化を遂げていることを、宮下さんが魅力たっぷりに教えてくださいました。 大人数でプレイするものが多いと勝手に思っていましたが、ひとりでできるゲームもたくさんあるそう。ひとりでボードゲームをするのは果たして楽しいのだろうかと思ってしまいましたが、実際にあるゲームの話を聞くとおもしろそうでした。購入してみたくなってしまいます。 ボードゲームのよさのひとつが、パーツや付属品などがかわいいということ。デジタルのゲームでは感じられない、手元にあるというよさは大きな魅力だと思います。見た目のかわいさから選んで始めるのも楽しそうです。 ランキングでは「もはや自分のマルチバース」ベスト3をご紹介いただきました。宮下さんが実際にプレイした中でも没入感が強くのめり込んだゲームたちは、どれも最高におもしろそうでした。 「重量級」と呼ばれる、プレイ時間が長くルールが複雑で難しいものも、現物をお持ちいただきましたが、あまりにもパーツが多すぎて驚きました。 それらをすべて理解しながら進めるのは大変だと感じますが、ゲームマスターがいればどうにかできるようです。かっこいい響き。ゲームマスター。 まずはボードゲームカフェで誰かに教わりながら始めたいと思います。本当に興味深いです、ボードゲームの世界は広い。 お城を歩くときは、自分が死ぬ回数を数える (写真:奥森皐月の公私混同 第33回「城、私に教えてください!」) 第33回は、ゲストに城マニア・観光ライターのいなもとかおりさんお越しいただき、「城、教えてください!」のテーマでお送りしました。 建物は好きなのですが歴史にあまり詳しくないため、お城についてはよくわかりません。お城好きの人は多い印象だったのですが、知識が必要そうで自分には難しいのではないかというイメージを抱いていました。 ただ、いなもとさんのお城のお話は、本当におもしろくてわかりやすかった。随所に愛があふれているけれど、初心者の私でも理解できるように丁寧に教えてくださる。熱量と冷静さのバランスが絶妙で、あっという間の1時間でした。 「城」と聞くと、名古屋城や姫路城などのいわゆる「天守」の部分を想像してしまいます。ただ、城という言葉自体の意味では、天守のまわりの壁や堀などもすべて含まれるとのこと。 土が盛られているだけでも城とされる場所もあって、そういった城跡などもすべて含めると、日本に城は4万から5万箇所あるそうです。想像していた数の100倍くらいで本当に驚きました。 いなもとさん流のお城の楽しみ方「攻め込むつもりで歩いたときに何回自分がやられてしまうか数える」というお話がとても印象的です。いかに敵に対抗できているお城かというのを実感するために、天守まで歩きながら死んでしまう回数を数えるそう。おもしろいです。 歴史の知識がなくてもこれならすぐに試せる。次にお城に行くことがあれば、私も絶対に攻める気持ち、そして敵に攻撃されるイメージをしながら歩こうと思います。 コーナーでは「昔の人が残した愛おしいらくがきベスト3」を紹介していただきました。 お城の中でも石垣が好きだといういなもとさん。石垣自体に印がつけられているというのは今回初めて知りました。 それ以外にも、お城には昔の人が残したらくがきがいくつもあって、どれもかわいらしくおもしろかったです。それぞれのお城で、そのらくがきが実際に展示されているとのことで、実物も見てみたいと思いました。 プラスチックを分解できる!? きのこの無限の可能性 (写真:奥森皐月の公私混同 第34回「きのこ、私に教えてください!」) 第34回のテーマは「きのこ、教えてください!」。ゲストに、きのこ大好き芸人・坂井きのこさんをお招きしました。 きのこって身近なのに意外と知らない。安いからスーパーでよく買うし、そこそこ食べているはずなのに、実態についてはまったく理解できていませんでした。「きのこってなんだろう」と考える機会がなかった。 坂井さんは筋金入りのきのこ好きで、幼少期から今までずっときのこに魅了されていることがお話を聞いてわかりました。 山や森などできのこを見つけると、少しうれしい気持ちになりますよね。きのこ狩りをずっとしていると珍しいきのこにもたくさん出会えるようで、単純に宝探しみたいで楽しそうだなぁと思いました。 菌類で、毒があるものもあって、鑑賞してもおもしろくて、食べることもできる。ほかに似たものがない不思議な存在だなぁと改めて思いました。 野菜だったら「葉の部分を食べている」とか「実を食べている」とかわかりやすいですけれど、きのこってじゃあなんだといわれると説明ができない。 基本の基本からきのこについてお聞きできてよかったです。菌類には分解する力があって、きのこがいるから生態系は保たれている。命が尽きたら森に葬られてきのこに分解されたい……とおっしゃっていたときはさすがに変な声が出てしまいました。これも愛のかたちですね。 ランキングコーナーの後半では、きのこのすごさが次々とわかってテンションが上がりました。 特に「プラスチックを分解できるきのこがある」という話は衝撃的。研究がまだまだ進められていないだけで、きのこには無限の可能性が秘められているのだとわかってワクワクしちゃった。 この収録を境に、きのこを少し気にしながら生きるようになった。皆さんもこの配信を観ればきのこに対する心持ちが少し変わると思います。教育番組らしさもあるいい回でした。 「神オブ神」な花火を見てみたい! (写真:奥森皐月の公私混同 第35回「花火、私に教えてください!」) 7月最後の配信のテーマは「花火、教えてください!」で、ゲストに花火マニアの安斎幸裕さんにお越しいただきました。 コロナ禍も落ち着き、今年は本格的にあちこちで花火大会が開催されていますね。8月前半の土日は全国的にも花火大会がたくさん開催される時期とのことで、その少し前の最高のタイミングでお越しいただきました。 花火大会にはそれぞれ開催される背景があり、それらを知ってから花火を見るとより楽しめるというお話が素敵でした。かの有名な長岡の花火大会も、古くからの歴史と想いがあるとのことで、見え方が変わるなぁと感じます。 それから、花火玉ひとつ作るのに相当な時間と労力がかけられていることを知って驚きました。中には数カ月かかって作られるものもあるとのことで、それが一瞬で何十発も打ち上げられるのは本当に儚いと思いました。 このお話を聞いて今年花火大会に行きましたが、一発一発にその手間を感じて、これまでと比べ物にならないくらいに感動しました。派手でない小さめの花火も愛おしく思えた。 安斎さんの花火職人さんに対するリスペクトの気持ちがひしひしと伝わってきて、とてもよかったです。 最初は、本当に尊敬しているのだなぁという印象だったのですが、だんだんその思いがあふれすぎて、推しを語る女子高校生のような口調になられていたのがおもしろかったです。見た目のイメージとのギャップもあって素敵でした。 最終的に、あまりにすごい花火のことを「神オブ神」と言ったり、花火を「神が作った子」と言ったりしていて、笑ってしまいました。 この週の「大喜利公私混同カップ2」のお題が「進化しすぎた最新花火の特徴を教えてください」だったのですが、大喜利の回答に近い花火がいくつも存在していることを教えてくださっておもしろかったです。 大喜利が大喜利にならないくらいに、花火が進化していることがわかりました。このコーナーの大喜利と現実が交錯する瞬間がすごく好き。 真夏以外にも花火大会はあり、さまざまな花火アーティストによってまったく違う花火が作られていることをこの収録で知りました。きちんと事前にいい席を取って、全力で花火を楽しんでみたいです。 成田の花火大会がどうやらかなりすごいので行ってみようと思います。「神オブ神」って私も言いたい。 『奥森皐月の公私混同』は毎週木曜18時に最新回が公開 『奥森皐月の公私混同』ではメールを募集しています。 募集内容はTwitterに定期的に掲載しているので、テーマや大喜利のお題などそちらからご確認ください。 宛先は s-okumori@tv-asahi.co.jp です、たくさんのメールをお待ちしております。 logirl公式サイト内「ラジオ」のページでは、毎週アフタートークが公開されています。 ゆったり作家のみなさんとおしゃべりしています。無料でお聴きいただけるのでぜひ。 (写真:『奥森皐月の公私混同 アフタートーク』) 『奥森皐月の公私混同』番組公式Twitterアカウントがあります。 最新情報やメール募集についてすべてお知らせしていますので、チェックしていただけるとうれしいです。 また、番組やこの収録後記の感想などは「#奥森皐月の公私混同」をつけて投稿してください。 メール募集! テーマは【カレー
】【ラグビー
】です! ▼奥森!コレ知ってんのか!ニュース▼ゲストへの質問▼大喜利公私混同カップ2▼リアクションメール▼感想メール
宛先は s-okumori@tv-asahi.co.jp メールの〆切は8/22(火)10時です! pic.twitter.com/xJrDL41Wc9 — 奥森皐月の公私混同は傍若無人 (@s_okumori) August 20, 2023 奥森皐月個人のTwitterアカウントもあります。 番組アカウントとともにぜひフォローしてください。たまにおもしろいことも投稿しています。 大喜る人たち生配信を真剣に見ている奥森皐月。お前は中途半端だからサッカー選手にはなれないと残酷な言葉で説く父親、聞く耳を持たない小2くらいの息子、黙っている妹と母親の4人家族。啜り泣くギャル。この3組がお客さんのカレー屋さんがさっきまであった。出てしまったので今はもうない。 — 奥森皐月 (@okumoris) August 20, 2023 『奥森皐月の公私混同』はlogirlにて毎週木曜18時に最新回が公開。 次回は「未体験のジャンルからやってくる強者たち」を中心にお送りします。お楽しみに。
AKB48 Team 8 私服グラビア
大好評企画が復活!AKB48 Team 8メンバーひとりずつの撮り下ろし連載
【会員限定】AKB48 Team 8 私服グラビア Extra
【会員限定】AKB48 Team 8メンバーひとりずつの撮り下ろし連載
生きづらさを乗り越える「大人のためのマンガ入門」
仕事、恋愛、家族、結婚……大人のありきたりでありがちな悩みや生きづらさと向き合い、乗り越えていくためのヒントを探るマンガレビュー連載(文=山本大樹)
-
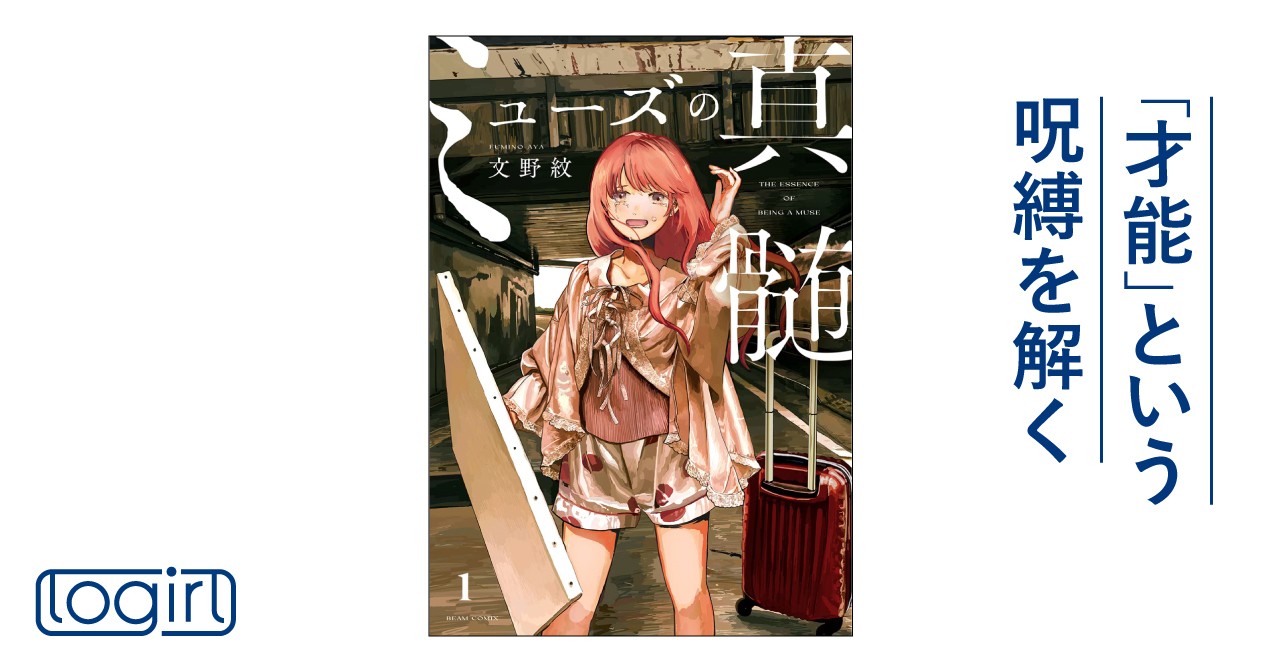 「才能」という呪縛を解く ミューズの真髄
「才能」という呪縛を解く ミューズの真髄【連載】生きづらさを乗り越える「大人のためのマンガ入門」 仕事、恋愛、家族、結婚……大人のありきたりでありがちな悩みや生きづらさと向き合い、乗り越えていくためのヒントを探るマンガレビュー連載。月1回程度更新。 『ブルー・ピリオド』をはじめ美大受験モノマンガがブームを呼んでいる昨今。特に芸術というモチーフは、その核となる「才能とは何か?」を掘り下げることで、主人公の自意識をめぐるドラマになりやすい。 文野紋『ミューズの真髄』も、一度は美大受験に失敗した会社員の主人公・瀬野美優が、一念発起して再び美大受験を志し、自分を肯定するための道筋を探るというストーリーだ。しかし、よくある美大受験マンガかと思ってページをめくっていくと、「才能」の扱い方に本作の特筆すべき点を見出すことができる。 「美大に落ちたあの日。“特別な私”は、死んでしまったから。仕方がないのです。“凡人”に成り下がった私は、母の決めた職場で、母の決めた服を着て、母が自慢できるような人と母が言う“幸せ”を探すんです。でも、だって、仕方ない、を繰り返しながら。」 (『ミューズの真髄』あらすじより) 主人公の美優は「どこにでもいる平凡な私」から、自分で自分を肯定するために、少しずつ自分の意志を周囲に示すようになる。芸術の道に進むことに反対する母親のもとを飛び出し、自尊心を傷つける相手にはNOを突きつけ、自分の進むべき道を自ら選び取っていく。しかし、心の奥深くに根づいた自己否定の考えはそう簡単に変えることはできない。自尊心を取り戻す過程で立ち塞がるのが「才能」の壁だ。 24歳という年齢で美術予備校に飛び込んだ美優は、最初の作品講評で57人中47位と悲惨な成績に終わる。自分よりも年下の生徒たちが才能を見出されていくなかで、自分の才能を見つけることができない美優。その後挫折を繰り返しながら、予備校の講師である月岡との出会いによって少しずつ自分を肯定し、前向きに進んでいく姿には胸が熱くなる。 「私は地獄の住人だ あの人みたいにあの子みたいに漫画みたいに 才能もないし美術で生きる資格はないのかもしれない バカで中途半端で恋愛脳で人の影響ばかり受けてごめんなさい でももがいてみてもいいですか? 執着してみていいですか?」 冒頭で述べたとおり、本作の「才能」への向き合い方を端的に示しているのがこのセリフである。才能がなくても好きなことに執着する──功利主義の社会では蔑まれがちなこのスタンスこそが、他者の否定的な視線から自分を守り、自分の人生を肯定していくためには重要だ。才能に執着するのではなく、「絵」という自分の愛する対象に執着する。その執着が自分を愛することにつながるのだ。それは「好きなことを続けられるのも才能」のような安い言葉では語り切れるものではない。 才能と自意識の話に収斂していく美大受験マンガとは別の視座を、美優の生き方は示してくれる。そして、美優にとっての「美術」と同じように、執着できる対象を見つけることは、「才能」の物語よりも私たちにとっては遥かに重要なことのはずである。 文=山本大樹 編集=田島太陽 山本大樹 編集/ライター。1991年、埼玉県生まれ。明治大学大学院にて人文学修士(映像批評)。QuickJapanで外部編集・ライターのほか、QJWeb、BRUTUS、芸人雑誌などで執筆。(Twitter/はてなブログ)
-
 勝ち負けから離れて生きるためには? 真造圭伍『ひらやすみ』
勝ち負けから離れて生きるためには? 真造圭伍『ひらやすみ』【連載】生きづらさを乗り越える「大人のためのマンガ入門」 仕事、恋愛、家族、結婚……大人のありきたりでありがちな悩みや生きづらさと向き合い、乗り越えていくためのヒントを探るマンガレビュー連載。月1回程度更新。 30代を迎えて、漠然とした焦りを感じることが増えた。20代のころに感じていた将来への不安からくる焦りとはまた種類の違う、現実が見えてきたからこその焦りだ。 周囲の同世代が着々と実績を残していくなか、自分だけが取り残されているような感覚。いつまで経っても増えない収入、一年後の見通しすらも立たない生活……焦りの原因を数え始めたらキリがない。 真造圭伍のマンガ『ひらやすみ』は、30歳のフリーター・ヒロト君と従姉妹のなつみちゃんの平屋での同居生活を描いたモラトリアム・コメディだ。 定職に就かずに30歳を迎えてもけっして焦らず、のんびりと日々の生活を愛でながら過ごすヒロト君の生き方は、素直にうらやましく思う。身の回りの風景の些細な変化や季節の移り変わりを感じながら、家族や友達を思いやり、目の前のイベントに全力を注ぐ。どうしても「こんなふうに生きられたら」と考えてしまうくらい、魅力的な人物だ。 そんなヒロト君も、かつては芸能事務所に所属し、俳優として夢を追いかけていた時期もあった。高校時代には親友のヒデキと映画を撮った経験もあり、純粋に芝居を楽しんでいたヒロト君。芸能事務所のマネージャーから「なんで俳優になろうと思ったの?」と聞かれ、「あ、オレは楽しかったからです!演技するのが…」と答える。 「でも、これからは楽しいだけじゃなくなるよ──」 「売れたら勝ち、それ以外は負けって世界だからね」 数年後、役者を辞めたヒロト君は、漫画家を目指す従姉妹のなつみちゃんの姿を見て、かつて自分がマネージャーから言われた言葉を思い出す。純粋に楽しんでいたはずのことも、社会では勝ち負け──経済的な成功/失敗に回収されていく。出版社にマンガを持ち込んだなつみちゃんも、もしデビューすれば商業誌での戦いを強いられていくだろう。 運よく好きなことや向いていることを仕事にできたとしても、資本主義のルールの中で暮らしている以上、競争から距離を置くのはなかなか難しい。結果を出せない人のところにいつまでも仕事が回ってくることはないし、自分の代わりはいくらでもいる。嫌でも他者との勝負の土俵に立たされることになるし、純粋に「好き」だったころの気持ちとはどんどんかけ離れていく。 「アイツ昔から不器用でのんびり屋で勝ち負けとか嫌いだったじゃん? 業界でそういうのいっぱい経験しちまったんだろーな。」 ヒロト君の親友・ヒデキは、ヒロトが俳優を辞めた理由をそう推察する。私が身を置いている出版業界でも、純粋に本や雑誌が好きでこの業界を志した人が挫折して去っていくのをたくさん見てきた。でも、彼らが負けたとは思わないし、なんとか端っこで食っているだけの私が勝っているとももちろん思わない。勝ち/負けという物差しで物事を見るとき、こぼれ落ちるものはあまりに多い。むしろ、好きだったはずのことが本当に嫌いにならないうちに、別の仕事に就いたほうが幸せだと思う。 私も勝ち負けが本当に苦手だ。優秀な同業者も目の前でたくさん見てきて、同じ土俵に上がったらまず自分では勝負にならないということも30歳を過ぎてようやくわかった。それでも続けているのは、勝ち負けを抜きにして、いつか純粋にこの仕事が好きになれる日が来るかもしれないと思っているからだ。もちろん、仕事が嫌いになる前に逃げる準備ももうできている。 暗い話になってしまったが、『ひらやすみ』のヒロト君の生き方は、競争から逃れられない自分にとって、大きな救いになっている。なつみちゃんから「暇人」と罵られ、見知らぬ人からも「みんながみんなアナタみたいに生きられると思わないでよ」と言われるくらいののんびり屋でも、ヒロト君の周囲には笑顔が絶えない。自分ひとりの意志で勝ち負けから逃れられないのであれば、せめてまわりにいる人だけでも大切にしていきたい。そうやって自分の生活圏に大切なものをちゃんと作っておけば、いつでも競争から降りることができる。『ひらやすみ』は、そんな希望を見せてくれる作品だった。 文=山本大樹 編集=田島太陽 山本大樹 編集/ライター。1991年、埼玉県生まれ。明治大学大学院にて人文学修士(映像批評)。QuickJapanで外部編集・ライターのほか、QJWeb、BRUTUS、芸人雑誌などで執筆。(Twitter/はてなブログ)
-
 克明に記録されたコロナ禍の息苦しさ──冬野梅子『まじめな会社員』
克明に記録されたコロナ禍の息苦しさ──冬野梅子『まじめな会社員』【連載】生きづらさを乗り越える「大人のためのマンガ入門」 仕事、恋愛、家族、結婚……大人のありきたりでありがちな悩みや生きづらさと向き合い、乗り越えていくためのヒントを探るマンガレビュー連載。月1回程度更新。 5月に『コミックDAYS』での連載が完結した冬野梅子『まじめな会社員』。30歳の契約社員・菊池あみ子を取り巻く苦しい現実、コロナ禍での転職、親の介護といった環境の変化をシビアに描いた作品だ。周囲のキラキラした友人たちとの比較、自意識との格闘でもがく姿がSNSで話題を呼び、あみ子が大きな選択を迫られる最終回は多くの反響を集めた。 「コロナ禍における、新種の孤独と人生のたのしみを、「普通の人でいいのに!」で大論争を巻き起こした新人・冬野梅子が描き切る!」と公式の作品紹介にもあるように、本作は2020年代の社会情勢を忠実に反映している。疫病はさまざまな局面で社会階層の分断を生み出したが、特に本作で描かれているのは「働き方」と「人間関係」の変化と分断である。『まじめな会社員』は、疫禍による階層の分断を克明に描いた作品として貴重なサンプルになるはずだ。 2022年5月末現在、コロナがニュースの時間のほとんどを占めていた時期に比べると、世間の空気は少し緩やかになりつつある。飲食店は普通にアルコールを提供しているし、休日に友達と遊んだり、ライブやコンサートに出かけることを咎められるような空気も薄まりつつある。しかし、過去の緊急事態宣言下の生活で感じた孤独や息苦しさはそう簡単に忘れられるものではないだろう。 たとえば、スマホアプリ開発会社の事務職として働くあみ子は、コロナ禍の初期には在宅勤務が許されていなかった。 「持病なしで子供なしだとリモートさせてもらえないの?」「私って…お金なくて旅行も行けないのに通勤はさせられてるのか」(ともに2巻)とリモートワークが許される人々との格差を嘆く場面も描かれている。 そして、あみ子の部署でもようやくリモートワークが推奨されるようになると、それまで事務職として上司や営業部のサポートを押しつけられていた今までを振り返り、飲食店やライブハウスなどの苦境に思いを巡らせつつも、つい「こんな生活が続けばいいのに…」とこぼしてしまう。 自由な働き方に注目が集まる一方で、いわゆるエッセンシャルワーカーはもちろん、社内での立場や家族の有無によって出勤を強いられるケースも多かった。仕事上における自身の立場と感染リスクを常に天秤にかけながら働く生活に、想像以上のストレスを感じた人も多かったはずだ。 「抱き合いたい「誰か」がいないどころか 休日に誰からも連絡がないなんていつものこと おうち時間ならずっとやってる」(2巻) コロナによる分断は、働き方の面だけではなく人間関係にも侵食してくる。コロナ禍の初期には「自粛中でも例外的に会える相手」の線引きは、限りなく曖昧だった。独身・ひとり暮らしのあみ子は誰とも会わずに自粛生活を送っているが、インスタのストーリーで友人たちがどこかで会っているのを見てモヤモヤした気持ちを抱える。 「コロナだから人に会えないって思ってたけど 私以外のみんなは普通に会ってたりして」「綾ちゃんだって同棲してるし ていうか世の中のカップルも馬鹿正直に自粛とかしてるわけないし」(2巻) 相互監視の状況に陥った社会では、当事者同士の関係性よりも「(世間一般的に)会うことが認められる関係性かどうか」のほうが判断基準になる。家族やカップルは認められても、それ以外の関係性だと、とたんに怪訝な目を向けられる。人間同士の個別具体的な関係性を「世間」が承認するというのは極めておぞましいことだ。「家族」や「恋人」に対する無条件の信頼は、家父長制的な価値観にも密接に結びついている。 またいつ緊急事態宣言が出されるかわからないし、そうなれば再び社会は相互監視の状況に陥るだろう。感染者数も落ち着いてきた今のタイミングだからこそ本作を通じて、当時は語るのが憚られた個人的な息苦しさや階層の分断に改めて目を向けておきたい。 文=山本大樹 編集=田島太陽 山本大樹 編集/ライター。1991年、埼玉県生まれ。明治大学大学院にて人文学修士(映像批評)。QuickJapanで外部編集・ライターのほか、QJWeb、BRUTUS、芸人雑誌などで執筆。(Twitter/はてなブログ)
L'art des mots~言葉のアート~
企画展情報から、オリジナルコラム、鑑賞記まで……アートに関するよしなしごとを扱う「L’art des mots~言葉のアート~」
-
 【News】西洋絵画の500年の歴史を彩った巨匠たちの傑作が、一挙来日!『メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年』が大阪市立美術館・国立新美術館にて開催!
【News】西洋絵画の500年の歴史を彩った巨匠たちの傑作が、一挙来日!『メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年』が大阪市立美術館・国立新美術館にて開催!先史時代から現代まで5000年以上にわたる世界各地の考古遺物・美術品150万点余りを有しているメトロポリタン美術館。 同館を構成する17部門のうち、ヨーロッパ絵画部門に属する約2500点の所蔵品から、選りすぐられた珠玉の名画65 点(うち46 点は日本初公開)を展覧する『メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年』が、11月に大阪、来年2月には東京で開催されます。 この展覧会は、フラ・アンジェリコ、ラファエロ、クラーナハ、ティツィアーノ、エル・グレコから、カラヴァッジョ、ジョルジュ・ド・ラ・トゥール、レンブラント、 フェルメール、ルーベンス、ベラスケス、プッサン、ヴァトー、ブーシェ、そしてゴヤ、ターナー、クールベ、マネ、モネ、ルノワール、ドガ、ゴーギャン、ゴッホ、セザンヌに至るまでを、時代順に3章で構成。 第Ⅰ章「信仰とルネサンス」では、イタリアのフィレンツェで15世紀初頭に花開き、16世紀にかけてヨーロッパ各地で隆盛したルネサンス文化を代表する画家たちの名画、フラ・アンジェリコ《キリストの磔刑》、ディーリック・バウツ《聖母子》、ティツィアーノ・ヴェチェッリオ《ヴィーナスとアドニス》など、計17点を観ることが出来ます。 第Ⅱ章「絶対主義と啓蒙主義の時代」では、絶対主義体制がヨーロッパ各国で強化された17世紀から、啓蒙思想が隆盛した18世紀にかけての美術を、各国の巨匠たちの名画30点により紹介。カラヴァッジョ《音楽家たち》、ヨハネス・フェルメール《信仰の寓意》、レンブラント・ファン・レイン《フローラ》などを御覧頂けます。 第Ⅲ章「革命と人々のための芸術」では、レアリスム(写実主義)から印象派へ……市民社会の発展を背景にして、絵画に数々の革新をもたらした19世紀の画家たちの名画、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー《ヴェネツィア、サンタ・マリア・デッラ・サルーテ聖堂の前廊から望む》、オーギュスト・ルノワール《ヒナギクを持つ少女》、フィンセント・ファン・ゴッホ《花咲く果樹園》、さらには日本初公開となるクロード・モネ《睡蓮》など、計18点が展覧されます。 15世紀の初期ルネサンスの絵画から19世紀のポスト印象派まで……西洋絵画の500 年の歴史を彩った巨匠たちの傑作を是非ご覧下さい! 『メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年』 ■大阪展 会期:2021年11月13日(土)~ 2022年1月16日(日) 会場:大阪市立美術館(〒543-0063大阪市天王寺区茶臼山町1-82) 主催:大阪市立美術館、メトロポリタン美術館、日本経済新聞社、テレビ大阪 後援:公益財団法人 大阪観光局、米国大使館 開館時間:9:30ー17:00 ※入館は閉館の30分前まで 休館日:月曜日( ただし、1月10日(月・祝)は開館)、年末年始(2021年12月30日(木)~2022年1月3日(月)) 問い合わせ:TEL:06-4301-7285(大阪市総合コールセンターなにわコール) ■東京展 会期:2022年2月9日(水)~5月30日(月) 会場:国立新美術館 企画展示室1E(〒106-8558東京都港区六本木 7-22-2) 主催:国立新美術館、メトロポリタン美術館、日本経済新聞社 後援:米国大使館 開館時間:10:00ー18:00( 毎週金・土曜日は20:00まで)※入場は閉館の30分前まで 休館日:火曜日(ただし、5月3日(火・祝)は開館) 問い合わせ:TEL:050-5541-8600( ハローダイヤル) text by Suzuki Sachihiro
-
 【News】約3,000点の新作を展示。国立新美術館にて「第8回日展」が開催!
【News】約3,000点の新作を展示。国立新美術館にて「第8回日展」が開催!10月29日(金)から11月21日まで、国立新美術館にて「第8回日展」が開催されます。日本画、洋画、彫刻、工芸美術、書の5部門に渡って、秋の日展のために制作された現代作家の新作、約3,000点が一堂に会します。 明治40年の第1回文展より数えて、今年114年を迎える日本最大級の公募展である日展は、歴史的にも、東山魁夷、藤島武二、朝倉文夫、板谷波山など、多くの著名な作家を生み出してきました。 展覧会名:第8回 日本美術展覧会 会 場:国立新美術館(東京都港区六本木7-22-2) 会 期:2021年10月29日(金)~11月21日(日)※休館日:火曜日 観覧時間:午前10時~午後6時(入場は午後5時30分まで) 主 催:公益社団法人日展 後 援:文化庁/東京都 入場料・チケットや最新の開催情報は「日展ウェブサイト」をご確認下さい (https://nitten.or.jp/) 展示される作品は作家の今を映す鏡ともいえ、作品から世相や背景など多くのことを読み取る楽しさもあります。 あらゆるジャンルをいっぺんに楽しめる機会、新たな日本の美術との出会いに胸躍ること必至です! 東京展の後は、京都、名古屋、大阪、安曇野、金沢の5か所を巡回(予定)します。 日本画 会場風景 2020年 洋画 会場風景 2020年 彫刻 会場風景 2020年 工芸美術 会場風景 2020年 書 会場風景 2020年 text by Suzuki Sachihiro
-
 【News】和田誠の全貌に迫る『和田誠展』が開催!
【News】和田誠の全貌に迫る『和田誠展』が開催!イラストレーター、グラフィックデザイナー和田誠わだまこと(1932-2019)の仕事の全貌に迫る展覧会『和田誠展』が、今秋10月9日から東京オペラシティアートギャラリーにて開催される。 和田誠 photo: YOSHIDA Hiroko ©Wada Makoto 和田誠の輪郭をとらえる上で欠くことのできない約30のトピックスを軸に、およそ2,800点の作品や資料を紹介。様々に創作活動を行った和田誠は、いずれのジャンルでも一級の仕事を残し、高い評価を得ている。 展示室では『週刊文春』の表紙の仕事はもちろん、手掛けた映画の脚本や絵コンテの展示、CMや子ども向け番組のアニメーション上映も予定。 本展覧会では和田誠の多彩な作品に、幼少期に描いたスケッチなども交え、その創作の源流をひも解く。 ▽和田誠の仕事、総数約2,800点を展覧。書籍と原画だけで約800点。週刊文春の表紙は2000号までを一気に展示 ▽学生時代に制作したポスターから初期のアニメーション上映など、貴重なオリジナル作品の数々を紹介 ▽似顔絵、絵本、映画監督、ジャケット、装丁……など、約30のトピックスで和田誠の全仕事を紹介 会場は【logirl】『Musée du ももクロ』でも何度も訪れている、初台にある「東京オペラシティアートギャラリー」。 この秋注目の展覧会!あなたの芸術の秋を「和田誠の世界」で彩ろう。 【開催概要】展覧会名:和田誠展( http://wadamakototen.jp/ ) 会期:2021年10月9日[土] - 12月19日[日] *72日間 会場:東京オペラシティ アートギャラリー 開館時間:11:00-19:00(入場は18:30まで) 休館日:月曜日 入場料:一般1,200[1,000]円/大・高生800[600]円/中学生以下無料 主催:公益財団法人 東京オペラシティ文化財団 協賛:日本生命保険相互会社 特別協力:和田誠事務所、多摩美術大学、多摩美術大学アートアーカイヴセンター 企画協力:ブルーシープ、888 books お問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル) *同時開催「収蔵品展072難波田史男 線と色彩」「project N 84 山下紘加」の入場料を含みます。 *[ ]内は各種割引料金。障害者手帳をお持ちの方および付添1名は無料。割引の併用および入場料の払い戻しはできません。 *新型コロナウイルス感染症対策およびご来館の際の注意事項は当館ウェブサイトを( https://www.operacity.jp/ag/ )ご確認ください。 ▽和田誠(1932-2019) 1936年大阪に生まれる。多摩美術大学図案科(現・グラフィックデザイン学科)を卒業後、広告制作会社ライトパブリシティに入社。 1968年に独立し、イラストレーター、グラフィックデザイナーとしてだけでなく、映画監督、エッセイ、作詞・作曲など幅広い分野で活躍した。 たばこ「ハイライト」のデザインや「週刊文春」の表紙イラストレーション、谷川俊太郎との絵本や星新一、丸谷才一など数多くの作家の挿絵や装丁などで知られる。 報知映画賞新人賞、ブルーリボン賞、文藝春秋漫画賞、菊池寛賞、毎日デザイン賞、講談社エッセイ賞など、各分野で数多く受賞している。 仕事場の作業机 photo: HASHIMOTO ©Wada Makoto 『週刊文春』表紙 2017 ©Wada Makoto 『グレート・ギャツビー』(訳・村上春樹)装丁 2006 中央公論新社 ©Wada Makoto 『マザー・グース 1』(訳・谷川俊太郎)表紙 1984 講談社 ©Wada Makoto text by Suzuki Sachihiro
logirl staff voice
logirlのスタッフによるlogirlのためのtext
-
 「誰も観たことのないバラエティを」。『ももクロChan』10周年記念スタッフ座談会
「誰も観たことのないバラエティを」。『ももクロChan』10周年記念スタッフ座談会ももいろクローバーZの初冠番組『ももクロChan』が昨年10周年を迎えた。 この番組が女性アイドルグループの冠番組として異例の長寿番組となったのは、ただのアイドル番組ではなく、"バラエティ番組”として破格におもしろいからだ。 ももクロのホームと言っても過言ではないバラエティ番組『ももクロChan』。 彼女たちが10代半ばのころから、その成長を見続けてきたプロデューサーの浅野祟氏、吉田学氏、演出の佐々木敦規氏の3人が集まり、番組への思い、そしてももクロの魅力を存分に語ってくれた。 浅野 崇(あさの・たかし)1970年、千葉県出身。プロデューサー。 <現在の担当番組> 『ももクロChan』 『ももクロちゃんと!』 『Musee du ももクロ』 『川上アキラの人のふんどしでひとりふんどし』、など 吉田 学(よしだ・まなぶ)1978年、東京都出身。プロデューサー。 <現在の担当番組> 『ももクロChan~Momoiro Clover Z Channel~』 『ももクロちゃんと!』 『川上アキラの人のふんどしでひとりふんどし』 『Musée du ももクロ』、など 佐々木 敦規(ささき・あつのり)1967年、東京都出身。ディレクター。 有限会社フィルムデザインワークス取締役 「ももクロはアベンジャーズ」。そのずば抜けたバラエティ力の秘密 ──最近、ももクロのメンバーたちが、個々でバラエティ番組に出演する機会が増えていますね。 浅野 ようやくメンバー一人ひとりのバラエティ番組での強さに、各局のディレクターやプロデューサーが気づいてくれたのかもしれないですね。間髪入れずに的確なコメントやリアクションをしてて、さすがだなと思って観てます。 佐々木 彼女たちはソロでもアリーナ公演を完売させるアーティストですけど、バラエティタレントとしてもその実力は突き抜けてますから。 浅野 あれだけ大きなライブ会場で、ひとりしゃべりしても飽きがこないのは、すごいことだなと改めて思いますよ。 佐々木 そして、4人そろったときの爆発力がある。それはまず、バラエティの天才・玉井詩織がいるからで。器用さで言わせたら、彼女はめちゃくちゃすごい。百田夏菜子、高城れに、佐々木彩夏というボケ3人を、転がすのが本当にうまくて助かってます。 昔は百田の天然が炸裂して、高城れにがボケにいくスタイルだったんですが、いつからか佐々木がボケられるようになって、ももクロは最強になったと思ってます。 キラキラしたぶりっ子アイドル路線をやりたがっていたあーりんが、ボケに回った。それどころか、今ではそのポジションに味をしめてる。昔はコマネチすらやらなかった子なのに、ビックリですよ(笑)。 (写真:佐々木ディレクター) ──そういうメンバーの変化や成長を見られるのも、10年以上続く長寿番組だからこそですね。 吉田 昔からライブの舞台裏でもずっとカメラを回させてくれたおかげで、彼女たちの成長を記録できました。結果的に、すごくよかったですね。 ──ずっとももクロを追いかけてきたファンは思い出を振り返れるし、これからももクロを知る人たちも簡単に過去にアクセスできる。「テレ朝動画」で観られるのも貴重なアーカイブだと思います。 佐々木 『ももクロChan』は、早見あかりの脱退なども撮っていて、楽しいときもつらいときも悲しいときも、ずっと追っかけてます。こんな大事な仕事は、途中でやめるわけにはいかないですよ。彼女たちの成長ドキュメンタリーというか、ロードムービーになっていますから。 唯一無二のコンテンツになってしまったので、ももクロが活動する限りは『ももクロChan』も続けたいですね。 吉田 これからも続けるためには、若い世代にもアピールしないといけない。10代以下の子たちにも「なんかおもしろいお姉ちゃんたち」と認知してもらえるように、我々もがんばらないと。 (写真:吉田プロデューサー) 浅野 彼女たちはまだまだ伸びしろありますからね。個々でバラエティ番組に出たり、演技のお仕事をしたり、ソロコンをやったりして、さらにレベルアップしていく。そんな4人が『ももクロChan』でそろったとき、相乗効果でますますおもしろくなるような番組をこれからも作っていきたいです。 佐々木 4人は“アベンジャーズ"っぽいなと最近思うんだよね。 浅野 わかります。 ──アベンジャーズ! 個人的に、ももクロって令和のSMAPや嵐といったポジションすら狙えるのではないか、と妄想したりするのですが。 浅野 あそこまで行くのはとんでもなく難しいと思いますが……。でも佐々木さんの言うとおりで、最近4人全員集まったときに、スペシャルな瞬間がたまにあるんですよ。そういう大物の華みたいな部分が少しずつ見えてきたというか。 佐々木 そうなんだよねぇ。ももクロの4人はやたらと仲がいいし、本人たちも30歳、40歳、50歳になっても続けていくつもりなので、さらに化けていく彼女たちを撮っていかなくちゃいけないですね。 早見あかりが抜けて、自立したももクロ (写真:浅野プロデューサー) ──先ほど少し早見あかりさん脱退のお話が出ましたけど、やはり印象深いですか。 吉田 そうですね。そのとき僕はまだ『ももクロChan』に関わってなかったんですが、自分の局の番組、しかも動画配信でアイドルの脱退の告白を撮ったと聞いて驚きました。 当時はAKB48がアイドル界を席巻していて、映画『DOCUMENTARY of AKB48』などでアイドルの裏側を見せ始めた時期だったんです。とはいえ、脱退の意志をメンバーに伝えるシーンを撮らせてくれるアイドルは画期的でした。 佐々木 ももクロは最初からリミッターがほとんどないグループだからね。チーフマネージャーの川上アキラさんが攻めた人じゃないですか。だって、自分のワゴン車に駆け出しのアイドル乗っけて、全国のヤマダ電機をドサ回りするなんて、普通考えられないでしょう(笑)。夜の駐車場で車のヘッドライトを背に受けながらパフォーマンスしてたら、そりゃリミッターも外れますよ。 (写真:『ももクロChan』#11) ──アイドルの裏側を見せる番組のコンセプトは、当初からあったんですか? 佐々木 そうですね、ある程度狙ってました。そもそも僕と川上さんが仲よしなのは、プロレスや格闘技っていう共通の熱狂している趣味があるからなんですけど。 当時流行ってた総合格闘技イベント『PRIDE』とかって、ブラジリアントップファイターがリング上で殺し合いみたいなガチの真剣勝負をしてたんですよ。そんな血気盛んな選手が闘い終わってバックヤードに入った瞬間、故郷のママに「勝ったよママ! 僕、勝ったんだよ!」って電話しながら泣き出すんです。 ああいうファイターの裏側を生々しく映し出す映像を見て、表と裏のコントラストには何か新しい魅力があるなと、僕らは気づいて。それで、川上さんと「アイドルで、これやりましょうよ!」って話がスムーズにいったんです。 吉田 ライブ会場の楽屋などの舞台裏に定点カメラを置いてみる「定点観測」は、ももクロの裏の部分が見える代表的なコーナーになりました。ステージでキラキラ輝くももクロだけじゃなくて、等身大の彼女たちが見られるよう、早いうちに体制を整えられたのもありがたかったですね。 ──番組開始時からももクロのバラエティにおけるポテンシャルは図抜けてましたか? 佐々木 いや、最初は普通の高校生でしたよ。だから、何がおもしろくて何がウケないのか、何が褒められて何がダメなのか。そういう基礎から丁寧に教えました。 ──転機となったのは? 佐々木 やはり早見あかりが抜けたことですね。当時は早見が最もバラエティ力があったんです。裏リーダーとして場を回してくれたし、ほかのメンバーも彼女に頼りきりだった。我々も困ったときは早見に振ってました。 だから早見がいなくなって最初の収録は、残ったメンバーでバラエティを作れるのか正直不安で。でも、いざ収録が始まったら、めちゃめちゃおもしろかったんですよ。「お前らこんなにできたのっ!?」といい意味で裏切られた。 早見に甘えられなくなり、初めて自立してがんばるメンバーを見て、「この子たちとおもしろいバラエティ作るぞ!」と僕もスイッチが入りましたね。 あと、やっぱり2013年ごろからよく出演してくれるようになった東京03の飯塚(悟志)くんが、ももクロと相性抜群だったのも大きかった。彼のシンプルに一刀両断するツッコミのおかげで、ももクロはボケやすくなったと思います。 吉田 飯塚さんとの絡みで学ぶことも多かったですよね。 佐々木 トークの間合いとか、ボケの伏線回収的な方程式なんかを、お笑い界のトップランナーと実戦の中で知っていくわけですから、貴重な経験ですよね。それは僕ら裏方には教えられないことでした。 浅野 今のももクロって、収録中に何かおもしろいことが起きそうな気配を感じると、各々の役割を自覚して、フィールドに散らばっていくイメージがあるんですよね。 言語化はできないんだろうけど、彼女たちなりに、ももクロのバラエティ必勝フォーメーションがいくつかあるんでしょう。状況に合わせて変化しながら、みんなでゴールを目指してるなと感じてます。 ももクロのバラエティ史に残る奇跡の数々 ──バラエティ番組でのテクニックは芸人顔負けのももクロですが、“笑いの神様”にも愛されてますよね。何気ないスタジオ収録回でも、ミラクルを起こすのがすごいなと思ってて。 佐々木 最近で言うと、「4人連続ピンポン球リフティング」は残り1秒でクリアしてましたね。「持ってる」としか言えない。ああいう瞬間を見るたびに、やっぱりスターなんだなぁと思いますね。 浅野 昔、公開収録のフリースロー対決(#246)で、追い込まれた百田さんが、うしろ向きで投げて入れるというミラクルもありました。 あと、「大人検定」という企画(#233)で、高城さんがタコの踊り食いをしたら、鼻に足が入ってたのも忘れられない(笑)。 吉田 あの高城さんはバラエティ史に残る映像でしたね(笑)。 個人的にはフットサルも印象に残ってます。中学生の全国3位の強豪チームとやって、善戦するという。 佐々木 なんだかんだ健闘したんだよね。しかも終わったら本気で悔しがって、もう一回やりたいとか言い出して。 今度のオンラインライブに向けて、過去の名シーンを掘ってみたんですが、そういうミラクルがたくさんあるんですよ。 浅野 今ではそのラッキーが起こった上で、さらにどう転していくかまで彼女たちが自分で考えて動くので、昔の『ももクロChan』以上におもしろくなってますよね。 写真:『ももクロChan』#246) (写真:『ももクロChan』#233) ──皆さんのお話を聞いて、『ももクロChan』はアイドル番組というより、バラエティ番組なんだと改めて思いました。 佐々木 そうですね。誤解を恐れずに言えば、僕らは「ももクロなしでも通用するバラエティ」を作るつもりでやってるんです。 お笑いとしてちゃんと観られる番組がまずあって、その上でとんでもないバラエティ力を持ったももクロががんばってくれる。そりゃおもしろくなりますよね。 ──アイドルにここまでやられたら、ゲストの芸人さんたちも大変じゃないかと想像します。 佐々木 そうでしょうね(笑)。平成ノブシコブシの徳井(健太)くんが「バラエティ番組いろいろ出たけど、今でも緊張するのは『ゴッドタン』と『ももクロChan』ですよ」って言ってくれて。お笑いマニアの彼にそういう言葉をもらえたのは、ありがたかったなぁ。 誰も見たことのない破格のバラエティ番組を届ける ──そして11月6日(土)には、『テレビ朝日 ももクロChan 10周年記念 オンラインプレミアムライブ!~最高の笑顔でバラエティ番組~』を開催しますね。 吉田 もともとは去年やるつもりでしたが、コロナ禍で自粛することになり、11周年の今年開催となりました。これから先『ももクロChan』を振り返ったとき、このイベントが転機だったと思えるような特別な日にしたいですね。 浅野 歌あり、トークあり、コントあり、ゲームあり。なんでもありの総合バラエティ番組を作るつもりです。 2時間の生配信でゲストも来てくださるので、通常回以上に楽しいのはもちろん、ライブならではのハプニングも期待しつつ……。まぁプロデューサーとしては、いろんな意味でドキドキしてますけど(苦笑)。 佐々木 ライブタイトルに「バラエティ番組」と入れて、我々も自分でハードル上げてるからなぁ(笑)。でも「バラエティを売りにしたい」と浅野Pや吉田Pに思っていただいているので、ディレクターの僕も期待に応えるつもりで準備してるところです。 浅野 ここで改めて、ももクロは歌や踊りのパフォーマンスだけじゃなく、バラエティも最高におもしろいんだぞ、と知らしめたい。 さっき佐々木さんも言ってましたけど、まだももクロに興味がない人でも、バラエティ番組として楽しめるはずなので、お笑い好きとか、バラエティをよく観る人に観てもらいたいです。 佐々木 誰も見たことない、新しくておもしろい番組を作るつもりですよ。 浅野 『ももクロChan』が始まった2010年って、まだ動画配信で成功している番組がほとんどなかったんですね。そんな環境で番組がスタートして、テレビ朝日の中で特筆すべき成功番組になった。 そういう意味では、配信動画のトップランナーとして、満を持して行う生配信のオンラインイベントなので、業界の中でも「すごかった」と言ってもらえる番組にするつもりです。 吉田 『ももクロChan』スタッフとしては、番組が11周年を迎えることを感慨深く思いつつ、テレビを作ってきた人間としては、コロナ以降に定着してきたオンライン生配信の意義を今改めて考えながら作っていきたいです。 (写真:『テレビ朝日 ももクロChan 10周年記念 オンラインプレミアムライブ!~最高の笑顔でバラエティ番組~』は、11月6日(土)19時開演 logirl会員は割引価格でご視聴いただけます) ──具体的にどういった企画をやるのか、少しだけ教えてもらえますか? 浅野 「あーりんロボ」(佐々木彩夏がお悩み相談ロボットに扮するコントコーナー)はやるでしょう。 佐々木 生配信で「あーりんロボ」は怖いですよ、絶対時間押しますから(笑)。佐々木も度胸ついちゃってるからガンガンボケて、百田、高城、玉井がさらに煽って調子に乗っていくのが目に見える……。 あと、配信ならではのディープな企画も考えていますが、ちょっと今のままだとディープすぎてできないかもしれないです。 浅野 配信を観た方は、ネタバレ禁止というルールを決めたら、攻められますかねぇ。 佐々木 たしかに視聴者の方々と共犯関係を結べるといいですね。 とにかく、モノノフさんはもちろんですが、少しでも興味を持った人に観てほしいんですよ。バラエティ史に残る番組の記念すべき配信にしますので、絶対損はさせません。 浅野 必ず、期待にお応えします。 撮影=時永大吾 文=安里和哲 編集=後藤亮平
-
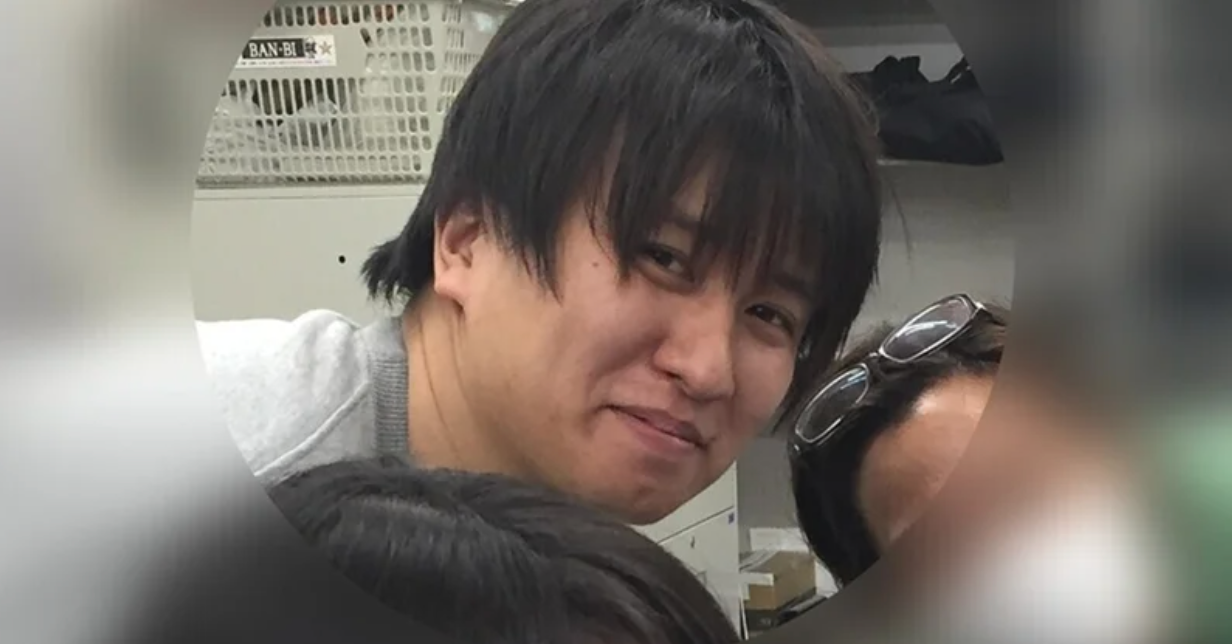 logirlの「起爆剤になりたい」ディレクター・林洋介(『ももクロちゃんと!』)インタビュー
logirlの「起爆剤になりたい」ディレクター・林洋介(『ももクロちゃんと!』)インタビューももいろクローバーZ、でんぱ組.inc、AKB48 Team8などのオリジナルコンテンツを配信する動画配信サービス「logirl」スタッフへのリレーインタビュー第5弾。 今回は10月からリニューアルする『ももクロちゃんと!』でディレクターを務める林洋介氏に話を聞いた。 林洋介(はやし・ようすけ)1985年、神奈川県出身。ディレクター。 <現在の担当番組> 『ももクロちゃんと!』 『WAGEI』 『小川紗良のさらまわし』 『まりなとロガール』 リニューアルした『ももクロちゃんと!』の収録を終えて ──10月9日から土曜深夜に枠移動する『ももクロちゃんと!』。林さんはリニューアルの初回放送でディレクターを務めています。 林 そうですね。「ももクロちゃんと、〇〇〇!」という基本的なルールは変わらずやっていくんですけど、画面上のCGやテロップなどが変わるので、視聴者の方の印象はちょっと違ってくるかなと思います。 (写真:「ももクロちゃんと!」) ──収録を終えた感想はいかがですか? 林 自粛期間中に自宅で推し活を楽しめる「推しグッズ」作りがトレンドになっていたので、今回は「推しグッズ」というテーマでやったんですが、ももクロのみなさんに「推しゴーグル」を作ってもらう作業にけっこう時間がかかってしまったんですよね。「安全ゴーグル」に好きなキャラクターや言葉を書いてデコってもらったんですが、本当はもうひとつ作る予定が収録時間に収まりきらず……それでもリニューアル1発目としては、期待を裏切らない内容になったと思います。 ──『ももクロちゃんと!』を担当するのは今回が初めてですが、収録に臨むにあたって何か考えはありましたか? 林 やっぱり、リニューアル一発目なので盛り上がっていけたらなと。あとは、ももクロは知名度のあるビッグなタレントさんなので、その空気に飲まれないようにしないといけないなと考えていましたね。 ──先輩スタッフの皆さんからとも相談しながらプランを立てていったのでしょうか? 林 そうですね。ももクロは業界歴も長くてバラエティ慣れしているので、トークに関しては心配ないと聞いていました。ただ、自分たちで考えて何かを書いたり作ったりしてもらうのは、ちょっと時間がいるかもしれないよとも……でも、まさかあそこまでかかるとは思いませんでした(笑)。ちょっとバカバカしいものを書いてもらっているんですけど、あそこまで真剣に取り組んでくれるのかって逆に感動しました。 (写真:「ももクロちゃんと! ももクロちゃんと祝!1周年記念SP」) 「まだこんなことをやるのか」という無茶をしたい ──ももクロメンバーと仕事をする機会は、これまでもありましたか? 林 logirlチームに入るまで一度もなくて、今回がほぼ初対面です。ただ一度だけ、DVDの宣伝のために短いコメントをもらったことがあって、そのときもここまで現場への気遣いがしっかりしているんだという印象を受けました。 もちろん名前はよく知っていますが、僕は正直あまりももクロのことを知らなかったんですよね。キャリア的に考えたら当然現場では大物なわけで、そのときは僕も時間を巻きながら無事に5分くらいのコメントをもらったんですが、あとから撮影した素材を見返したら、あの短いコメント取材だけなのに、わざわざみんなで立ち上がって「ありがとうございました」と丁寧に言ってくれていたことに気がついて、「めっちゃいい子たちやなあ」って思ってました。 ──一緒に仕事をしてみて、印象は変わりましたか? 林 『ももクロちゃんと!』は、基本的にその回で取り上げる専門的な知識を持った方にゲストで来ていただいてるんですが、タレントさんでない方が来ることも多いんですよね。そういった一般の方に対しても壁がないというか、なんでこんなになじめるのかってくらいの親しみ深さに驚きました。そういう方たちの懐にもすっと入っていけるというか、その気遣いを大切にしているんですよね。しかもそれをすごく自然にやっているのが、すごいなと思いました。 ──『ももクロちゃんと!』は2年目に突入しました。今後の方向性として、考えていることはありますか? 林 「推しグッズ」でも、あそこまで真剣に取り組んでるんだったら、短い収録時間の中ではありますが、「まだこんなことをやってくれるのか」という無茶をしてみたいなと個人的には思いました。過去の『ももクロChan』を観ていても、すごくアクティブじゃないですか。だから、トークだけでは終わらせたくないなっていう気持ちはあります。 (写真:「ももクロChan~Momoiro Clover Z Channel~」) 情報番組のディレクターとしてキャリアを積む ──テレビの仕事を始めたきっかけを教えてください。 林 大学を卒業して特にやりたいことがなかったので、好きだったテレビの仕事をやってみようかなというのが入口ですね。最初に入ったのがテレビ東京さんの『お茶の間の真実〜もしかして私だけ!?〜』というバラエティ番組で、そこでADをやっていました。長嶋一茂さんと石原良純さんと大橋未歩さんがMCだったんですが、初めは知らないことだらけだったので、いろいろなことが学べたのは楽しかったですね。 ──そこからずっとバラエティ畑ですか。 林 AD時代は基本的にバラエティでしたね。ディレクターの一発目はTBSの『ビビット』という情報番組でした。曜日ディレクターとして、日々のニュースを追う感じだったんですが、そもそもニュースというものに興味がなかったので、そこはかなり苦戦しました。バラエティの“おもしろい”は単純というか、わかりやすいですが、ニュースの“おもしろい”ってなんだろうってずっと考えていましたね。たとえば、殺人事件の何を見せたらいいんだろうとか、まったくわからない世界に入ってしまったなという感じがしていました。 ──情報番組はどのくらいやっていたんですか? 林 『ビビット』のあとに始まった、立川志らくさんの『グッとラック!』もやっていたので、6年間ぐらいですかね。でも、最後まで情報番組の感覚はつかめなかった気がします。きっとこういうことが情報番組の“おもしろい”なのかなって想像しながら、合わせていたような感じです。 番組制作のモットーは「事前準備を超えること」 ──ご自身の好みでいえば、どんなジャンルがやりたかったんですか? 林 いわゆる“どバラエティ”ですね。当時でいえば、めちゃイケ(『めちゃ×イケてるッ!』/フジテレビ)に憧れてました。でも、情報バラエティが全盛の時代だったので、結果的にAD時代、ディレクター時代を含めてゴリゴリのバラエティはやれなかったですね。 ──情報番組のディレクター時代の経験で、印象に残っていることはありますか? 林 芸能人の密着をやったり、街頭インタビューでおもしろ話を拾ってきたりと、仕事としては濃い時間を過ごしたと思いますが、そういったネタよりも、当時の上司からの影響が大きかったかなと思います。『ビビット』や『グッとラック!』は、ワイドショーだけどバラエティに寄せたい考えがあったので、コーナー担当の演出はバラエティ畑で育った人たちがやっていたんですよね。今思えば、バラエティのチームでワイドショーを作っているような感覚だったので、特殊といえば特殊な場所だったのかもしれません。僕のコーナーを見てくれていた演出の人もなかなか怖い人でしたから(笑)。 ──その経験も踏まえ、番組を作るときに心がけていることはありますか? 林 どんなロケでも事前に構成を作ると思うんですが、最初に作った構成を越えることをひとつの目標としてやっていますね。「こんなものが撮れそうです」と演出に伝えたところから、ロケのあとのプレビューで「こんなのがあるんだ」と驚かせるような何かをひとつでも持って帰ろうとやっていましたね。 自由度の高い「配信番組」にやりがいを感じる ──logirlチームには、どのような経緯で入ったんでしょうか? 林 『グッとラック!』が終わったときに、会社から「次はどうしたい?」と提示された候補のひとつだったんですよね。それで、僕はもう地上波に未来はないのかなと思っていたので、詳細は知らなかったんですけど、配信の番組というところに興味を持ってやってみたいなと思い、今年の4月から参加しています。 ──参加して半年ほど経ちますが、配信番組をやってみた感触はいかがですか? 林 そうですね。まだ何かができたわけじゃないんですけど、自分がやりたいことに手が届きそうだなという感じはしています。もちろん、仕事として何かを生み出さなければいけないですが、そこに自分のやりたいことが添えられるんじゃないかなって。 具体的に言うと、僕はいつか好きな「バイク」を絡めた企画をやりたいと思っているんですが、地上波だったら一発で「難しい」となりそうなものも、企画をもう少ししっかり詰めていけば、実現できるんじゃないかという自由度を感じています。 ──そこは地上波での番組作りとは違うところですよね。 林 はい、少人数でやっていることもありますし、聞く耳も持っていただけているなと感じます。まだ自分発信の番組は何もないんですけど、がんばれば自分発信でやろうという番組が生まれそうというか、そこはやりがいを感じる部分ですね。 logirlを大きくしていく起爆剤になりたい ──logirlはアイドル関連の番組も多いです。制作経験はありますか? 林 テレビ東京の『乃木坂って、どこ?』でADをやっていたことがあります。本当に初期で『制服のマネキン』の時期くらいまでだったので、もう9年前くらいですかね。いま売れている子も多いのでよかったなと思います。 ──ご自身がアイドル好きだったことはないですか。 林 それこそ、中学生のころにモーニング娘。に興味があったくらいですね。ちょうど加護(亜依)ちゃんや辻(希美)ちゃんが入ってきたころで、当時はみんな好きでしたから。でも、アイドルに熱狂的になったことはなくて、ああいう気持ちを味わってみたいなとは思うんですけど、なかなか。 ──これからlogirlでやりたいことはありますか? 林 先ほども言ったバイク関連の企画もそうですが、単純に何をやればいいというのはまだ見えてないんですよね。ただ、logirlはまだまだ小さいので、僕が起爆剤になってNetflixみたいにデカくなっていけたらいいなって勝手に思っています。 ──最後に『ももクロちゃんと!』の担当ディレクターをとして、番組のリニューアルに向けた意気込みをお願いします。 林 『ももクロちゃんと!』はこれから変わっていくはずなので、ファンのみなさんにはその変化にも注目していただければと思います。よろしくお願いします! 文=森野広明 編集=中野 潤
-
 言葉を引き出すために「絶対的な信頼関係を」プロデューサー・河合智文(『でんぱの神神』等)インタビュー
言葉を引き出すために「絶対的な信頼関係を」プロデューサー・河合智文(『でんぱの神神』等)インタビューももいろクローバーZ、でんぱ組.inc、AKB48 Team8などのオリジナルコンテンツを配信する動画配信サービス「logirl」スタッフへのリレーインタビュー第4弾。 今回は『でんぱの神神』『ナナポプ』などのプロデューサー、河合智文氏に話を聞いた。 河合智文(かわい・ともふみ)1974年、静岡県出身。プロデューサー。 <現在の担当番組> 『でんぱの神神』 『ナナポプ 〜7+ME Link Popteen発ガールズユニットプロジェクト〜』 『美味しい競馬』(logirl YouTubeチャンネル) 初めて「チーム神神」の一員になれた瞬間 ──『でんぱの神神』には、いつから関わるようになったんでしょうか? 河合 2017年の3月から担当になりました。ちょうど、でんぱ組.incがライブ活動をいったん休止したタイミングでした。「密着」が縦軸としてある『でんぱの神神』をこれからどうしていこうか、という感じでしたね。 (写真:『でんぱの神神』) ──これまでの企画で印象的なものはありますか? 河合 古川未鈴さんが『@JAM EXPO 2017』で総合司会をやったときに、会場に乗り込んで未鈴さんの空き時間にジャム作りをしたんですよ。企画名は「@JAMであっと驚くジャム作り」。簡易キッチンを設置して、現場にいるアイドルさんたちに好きな材料をひとつずつ選んで鍋に入れていってもらい、最終的にどんな味になるのかまったくわからないというような(笑)。 極度の人見知りで、ほかのアイドルさんとうまくコミュニケーションが取れないという未鈴さんの苦手克服を目的とした企画でもあったんですが、@JAMの現場でロケをやらせてもらえたのは大きかったなと思います。 (写真:『でんぱの神神』#276/2017年9月22日配信) 企画ではありませんが、ねも・ぺろ(根本凪・鹿目凛)のふたりが新メンバーとしてお披露目となった大阪城ホール公演(2017年12月)までの密着も印象に残っていますね。 ライブ活動休止中はバラエティ企画が中心だったので、リハーサルでメンバーが歌っている姿がとても新鮮で……その空間を共有したとき、初めて「チーム神神」の一員になれたという感じがしました。 そういった意味ではねも・ぺろのふたりに対しては、でんぱ組.incという会社の『でんぱの神神』部署に配属された同期入社の仲間だと勝手に感じています (笑)。 でんぱ組.incが秀でる「自分の魅せ方」 ──でんぱ組.incというグループにどんな印象を持っていますか? 河合 僕が関わり始めたころは、2度目の武道館公演を行うなどすでにアイドルグループとして大きく、メジャーな存在だったんです。番組としてもスタートから6年目だったので、自分が入ってしっかり接していけるのかな、という不安はありました。 自分の趣味に特化したコアなオタクが集まったグループ……ということで、それなりにクセがあるメンバーたちなのかなと構えていたんですけど、そのあたりは気さくに接してもらって助かりました。とっつきにくさとかも全然なくて(笑)。 むしろ、ロケを重ねていくうちにセルフプロデュースや自己表現がすごくうまいんだなと思いました。自分の魅せ方をよくわかっているんですよね。 ──そういったご本人たちの個性を活かして企画を立てることもあるのでしょうか? 河合 マンガ・アニメ・ゲームなどメンバーが愛した男性キャラクターを語り尽くすという「私の愛した男たち」はでんぱ組にうまくハマった企画で、反響が大きかったので、「私の憧れた女たち」「私のシビれたシーンたち」と続く人気シリーズになりました。 やはり好きなことについて語るときはエネルギーがあるというか、とてもテンション高くキラキラしているんですよね。メンバーそれぞれの好みというか、人間性というか……隠れた一面を知ることのできた企画でしたね。 (写真:『でんぱの神神』#308/2018年5月4日配信) ──そして5月に『でんぱの神神』のレギュラー配信が2年ぶりに再開しました。これからどんな番組にしていきたいですか? 河合 2019年2月にレギュラー配信が終了しましたが、それでも不定期に密着させてもらっていたんです。そのたびにメンバーから「『神神』は何度でも蘇る」とか、「ぬるっと復活」みたいに言われていましたが(笑)。そんな『神神』が2年ぶりに完全復活できました。 長寿番組が自分の代で終了してしまった負い目も感じていましたし、不定期でも諦めずに配信を続けたことがレギュラー再開につながったと思うと、正直うれしいですね。 今回加入した新メンバーも超個性的な5人が集まったと思います。やはり今は多くの人に新メンバーについて知ってほしいですし、先ほどの「私の愛した男たち」は彼女たちを深掘りするのにうってつけの企画ですよね。これまで誰も気づかなかった個性や魅力を引き出して、新生でんぱ組.incを盛り上げていきたいです。 (写真:『でんぱの神神』#363/2021年5月12日配信) 密着番組では、事前にストーリーを作らない ──ティーンファッション誌『Popteen』のモデルが音楽業界を駆け上がろうと奮闘する姿を捉えた『ナナポプ』は、2020年の8月にスタートしました。 河合 『Popteen』が「7+ME Link(ナナメリンク)」というプロジェクトを立ち上げることになり、そこから生まれたMAGICOURというダンス&ボーカルユニットに密着しています。これまでのlogirlの視聴者層は20〜40代の男性が多かったですが、『ナナポプ』のファンの中心はやはり『Popteen』読者である10代の女性。そういった人たちにもlogirlを知ってもらうためにも、新しい視聴者層への訴求を意識した企画でもあります。 (写真:『ナナポプ』#29/2021年3月5日配信) ──番組の反響はいかがでしょうか? 河合 スタート当初は賛否というか、「モデルさんにダンステクニックを求めるのはいかがなものか?」といった声もありました。ですが、ダンス講師のmai先生はBIGBANGやBLACKPINKのバックダンサーもしていた一流の方ですし、メンバーたちも常に真剣に取り組んでいます。 だから、実際に観ていただければそれが伝わって応援してもらえるんじゃないかと思っています。番組も「“リアル”だけを描いた成長の記録」というテーマになっているので、本気の姿をしっかり伝えていきたいですね。 ──密着番組を作るときに意識していることはありますか? 河合 特に自分がディレクターとしてカメラを回すときの場合ですが、ナレーション先行の都合のよいストーリーを勝手に作らないことですね。 僕は編集のことを考えて物語を固めてしまうと、その画しか撮れなくなっちゃうタイプで。現場で実際に起きていることを、リアルに受け止めていこうとは常に考えています。一方で、事前に狙いを決めて、それをしっかり押さえていく人もいるので、僕の考えが必ずしも正解ではないとも思うんですけどね。 音楽の仕事をするために、制作会社に入社 ──テレビ業界を目指したきっかけを教えてください。 河合 高校時代に世間がちょうどバンドブームで、僕も楽器をやっていたんです。「学園祭の舞台に立ちたい」くらいの活動だったんですけど、当時から「仕事にするならクリエイティブなことがいい」とはずっと考えていました。初めは音楽業界に入りたかったんですが、専門学校に行って音楽の知識を学んだわけでもないので、レコード会社は落ちてしまって。 ほかに音楽の仕事ができる手段はないかなと考えたときに浮かんだのが「音楽番組をやればいい」でした。多少なりとも音楽に関われるなら、ということで番組制作会社に入ったのがきっかけです。 ──すぐに音楽番組の担当はできましたか? 河合 研修期間を経て実際に採用となったときに「どんな番組をやりたいんだ?」と聞かれて、素直に「音楽番組じゃなきゃ嫌です」と言ったら希望を叶えてくれたんです。1998年に日本テレビの深夜にやっていた、遠藤久美子さんがMCの『Pocket Music(ポケットミュージック)』という番組のADが最初の仕事です。そのあとも、同じ日本テレビで始まった『AX MUSIC- FACTORY』など、音楽番組はいくつか関わってきました。 大江千里さんと山川恵里佳さんがMCをしていた『インディーウォーズ』という番組ではディレクターをやっていました。タレントさんがインディーアーティストのプロモーションビデオを10万円の予算で制作するという、企画性の高い番組だったんですが、10万円だから番組ディレクターが映像編集までやることになったんです。 放送していた2004〜2005年ごろ、パソコンでノンリニア編集をする人なんてまだあまりいませんでした。ただ僕はひと足先に手を出していたので、タレントさんとマンツーマンで、ああでもないこうでもないと言いながら何時間もかけて動画を編集した思い出がありますね。 ──現在も動画の編集作業をすることはあるんですか? 河合 今でもバリバリやっています(笑)。YouTubeチャンネルでも配信している『美味しい競馬』の初期もそうですし、『でんぱの神神』がレギュラー配信終了後に特別編としてライブの密着をしたときは、自分でカメラを担いで密着映像とライブを収録して、それを自分で編集したりもしました。 やっぱり、自分で回した素材は自分で編集したいっていう気持ちが湧くんですよね。忘れかけていたディレクター心に火がつくというか……編集で次第に形になっていくのがおもしろくて。編集作業に限らず、構成台本を作成したり、けっこうなんでも自分でやっちゃうタイプですね。 (写真:『でんぱの神神』特別編 #349/2019年5月27日配信) logirlは、やりたいことを実現できる場所 ──logirlに参加した経緯を教えてください。 河合 実は『Pocket Music(ポケットミュージック)』が終わったとき、ADだったのに完全にフリーになったんですよ。そこから朝の情報番組などいろんなジャンルの番組を経験して、番組を通して知り合った仲間からいろいろと声をかけてもらって仕事をしていました。紀行番組で毎月海外に行ったりしたこともありましたね。 ちょうど一段落して、テレビ番組以外のこともやってみたいなと考えていたときに、日テレAD時代の仲間から「テレ朝で仕事があるけどやらない?」と紹介してもらい、それがまだ平日に毎日生配信をしていたころ(2015〜2017年)のlogirlだったんです。 (写真:撮影で訪れたスペイン・バルセロナにて) ──番組を作る上でモットーにしていることはありますか? 河合 今は一般の方でも、タレントさんでも、編集ソフトを使って誰でも動画制作ができる時代になったじゃないですか。だからこそ、「テレビ局の動画スタッフが作っている」というクオリティを出さなければいけないと思っています。難しいことですが、これを諦めたら番組を作る意味がないのかなという気がするんですよね。 あとは、出演者との信頼関係を大切に…..といったことですね。特に『でんぱの神神』『ナナポプ』といった密着系の番組は、出演者の気持ちをいかに言葉として引き出すかにかかっていますので、そこには絶対的な信頼関係を築いていくことが必要だと思います。 ──実際にlogirlで仕事してみて、いかがでしたか? 河合 自分でイチから企画を考えてアウトプットできる環境ではあるので、そこは楽しいですね。自分のやりたいことを、がんばり次第で実現できる場所。そういった意味でやりがいがあります。 ──リニューアルをしたlogirlの今後の目標を教えてください。 河合 まずは、どんどん新規の番組を作って、コンテンツを充実させていきたいです。これまで“ガールズ”に特化していましたが、今はその枠がなくなり、落語・講談・浪曲などをテーマにした『WAGEI』のような番組も生まれているので、いい意味でいろいろなジャンルにチャレンジできると思っています。 時期的にまだ難しいですが、ゆくゆくはlogirlでイベントをすることも目標です。logirlだからこそ実現できるラインナップになると思うので、いつか必ずやりたいと思っています。 文=森野広明 編集=田島太陽
大胆に予想!『美味しい馬券〜「美味しい競馬」スピンオフ〜』
仙波広雄@スポーツニッポン新聞社 競馬担当によるコラム。週末のメインレースを予想&分析/「logirl」でアーカイブ公開中『美味しい競馬』MC
-
 大胆に予想!『美味しい馬券〜「美味しい競馬」スピンオフ〜』(北九州記念)
大胆に予想!『美味しい馬券〜「美味しい競馬」スピンオフ〜』(北九州記念)大胆に予想!『美味しい馬券〜「美味しい競馬」スピンオフ〜』(北九州記念) 先週も言及しましたが、今年はわりと大きな開催変更がありました。今週、唯一の重賞開催となる北九州記念もあおりを受けた重賞の一つ。2年前までとは盆過ぎの開催で施行時期が違います。昨年は西日本夏競馬の最初の開催でしたが、開幕週でした。今年は2週目。夏の小倉は1週ごとに馬場コンディションも変化しますので、昨年のレースも参考にしづらい。参考になるローテーションはなくもありませんが、鵜呑みにするのも危険でしょう。なんとも手探りながら今週は7月6日(日)の小倉11R・北九州記念を予想します。 【北九州記念の傾向・特異点】(過去10年) ・上記の理由であまり当てにならない ・牝馬6勝。夏は牝馬 ・3~7歳まで勝ち馬が出る ◎⑨ヤマニンアルリフラ。 ◎にするほどピンと来る牝馬がいないので、4歳牡馬のこの馬でいきます。3歳時は新馬、未勝利を7戦して勝ち上がれず、10月に1勝クラスでなお勝てず、12月に2勝クラス特別で初勝利。斉藤崇師には走る確信もあったのでしょうが、順当とは言えない滑り出し。そこからは快進撃で、今年は3月に2勝クラス、5月に3勝クラスをクリア。どうも芝1200が一番合いそう、で落ち着いています。姉には①ヤマニンアンフィル、兄にはプロキオンS勝ちヤマニンウルスがいるのも未勝利を勝てずとも諦めなかった理由の一つでしょう。曽祖母ワンオブアクラインはダンチヒ産駒。米G1オークリーフS勝ち馬で「ヤマニン」の錦岡牧場が輸入。ヤマニンを支える重要牝系で、どんなに配合表の深い位置にいこうがダンチヒはダンチヒ。夏競馬に強いのもこの牝系の特徴の一つでここはチャンスとみました。①⑨の姉弟丼も買っておきたい。 ○⑮ロードフォアエース。 今は千二専科ですが、デビューは芝マイル。ダートを経て適性が判明した馬です。好位から手堅い運びですが、どうにも詰めが甘く13戦で4勝、2着8回。大崩れはないはずですが、ハンデ戦でアタマを買うのはちょっと怖いタイプ。川田、友道厩舎、ロードカナロアと隙なしの陣営で人気もしますが、名門友道厩舎はスプリントのJRA重賞を勝ったことがありません。 ▲⑱ヨシノイースター。 個人的にひいきにしている1頭なのですが、どうも馬券のタイミングが合いません。外枠の方がいいかとは思うのですが。 馬券は3連単1頭軸流し。 <1着>⑨→<相手>①③⑤⑥⑮⑰⑱。42点。 text:仙波広雄@大阪スポーツニッポン新聞社 競馬担当/【logirl】でアーカイブ公開中『美味しい競馬』MC
-
 大胆に予想!『美味しい馬券〜「美味しい競馬」スピンオフ〜』(ラジオNIKKEI賞)
大胆に予想!『美味しい馬券〜「美味しい競馬」スピンオフ〜』(ラジオNIKKEI賞)大胆に予想!『美味しい馬券〜「美味しい競馬」スピンオフ〜』(ラジオNIKKEI賞) 配信(YouTube(logirl 【テレ朝動画公式】YouTube)美味しい競馬はお休みをいただきます。このコラムは毎週、重賞を取り上げていきますので、ご愛顧をよろしくお願いいたします。今年は重賞スケジュールが一部変更されましたので、正直なところわりと困っています。巴賞組のいない函館記念は今ひとつアプローチの仕方が分からないので、今週は6月29日(日)の福島11R・ラジオNIKKEI賞を予想します。わりと傾向が偏った重賞ですが、さて今年はどうでしょうか。 【ラジオNIKKEI賞傾向・特異点】 ・ディープブリランテ産駒が2勝 ・母父キングヘイロー2勝含め母父リファール系3勝 ・母父キングマンボ系3勝 ・母父ブライアンズタイム2勝 ・勝ち馬の配合表には欧州志向が目立つ ・前走オープン以上の場合は着順不問 ◎②フクノブルーレイク。 先週までの種牡馬ウインブライトはJRA12勝。芝10勝、ダート2勝で芝1800、芝2000で計8勝。勝ち星は全て未勝利のもので2勝馬は0ですが、フクノブルーレイクにスプリングS2着があり現時点での代表産駒。ここまでの戦績を見て言えることは、ウインブライトが明らかにステイゴールド系らしさを見せている、ということ。ステイゴールドの本質はサンデーサイレンスよりディクタスですから、小回り福島芝1800重賞はしっくり来ます。皐月賞の大敗でクラシックからスパッと切り替えて夏場を使うのも好判断だと思います。大きな馬ではないのでトップハンデ57キロは他馬との比較上、不利ではありますが、唯一の重賞連対馬なので仕方ないところ。 ○④レーヴブリリアント。 連闘、ルメールという、いかにも勝負がかりでスプリングSに使いましたが7着。この馬もそこでクラシックから切り替えてここ目標に乗り込んできました。6月一杯、きっちり時計を出して調整は順調。ただ鞍上が重賞初挑戦の舟山というのが、なかなか考えさせられるところ。この馬なら乗ってくれるジョッキーは何人でもいますからね。田中博師は所属の弟子である舟山を大切に育てています。重賞でジャンプアップしてこいという意図でしょうか。オーナーも理解があるというか太っ腹というか。そういう理解ある大人に囲まれた18歳、まぶしくないですか?筆者はまぶしいです。応援票であることは否定しません。 ▲⑤センツブラッド。 切れる脚を使うタイプではないので、小回りは合っていそうです。調教過程としては中3週にしても緩い気はしますが、夏場の叩き3走目ならこのぐらいの調教でも走るのかも。 馬券は3連単2頭軸マルチ。 <軸>②④→<相手>⑤⑥⑧⑨⑫⑭。36点。夏競馬でもあり、夢のある馬券です。 text:仙波広雄@大阪スポーツニッポン新聞社 競馬担当/【logirl】でアーカイブ公開中『美味しい競馬』MC
-
 大胆に予想!『美味しい馬券〜「美味しい競馬」スピンオフ〜』(しらさぎステークス)
大胆に予想!『美味しい馬券〜「美味しい競馬」スピンオフ〜』(しらさぎステークス)大胆に予想!『美味しい馬券〜「美味しい競馬」スピンオフ〜』(しらさぎS) 宝塚記念は▲◯で、◎にしたロードデルレイは行方不明。武豊を逃がすとこうなるという競馬ファンの大半が「知ってた」というレースでしたが、逃げのラップはすさまじかったです。筆者は5F59秒1、そこから後ろが詰め切れないのを見て、メイショウタバルの勝利が見えてしまいました。ベラジオオペラがカベ役だったのも後続の運び方が難しい一因。3~6着は後方待機の馬ばかりなので、1着が完璧ラップの逃げ、2着が強い先行馬というだけで、展開そのものは差し優位という形。こういうレースは理詰めより感性が求められると思う次第。上位2頭にジャスティンパレスを付けるのはなかなかの難易度でしょう。さて、しばらくG1はお休みですが、今週は配信(YouTube(logirl 【テレ朝動画公式】YouTube)美味しい競馬#206)があります。ほのかさんをゲストに迎えて6月22日(日)の阪神11R・しらさぎSの予想です。昨年までの米子Sが重賞昇格で名称も変わりました。名称変更の理由なんかも配信で推察しています。全くの推察ですが。 ◎⑧シヴァース。 実績ではチェルヴィニアとレーベンスティールがだいぶ上です。というか、その2頭が宝塚記念でなく、こちらを使うというのは、「第1回」というなかなかの名誉なシチュエーションや主戦騎手が乗れるかなどの兼ね合い、かつマイルへの短縮で結果が出ていない現状からの反発を狙うという側面もあります。要するに能力が上なのは分かっていても、軸で買いたいかと言われるとそうでもない。格上2頭はマイルの序盤スピードに置かれて直線勝負でしょうから、ある程度前に行けるマイラーを狙いたい、それならシヴァースだろうという算段。一度も連勝がないように、安定したタイプでもなく、乗り難しさもある。鞍上のスタートも不安ですが、3勝クラスV直後の重賞という格上げシチュエーションこそ折り合いそうなタイプとも言えます。 ○⑦チェルヴィニア、▲⑥レーベンスティール。 2頭とも、少なくとも成果が明らかな内容のレースをしないとほぼ夏競馬のここを使う意味がないレベルの馬です。なので、それなりの仕上げにしています。筆者の立ち位置として、現代競馬は適性の占める割合が大きい論者ですから、どうにも距離不足の2頭に◎を打つ気はありません。といって、無理に消すこともないかと。チェルとレーベンのどちらかを◎にするなら、もう片方は消したいところですが。 馬券は3連単フォーメーション。 <1着>⑧→<2着>⑥⑦→<3着>②③⑥⑦⑩⑪⑬。 <1着>⑧→<2着>②③⑩⑪⑬→<3着>⑥⑦。22点。 text:仙波広雄@大阪スポーツニッポン新聞社 競馬担当/【logirl】でアーカイブ公開中『美味しい競馬』MC
その他
番組情報・告知等のお知らせページ
-
 WAGEI公開収録<概要・応募規約>
WAGEI公開収録<概要・応募規約>テレ朝動画「WAGEI 公開収録」番組観覧無料ご招待! 2025年1月18日(土)開催! logirl(ロガール)会員の中から抽選で100名様に番組観覧ご招待! 番組概要 テレ朝動画で配信中の伝統芸能番組『WAGEI』の公開収録! 番組MCを務める浪曲師「玉川太福」と、五代目三遊亭円楽一門の落語家「三遊亭らっ好」が珠玉のネタを披露します。 ゲストには須田亜香里と、SKE48赤堀君江が登場!出演者からの貴重なプレゼントも用意する予定です。 超レアなプログラムを是非お楽しみください。 日時:2025年1月18日(土)開場12:30 開演13:00(終演15:15予定) 場所:浅草木馬亭 東京都台東区浅草2−7−5 出演:玉川太福(浪曲師)・玉川みね子(曲師)/三遊亭らっ好(落語家)/須田亜香里/赤堀君江(SKE48) 応募詳細 追加応募期間:2024年12月27日(金)15:00~2025年1月9日(木)17:00締切 応募条件:logirl(ロガール)会員のみ対象(当日受付で確認させていただきます) 下記「応募規約」をよく読んでご応募ください。 応募フォーム:https://www.tv-asahi.co.jp/apps/apply/jump.php?fid=10062 追加当選発表:当選した方のみ、2025年1月10日(金)23:59までに 当選メール(ご招待メール)をご登録されたアドレスまでお送りさせていただきます。 「WAGEI公開収録」応募規約 【応募規約】 この応募規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社テレビ朝日(以下「当社」といいます。)が 運営する動画配信サービス「テレ朝動画」における「WAGEI」(以下「番組」といいます。)に関連して 実施する、公開収録の参加者募集に関する事項を定めるものです。参加していただける方は、本規約の 内容をご確認いただき、ご同意の上でご応募ください。 【募集要項】 開催日時:2025年1月18日(土)13:00開始~15:15頃終了予定 (途中、休憩あり) ※スケジュールは変更となる場合があります。集合時間等の詳細は当選連絡にてお伝えいたします。 場所:浅草木馬亭(東京都台東区浅草2-7-5) 出演者(予定):玉川太福(浪曲師)・玉川みね子(曲師)/三遊亭らっ好(落語家)/須田亜香里/赤堀君江(SKE48) ※出演者は予告なく変更される場合があります。 募集人数:100名様(予定) ※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。 【応募資格】 ・テレ朝動画logirl(ロガール)会員限定 ・年齢性別は問いません 【応募方法】 応募フォームへの必要事項の入力 ・テレ朝動画にログインの上、必要事項を入力してください。 【ご参加お願い(参加決定)のご連絡】 ■ご参加をお願いする方(以下「参加決定者」といいます。)には、1月10日(金)23:59までに、応募フォームにご入力いただいたメールアドレス宛に、集合時間と場所、受付手続等の詳細を記載した「番組公開収録ご招待メール」(以下「ご招待メール」といいます。)を送信させていただきます。なお、ご入力いただいた電話番号にお電話をさせて頂く場合がございます。非通知設定でかけさせていただく場合もございますので、非通知拒否設定は解除して頂きますようお願いします。 ■当日の集合時間と集合場所は「ご招待メール」に記載します。集合時間に遅ることのないようご注意ください。 ■「ご招待メール」が届かない場合は、残念ながらご参加いただけませんのでご了承ください。 ■「ご招待メール」の送信の有無に関するお問い合わせはご遠慮ください。 ■公開収録の参加は無料です。参加決定のご連絡にあたって、参加決定者に対し、参加料等のご入金のお願いや銀行口座情報、クレジットカード情報等のお問い合わせをすることは、一切ございません。「テレビ朝日」や本サービスの関係者を名乗る悪質な連絡や勧誘には十分ご注意ください。また、そのような被害を防止するため、ご応募いただいた事実を第三者に口外することはお控えいただけますようお願い申し上げます。 ■「ご招待メール」および公開収録への参加で知り得た情報、公開収録の内容に関する情報、及び第三者の企業秘密・プライバシー等に関わる情報をブログ、SNS等への記載を含め、方法や手段を問わず第三者への開示を禁止いたします。また、当選権利および当選者のみが知り得た情報に関して、譲渡や販売は一切禁止いたします。 【注意事項】 ■ご案内は当選したご本人様1名のみのご参加となります。(同伴者はご案内できません) ■未成年の方がご応募いただく場合は、必ず事前に保護者の方の同意を得てください。その場合は、電話番号の入力欄に保護者の方と連絡の取れる電話番号をご入力ください。(保護者にご連絡させていただく場合がございます。) ■開催当日、今回の公開収録の参加および撮影・映像使用に関しての承諾書をご提出いただきます。(未成年の方は保護者のサインが必要となります。) ■1名につき応募は1回までとします。重複応募は全て無効になりますので、お気をつけください。 ■会場ではスタッフの指示に従ってください。指示に従っていただけない場合は、会場から退去していただく場合がございます。 ■会場でのスマートフォン等を用いての録画・録音についてはご遠慮ください。 ■会場までの交通手段は、公共交通機関をご利用ください。駐車場はございません。 ■会場までの交通費、宿泊費等は参加者のご負担にてお願いいたします。 ■当日は、ご本人であることを確認させていただくために、お手持ちのスマートフォン等で表示または印刷した「ご招待メール」と、「身分証明書」(運転免許証・パスポート等、氏名と年齢が確認できるもの)をお持ち下さい。ご本人確認が出来ない方は、ご参加いただけません。 ■荷物置き場はご用意しておりません。貴重品の管理等はご自身にてお願いいたします。貴重品を含む持ち物の紛失・盗難については、当社は一切責任を負いません。 ■公開収録に伴い、参加者・客席を含み場内の撮影・録音を行い、それらの映像または画像等の中に映り込む可能性があります。参加者は、収録した動画、音声を、当社または当社が利用を許諾する第三者(以下、当社および当該第三者を総称して「当社等」といいます)が国内外テレビ放送(地上波放送・衛星波放送を含みます)、雑誌、新聞、インターネット配信およびPC・モバイルを含むウェブサイトへの掲載をはじめとするあらゆる媒体において利用することについてご同意していただいたものとみなします(以下、かかる利用を「本件利用」といいます)。なお、本件利用の対価は無料とさせていただきますので、ご了承ください。 ■諸事情により番組の公開収録が中止又は延期となる場合がありますのでご了承ください。 【個人情報の取り扱いについて】 ■ご提供いただいた個人情報は、番組公開収録への参加に関する抽選、案内、手配又は連絡及び運営等のために使用し、収録後に消去させていただきます。 ■当社における個人情報等の取扱いの詳細については、以下のページをご覧下さい。 https://www.tv-asahi.co.jp/privacy/ https://www.tv-asahi.co.jp/privacy/online.html
-
 新番組『WAGEIのじかん』(CS放送)
新番組『WAGEIのじかん』(CS放送)CSテレ朝チャンネル1「WAGEIのじかん」 落語・浪曲・講談など日本の伝統芸能が楽しめる番組。MCを務める浪曲師玉川太福と話芸の達人(=ワゲイスト)たちが珠玉のネタを披露します。さらに、お笑いを愛する市川美織が番組をサポート!お茶の間の皆様に笑いっぱなしの15分をお届けします。 お届けするネタ(3月放送)は、玉川太福の浪曲ほか、古今亭雛菊・春風亭かけ橋・春風亭昇吉・昔昔亭昇・柳家わさび・柳亭信楽の落語、神田松麻呂の講談などが登場します。お楽しみに〜!(※出演者50音順) ★3月の放送予定 3月17日(日)25:00~26:00 3月21日(木)26:00~27:00 3月24日(日)25:00~26:00 ⇩【収録中の様子】市川美織さん箱馬に乗って高さのバランスを調整しました。笑