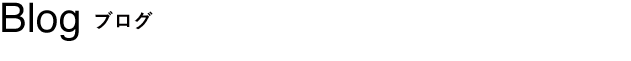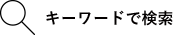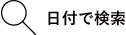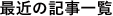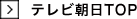- トップ
- ブログ
- 30年ひと昔
- 2022年12月28日
1991年1月17日。僕は早朝から、首相官邸の記者クラブにひとり、詰めていた。予感のようなものがあった。
前日の夜、当時の僕が番記者として張り付いていた政府高官Aは、その帰宅を待つ記者たちの前に、ついに姿を現さなかった。普段、待ち受ける記者に無言を通すことはあっても、身を隠すことはしない人だった。それがこのときだけは違った。
待ちぼうけを食らう形となった僕は、「何かがある」と思った。自宅に帰って2~3時間眠り、ふたたび官邸にとって返し、その「何か」を待つことにしたのである。
すると、テレビ各局がアメリカのニュース報道の映像を一斉に流し出した。イラクの首都・バグダッドの夜空に閃光が走っている。アメリカを中心とする多国籍軍の空爆だ。湾岸戦争が始まったのである。
まだ、官邸には職員がポツポツと出勤し始めたころだ。僕は官邸の玄関に陣取り、前夜待ちぼうけを食らった政府高官Aを待つことにした。ほどなく公用車が玄関に到着した。後部座席にいたAが車外に降り立つとほぼ同時のタイミングで駆け寄った僕が、「イラクで戦争、ですね」と声をかけると、Aは「始まったな」と言った。「昨夜は?」という問いに、「アメリカ側に動きがあって、ちょっとな」とつぶやくように言うと、Aは小走りに自室へと向かった。おそらく前夜から開戦間近との情報があり、官邸近くで待機していたのだろう。
アメリカ発の報道で既報のこととはいえ、日本政府の高官が開戦の事実を把握し、記者である僕にそれを認めたことは小さくない。僕はすでに大騒動になっていると思われる渋谷の報道局に電話をかけ、早出の政治部デスクに伝えた。
「イラクで戦争が始まりました。日本政府も把握していると、Aが認めました」。
なんだか国際サスペンス小説のような書きっぷりになってしまったぞ。
実際の僕の動きは、政府高官が「車外に一歩踏み出すとほぼ同時」というほどスピーディーではなかったかもしれないし、「日本政府も把握している」という僕の取材報告に対し、政治部デスクは「そんなの当たり前だろ」と言っただけかもしれない。忘れたけど。
しかし、日本の公共放送の若僧記者ですら、小説の主人公になれると勘違いするくらいの世界的激動の年だったのだ。1991年という年は。
先日、作成から30年以上たった外交文書の一部が公開された。1991年に日本政府内で交わされた機密文書が含まれる。機密が解除された文書の中で、報道ステーションが紹介したのは、当時の村田良平駐米大使から発せられた極秘公電だった。
少し経緯を述べよう。前年8月のイラクによるクウェート侵攻に対し、多国籍軍がイラクへの武力行使に踏み切ったのは1991年1月17日。クウェートが解放され、戦闘が停止されたのが2月28日。この前後を含めた期間、日本には悩ましい日々だった。
石油資源の多くを中東に依存してきた経済大国・日本。クウェートが侵攻されて以降、日本は中東の安定のための役割を担うことが国際社会から期待されていた。そして同盟国アメリカからは、戦闘の後方支援としての自衛隊の派遣を要請されていた。
しかし、専守防衛を国是とする日本にとって、自衛隊の海外派遣というハードルは高く、国内世論も大きく割れた。130億ドルに及ぶ資金援助は行ってはいたものの、日本は「カネは出しても汗は流さない国」と揶揄され、切ない立場にあった。
戦闘停止からほぼ半月後の3月13日に発せられたのが、公表された村田駐米大使の公電だ。このとき、ペルシャ湾を行き交う船舶の大きな障害となっていたのが機雷だった。その除去という平和目的なら、自衛隊の掃海艇派遣は可能ではないかという議論はずっとくすぶっていた。そこに公電が発され、「決断のタイミングは今からでも決して遅くはない。不退転の決意で実行することが必要だ」と、当時の海部首相の決断を促していた。
果たして海部内閣は4月、派遣を閣議決定。ただちに自衛隊の掃海艇「あわしま」が、海上自衛隊横須賀基地を出港した。ちなみに僕はこの時の現場も取材している。
話を番組に戻そう。僕にとってありがたかったのは、村田大使の公電を番組で取り上げようと考えた担当者たちが、「キャスターはこのころ、まさに取材の最前線にいたのではないか」と考えを巡らせ、立案の段階から僕に意見を求めてくれたことだ。
そこで僕は語ったのだった。「政府高官Aに張り付くO記者」が主人公の物語ではなく、もっと大事なことを思い出し、スタッフに伝えたのである。
人的貢献へと一歩を踏み出さない日本にとって、ショッキングな出来事が起きていた。3月11日、解放されたクウェート政府がアメリカの新聞に掲載した「感謝広告」の中に、日本の名前がなかったのである。130億ドルもの大金を拠出していたにもかかわらず。
政府・自民党に強い危機感が広がった。それは官邸に張り付く若手記者の僕から見ても明白だった。「小切手外交・ニッポン」という烙印が決定的になってしまうという焦りは、もはや抜き差しならぬものとなり、それを僕は肌で感じていた。
その2日後に発出されたのが村田大使の公電ということになる。戦後日本の自衛隊政策の転換は、日本の名前が存在しない新聞の1ページによって導かれ、直後に駐米大使から発された公電がダメ押しになった、というのが僕なりの見立てとなった。
そして、番組もそうした見解のもとで構成し、放送した。
自衛隊はその後、国連の平和維持活動(PKO)への参加をはじめ、アメリカなどによるテロ掃討作戦では米軍艦船への洋上補給を行うなど、活動の幅を広げていった。その時々の政権の判断であり、是非は歴史が判断することになるだろう。
確かに言えるのは、ひとりの記者であった僕が、歴史的瞬間のそのときを生き、取材をし、それが自分の見える狭い範囲に過ぎなかったとしても、世の中に伝えることができたということだ。そして今も、僕は報道番組の最前線にいて、最終表現者として時代に関与している。それはずしりと重い。
重い責任を感じながら、これからも仕事に取り組もうと思います。今年一年、叱咤とともにたくさんの応援をありがとうございました。ネコとストレッチングしながらお別れです。
2023年が皆さんにとって良い年でありますように。
(2022年12月28日)
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)