バックナンバー
#887
2023年10月22日
「野口聡一さんとテレビ」後編
【番組司会】山口豊(テレビ朝日アナウンサー)
八木麻紗子(テレビ朝日アナウンサー)
【ナレーション】田中萌(テレビ朝日アナウンサー)
【出演】野口聡一(宇宙飛行士)
八木麻紗子(テレビ朝日アナウンサー)
【ナレーション】田中萌(テレビ朝日アナウンサー)
【出演】野口聡一(宇宙飛行士)
今年4月から、テレビ朝日放送番組審議会委員に就任した
宇宙飛行士の野口聡一さん。
長年にわたり様々なミッションを行ってきた野口さんに、
宇宙とテレビについてお話を伺いました。(後編)
宇宙飛行士の野口聡一さん。
長年にわたり様々なミッションを行ってきた野口さんに、
宇宙とテレビについてお話を伺いました。(後編)
<アメリカのテレビ>
―野口さんが宇宙飛行士に選抜されたのが1996年、
訓練が行われたアメリカでは、テレビを観ていましたか?
1つは朝の番組、情報番組。出勤前にテレビをつけて。
ローカルニュースと全国ニュースがあるわけですが、それぞれにね、やっぱり面白さがあるなっていうのは、アメリカにいる間の方がすごく感じていて。
ローカル(地方)局にも、メインキャスターとサブキャスターと気象予報士がいて、それぞれの面白さがあって。
キー局の人は全国レベルの人気者になるわけですけれども。
アメリカの場合は、日本以上に地方分権がちゃんとあるというか。
あくまでも州の固まりが国ですので、その州の持っている独自性はすごく大事に、誇りを持っていて。
ローカル局はキー局の下請けではないんですね。
だから、そこら辺がすごく面白いなと思いました。
―情報番組を比較した場合、日本と比べてどんな違いが?
日本の場合には、キー局のポテンシャルと影響力が非常に強いので、
誤解を恐れずに言うと日本ではどこに行っても、いわゆるキー局の作った番組をちゃんと観れるわけですよね、朝の番組も夜の番組も。
たとえば、夜でいうと「報道ステーション」。
北海道から沖縄まで、「報道ステーション」と言えばわかるわけです。
キャスターが誰かというのも、大体わかっている。
アメリカの場合は、もちろんそれもあるとは思いますけども、
それと同じくらい
「自分の町のローカル局のメインキャスターの有名な人はこの人だ」
というのをちゃんとわかっている感じがあるので、そこは面白いなと思います。
訓練が行われたアメリカでは、テレビを観ていましたか?
1つは朝の番組、情報番組。出勤前にテレビをつけて。
ローカルニュースと全国ニュースがあるわけですが、それぞれにね、やっぱり面白さがあるなっていうのは、アメリカにいる間の方がすごく感じていて。
ローカル(地方)局にも、メインキャスターとサブキャスターと気象予報士がいて、それぞれの面白さがあって。
キー局の人は全国レベルの人気者になるわけですけれども。
アメリカの場合は、日本以上に地方分権がちゃんとあるというか。
あくまでも州の固まりが国ですので、その州の持っている独自性はすごく大事に、誇りを持っていて。
ローカル局はキー局の下請けではないんですね。
だから、そこら辺がすごく面白いなと思いました。
―情報番組を比較した場合、日本と比べてどんな違いが?
日本の場合には、キー局のポテンシャルと影響力が非常に強いので、
誤解を恐れずに言うと日本ではどこに行っても、いわゆるキー局の作った番組をちゃんと観れるわけですよね、朝の番組も夜の番組も。
たとえば、夜でいうと「報道ステーション」。
北海道から沖縄まで、「報道ステーション」と言えばわかるわけです。
キャスターが誰かというのも、大体わかっている。
アメリカの場合は、もちろんそれもあるとは思いますけども、
それと同じくらい
「自分の町のローカル局のメインキャスターの有名な人はこの人だ」
というのをちゃんとわかっている感じがあるので、そこは面白いなと思います。
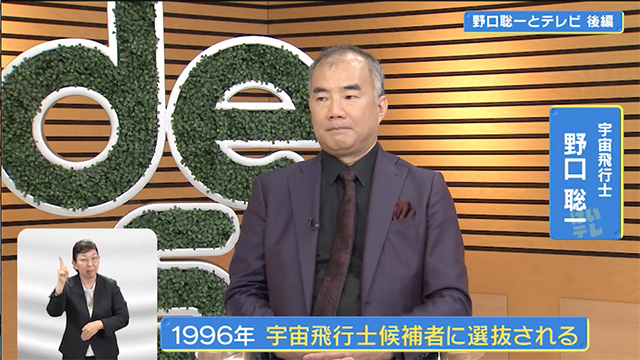

<宇宙の感動と映像>
―宇宙飛行士としての活動の中で、一番思い出に残っていることは?
宇宙ステーションでの船外活動です。
宇宙船の外に出てやる活動が、やっぱり一番の花形だと思うんですけれども、
そこで映像を自分で撮って、それを宇宙ステーションから流したっていうのが一番大きいかな、と。
最終的にYouTubeになったんですけど、
宇宙のありのままの姿をお伝えしたい、そこでの自分の反応というか、感動みたいなものを映像にしたいと思った時に、船外活動は本当に待ったなしの緊張感の中で、自分自身がどう反応するか分からない。
そういうところの映像を撮れて流せたっていうのは、すごく面白かったなと思います。
―スペースシャトル、ソユーズ、クルードラゴンという
異なる3つの宇宙船で宇宙に行ったのは野口さんだけ。
乗り心地に違いはあるんでしょうか?
違いはありますね、明確に。
これは本当にラッキーなことに、3回4回ね、宇宙に行った人は他にいっぱいいるんですけど、3回違った宇宙船に乗せていただいたっていうのは、私が初めてだったということで、本当に時代がうまく合ったというかね。
いろいろな乗り物と同じで宇宙船も時代によって進化していく。
自動車、船、飛行機もそうだと思うんですけど、ロケット自体の歴史が浅い乗り物ですから、進化のスピードがすごく速い。
スペースシャトルは1970年代くらいに設計されて、2番目に乗ったソユーズ、こちらも結構古い。
それに対してスペースX社、アメリカのイーロン・マスクさんの会社ですね、
すごくユニークな経営者でいらっしゃるし、テスラを作って。
21世紀的な乗り物。
タッチパネルを使って、いわゆるスマホ的な操作が可能であるとか、宇宙船の中もインテリアが、ショールームのような美しい白と黒のモノトーンで統一してあって。
なによりも、室内にケーブルがないっていう、これは特に、スペースシャトルからすると考えられない。
何千本というケーブルをスペースシャトルはつないで動かしていたので。
スペースX社の場合には、全てケーブルは壁の中に入っている。
それは見た目だけの問題ではなくて、故障箇所が減ってくる訳なので、
ケーブルに何か引っ掛けてとか、繋ぎ直して間違えて、みたいな話が全くなくなるので。
すごく居住性もいいし、操作性もいいなと思っていました。
宇宙ステーションでの船外活動です。
宇宙船の外に出てやる活動が、やっぱり一番の花形だと思うんですけれども、
そこで映像を自分で撮って、それを宇宙ステーションから流したっていうのが一番大きいかな、と。
最終的にYouTubeになったんですけど、
宇宙のありのままの姿をお伝えしたい、そこでの自分の反応というか、感動みたいなものを映像にしたいと思った時に、船外活動は本当に待ったなしの緊張感の中で、自分自身がどう反応するか分からない。
そういうところの映像を撮れて流せたっていうのは、すごく面白かったなと思います。
―スペースシャトル、ソユーズ、クルードラゴンという
異なる3つの宇宙船で宇宙に行ったのは野口さんだけ。
乗り心地に違いはあるんでしょうか?
違いはありますね、明確に。
これは本当にラッキーなことに、3回4回ね、宇宙に行った人は他にいっぱいいるんですけど、3回違った宇宙船に乗せていただいたっていうのは、私が初めてだったということで、本当に時代がうまく合ったというかね。
いろいろな乗り物と同じで宇宙船も時代によって進化していく。
自動車、船、飛行機もそうだと思うんですけど、ロケット自体の歴史が浅い乗り物ですから、進化のスピードがすごく速い。
スペースシャトルは1970年代くらいに設計されて、2番目に乗ったソユーズ、こちらも結構古い。
それに対してスペースX社、アメリカのイーロン・マスクさんの会社ですね、
すごくユニークな経営者でいらっしゃるし、テスラを作って。
21世紀的な乗り物。
タッチパネルを使って、いわゆるスマホ的な操作が可能であるとか、宇宙船の中もインテリアが、ショールームのような美しい白と黒のモノトーンで統一してあって。
なによりも、室内にケーブルがないっていう、これは特に、スペースシャトルからすると考えられない。
何千本というケーブルをスペースシャトルはつないで動かしていたので。
スペースX社の場合には、全てケーブルは壁の中に入っている。
それは見た目だけの問題ではなくて、故障箇所が減ってくる訳なので、
ケーブルに何か引っ掛けてとか、繋ぎ直して間違えて、みたいな話が全くなくなるので。
すごく居住性もいいし、操作性もいいなと思っていました。
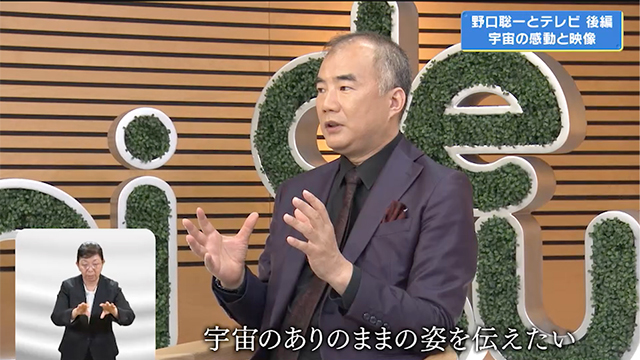
<宇宙旅行>
―宇宙旅行に普通に行けるような時代が来るのでしょうか?
いろんなレベルがあると思うのですが、地球の重力を一時的に振り払って大体高度100km、ジェット機が飛んでいるのが10kmなんですけど、その10倍の高さですね、100kmまで行くと国際的には宇宙空間に出たと言われているので、そこまで上がって帰ってくるだけであれば、これからいろんな商業サービスが出てくると思います。
いま我々プロの宇宙飛行士が乗っているのは、そのまま宇宙空間に何日でも、半年くらいいられるような乗り物ですけど、それはなかなか数も含めて多くはできないので、急激には市場は増えないんですけれども、100kmまで安全に到達して、訓練期間もあまりなく宇宙体験ができるっていうのは、これからいろんなサービスができてくると思います。
あとは価格ですよね。
価格が下がってこないことには。
なかなか市場の競争力がないんですけれど、1つの例として、私が最後に乗ったスペースX社もかなりの価格破壊力を持っていて、恐らくスペースシャトルやソユーズの時代に1人当たり100億円と言われていた価格は、本当にその何分の1まで、いま既に下がってきていると思います。
それはロケット自体の安全性が上がっているのと、再使用ができるようになった。
これがすごく大きくて、そういう意味ではスペースX社は最初からその価格競争を意識して、民間ならではのフレキシブルな考えで、これから価格競争をリードしていくと思います。
いろんなレベルがあると思うのですが、地球の重力を一時的に振り払って大体高度100km、ジェット機が飛んでいるのが10kmなんですけど、その10倍の高さですね、100kmまで行くと国際的には宇宙空間に出たと言われているので、そこまで上がって帰ってくるだけであれば、これからいろんな商業サービスが出てくると思います。
いま我々プロの宇宙飛行士が乗っているのは、そのまま宇宙空間に何日でも、半年くらいいられるような乗り物ですけど、それはなかなか数も含めて多くはできないので、急激には市場は増えないんですけれども、100kmまで安全に到達して、訓練期間もあまりなく宇宙体験ができるっていうのは、これからいろんなサービスができてくると思います。
あとは価格ですよね。
価格が下がってこないことには。
なかなか市場の競争力がないんですけれど、1つの例として、私が最後に乗ったスペースX社もかなりの価格破壊力を持っていて、恐らくスペースシャトルやソユーズの時代に1人当たり100億円と言われていた価格は、本当にその何分の1まで、いま既に下がってきていると思います。
それはロケット自体の安全性が上がっているのと、再使用ができるようになった。
これがすごく大きくて、そういう意味ではスペースX社は最初からその価格競争を意識して、民間ならではのフレキシブルな考えで、これから価格競争をリードしていくと思います。
<宇宙で行きたい場所>
―野口さんが宇宙旅行をするとしたら、どこに行きたいですか?
地球が見えるところがいいので、
月面のウサギさんのいる辺りに広大な土地を買って、
露天風呂を掘って地球見酒をしながら余生を過ごしたい、それが理想です。
―やっぱり地球を見ていたいですか?
地球はきれいですからね。
地球が見えないところまで、やがて人類は行くと思いますけれど、そうした時に、
自分のルーツとなる星が見えないところまで行ってしまうのは、僕はやっぱり寂しいなと思うので。
そういう意味では、まだ僕は本当の意味で宇宙時代になっていないんだと思いますけど、地球を見ながら浮かんでいたいなと思いますね。
地球が見えるところがいいので、
月面のウサギさんのいる辺りに広大な土地を買って、
露天風呂を掘って地球見酒をしながら余生を過ごしたい、それが理想です。
―やっぱり地球を見ていたいですか?
地球はきれいですからね。
地球が見えないところまで、やがて人類は行くと思いますけれど、そうした時に、
自分のルーツとなる星が見えないところまで行ってしまうのは、僕はやっぱり寂しいなと思うので。
そういう意味では、まだ僕は本当の意味で宇宙時代になっていないんだと思いますけど、地球を見ながら浮かんでいたいなと思いますね。
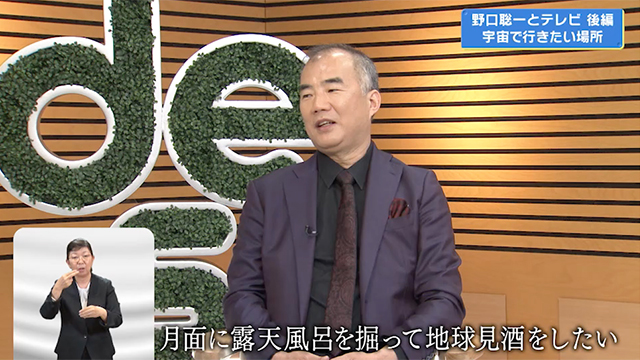
<宇宙という存在>
―野口さんにとって「宇宙」とはどういう存在でしょうか?
いろんな可能性を開いてくれる扉だと思うんです。
ゲートウェイという言い方をしていますけれど。
僕たちは最終的には地球で生まれて地球で死んでいくので、地球での生活を大事にしていくべきというか、それしかないんですけど、
一方で、地球上の問題を地球だけで解決しなくてもいいんじゃないの?と。
宇宙に出ることで新しい知見があるとか、宇宙空間も経済圏として使って、
それが様々な地上の問題を解決するのであれば、それはもうどんどん使っていくべきだと思いますし。
そういう意味で、地球上の問題を解決するための様々な可能性のドアとして
宇宙を使っていけばいいんじゃないかなと思いますね。
いろんな可能性を開いてくれる扉だと思うんです。
ゲートウェイという言い方をしていますけれど。
僕たちは最終的には地球で生まれて地球で死んでいくので、地球での生活を大事にしていくべきというか、それしかないんですけど、
一方で、地球上の問題を地球だけで解決しなくてもいいんじゃないの?と。
宇宙に出ることで新しい知見があるとか、宇宙空間も経済圏として使って、
それが様々な地上の問題を解決するのであれば、それはもうどんどん使っていくべきだと思いますし。
そういう意味で、地球上の問題を解決するための様々な可能性のドアとして
宇宙を使っていけばいいんじゃないかなと思いますね。

<宇宙飛行士として取り組みたいこと>
―今後、宇宙飛行士として取り組みたいことは?
僕自身はまた宇宙に行きたいなと思っているので、次は国としてやるべきことをやるというよりは宇宙旅行とかね。
一般の方が宇宙に初めて行くというようなところをお手伝いしたいなと思っているので、そういうビジネスに関わる可能性もありますし。
もうちょっと平たい言い方をすると、宇宙ツアーガイドみたいな、宇宙水先案内人みたいな。
10人くらいのツアーの時に1人くらいは経験者がいる方が安心ですから、
そういう存在になれるといいかなと思ってます。
僕自身はまた宇宙に行きたいなと思っているので、次は国としてやるべきことをやるというよりは宇宙旅行とかね。
一般の方が宇宙に初めて行くというようなところをお手伝いしたいなと思っているので、そういうビジネスに関わる可能性もありますし。
もうちょっと平たい言い方をすると、宇宙ツアーガイドみたいな、宇宙水先案内人みたいな。
10人くらいのツアーの時に1人くらいは経験者がいる方が安心ですから、
そういう存在になれるといいかなと思ってます。
<宇宙でテレビ>
―宇宙でテレビって観るものなんでしょうか?
基本的に地上でできることは何でもしたいというのが、我々宇宙飛行士の願いではあるんですけど。
結論から言うと、いわゆる普段みなさんが観られているような地上波放送を
リアルタイムで観ることはできません。
地上で放送している番組はスカイツリーから電波を出しているわけですけれども、あの電波は下向きに出していますので、宇宙空間には出してないわけですよ。
ですから残念ながら、宇宙ではリアルタイムで放送しているテレビ番組は観られないんです。
ただし最近は、いわゆる見逃し配信、TVerとかですね。
インターネット自体はつながっていますのでTVerなどで観る方法と、
あとは「この番組を観たい」と、たとえば年末のお笑い番組がありますね、一番を決める!あの番組がどうしても観たいな、と。
私は2回、年末年始を宇宙で過ごしているんですけれど、2回ともあの番組は指定してですね。
そうすると地上でJAXAが録画して、そのデータを宇宙に送ってくれるんです。そうすると、3日遅れくらいで来るので、ちゃんと年内のうちに、誰が今年はトップだったかっていうのを確認できます。
―宇宙空間で「M-1グランプリ」を観ていた?
「M-1」って言っちゃっていいんですか?あ、そうですね、テレビ朝日ですね。
「M-1グランプリ」は、もうバッチリ観ていましたね。
もう予選から観ていますね。
―宇宙空間でも観たかったんですか?
そうですね、地上で観ている時と同じような雰囲気にできるだけしておきたい。
どこまで行っても宇宙と地上は別物なんですけど、ただリラックスする、仕事の合間にちょっと違うことを考えるみたいな時に、
地上のルーティンを宇宙に持っていけるのはすごく素晴らしいことで、
ただリラックスするというと美しい自然の番組とかね、もちろんそういうのもあるんです。
ただ、宇宙ステーションは超美しい地球の姿が目の前で見れるので、あまり地球の絶景とかいっても大して響かないんです、本物があるので。
それよりは、宇宙に決してない芸人さんのおふざけの方がよっぽどリラックスできるというか、もちろんすごく真面目な仕事をしている時は真面目に集中しますけど、オフの時、週末、あるいは夜、仕事が終わって寝る前のひと時にはバラエティー番組とかお笑いの方がずっと意味があるかな。
自分にとっては大事な時間だと思っています。
―好きな芸人さんはいらっしゃるんですか?
そうですね、オードリーとかね。共演することが多かったので。
宇宙で初めて観たのが錦鯉さんで、この人たちは決して地上では見ないだろうなと思いながら、最初で最後が宇宙で観る「M-1グランプリ」かと思っていたら、もう御存じのとおりね、大ブレイクで。
一度ご一緒させていただきましたけど、面白いですよね。
基本的に地上でできることは何でもしたいというのが、我々宇宙飛行士の願いではあるんですけど。
結論から言うと、いわゆる普段みなさんが観られているような地上波放送を
リアルタイムで観ることはできません。
地上で放送している番組はスカイツリーから電波を出しているわけですけれども、あの電波は下向きに出していますので、宇宙空間には出してないわけですよ。
ですから残念ながら、宇宙ではリアルタイムで放送しているテレビ番組は観られないんです。
ただし最近は、いわゆる見逃し配信、TVerとかですね。
インターネット自体はつながっていますのでTVerなどで観る方法と、
あとは「この番組を観たい」と、たとえば年末のお笑い番組がありますね、一番を決める!あの番組がどうしても観たいな、と。
私は2回、年末年始を宇宙で過ごしているんですけれど、2回ともあの番組は指定してですね。
そうすると地上でJAXAが録画して、そのデータを宇宙に送ってくれるんです。そうすると、3日遅れくらいで来るので、ちゃんと年内のうちに、誰が今年はトップだったかっていうのを確認できます。
―宇宙空間で「M-1グランプリ」を観ていた?
「M-1」って言っちゃっていいんですか?あ、そうですね、テレビ朝日ですね。
「M-1グランプリ」は、もうバッチリ観ていましたね。
もう予選から観ていますね。
―宇宙空間でも観たかったんですか?
そうですね、地上で観ている時と同じような雰囲気にできるだけしておきたい。
どこまで行っても宇宙と地上は別物なんですけど、ただリラックスする、仕事の合間にちょっと違うことを考えるみたいな時に、
地上のルーティンを宇宙に持っていけるのはすごく素晴らしいことで、
ただリラックスするというと美しい自然の番組とかね、もちろんそういうのもあるんです。
ただ、宇宙ステーションは超美しい地球の姿が目の前で見れるので、あまり地球の絶景とかいっても大して響かないんです、本物があるので。
それよりは、宇宙に決してない芸人さんのおふざけの方がよっぽどリラックスできるというか、もちろんすごく真面目な仕事をしている時は真面目に集中しますけど、オフの時、週末、あるいは夜、仕事が終わって寝る前のひと時にはバラエティー番組とかお笑いの方がずっと意味があるかな。
自分にとっては大事な時間だと思っています。
―好きな芸人さんはいらっしゃるんですか?
そうですね、オードリーとかね。共演することが多かったので。
宇宙で初めて観たのが錦鯉さんで、この人たちは決して地上では見ないだろうなと思いながら、最初で最後が宇宙で観る「M-1グランプリ」かと思っていたら、もう御存じのとおりね、大ブレイクで。
一度ご一緒させていただきましたけど、面白いですよね。

<宇宙からの生中継>
テレビ局の皆さんは、生放送は大変だと思うんですけど、我々の場合には、その前提となる衛星回線が、地上でみなさんが思っているほど安定していないので、我々プロの宇宙飛行士というか、宇宙ステーションでいろんなデータを扱っている者としては、多少の通信途絶は慣れっこなんですよ。
「あ、通信切れちゃった」みたいな感じでね。
数秒から数分待っていればまた通信は戻ってくるので全然気にしていないんですけれど、生放送でそれがあったらね、放送事故じゃないですか?
そもそもNASAから割り当てられる時間というのが1回で大体15分とか20分しかないので、そこでかっちりと組んだところの真ん中に3分間あいちゃうとすごく大変なわけですよね、地上波放送としては。
ですから、毎回、地上の管制官、そしてテレビ局の方は大変だったと思いますね。
私たちは全然気にしていないんですよ。
宇宙で話をしていて「あれ?切れたみたい」ってなると、平気でほかのことをしに行っちゃいますんで、スタジオで待っているとかしないんです。
「あ、通信切れちゃった」みたいな感じでね。
数秒から数分待っていればまた通信は戻ってくるので全然気にしていないんですけれど、生放送でそれがあったらね、放送事故じゃないですか?
そもそもNASAから割り当てられる時間というのが1回で大体15分とか20分しかないので、そこでかっちりと組んだところの真ん中に3分間あいちゃうとすごく大変なわけですよね、地上波放送としては。
ですから、毎回、地上の管制官、そしてテレビ局の方は大変だったと思いますね。
私たちは全然気にしていないんですよ。
宇宙で話をしていて「あれ?切れたみたい」ってなると、平気でほかのことをしに行っちゃいますんで、スタジオで待っているとかしないんです。
<テレビとは>
―野口聡一さんにとって「テレビ」とは何でしょうか?
テレビは自分と社会を繋ぐ窓です。
テレビを通じて学んだこと、知ったことはいっぱいありますし、観たくなかったこともあったと思います。
ですけど、とにかく自分が社会のことを知りたい、社会と繋がっていたいと思った時の一つの窓であるのは間違いないと思います。
本当に幸いなことに、放送番組審議会委員という形で関わらせていただいているので、窓としての、人間が社会につながる窓の一つとしてのこの役割っていうのをこれからもしっかり活かしていけるように、影響力をしっかり保って、
次の世代にもまさしく役に立つ、次の世代にとって役に立つ存在であり続けられるように協力していきたいと思っています。
テレビは自分と社会を繋ぐ窓です。
テレビを通じて学んだこと、知ったことはいっぱいありますし、観たくなかったこともあったと思います。
ですけど、とにかく自分が社会のことを知りたい、社会と繋がっていたいと思った時の一つの窓であるのは間違いないと思います。
本当に幸いなことに、放送番組審議会委員という形で関わらせていただいているので、窓としての、人間が社会につながる窓の一つとしてのこの役割っていうのをこれからもしっかり活かしていけるように、影響力をしっかり保って、
次の世代にもまさしく役に立つ、次の世代にとって役に立つ存在であり続けられるように協力していきたいと思っています。


