【展望】
3連覇へ駒大が仕掛けるスピード駅伝
五輪選手・竹澤率いる早大が対峙
五輪選手・竹澤率いる早大が対峙
44年ぶりに現役学生の五輪選手を生むなど、著しいレベルアップを遂げた学生長距離界。第40回の節目を迎えたこの全日本大学駅伝で、大学日本一の覇権を競い合う。3連覇を狙う駒大か、五輪代表・竹澤健介を擁する早大か。ほかにも強大なエースが率いる東海大、山梨学大、主力が充実している東洋大、明大など、注目のチームが目白押し。高速化必至のレースを展望する。
前回6位以内に入った駒大・日体大・中大・東海大・早大・山梨学大が、シード権を獲得。その後、各地区の予選が9月23日までに開催され、これを勝ち抜いた19校(関東6・関西3・九州3・北信越2・東海2・北海道1・東北1・中四国1)を加え、計25校が出そろった。東海学連選抜(オープン参加)を加えた26チームがスタートラインにつく(表1)。なお、今年のシード6校を除く各地区学連の代表基本枠は、北海道1・東北1・関東6・北信越2・東海2・関西3・中四国1・九州3である(前回より中四国が1減・北信越が1増)。
関東地区は6枠あったシード権すべてを獲得した。次に、箱根駅伝3位以内に入ると関東学連の推薦を得られるのだが、中央学大がこの条件を満たして出場権を確保。6月22日の予選会(10000mのタイムレースを4組実施)が残り5枚の切符を争う大激戦となった。この狭き門をくぐり抜けたのが、明大・東洋大・帝京大・東農大・日大である。過去に優勝経験のある順大・大東大が落選したほか、城西大が3秒弱、神大が9秒弱の差で涙をのんだ。
関西では前回同様、関西学生駅伝を制した立命大が真っ先に出場を決め、6月21日の予選会(10000mのタイムレースを4組実施)で京産大と奈良産大が新たに名乗りを挙げた。京産大は最多連続出場記録を「37」に伸ばし、通算出場回数「37」も大東大に並ぶ最多タイに。また,各地で国立大学が健闘し、中四国では前回28大会ぶりの復活となった広大が連続出場、北信越では信大が6年ぶりの出場を果たした。このほか、福岡大・中京大が伊勢路に復活する。
今年も各校のマネージャーに、メンバー候補約20名とそのベスト記録(5000m/10000m)を提出していただいた。各校ごとに上位8人の平均タイムを集計したものが表2だ。データは候補選手のものに限定し、10月1日までの持ち記録を反映している。
5000mの平均タイムは早大・駒大・日大が13分台。14分ひとケタに関東の7校が横一線だ。10000m部門は早大・山梨学大・日体大・東洋大・駒大が優れていて、続いて29分15秒から29分21秒までに5校がひしめき、やはり混戦を示唆している。すなわち、早大と駒大が〝2強〟として抜け出し、山梨学大・明大・日体大・東洋大・東海大・日大・中大の一団が僅差で続く勢力図を持ちタイムから読み取ることができる。
前回6位以内に入った駒大・日体大・中大・東海大・早大・山梨学大が、シード権を獲得。その後、各地区の予選が9月23日までに開催され、これを勝ち抜いた19校(関東6・関西3・九州3・北信越2・東海2・北海道1・東北1・中四国1)を加え、計25校が出そろった。東海学連選抜(オープン参加)を加えた26チームがスタートラインにつく(表1)。なお、今年のシード6校を除く各地区学連の代表基本枠は、北海道1・東北1・関東6・北信越2・東海2・関西3・中四国1・九州3である(前回より中四国が1減・北信越が1増)。
関東地区は6枠あったシード権すべてを獲得した。次に、箱根駅伝3位以内に入ると関東学連の推薦を得られるのだが、中央学大がこの条件を満たして出場権を確保。6月22日の予選会(10000mのタイムレースを4組実施)が残り5枚の切符を争う大激戦となった。この狭き門をくぐり抜けたのが、明大・東洋大・帝京大・東農大・日大である。過去に優勝経験のある順大・大東大が落選したほか、城西大が3秒弱、神大が9秒弱の差で涙をのんだ。
関西では前回同様、関西学生駅伝を制した立命大が真っ先に出場を決め、6月21日の予選会(10000mのタイムレースを4組実施)で京産大と奈良産大が新たに名乗りを挙げた。京産大は最多連続出場記録を「37」に伸ばし、通算出場回数「37」も大東大に並ぶ最多タイに。また,各地で国立大学が健闘し、中四国では前回28大会ぶりの復活となった広大が連続出場、北信越では信大が6年ぶりの出場を果たした。このほか、福岡大・中京大が伊勢路に復活する。
今年も各校のマネージャーに、メンバー候補約20名とそのベスト記録(5000m/10000m)を提出していただいた。各校ごとに上位8人の平均タイムを集計したものが表2だ。データは候補選手のものに限定し、10月1日までの持ち記録を反映している。
5000mの平均タイムは早大・駒大・日大が13分台。14分ひとケタに関東の7校が横一線だ。10000m部門は早大・山梨学大・日体大・東洋大・駒大が優れていて、続いて29分15秒から29分21秒までに5校がひしめき、やはり混戦を示唆している。すなわち、早大と駒大が〝2強〟として抜け出し、山梨学大・明大・日体大・東洋大・東海大・日大・中大の一団が僅差で続く勢力図を持ちタイムから読み取ることができる。
駒大vs早大 新戦力がカギ
優勝争いの最前線では、早大と駒大が存在感を示すだろう。なかでも近年の学生駅伝で必ず優勝争いに加わっているのが駒大だ。前回も優勝への原動力となった5人が健在。特に10000m28分台、5000m13分台を併せ持つ4人 深津卓也・宇賀地強・池田宗司・星創太の複合パワーは他校にない武器になる。順当なら、流れを作る1・2区、中盤の要である4区、最長区間の8区と、主要4区間にこのカルテットをあてがうことができるのだ。高林祐介が復調し、我妻伸洋が新たに13分台を出すなど戦力の整備も進んでいる。
対する早大は、やはりエース竹澤健介の存在が大きい。2区を務めた前回のように、前半に投入すればたちまち主導権を握れるだろうし、アンカー決戦に備えれば多少の遅れも逆転可能だ。彼の走力は、チーム全体の士気を高める効果もある。竹澤を含め前回のメンバー7人が残り、高原聖典・加藤創大らは駒大の4本柱に対峙する役目が期待できるだろう。
この2強の優劣は、学生駅伝未経験の選手たちがカギを握るのではないか。駒大は今年も夏場に力をつけた選手が9月下旬の記録会で好記録をマーク。駅伝ではどんな働きを見せるか。早大の場合は、強力な1年生たちの存在。その走力はトラックの記録で証明済みだが、駅伝でもその能力を発揮できればおもしろい。彼らの成長度はおそらく、出雲駅伝や秋の記録会ではかることができるだろう。
対する早大は、やはりエース竹澤健介の存在が大きい。2区を務めた前回のように、前半に投入すればたちまち主導権を握れるだろうし、アンカー決戦に備えれば多少の遅れも逆転可能だ。彼の走力は、チーム全体の士気を高める効果もある。竹澤を含め前回のメンバー7人が残り、高原聖典・加藤創大らは駒大の4本柱に対峙する役目が期待できるだろう。
この2強の優劣は、学生駅伝未経験の選手たちがカギを握るのではないか。駒大は今年も夏場に力をつけた選手が9月下旬の記録会で好記録をマーク。駅伝ではどんな働きを見せるか。早大の場合は、強力な1年生たちの存在。その走力はトラックの記録で証明済みだが、駅伝でもその能力を発揮できればおもしろい。彼らの成長度はおそらく、出雲駅伝や秋の記録会ではかることができるだろう。
最前線に浮上する山梨学大・東洋大
2強を追うグループは7校が横一線。この混戦から上位進出を果たすには、ブレーキを起こさない堅実な継走が1つのスタイル。それとは別に、序盤から優勝争いの前線へ飛び出せると好成績に結びつくことが多い。
トラックの持ちタイムが急上昇している山梨学大は、去の実績からも襷によるプラスアルファの力が期待できるチームだ。前回の1・8区である松村康平とメクボ・J・モグスが健在で、前回2区の高瀬無量が成長著しい。さらに松本葵、オンディバ・コスマスが新戦力となり、ほかのつなぎ区間を埋める底上げも進行。モグスが4度目の8区に座ると仮定し、過去の3度より優勝戦線に近いタイム差となれば、アンカーでの大逆転も起こり得るのではないか。
次に東洋大を注目チームに挙げたい。10000mのタイムが示す選手層は随一。大西智也・山本浩之・若松儀裕ら既存の実力者に、今季の学生界で最大のブレイクを果たした柏原竜二が加入。市川健一の復調もあり、主力の密度は見劣りしない。上位グループにしっかり生き残ってレースを進めそうだ。
古豪・明大は久しぶりの学生駅伝。経験不足を露呈した場合の失速は大きいかもしれないが、フレッシュな旋風を起こす可能性もあるチームだ。トラックで充実していた松本昂大・石川卓哉をツートップに、スピード駅伝への対応力、上位争いが可能な選手層はある。2度目の出場で大仕事を果たすか。
東海大は伊達秀晃、日体大は北村聡、中大は上野裕一郎が卒業。大エースが去った後、総合力で立ち向かう。ただ東海大には佐藤悠基が残っている。ここ2シーズンは100%の状態でないものの、彼の根幹能力は非常に高い。エース区間で順位を引き上げる働きを十分に期待していい。むしろその脇を固める選手たちが、浮沈のポイントになるだろう。
日体大は前回、アンカーの北村に4位でタスキを渡したメンバー7人がそっくり残っている。中大も前回メンバー6人が健在。大エースが卒業しても、戦力の低下が小さいのはそのためだ。新エースは日体大が森賢大・中大が地悠一。エース区間の荒波をしのぎ切る役目になる。両校とも、エースの脇を固める主力が好調であり、前回のような堅実な走りを再現できるか。ただ、明大・日体大・東海大は、10月18日に箱根駅伝予選会を経る日程が大きな重しとなるかもしれない。
3年前の優勝校である日大は、今年度の関東の予選会で最下位通過だった。しかしチーム状況は底を脱している。景気浮揚の速度によっては、上位争いに絡んでくるだろう。何よりギタウ・ダニエルがインカレでモグスに競り勝つなど絶好調。ダニエルが序盤に配置されれば、トップを独走する場面もあり得る。
トラックの持ちタイムが急上昇している山梨学大は、去の実績からも襷によるプラスアルファの力が期待できるチームだ。前回の1・8区である松村康平とメクボ・J・モグスが健在で、前回2区の高瀬無量が成長著しい。さらに松本葵、オンディバ・コスマスが新戦力となり、ほかのつなぎ区間を埋める底上げも進行。モグスが4度目の8区に座ると仮定し、過去の3度より優勝戦線に近いタイム差となれば、アンカーでの大逆転も起こり得るのではないか。
次に東洋大を注目チームに挙げたい。10000mのタイムが示す選手層は随一。大西智也・山本浩之・若松儀裕ら既存の実力者に、今季の学生界で最大のブレイクを果たした柏原竜二が加入。市川健一の復調もあり、主力の密度は見劣りしない。上位グループにしっかり生き残ってレースを進めそうだ。
古豪・明大は久しぶりの学生駅伝。経験不足を露呈した場合の失速は大きいかもしれないが、フレッシュな旋風を起こす可能性もあるチームだ。トラックで充実していた松本昂大・石川卓哉をツートップに、スピード駅伝への対応力、上位争いが可能な選手層はある。2度目の出場で大仕事を果たすか。
東海大は伊達秀晃、日体大は北村聡、中大は上野裕一郎が卒業。大エースが去った後、総合力で立ち向かう。ただ東海大には佐藤悠基が残っている。ここ2シーズンは100%の状態でないものの、彼の根幹能力は非常に高い。エース区間で順位を引き上げる働きを十分に期待していい。むしろその脇を固める選手たちが、浮沈のポイントになるだろう。
日体大は前回、アンカーの北村に4位でタスキを渡したメンバー7人がそっくり残っている。中大も前回メンバー6人が健在。大エースが卒業しても、戦力の低下が小さいのはそのためだ。新エースは日体大が森賢大・中大が地悠一。エース区間の荒波をしのぎ切る役目になる。両校とも、エースの脇を固める主力が好調であり、前回のような堅実な走りを再現できるか。ただ、明大・日体大・東海大は、10月18日に箱根駅伝予選会を経る日程が大きな重しとなるかもしれない。
3年前の優勝校である日大は、今年度の関東の予選会で最下位通過だった。しかしチーム状況は底を脱している。景気浮揚の速度によっては、上位争いに絡んでくるだろう。何よりギタウ・ダニエルがインカレでモグスに競り勝つなど絶好調。ダニエルが序盤に配置されれば、トップを独走する場面もあり得る。
シード権はプラチナチケット
これまでに9校が挙がったように、どのチームにとってもシード権獲得は容易ではない。これから取り上げるチームのシード獲得はますます難しいことになる。ただし帝京大・東農大・第一工大・立命大・中央学大については、データ上の比較では上位候補にやや劣るものの、その差は小さい。ソツのない継走を実現すれば、シード権への突破口が開けるに違いない。
データ上は劣っているものの・やはり見逃せないのが中央学大だろう。エース・木原真佐人はモグス(山梨学院大)・竹澤(早大)・佐藤(東海大)ら、〝最強世代〟の一角。竹澤を脅かし、さらには競り勝つ可能性を秘める実力者である。また、箱根駅伝3位の快走に参加した選手が木原を含めて6人いる。駅伝巧者の一面を見せるか。シード権獲得へのカギは木原が起用される区間か。川崎勇二監督は木原の4区起用をほのめかしている。
飛び抜けたエースがいないものの、穴のないオーダーを組めそうなのが帝京大。昨年秋からすっかり波に乗っているチームであり、6年ぶりの舞台でフレッシュな旋風を起こすか。過去5度の準優勝経験がある東農大は16年ぶりの復活。大切なレースで力を発揮できるエースの外丸和輝・清水和朗を軸にレースを組み立てる。
第一工大は今年も3人の留学生を登録。前回2区7位の中野良平・前回3区6位の厚地翔太も力をつけている。5~7区で踏ん張ればシード権が見えてくる。立命大は前回メンバー5人が残る。前回は序盤で乗り遅れたが、関東勢が作る上位の波に乗れるかどうか。 シード制の創設以来、その権利はすべて関東が独占中。今回も関東勢が占める可能性は高いが、第一工大・立命大・京産大の奮闘を期待せずにはいられない。第一工大は3年前にシードラインまであと54秒に迫ったことがある。
学生駅伝日本一決定戦の幕開けは11月2日,午前8時10分。今年も序盤から緊迫したレースが展開されそうだ。
(奥村 崇)
データ上は劣っているものの・やはり見逃せないのが中央学大だろう。エース・木原真佐人はモグス(山梨学院大)・竹澤(早大)・佐藤(東海大)ら、〝最強世代〟の一角。竹澤を脅かし、さらには競り勝つ可能性を秘める実力者である。また、箱根駅伝3位の快走に参加した選手が木原を含めて6人いる。駅伝巧者の一面を見せるか。シード権獲得へのカギは木原が起用される区間か。川崎勇二監督は木原の4区起用をほのめかしている。
飛び抜けたエースがいないものの、穴のないオーダーを組めそうなのが帝京大。昨年秋からすっかり波に乗っているチームであり、6年ぶりの舞台でフレッシュな旋風を起こすか。過去5度の準優勝経験がある東農大は16年ぶりの復活。大切なレースで力を発揮できるエースの外丸和輝・清水和朗を軸にレースを組み立てる。
第一工大は今年も3人の留学生を登録。前回2区7位の中野良平・前回3区6位の厚地翔太も力をつけている。5~7区で踏ん張ればシード権が見えてくる。立命大は前回メンバー5人が残る。前回は序盤で乗り遅れたが、関東勢が作る上位の波に乗れるかどうか。 シード制の創設以来、その権利はすべて関東が独占中。今回も関東勢が占める可能性は高いが、第一工大・立命大・京産大の奮闘を期待せずにはいられない。第一工大は3年前にシードラインまであと54秒に迫ったことがある。
学生駅伝日本一決定戦の幕開けは11月2日,午前8時10分。今年も序盤から緊迫したレースが展開されそうだ。
(奥村 崇)
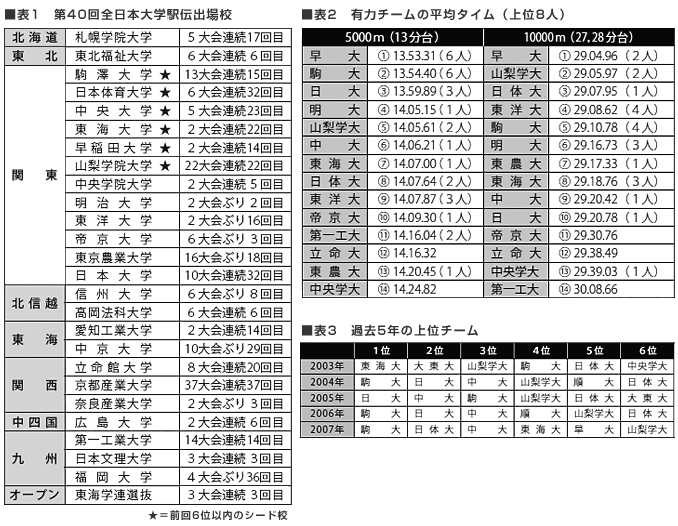
奥村 崇 / 情報提供:月刊陸上競技(2008年11月号より)