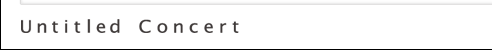元はバレエ音楽として書かれた作品で1912年に初演。後にここから2つの組曲をラヴェル自身が作りました。バレエ音楽版は、ロシア舞踊団の団長ディアギレフからの委嘱作品で、ラヴェル自身が「私が目指し
たのは音楽の巨大な壁画(フレスコ)を作曲すること」と話しているように、非常に視覚的な音楽です。<夜明け>は静かな夜が白々と明け、鳥のさえずりが聞こえ始め、やがて陽の光が差してくる様子を描写しています。“オーケストラの魔術師”といわれたラヴェルならではの楽器の使用法が光ります。
戯曲「アルルの女」の劇中曲としてビゼーが作曲したものの中から、ビゼーの親友でパリ国立音楽院作曲学教授であるギローが管弦楽用に編曲しました。原曲の初演は1872年です。<ファランドール>とは南フランス地方の踊りのことで、曲中の最弱音の太鼓からはじまる軽快な音楽は賑やかなファランドールの踊りを表現しています。この旋律はプロヴァンス地方に民謡「馬のダンス」に基づいています。
原曲はチャイコフスキー「弦楽四重奏曲 第1番」の第2楽章で1871年作曲。この第2楽章が「アンダンテ・カンタービレ」で、民謡の旋律を用いています。1876年、大文豪トルストイのために開かれた音楽会でこの「アンダンテ・カンタービレ」が演奏されましたが、トルストイがこの曲を聴いて涙を流したそうです。隣に座っていたチャイコフスキーは感激し、「あの時ほど、喜びと感動をもって作曲家としての誇りを抱いたことは、二度とないだろう」と日記に記しています。
イタリアの作曲家レスピーギは心からローマを愛し、ローマをテーマに3曲の交響詩「ローマの噴水」「ローマの松」「ローマの祭り」3部作を書き上げました。「ローマの松」は1926年作曲で、古代ローマへ眼を向け、ローマの往時に幻影をも追った作品です。ここでは4箇所の松がテーマとなっていますが、今回は終曲に当たる「アッピア街道の松」を取り上げます。アッピア街道は古代ローマ軍の進軍道路でしたが、打楽器やピアノでその足音を示すように正確にリズムを刻んでいます。曲が進むにつれてローマ軍の行進がだんだん近づいてくる様子が分かります。
| 指揮 : |
佐渡 裕 |
| 演奏 : |
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 |
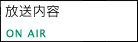
|