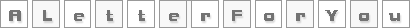
| |
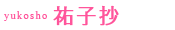
|
 |
Vol.89 「クラムボン」 (2005/12/05) |
 |
先月、生まれて初めて岩手県に出張に出かけた。
新幹線を降り立つと、銀の冷気が身を包む。
肩をすくめて駅構内を見渡した時に目に飛び込んで来たのは、
電車の乗り換え案内の看板だった。
「○番線”いわて銀河鉄道”乗り換え」
盛岡は、宮沢賢治のゆかりの地。
このまま”銀河鉄道”を乗り継いで、旅を続けたい衝動に駆られた。
『よだかの星』、『注文の多い料理店』、『なめとこ山の熊』…。
以前から、どの作品にもどこかに死の影が漂っている気がしていた。
優しさと残酷さ、繊細さと生々しさ―二律背反する感覚に、戸惑うことが多かった。
中でも忘れられないのは、『やまなし』という短編である。
川底で遊ぶカニの兄弟の会話によって、幻想的な物語が進んでいく。
「クラムボンはわらったよ」
「クラムボンはかぷかぷわらったよ」
ぽつぽつぽつと、水銀のように光る泡。
水底まで届く、透き通ったラムネの瓶の月光。
「クラムボンは殺されたよ」
「クラムボンは死んでしまったよ」
笑ったかと思えば、突然死んでしまう。
誰に?なぜ?
この物語は、小学校の国語の教科書に載っていた。
当時は教室でも、得体が知れない「クラムボン」は大いに話題になった。
「クラムボンは、泡だと思います」
「ぼくは、プランクトンだと思います」
「わたしは、光だと思います」
ああでもない、こうでもない。
その正体は、最後まで謎のままだった。
後日、テストでも「クラムボンとは何か」と問われたが、
担任の先生は、私たち一人一人の答えにマルをくれた。
色々な感じ方がある。
遠い記憶の先に、揺るぎない答えが見付かった。
いかようにも受け取れる答えは、時として「玉虫色」だと揶揄されるけれど。
感じたままの素直な思いは、強いて言うなら「虹色」の答えだ。
(底本:「宮沢賢治全集8」ちくま文庫、筑摩書房) |
|
|
|
| |
|