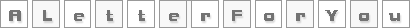
| |
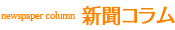
|
 |
Vol.30 「寮監のおばあちゃん」 (2006/02/04) |
 |
27歳の私は、熱を出した。
一人暮らしで何が辛いかって、こういう時だ。
口の中はカラカラ、関節はギシギシ。
着膨れしたまま、ベッドでぶるぶる震えている。
うさぎのリンゴも、卵入りのおかゆも出てこない。
目をつぶって、ただただ耐えるのだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
16歳の私が、固いベッドで眠っている。
高校3年間、親元を離れて寮で過ごした。
山全体が学校の敷地で、中腹にある校舎から少し登った場所に、古びたその寮はあった。
熱を出しがちな私は、よく学校を休んだ。
誰もいなくなった寮内はすっかり色彩を失って、
コンクリートの天井が、黒ごまのプリンみたいにふるふる歪んで見える。
午前11時。
ぱたん、ぱたん、スリッパの音が近付いてくる。
ぎぃ、と扉が開いた。
おもむろに顔を上げると、丹塗りのお盆が浮かんでいる。
「おうどん、出来たわよ」
寮監のおばあちゃん先生はいつもかわいいレースの割烹着を着ていて、
熱が出ると必ずうどんを作ってくれた。
伊達巻とワカメが入っている、関東風のうどん。
そして、もう一品。
「今日は、モンブランとエクレアにしましたよ」
確かに私は甘いものが好きだ。
ただ、熱が出た時にはゼリーやヨーグルトが食べたい。
だが、先生はいつも、寮生が熱を出すとわざわざ30分かけて下山して、
駅前でケーキを必ず2つ買ってきてくれた。
生クリームが喉にへばりつく。
フォークを持つ手が震える。
「残りは、眠った後に食べてもいいですか?」
吐き気が収まらず、後でこっそり洗面所に向かうのが常だった。
洗濯機を回す音、掃除機をかける音。
からっぽになった寮で、先生は休まないでずっと働いている。
朦朧とする中で、いつも何かしらの物音が聞こえてきた。
消灯後は、彼女のいびきが廊下じゅうに響き渡る。
でも、苦情など言えなかった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして、27歳の私。
ケーキは出てこない。いびきも聞こえない。
部屋でひとり、今見た夢をぼんやりと思い出していた。
(「日刊ゲンダイ」2月4日発刊) |
|
|
|
| |
|