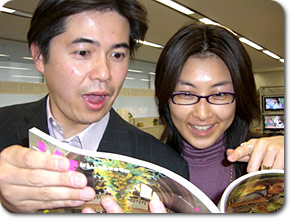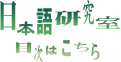|
|
| -
���t�̐헪�H�I�a���O����̗p�@- |
|
|
|
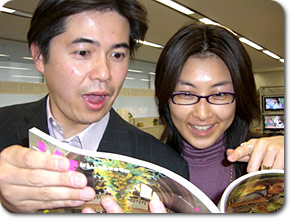
�؈䂳�[��A���̕��I |
�@
| ���� |
�@ |
�؈䂳�[��A���̕������ɂ��Z���u���Ċ����ł���ˁ[�I |
| �؈� |
�@ |
����������Ȃ�A�Z���u���Ȃ�Ȃ��́H�Z���u���Đl�̂��Ƃł���B |
| ���� |
�@ |
�͂͂�(��)�I�������؈䂳��I�ŋ߂͢�Z���u����Ă����\�������̂��������p����Ă��܂���ˁB |
| �؈� |
�@ |
�������ࢃZ���u����Ă��A�Z���u���e�B�icelebrity������X�́u�����A���m�v�Ƃ����Ӗ��B��������j�����ꂽ�l�X�B�܂����ꂽ�����ҁA�����l�Ƃ����Ӗ��j���Ă����p��ł���B����ꂽ�����̐l�ɂ����g���Ȃ��Ǝv�����ǁB |
| �c�� |
�@ |
��Z���u����Č��t�́A��i�ō��M�ȕ��͋C�̓C���[�W�o���邯�ǁA�˂��l�߂Ă����Ɖ������悭������Ȃ����t���ˁB
������������A����ȕ��ɁA�O���ꂪ���{��ɒ蒅���čL�܂�ߒ��ŁA�{���̈Ӗ��Ƃ̓Y�������t���đ�R�����Ȃ��̂��ȁB�܂��A�ŏ�����Ⴄ�j���A���X�ŗA������Ă��錾�t���A���邩���m��Ȃ��ˁB |
| �؈� |
�@ |
�a���p��͂��̓T�^�ł���ˁB�Ⴆ�u�I�[�_�[���C�h�v |
|

�C�^���A��ł͂ł��� |
�@
| ���� |
�@ |
�p�ꂾ���łȂ��A���ɘa���C�^���A�������܂���B�Ⴆ��J�t�F���e��Ɏn�܂�A�u�L�����������e�v��u�~���N�e�B�[���e�v�B�{���̢�J�b�t�F���b�ecaffelatte��́Acaffe���R�[�q�[��latte�������B������A�ŋ߂悭�g����J�t�F���e�̂��Ƃ��w���u���e�v�Ƃ������t���ƁA���������ɂȂ����Ⴄ��ł��B���ꂩ�碃p�X�^��B�C�^���A���pasta�͐��n�S�ʂ��w�����t�Ȃ̂ŁA�X�p�Q�b�e�B��U�j�A���p�X�^�Ȃ�A�f�U�[�g�̃P�[�L�������ꍇ�������ł��B������A�X�p�Q�b�e�B��H�ׂ�Ƃ��́A��X�p�Q�b�e�B���H�ׂ���Č�����ł���ˁB |
| �c�� |
�@ |
�ł��A�s�v�c�Ȃ��ƂɃp�X�^�̕����������Ȋ����������ˁB |
| ���� |
�@ |
�����ł��ˁB�ŋ߂ł͂�������A�������Ȍ���������p�X�^��ŁA���������i�|���^
���̂悤�ȃ��j���[����X�p�Q�b�e�B����Ă����C���[�W�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂�����ˁB���i�|���^����D��(��)�B |
| �؈� |
�@ |
�m���ɖ{��̃C�^���A�����X�g�����֍s���ƃ��j���[�ɂ́u�p�X�^�v�Ƃ�������ɂȂ��Ă��̒��Ɂu�X�p�Q�b�e�B�v��u�t�F�g�`�[�l�v�u�j���b�L�v�Ȃǂ̎�ނ������Ă����ˁB����������A�i�A�C�^���A��ɂ͂��邳���Ȃ��B |
|
 |
 |
| �e���r�����̐H�����u�p�X�^�v |
���i�|���^����D���I |
|
�@
| �c�� |
�@ |
��������čl���Ă݂�ƁA���{��͂��Ȃ�O���������₷������������悤���ˁB�����āA���ꂽ�O���ꂪ���{�ł����ʗp���Ȃ��Ӗ���`�ɕω��������u�a���O����v�ɂȂ�낤�ˁB���ꂪ�p��Ȃ�u�u�I�[�_�[���C�h�v�̂悤�Șa���p��v�Ƃ����ӂ��ɁB |
| �؈� |
�@ |
�����ł��ˁB���ꂾ���O�����a���O���ꂪ�×����Ă���̂ł�����A���肪�������炢����܂���ˁB |
|
�u���{��͊O���������₷�����t�H�v |

������Ј����ɒ��� |
�@
| �c�� |
�@ |
���j�I�Ɍ��Ă��A���{�͑嗤�⒩�N�����Ƃ̂Ȃ��肪�Â����炠�邱�Ƃ́A���w�Z�ł���������ˁB�u���@�g�v�����̏��߂��ˁB�Â��͖��t�̎��ォ��A�O�����當���⌾�t�A������A�����Ă���E�E�E�B |
| ���� |
�@ |
�����ƁI������ۂ��Ȃ��Ă��܂�����(��) |
| �c�� |
�@ |
���[�ƁA���_�������ƂˁA�������Ƃ��ڂ荞��ŁA�ŋߎg���Ă���u�a���O����v��u�O����v�̗p�@�����u�Ј���v�Ƃ�����̂ɏœ_�Ă悤�Ǝv���Ă����B |
| �؈�E���� |
�@ |
�Ј���ł����H���ł����H |
| �c�� |
�@ |
�w���{��̉��w�ω��x�⏼���g�Y���@���{���|�Ђɂ��ƁA���ۓI�ȍ������E�V�������C���[�W�����錾�t�������ĂԂ炵���B |
| �؈�E���� |
�@ |
�ւ��`�I |
| �c�� |
�@ |
�u�Z���u�v�͂��̑�\�I�ȗႾ�Ƃ�����ˁB���Ƃ��Ƃ́A��������ꂽ�A�����������߂��l�B���x�����w���Ă����̂��A�n���E�b�h�X�^�[�ȂǁA��ʐl����͎�̓͂��Ȃ��_�̏�̑��݂��w���悤�ɈӖ��̊g�傪�N�����Ă����ˁB |
| ���� |
�@ |
�����ł��ˁB����ɁA�Z���u���e�B�[����Z���u��Ƃ������ɗ����ꂽ�`�ōL�܂��Ă���Ƃ����̂������I�ł���ˁB����̌`�ŁA�������Ӗ����ϗe���ĐZ�����Ă���Ȃ�āB�܂��ɘa���O����ł��ˁB |
| �؈� |
�@ |
�ł����̒��ɐZ�������Ă���͎̂G����e���r�Ȃǂ̃}�X�R�~�̉e��������Ǝv���܂��ˁB�C���p�N�g��Ǝ��F���������Ƃ��邽�ߐV�������t���h���h������Đ��ɏo���Ă���B�����ĎႢ�l�B���L�߂�B�ӔC�͑傫���ł���B�����炱�����������߂Ă��ꂩ������t�ɂ͕q���ɂȂ낤�Ǝv���܂��B |
| �c�� |
�@ |
����u�Ј���v�Ƃ������t�͏��߂ĕ��������ǁA�V�������t�̎g������������Ȃ�����A�⏼�搶�ɕ����Ă݂悤�I |
|

�c���`�m��w�⏼���� |
�⏼�搶
���Ƃ��Ɗw��I�ɂ���ʓI�Ȍ��t�ł͂Ȃ�����A�u�Ј���v�Ƃ����͕̂�������Ȃ���������Ȃ��ˁB���͂��̗p�@�́A�b���肪������ɑ��āA���e������肭�`������ʂ�_�����u���t�̐헪�v�Ƃ������B
��{�I�ȁu���t�̐헪�v�͎��̓��ނ�����܂��B |
| �@������i�@�j |
�c |
����Ɠ������x���Ɏ��������킹�錾�t��A�b�����B
�c���q���Ɂu�ڂ��A�ԁ[���D���H�v�Ƙb�������邱�ƂŁA�e�ߊ����o���Ē��ǂ����悤�Ƃ��鎞�B
�~���ȃR�~���j�P�[�V������}�낤�Ƃ��ď�i�������ɑ��Ď�Ҍ��t�Řb�������鎞�ȂǂɌ����܂��B |
| �A�ى���i�@�j |
�c |
����Ɂu�����Ƃ͈Ⴄ�v�Ǝv�킹�āA����Ƃ̊W���̈Ⴂ���͂����肳���āA�����ʓI�ɓ`���悤�Ƃ��錾�t��b�����B
����ɑ����̈�a���E������^���āA�����̕��Ɉ������ތ��ʂ̂��錾�t��b�����B |
|
����̃e�[�}�́u�C�ɂȂ�a���O����v�͂��̈ى���i�@�j�̕\���̂ЂƂ��ˁB
�u�Z���u�v���ɋ����čl���Ă݂悤�B�u�Z���u�v�ȑO�Ɏg���Ă������ނ̌��t�́u�n�C�\�i�n�C�\�T�C�G�e�B�̗��ꥥ��a���p��j�v�������ˁB�������A�u�Z���u�v�Ƃ����O����̗�����g�����Ƃɂ���āA������Ɂu�V�����v�Ɠ����Ɂu������������ɏڂ����m���Ă��������v�u�����Ƃ͉������Ⴄ�v�Ǝv�킹�āA�b���Ɉ������ތ��ʂ����܂���B
�c���@�������ɁA�����ق��́u������H�v���ċ������킫�܂��ˁB
�⏼�搶
�����A������������ɁA���������u��������v��u��������v�ł��邱�Ƃ����������邱�ƂŁA�D�ʂɘb��W�J���邱�Ƃ��\�ɂȂ��B�v���[���e�[�V�����Ő��p��𑽗p����ꍇ�́A�u���m��������A���������Ă���v�Ƃ�����ۂ�^���ĕ�����������t���A���ʓI�ɓ��e��`���悤�Ƃ���헪��������ˁB
�c���@�ł����A�܂������m��Ȃ����t��A�������ƁA�������͂炢�ł��ˁB
�⏼�搶
�����I������A�����肪�m���Ă��邩�m��Ȃ����u�M���M���v�̂Ƃ�����U�߂āA�u�͂��I�v�Ƃ������B�t�@�b�V�����W�̍L���헪�͂����ɂ���悤���ˁB
�u�Z���u�v����ucelebrity
�v��A�z���āA�M���M���ňӖ����킩���ˁB���܂�u�Z���u�v�́u�n�C�\�v�����A���L���ŗ��h�ȂƂ����Ӗ������������A�������������Ƃ�����������Ȃ��Ȃ��Ă����B���Ƃ̏��ʂ������Ȃ��Ă���B
�u�n�C�\�v�Ƃ͎��Ă��邪�A���炩�ɈႤ�B���̈Ӗ��ł͈ى���ȂB������Ј���Ƃ��Ă̌��ʂ�������B
�u�Ј���v�͑�����͂��Ƃ����Ĉ����t����A�S���I�ȃC���p�N�g��^���Ĉ����t����p���\�����@�̂��ƁB
����������|�I�ɈЈ����āA�ޏk�����Ă��܂��ƈЊd�ɂȂ��Ă��܂��A���ʂ͂Ȃ�����A���Ȃ蓪�]�I�Ȑ헪���ˁB
�c���@�`����Ƃ��Ă̎��B���u���t�̐헪�v���������ׂ��ł��ˁB |

���t�̐헪�ł��� |
�⏼�搶
�b����́A���ӎ��̂����ɂ����t�̐헪�͏�ɍl���Ă���͂�����B������Ƃ̋�������W�����ǂ��z�肷�邩�ɂ���āA�b������ς��Ă���͂��ȂB�ى����Ȃ��瓯������ȂǁA���Ȃ�̓��]�v���[���K�v���ˁB���f�B�A�A���Ƀe���r�͎����҂̔��������̏�Ŋ������Ȃ�����A���t����Ƃ��̐헪���ӎ�����K�v������ˁB
**********************************************************
|
| �c�� |
�@ |
��b�̒��ɂ���߂��Ă���O����́A�g�����ɂ���āA���܂��܂Ȍ��ʂ�_������A�헪�𗧂Ă邱�Ƃ��o����ˁB�����炱���A�K�Ȑ헪�A���t�̑I�ѕ�����ȂˁB |
| �؈� |
�@ |
���E���̏��э���ł��鐢�̒��ɂȂ��āA���t���{�[�_���X�ɂȂ������ƂŐV�����\�����`�����܂�Ă���B�܂��Ɍ��t�͐����Ă���ƍĔF�����܂����B |
| ���� |
�@ |
�O�����A�����āA���{�Ɠ��̉��߂����V�O���ꂪ���܂��ΐ��܂��قǁA�{���̈Ӗ��ւ̒m����A�ϗe�̉ߒ��ɋC������y���邱�Ƃ���Ȃ̂ł͂ƁA���߂Ċ����܂����B |
|
 |
|
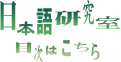 |