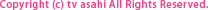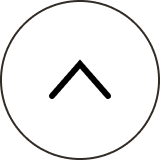2019/04/25令和

5月1日、「令和」の幕開けです。
「和」という漢字は元号に度々登場していますが、「令」は初登場。
「令」にどんな意味があるのか漢和辞典で調べてみました。(出典: 学研漢和大辞典)
1 《名》神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。「勅令」
2 おきて。お達し。「法令」「律令」
3 《形》よい。清らかで美しい。
4 《名》おさ(長)
5 《名》遊びごとのきまり。
6 《動》命令する。
7 《助詞》しむ・せしむ使役の意をあらわすことば
8 《助動》仮定の意をあらわすことば。
9 小令とは、南宋から明代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。
…なんと意味の多い漢字なのでしょう。笑
新元号に用いられた「令」は、
出典が万葉集の梅の歌の序文「初春の令月」なので、3の意味です。
辞典に「令月」は、
① 物事をするのに縁起のよい月。②陰暦2月の別名
と掲載されていました。
ちなみに他にも令を使った熟語として、
「令聞」(れいぶん)…清らかなことばやよい評判のこと
「令顔」…清らかで美しい顔、転じて美人のこと
「令室」(れいしつ)「令兄」(れいけい)「令妹」(れいまい)…妻や兄弟を尊んでいう言葉
などが。
なるほど考えてみれば「ご令嬢」も身近な「令」の用法ですね。
さてこの万葉集。
せっかくなので、梅の歌の部分を
万葉集研究の第一人者であり新元号の考案者と報じられている(ご本人は煙に巻いていますが)中西進さんの訳(「万葉集 全訳注 原文付」)で読んでみました。
初春の令月(時あたかも新春のよき月)…
梅の花咲く大伴旅人の家にみなが集まり宴会を開いたそうです。
梅が咲くいまを楽しんだり、
梅の花が散る様子を雪に例えたり、
梅が散っても次は桜が咲いてくれるではないかと希望を持たせたり…
そこには現代でも共感できる心情があふれていました。
中西さんの解説部分に、ことばに絡めてこんな表現がありました。
「本来ことばとは、自他の交通を機能としていた。」
「当時の歌が、なお多く口誦して伝えられたことは、その中でことばが本来的に生き生きと機能していたことになろう。」
当時の人たちは、
まるで会話するかのように生き生きと歌を口ずさんでいたのかもしれないなぁと想像します。
そうそう、万葉集の詞に曲をつけている人もいるんですよ。
作曲家の薮田翔一さんです。
約4500首もあるので完成までには時間がかかるのかもしれませんが、
「令和」の出てくる序文は出来上がって楽譜が公開されています。
美しい万葉集のことばにメロディーがつくとどうなるのでしょうか?!
口ずさみやすくなり、親しみがわいて、ますます後世に伝わっていくかもしれませんね!