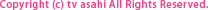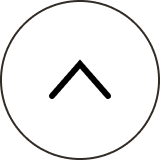2018/9/20言葉の解釈とは
こんにちは、寺川俊平です。
徐々に秋の気配を感じ始める今日この頃。
気候の変化についていけず、恥ずかしながら、私も少し体調を崩し風邪気味に。
そう、今回のテーマは“変化”です!!
やや強引です、すみません。
言葉の変化について記事を書きます。
題材は「確信犯」。
みなさんは普段、この「確信犯」という言葉をどういう意味合いで使っていますか?
既に、ここまで来てピンときている方。
いらっしゃると思います。
所謂“誤用”についての話でしょ?と。
しかし、今回はそこがスタートです。
最新の広辞苑を開きます。
するとまずこう書いてあります。
「道徳的・宗教的・または政治的確信に基づいて行われる犯罪。思想犯・政治犯・国事犯などに見られる。」
つまり、“悪いとわかっていて罪を犯すこと”ではなく
“かたく信じて疑わず罪を犯すこと”を示すのが「確信犯」であると書いてあるのです。
しかし、この話には続きがあります。
会社で約20年前の広辞苑第五版を探し「確信犯」を調べると
まさにこの上記の説明だけが書いてあります。
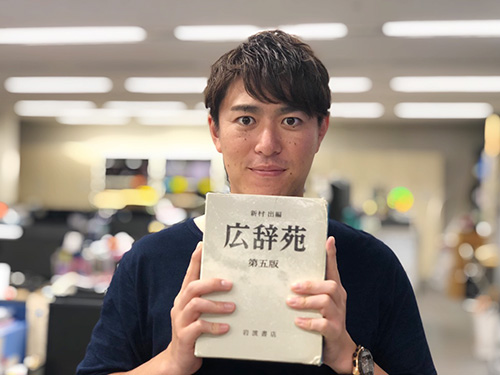
古い広辞苑を見つけました!
ただ、今年第一刷発行の第七版には上記が「①」とされていて、
その先に「②」があるのです。
その「②」には、こう書いてあります。
「俗に、それが悪いことと知りつつ、あえて行う行為。」
この「②」は20年前には正しくないとされ、記述のなかった項目。
そう、言葉の解釈が、“変化”してきているのです。
私たちアナウンサーは度々こうした変化に直面します。
言葉だけでなく、アクセントも、です。
実は、言葉の認識や標準語のアクセントはとても不安定なもののようなんです。
時代の流れ、流行、多くの人の認識と元来の意味とのズレ、
そういったものによって、変化しているものなのです。
「確信犯」についてはまだ「俗に」と書いてあるように
正しい日本語を求められる私たちは、誤解されないように、慎重に使っていかなければいけません。
ただ、時に、その言葉の意味の変化にビビッドに反応することも必要になってくるんです。
その変化は時に急に来るものではありますが
決して体調を崩さないように、興味をもっていつも敏感に対応していきたいものです。
それではまた!