今年没後50年を迎えたショスタコーヴィチは、20世紀最大の交響曲作曲家のひとり。その作品の真意を巡る議論は尽きることがありません。なにしろ当時はソビエト共産党による文化統制が敷かれていましたので、芸術家たちは自由な表現を許されていませんでした。国家の方針に逆らう者は粛清されるという危険な状況で、文字通り命がけの活動を余儀なくされていたのです。
そこで、ショスタコーヴィチが用いたのは、作品にメッセージを巧妙に隠すという手法。今回は指揮者の沼尻竜典さんが、隠されたメッセージについて考察してくれました。
交響曲第10番に隠されていたのは「ラブレター」。なんだか意外ですよね。この曲にはふたつのイニシャルが込められていると言います。ひとつはショスタコーヴィチのイニシャルからとったD-S-C-H(レ-ミ♭-ド-シ)。ドイツ語ではミ♭をEsと呼ぶので、SをEsに当てはめています。沼尻さんによれば、これは「政治に翻弄される自身の姿」。この音型はショスタコーヴィチのさまざまな作品に登場するのですが、決して耳に心地よい音ではなく、まるで警告を発するような雰囲気があります。
もうひとつのイニシャルは思いを寄せていた教え子、エルミラ。少し変則的なのですが、ELMIRAをE-L(a)-MI-R(e)-Aというふうに音名をイタリア語とドイツ語でミックスして読んで、ミラミレラに当てはめています。ホルンがこの主題を奏でていましたが、たまたまというべきなのでしょうか、D-S-C-Hとは対照的にロマンティックな性格が感じられるのがおもしろいところです。
交響曲第5番は、党から批判されて窮地に陥っていたショスタコーヴィチが名誉を回復した作品です。なにも知らずに聴けばとても輝かしいフィナーレだと感じます。当局はこの曲を成功作だと認めました。しかし沼尻さんは、ここにショスタコーヴィチの旧作、プーシキンの詩による4つのロマンスから第1曲「復活」が引用されていると指摘し、これは「強制された歓喜」だと言います。凡庸な画家が天才の絵を塗りつぶすけれど、時が経つと絵の具が剥がれ落ちて、本来の天才の絵があらわれる、という詩は、状況を考えればかなり物騒な内容です。
同じ曲を聴き方によって勝利とも皮肉とも受け止めることができる。音楽とはおもしろいものだと思いませんか。
飯尾洋一(音楽ジャーナリスト)

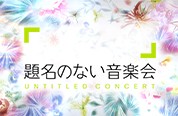 公式サイト
公式サイト しあわせ湯通信」|仮面ライダーリバイス
しあわせ湯通信」|仮面ライダーリバイス